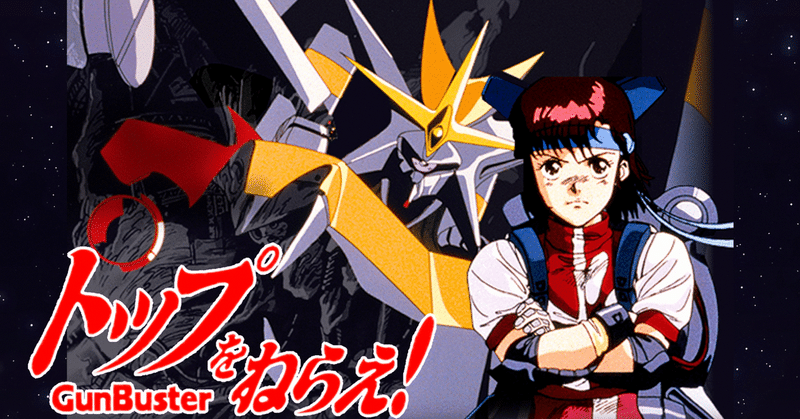
『トップをねらえ!』(1988)感想〜「女の子だって暴れたい」をロボアニメで一番如実に体現した昭和ロボアニメパロディ風味の名作〜
久々にOVA『トップをねらえ!』を全話見返してみたので感想・批評をば。
評価:A(名作)100点中85点
なぜ本作について書こうと思ったのかというと、1つは昨日書いた記事の反動からか無性に本作が見たくなったのが1つ、そしてもう1つはこの時のガイナックスというか庵野秀明が一番輝いていたからである。
読者の方々はきっと「女児向け漫画・アニメの感想・批評は書かないと言ったそばから書いてんじゃねえか!」とお思いであろうだが、断じて言わせてもらう。
『トップをねらえ!』は断じて女児向けのロボットアニメではない!70〜80年代の古典的ロボットアニメを楽しんだファン向けに作られた、立派な男児向けロボットアニメだ!
本作を改めて見直して思ったのは平成や令和の女児向けバトルものよりも昭和の『アタックNo.1』『エースをねらえ!』や本作の方がよほど「女の子だって暴れたい」を体現していたということである。
ここ数年の風潮として女性の社会進出が当たり前になったことで「女が強くなって男が弱体化した」なんて言われているが、そんなことはないと証明してくれる当時の時代性を示したのが本作ではなかろうか。
男が「24時間戦えますか?」のメンタリティーだったように、女だって昭和の頃は男に当たり負けしない気概と根性を持っている人が多かったし、何より「女だから」を言い訳にしなかった気がする。
少なくとも「女の子は身近な愛に生きるのよ」だの「ファイターより乙女チックに」だのというような「等身大の女の子らしさ」を本作はゼロではないが、ほぼ捨て去っているだろう。
そして何より本作で改めて再現されるスーパーロボット・ガンバスターの無双ぶりとラストに向けて高められていくボルテージに切ないながらもやりきった達成感のあるハッピーエンド。
アニメ・特撮オタクの庵野秀明の全盛期の切れ味と輝きが「歪んだ真っ直ぐさ」として表現された本作は当時マイナーな市場だったOVAというジャンルの有用性をこれでもかと示してくれた歴史的一作である。
そういえば近年劇場公開もされていたらしいが、1988年という昭和最後の年に生まれたということも踏まえて、改めて令和に見直す本作がどのような作品だったのかを論じてみよう。
「ウラシマ効果」という壮大なSFガジェットと3人の美少女の青春ドラマのシンクロ

まず作品全体を通して褒めるべき点の1つ目は「ウラシマ効果」という壮大なSFガジェットと3人の美少女の青春ドラマのシンクロであり、これは1988年当時としては変態的な画期性を持った設定と作劇であったと思う。
そもそも「大日本」を作っていた時からそうだが、庵野秀明をはじめとする初期ガイナックスの連中はとにかく揃いも揃って下品なオタク連中であり、そもそも何故に女の子がハイレグスーツ着て宇宙にわんさか出てくる怪獣と戦うのか?という話だ。
理由はシンプルに「女の子で遊びたい」というスケベなエロ根性であり、まあとにかく本作はノリコ・カズミ・ユングという3人の美少女を出しておきながら、風呂場といい戦いのシーンといいとにかく女の子たちにスケベな格好をさせる。
今の時代なら確実にコンプラその他で引っかかりそうなところが実に大らかだった時代であるが、一方でその3人の美少女が来るべき未曾有の脅威に備えてぐんぐん強くなるスポ根ものとウラシマ効果という壮大なSFとのシンクロが見事であった。
どういうことかというと、後半に入れば入るほどノリコとカズミは仲間たちから孤立していき、宇宙怪獣と戦っている一分一秒の間に地球ではもう何千年〜何万年という時間が過ぎ去ってしまうという事実を突きつけられる。
その「時間と距離が隔ててしまった人の運命の悲しさ」はかつての「ヤマト」「ガンダム」でも物語の核になるほどの重たいテーマとして表現されていたわけではなく、あくまで添え物扱いであった。
本作は過去のロボアニメでそこまで真正面からテーマとして扱われてこなかったものに敢えて挑み、しかもそれを女の子の青春物語として下品なスケベ根性とともに描いており、これがグロテスクながらに天才的である。
タカヤ・ノリコという天才的なセンスを持った直情径行の主人公にアマノ・カズミという天才肌に見せかけた努力型の才女、そしてノリコのライバルであるユング・フロイトの組み合わせ自体は昭和の女児向けスポ根漫画で見られた王道だ。
その女児向けの王道的なキャラ付けとロボットアニメで使われていたSFものという「混ぜるな危険」のものを凄まじくハイセンスなパロディによって融合させ、二次創作物でありながら立派に見える一次創作を作り出したのである。
だから本作は脱構築=破か再構築=離かでいうと間違いなく昭和ロボアニメの再構築=離なのだが、その高度な再構築のあり方が表面上のごてごてとしたパロディに覆われているため丁寧に因数分解しなければその高度な作りに気づけない。
そして面白いのはその美少女たちは最終的に「大切な人との別れ」によってむしろ活性化し、心の火がどんどん燃焼していき最終的に「炎のガンバスター」になっていくという皮肉めいた構造になっているということだ。
これはある意味『美少女戦士セーラームーン』やその精神的後継者である『ふたりはプリキュア』以降の女児向けのバトルものとは違ったところであり、決して安易に「仲間との絆」「連帯」というところに還元しないのである。
心が強くなろうとする時に最も大切なものは何か、それは決して他者に頼ることでも仲間のために戦う正義感ではなく「自分こそがこの宇宙を守るのだ!」という誇りと孤独を受け入れて戦う覚悟だ。
皮肉にも2人の女の子は自らにある「女性性」というものをある種捨て去って「男性性」に近い「心の強さ」に至った時に、コーチが言うように「炎のガンバスター」になるのである。
コーチが言う「お前とアマノは一人一人では単なる火だが、二人合わせれば炎となる。炎となったガンバスターは、無敵だ!」とはそういう意味だ。
それは昭和の兜甲児や流竜馬たちゲッターチームら先人のロボアニメの主人公が言葉にせずとも持っていた精神であるが、この精神をはっきりと言語化し誰の目にもわかりやすい形で可視化したのがノリコとカズミである。
ガンバスターという昭和スーパーロボットの集合体

そんな「一人一人だと単なる「火」だが、二人合わされば無敵な「炎のガンバスター」となる」という言葉の通り、ガンバスターというスーパーロボットは劇中でも無類の強さを発揮する昭和スーパーロボットの集合体である。
デザインそのものは決してかっこいいというわけではないが(ザクみたいなモノアイがダサい)、ヱクセリヲンの甲板から腕を組んでせり上がってくるガンバスターの構図はゲッタードラゴンとウザーラのオマージュを「ガイナ立ち」として完成させた。
そして一度目を開いたガンバスターは宇宙怪獣など歯牙にも掛けない怒涛の勢いで蹂躙し次々と蹴散らしていくが、それら1つ1つは全て昭和ロボアニメや特撮の先輩たちが切り開いてきた表現の借り物でしかない。
スーパーイナズマキックはウルトラ流星キックからゲッタートマホークのオマージュたるバスタートマホーク、そしてイデオンの全方位ミサイルから借りた名称なしのミサイルなど、特別に目新しい技がないことに気づくだろう。
そしてバスターマシン3号とラストの縮退炉も漫画版『ゲッターロボ』の巴武蔵の最期など元ネタがわかりやす過ぎるくらいにあざとい演出の数々なのだが、これらの演出がなぜ当時は斬新なものとして映っていたのか?
それは80年代後期に入るといわゆる「男児向けの王道ロボアニメ」がOVAなどを除いてもはや過去の文化となっており、「ガンダム」以降の歴史がミリタリー系の「リアルロボット」ものが主流だったからである。
本作は当時のトレンドの敢えて逆を行くかのように、設定そのものはリアルロボットアニメのようでありながら、実際のスペックと描写はむしろ「イデオン」辺りまでの70年代ロボアニメに先祖返りしているのだ。
しかもその先祖返りを安直にやるのではなく、上記した女児向けスポ根ものと掛け合わせながらも、どんどん男児向けのスポ根もののロジックに染めていくことで見事に男児向けロボアニメの文法に昇華した。
そういう意味でこの「ガンバスター」は昭和スーパーロボットの集合体にして、ある意味では「昭和最後のロボアニメ」という終焉をも司ったロボットとして象徴的だったのではないだろうか。
これが90年代に入ると「トランスフォーマー」「ウルトラマン」の文脈を色濃く継いだ勇者シリーズや搭乗者がそもそも超人級の強さを持つ「Gガンダム」のようなちょっと違うアプローチの新機軸を入れるようになる。
また、石川賢の漫画版『ゲッターロボ號』に出てくる突然変異の真ゲッターロボのようにもはやロボットというよりは奇怪な独立生命体とでもいうべきものも増えてくるので、その意味でも象徴的なロボットだ。
ノリコとカズミの心の炎が最高潮に達した時に真の力を発揮するというガンバスターはそういう意味で昭和最後のスーパーロボットと断言して差し支えあるまい。
特に私のような昭和スーパーロボットアニメを原体験として持たないプレッシャー世代にとってはこのガンバスターというロボットはその意味で「エクスカイザー」「Gガンダム」のような平成のスーパーロボットとは違う衝撃があった。
本作があったからこそ昭和のマジンガーZをはじめとするスーパーロボットは正に「24時間戦えますか」の右肩上がりの精神で敵をなぎ倒し、凄まじい鉄拳と武装で勇猛果敢に敵を蹴散らしていった英雄たちなのだと知らせてくれる。
実際、ゲーム「スーパーロボット大戦α」でもそういう立ち位置のスーパーロボットとして描かれていたし、今ではむしろマジンガーとゲッターが平成版として若返りしているので、貴重な昭和ロボアニメ枠の役割も果たしているのだ。
そしてそのことが見えた時、私が酷評してきた『新世紀エヴァンゲリオン』がどのような位置付けにあるのかが正しく見えてくるだろう。
『新世紀エヴァンゲリオン』は『トップをねらえ!』の裏返しである

上記を踏まえると、実は『新世紀エヴァンゲリオン』は見事なまでの本作の裏返しの構造になった作品であることがわかるであろう。
「トップをねらえ!」は2人の美少女が不治の病を抱えた男性コーチから「強くなれ!」と叱咤激励を受けながら努力していき、どんどん仲間たちから離れ「孤独」を受け入れる覚悟を持つことで「男性性」を手にして強くなる。
ガンバスターは昭和ロボットアニメの集合体=昭和の男らしさが詰まったものである、それに体を鍛え上げた2人の少女が乗ることによって勇ましくカッコ良い「強さ」を手にして敵に無双していく構造だ。
エヴァはそのガンバスターの更なる裏返しというか逆張りとして作られており、碇シンジが乗るエヴァは母親であるユイが核となっているので「女性性」の塊なのである。
それに合わせるかのようにエヴァのデザインも、そしてそのエヴァに乗るパイロットであるシンジくんもアスカもレイも全員線が細いフェミニンな印象を受け「力強さ」は微塵も感じさせない。
更に作劇上でもシンジくんをはじめアスカもレイも戦えば戦うほど強くなるどころかむしろ精神を病んだり弱体化したりしていき、パイロットスキルは上がってもそれが精神的成長に繋がらないのである。
以前こちらの記事でも述べたようにシンジくんは(少なくとも1995年のテレビ版では)公的動機も私的動機も心の中に持つことができないy=0の成長しないアンチヒーローだ。
むしろ「エヴァ」において戦いの動機を持っていたのはアスカとレイなのだが、じゃあこの2人がノリコとカズミのような右肩上がりの成長や平成方式の指数関数の成長をするかというと、それもしない。
そう、『トップをねらえ!』が徹底した昭和ロボアニメへの屈折したオマージュとオタクなりの歪んだ誇りで作られた成長物語なら、更にそれを裏返して「全く成長しないロボットアニメ」にしたのが「エヴァ」である。
未だに巷では「エヴァ」に関する解釈論争が繰り広げられているが、そんなことをしなくても本作で打ち出した構造を更にひねった形で裏返しにしたのが「エヴァ」だとわかれば難しくもなんともない。
言うなれば「ガオガイガー」と「ベターマン」のような関係性であり、「トップ」が「ガオガイガー」という「陽」、「エヴァ」が「ベターマン」という「陰」の図式になっている。
そのことを改めて分からせてくれる意味でも、庵野秀明というオタク作家のことを語るときにやはりこの「トップをねらえ!」について避けては通れないのだ。
私が本作を高く評価し「エヴァ」を貶す理由も明確にそこにあって、私自身がどちらかといえば「陽」の方が好きなのもあるが、最大の違いはフィルムそのものにこもっている「熱量」である。
私自身の庵野監督およびガイナックスに対する評価はあくまで「二流のC(中の下)」だが、この頃はそんな二流でも一流に負けず劣らずのものが作れることを証明しようという気概と迫力があった。
そして「エヴァ」も前半まではそういうオタクの屈折したあり方が外に対するアンダーグラウンドな強い毒となって芸風に昇華されていたのだが、後半から熱量が失われすっかりパワーダウンしたように思われる。
まるで『ドラゴンボール超』で弱体化してしまい強さのインフレに置いていかれた孫悟飯みたいだが、本作の成功を知っているからこそ尚近年の見るに堪えない劣化ぶりが何とも居た堪れない。
「戦う女ヒーロー」が希少価値を持っていた最後の作品

さて、最後に本作を「戦う女ヒーロー」という観点で見た場合何が違うのかというと、「戦う女ヒーロー」が希少価値を持っていた時代のある意味最後の作品ということだ。
戦う女ヒーローは別に「トップ」が初めてではないし、むしろ「ウルトラマン」の時代から戦うのは決して男の仕事というわけでもないことは示されていた。
しかし、その価値観は昭和時代においては決して「主流」ではなく「傍流」であり、スーパー戦隊シリーズのモモレンジャーの登場で確かに「戦う女ヒーロー」の概念は確立されている。
だからこそ当時としてはそれが画期的なものとして視聴者の目に映ったし、「アタックNo.1」「エースをねらえ!」にしたって「女の子がこんなに頑張ってるなんて!」という見られ方をしていたのではないか。
そりゃあそうだ、男の泥臭いダイナミックなスポ根と女のスポ根のどっちがカッコいいかと言われればいうまでもなく前者だし、いざ戦いになった時に頼れるのは断然女よりも男の方である。
それに異議申し立てを行うかのように「女の子だって頑張れば男のように暴れられるんだ!」=「女の子だって暴れたい」を言葉にせずとも昭和最後のロボアニメとして表現したのが本作だ。
とはいえ、これだって振り返れば結局のところは「男社会の理屈に女性を適合させる=女性性(弱さ)を捨て去って男性性(強さ)を手にする」ということでしかないのではないか?
女性が「等身大の感覚」を失うことなく「ヒーロー性」を獲得することは不可能なのか?という難題に取り組むために生まれたのが『美少女戦士セーラームーン』であろう。
その「セーラームーン」が一世風靡してギガヒットを叩き出したことで「戦う女ヒーロー」が「傍流」から「主流」の一角に食い込んだことで、確かに市民権も獲得し地位向上も果たしたであろう。
更に00年代に至って「プリキュア」「リリカルなのは」の登場で「戦う女ヒーロー」が世間の価値観の1つとして定着したが、問題はそこから先にあるのだ。
「女の子だって暴れたい」が『ふたりはプリキュア』の企画を通すキャッチフレーズとして使われるようになったということは、「戦う女ヒーロー」が希少価値ではなくなったということである。
昔はそんな簡単に戦う女の子なんて出なかったし認められていなかったからこそ、本作のような「健気に頑張って戦う女の子」の存在が世間に対して驚きや衝撃の対象たり得た。
しかしその価値観が女性の社会進出という現実の変化と相まって標準化=大衆化されてしまうと、もはや「戦う女ヒーロー」なんて珍しくもなんともない。
今回の記事での言及を最後とさせてもらうが、私が今年の『ひろがるスカイ!プリキュア』の1話感想で「ヒーローを自称させればヒーローというわけではない」と書いた真意はそこである。
「戦う女ヒーロー」なんて今の時代には珍しくも何ともないのだから大したインパクトにはなり得ないと詰ったわけであり、これからは何とかしてでも女ヒーローは男ヒーローと対等に立たなければならない。
それは決して「エヴァ」や「鬼滅」でやったような男を弱体化させるという対数関数的なデバフではなく、指数関数的な高いハードルとして表現することになるわけである。
その高いハードルを昭和最後のロボアニメとしてクリアしていたのが本作であり、男児向け女児向けを問わずバトルものを作りたい人こそ本作を徹底的に批評・研究すべきであろう。
二次創作的な一次創作のパロディとして作られた作品だからこそ、その構造を分解することで見えてくるものがある格好の材料であり、実に批評性と先見の明に飛んだA(名作)である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
