
花模様は明日に溶けて #教養のエチュード賞
二枚の写真がある。
池袋のはずれにある小さなアンティークショップで買ったフォトフレームに収まったその写真たちは、いずれも同じ女性を撮影している。
画像のデータはもうどこにも残っておらず、プリントしたそれらがなくなれば二度と見ることはできない。だからといって宝石のように厳重に扱っているかと言われれば少し違うような、不思議な写真たちだ。
妻が入れてくれたコーヒーを飲みながら折に触れて取り出し、眺める。するとその時々で異なった表情を見せる静止画の彼女と目が合う。
宝石のように厳重に扱ってはいないけれど、たとえばそれはたったひとりにだけ価値のある花束のようだった。
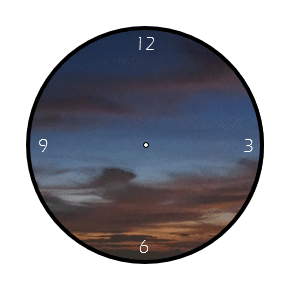
「あ、牛乳買うの忘れちゃった」
買い物袋の中身をあけていた千明がつぶやいた。
街に流れる夕焼け小焼けを聞いてからしばらくが経っていた。外はじっとりと闇に囲まれ、窓枠にわずかな朱色が引っかかっている。その繊細なコントラストの美しさに「カメラは、」と思ったが、目を離した一瞬の隙に景色は姿を変えていた。
何の予定もない休日の夕方は色違いのサンダルをつっかけて千明と買い出しに出る。料理ができない俺はただの荷物持ちだったが、確かに彼女が選んだ食材たちの中にお馴染みの牛乳パックはなかった。
しかし千明はそれ以上何を言うでもなく手際よくレタスや鶏肉を閉まっていき、空になった袋は三角形に畳んで専用のカゴに放った。
リビングのソファで先に寛いでいた俺のとなりに千明が座る。彼女が履いていた花模様の長いスカートがふうわりと広がり、手の甲に触れた。
くすぐったくて払おうとしたが、そのままスカートの端をつまんで少し引っ張ってみる。無造作に束ねられたポニーテールから落ちる後れ毛がゆっくりと揺れた。
「なあに? もうお腹すいた?」
まるで子どもに聞くような口調に「違うよ」と言いかけて、腹がぐるりと鳴いた。
「なんでわかったの?」
「わかるよ。どれだけ一緒にいたと思ってるの」
千明は少し得意げに口角をあげた。確かに彼女は俺よりもずっと俺のことをよくわかっていた。苦手な食べ物のことも、好きな音楽のことも。
嬉しい気持ちと悔しい気持ちとがない混ぜになって「今日はぶりの照り焼きが食べたい」と無茶を言ってみる。しかし千明は困った顔ひとつせずに頷いた。
「いいよ、今日で最後だからなんでも好きなもの作ってあげる」
「最後ってなんだよ、大袈裟だな」
いつの間にか重なっていた手をぎゅっと握り込み、浅くへこんだ寂しさを埋めるように言った。
明日の朝、俺は最寄駅から始発の電車に乗って上京する。淡くぼやけていた夢の輪郭をなぞるために。
千明と住んでいるワンルームの壁には一枚の写真が飾られていた。半年前に小さいながらも賞に引っかかった自信作だった。それをきっかけにあれよあれよという間に上京して働く運びになり、ついに一日を切るところまで迫ってきている。
会うのに電車で約3時間を必要とする距離がいわゆる遠距離恋愛であることはわかっていた。しかし手に馴染んだ毎日は素知らぬ顔をして今日まで過ぎていった。
俺をよそに千明はパッと手を離して立ち上がった。また手の甲に花模様が触れる。彼女だってこれまで上京の話題にはほとんど触れてこなかったのに、どうして今になってそんなことを言うのだろう。
「ちょっと待ってて、今作るから」
今度はスカートの端を摘まむ隙もなく身を翻してキッチンに入っていった。俺は彼女のぬくもりが残ったソファに上半身だけうつぶせにして沈み込む。淡いベージュのソファカバーは昨日洗濯していたせいか清潔な甘いにおいがした。
はじめはメンズ商品にありがちな清涼感のある香りが多い部屋だったのに、いつの間にかすっかり千明の趣味に塗り替えられている。肺いっぱいに広がる花の芳香に、自分まで中性的に柔らかくなったような心地がした。
キッチンに目をやると背の低い千明が冷凍庫の一番上の段から何かを取り出そうと背伸びしていた。友人からもらった旧型の大きな冷蔵庫は平均身長を大きく下回る千明には使いづらそうで「引っ越すときは責任もって引き取ってよね」とじっとりした目で言われたのを覚えている。あのときは「引っ越すってなんだよ」と笑ったけれど今は喉が引きつって枯れていた。
あれでもないこれでもないと見えない品物を取り出してはしまう彼女の背後に回って「これ?」と奥の方にあったジップロックを取り出してやる。
「そうそう、それ。ありがとう」
頷きながら振り向いた千明との距離は近く、胸の高さにある茶色い目がほとんど真上を向いていた。見上げるときの癖なのか口までぽっかりと穴を開けている。
小さいな、と言うと怒るので、代わりに冷凍のぶりを置き去りにしたまま彼女を抱きしめる。頭上からは波が寄せるように白い冷気が降りてきて、千明の長い髪に薄いベールが伸びていった。
「なあに?」
「千明が変なこと言うから」
口に出さずにいたことが喉まで押し寄せてきている。傷口を見ると痛みが体中を巡るように、一度自覚した感情は血液に溶けて全身に運ばれていった。
「変じゃないよ。わかってたことでしょ」
泣きじゃくる子供を宥めるような声に抱きしめる腕の力がこもった。自分が本当に幼くなったような気がして、千明の脱力した両腕を乱暴にとって背中に回してやりたくなる。
ゆるくウェーブのかかった髪に頬を寄せると驚くほど冷たくて自分の体温の高さを知る。自分の肌の、その沸騰したような熱さにどうしようもない衝動だけが増していった。
硬いフローリングの上じゃいやだと言う千明を抱えてリビングの電気を消した。暗闇の中で薄く微笑んだ口元が何を訴えるでもなく揺れている。
彼女の小さな体にぬくもりを与えることに夢中になりながら、顎を伝って落ちた汗の行方に目を走らせる。真下にいる千明の頬の高い位置を通ったところで目が合い、怖くなって反らした。
スローモーションみたいに一瞬間だけ静止画になった彼女の瞳の中に何もかもが写っている気がして直視できない。
千明もまた、視線が合わないように顔を背けた。何を思っているのだろう。こんなどうしようもない子供みたいな男に。
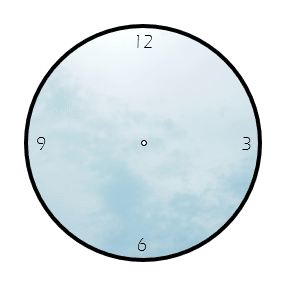
荷造りの済んだボストンバッグのポケットに手を突っ込むと、ライターは案外簡単に見つかった。
カチ、と弾いて火をつけると、薄闇と混ざって朝焼け色になる。くわえた煙草に近づけて先端を焼き、ゆっくり吸い込むと少しむせた。しばらくやめていたせいかやけに肺を締め上げるような熱さが染みた。
目が覚めると、セミダブルのベッドに千明はいなかった。綺麗好きな彼女が昨夜脱ぎ散らかした服もそのままで忽然と姿を消すなんて、と思ったがリビングのローテーブルに一枚のメモ書きが残してあった。
俺はシャワーで汗を洗い流し、のろのろと身支度を始める。「寝坊しないように目覚ましかけとくね」とシーツにくるまった千明がアラームをセットしてくれていたが、聞き慣れた音が鳴る前に起き出したせいか頭だけが妙に冴え冴えとしていた。
結局最後まで多くの言葉を交わすこともなく、彼女は静かに俺を受け入れていた。それが十二分すぎるほどに別れの言葉として脳裏を焼き、ことを終えれば手に取れるほどはっきりとした粘り気をもってこびりついていた。
何がいけなかったのだろう。上京を決めたことか。賞をとったことか。あの写真を、撮ったことか。
壁にかけられた一枚の写真に触れる。ありふれた朝のベランダではにかんだ笑みを浮かべる女性の、千明の写真だった。「洗濯物写ってるじゃない、恥ずかしい」と彼女はむくれていたけれど、コンペに出すと言ったときは止めなかった。
そのくらいに自信のあった一枚が俺を新しい場所へ連れていき、代わりに元の居場所を去ろうとしている。
遮光カーテンの隙間から差し込む光が強くなって、始発電車の出る時間が刻一刻と迫っているのがわかった。
千明だってきっと、いつ帰ってくるかもわからない男を待っていたくはないだろう。俺は彼女をおいていくのだ、生活の一部だったものをすべておいていくのだ。それが代償を払うということなのかもしれない。
支度を終えてボストンバッグと小さなキャリーケースを引きずり、最後に部屋を見渡してみる。
長年過ごしてきた場所の、いたるものたちが見送ってくれる。お気に入りのソファが、キッチンに置いた揃いの歯ブラシが、陽光に反射する写真立てが、ぺらりと一枚残されたメモ書きが、
牛乳買ってくるね。元気で。 千明
両手を強く握りしめていた。右の掌に小さく痛みが走るのを感じて見てみると、うっすらと細く血が滲んでいた。自分でも気づかないうちにできた瘡蓋が剥がれたらしかった。取り留めもない傷口だと思おうとした。
でも、ダメだった。
もたつく手足を空回しながら外へ出る。千明が本当に牛乳を買いに行ったとしたらコンビニかスーパーで、どちらも歩道橋を渡った右手側にある。始発の電車が出る駅も、右手側だ。
しかし彼女ならどうするだろうと考える。朝焼けが白く霧散して青みがかり、住宅街の隙間から覗く光の束も姿を消し始めていた。ランニング中の若い男や散歩中の犬が幾度も横をすり抜けていく。新しい一日がはじまろうとしていた。
俺は息を切らして歩道橋をのぼり、左手側の階段を降りていった。
確かに彼女は俺よりもずっと俺のことをよくわかっていた。苦手な食べ物のことも、好きな音楽のことも。そしてふたりのことも。しかし俺だって少しくらいは彼女のことをわかっている。
その証拠に大きな時計台とブランコが揺れる小さな公園で、あの花模様を見つけた。
遠目に見える千明の髪は少し濡れていて、朝露を飲んだ木々のきらめきに反射している。いつからここにいたのだろう。俺が起き出すよりもずっと前にひとりでベッドを出て、服に袖を通して、静かに家をあとにする彼女の背中が見てもいないのにちらついた。
俺たち、本当にこのままでいることはできないのだろうか。変わりたくないと思うのは強欲すぎるだろうか。そばにいてほしいと願うことは君の未来を食い潰すだろうか。
頭の中で白と黒の絵の具が混ざりあい、思考を行ったり来たりする。どっちつかずのその真ん中、ただぬかるんだ土に足を踏み込んで「千明、」と呼ぼうとしたその瞬間、朝露が落ちた。
頬のゆるいカーブをなぞって滴り、花模様に色を付ける。何度も何度も落ちては咲く花々と彼女の横顔が、新しい朝に滲んでいた。
それは言葉にすることすら躊躇われるようだったから、俺はボストンバッグからカメラを取り出して一度だけシャッターを切った。露出もピントも何もあわせていない、ただ指をボタンに押し込んだだけの一枚。
それが画面に表示される前に電源を落とし、何もかもがすでに終わっていたのだと項垂れて来た道を戻っていった。
最後に公園の時計台を見ると、ちょうど出発の時間だった。
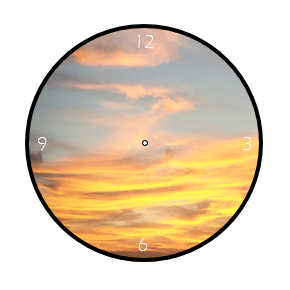
池袋駅で降りると彼女が待っていた。ふたり並んで夕飯の買い物をして帰る。
住宅街のはずれに借りたワンルームは築数十年のわりに綺麗で、部屋の奥の窓からは小さな公園が見えた。そこから覗く親子連れや学生たちの姿、また景色に見え隠れする生活の気配が気に入っていて、上京後に住み始めてから三年が経つ。
ベランダで煙草をくゆらせていると、心地よい苦みと共にキッチンから生姜と醤油の焼けるにおいがした。今夜は生姜焼きにしようと言った彼女が買った豚肉パックの端には三割引きのシールが貼られていて、過ぎ去っていった三年という時間が長いのか短いのか迷ってしまう。
カメラに触っていられる仕事に就いたとはいえ、ペーペーの新米であることに変わりはない。
そして上京してから一度も地元に帰っていない事実も、千明とはあれきりになっている現実も、変わりはなかった。
「あの写真、元カノでしょ」
知り合いに誘われて参加した小さな個展の打ち上げで、隣の席に座っていた女性に声をかけられた。いつだったか名刺を交換したはずだがさっぱり名前が思い出せなくて曖昧に笑みを返す。
「一目見てぴんときちゃった。これを撮った人は彼女のこと、一生忘れられないんだろうなーって」
酔いでうまく呂律が回っていないはずなのに薄くはがれた口紅の出す声がやけにはっきりと聞こえた。そんなことないよと言いかけて、ならどうして自分のブースの最後にあの一枚を選んだのか。
その答え合わせがようやくできた気がした。
薄甘い色の空が滲んで、世界が嫌に輝いていた。その中に千明がいて、俺がシャッターを切る。その時間のなんと美しいことだろう。あまりに美しすぎて最後を決めかねていた俺の代わりに彼女が告げてくれたんだ。「元気で」と。
「ね、ちょっと、そんな顔しないでよ」
大切なことを他人任せにするのは最後にしよう。どっちつかずのその真ん中、ただぬかるんだ土に足を踏み込んでじっと助けを待っているのはずるいから。
「でもね、こうも思ったの。こんなに誰かを愛せる人に想われて、彼女はきっと幸せだったんじゃないかなって」
そうかな。そうだといいな。
どうやら飲みすぎていたらしい。喋ってるのか考えてるのかわからなくなって、その夜の記憶は千明の字を思い出したところで途切れていた。
「なに黄昏てんの」
横に並んだ彼女の背丈は俺とそう変わらない。彼女はそれをコンプレックスだと言ったけど、俺は同じ目線で景色を見られるところが嫌いではなかった。
「そんなんじゃないよ」
「うそ。変な顔してたよ」
俺が付き合う女性はどうしてこう勘が鋭いのだろう。特別顔に出やすいほうでもないのに、なぜか千明にも彼女にも考えていることを見透かされてしまう。
観念して静かに頷き、煙を吐き出す。ベランダに広がる焼けた空が曇りを帯びて、忘れられないのだなと実感する。こういう自分を良いとも悪いとも思わなかった。ただあの痛みが心臓に刺さって抜けなくなり、そのまま癒着してしまったことだけは確かだった。
「ほんとに好きだったんだね」
「俺にはもったいないような、素敵な人だったから」
前の公園から届いた木枯らしが足元を滑り、お揃いの青いサンダルが冷え冷えと色をなくしていく。
季節が過ぎ去る瞬間は花が降るようにほんのわずかずつ、しかし確実にやってくるから自分もあわせて歩き出す。大抵は置いていかれないように慌てて右手と右足を同時に出すような日々だけれど。
煙草の火を消して中に入ろうとすると、彼女はあの打ち上げの夜と同じ口紅でつぶやいた。
「わたしはずるい人だと思うな。だってそんなの、誰も勝てないから」
健康そうに張った頬の半分は橙色を透かしたように明るく、残りの半分は夜に鋭く陰っていた。雲が出ているわけでもないのに秋の雨の湿った気配がする。
昼と夜の境目を眺める彼女の肩を静かに撫でた。わずかに近づいた距離が安心を連れてきて、今度は彼女が俺の肩に頭を乗せた。静かな重みが心地よくて、冬に身を寄せ合った鳥みたいに小さくなる。
ふたりの影が闇に溶けるまではこうしていたい、そう思ったのは本心だった。
ひとりの女性のすべてを理解しようだなんて傲慢な話なのかもしれない。
離れてもなお、千明の存在は俺の歩く先を彩っていく。それは変えようもない事実であり、変えたいと望むべくもなかった。これからもそうやってあの花模様を飾って生きていくのだろう。
淡いベージュのソファカバーと旧式の冷蔵庫と、彼女がいたワンルームを心のどこかに持ち続けながら。
別の人を愛して。
***
こちらの企画に参加しています*
第三回教養のエチュード賞。
盛り上がってますね。毎日のようにハッシュタグのついた記事がアップされていて、しかもどれも力作揃い。みんな日々隠した爪を研いでそのときに備えているんだなぁと実感しました。
とはいえ自分も頑張って書きました。お楽しみいただけたら嬉しいです。
さて、今回のコンテストには初めから小説を出すぞ決めてカリカリ書いていた矢先、こちらのツイートを見かけまして。
仲間内でもここTwitterでも話題になっている 嶋津亮太さんの #教養のエチュード賞
— verde (@verde88988252) October 17, 2020
皆さん力が入っているというか、構えちゃってるというか、参加に躊躇している人も多いのかな?
私的には「嶋津さんへのお手紙」的な「今私はこんなこと考えてます。嶋津さんはどう思います?」的な感じで →
この考え方がなんだかフラットで素敵だなぁと思って、小説を出すかたわらで嶋津さんへお手紙も書こうと決めていました。
お時間のある方はよければお付き合いください。
***
嶋津さん、こんにちは。七屋糸です。noteやTwitterではいつもお世話になっております。
コンテスト上は2回目のお手紙になります。実はこっそり第二回教養のエチュード賞にも参加しておりました。自分で読み返すのも恥ずかしいのですが、プーさんのぬいぐるみの可愛さについて好きに喋っていたあの記事です。
最初はわけもわからず「教養のエチュード賞というなんだか素敵な催しがあるらしい。参加したい」という気持ちだけで書いていました。不手際が多々合ったと思います。その節はごめんないさい。
あれからいくらか時間が経って無事に、というか幸運なことに第三回教養のエチュード賞にめぐりあうことができました。嬉しい。嶋津さんにはいつも勝手に頭が下がります。
*
この小説を書くにあたって考えていたこと、感じていたことを少しお話させてください。
物語の骨格自体は教養のエチュード賞の開催を知る前からあったのですが、なかなか筆が進まないまま中途半端なところでデスクトップの隅に放おってありました。
そんな作品を完成させようと思ったのは、今作のテーマの一つでもある「別れ」という題材を全力で書いたもので勝負したい気持ちがあったからです。
今までにも「別れ」について書いた作品はいくつか公開していて、七屋糸がもっとも好きなテーマと言っても過言ではないかもしれません。少し前に嶋津さんが開催されたMuse杯に出した小説も、形は違えど「別れ」という要素が隅っこに顔をのぞかせていたような気がします。
そこで今回はとことんこのテーマに向き合い、自分に書けるできるだけ良いものを読んでもらおうと、完成するかもわからなかった書きかけに手を出したわけでした。ちゃんと出来上がってよかった。
わたしの中で書きかけで止まっている作品にはいくつかの分類があります。
ひとつは途中でつまらなくなってしまったもの。自分ですら面白いと思えないものを人に読んでもらうのも申し訳ないし、何より書くのが退屈なんです。
またひとつは思いつきのワンアイデアだけで走り出してしまったもの。つまり後先考えずに突っ走った先が行き止まりでしたーという感じです。
最後に、本当はとても書きたいんだけど頭の中をうまく表現できるかわからないものです。今回の作品が書きかけだったのはまさにこのせいです。イメージはあるのにろくにまとまらず、ふわふわしたままずっとそこにありました。
後々まで長く残る記憶って、静止画のような一枚絵が生活と地続きになって繋がっているような気がするんです。そういう瞬間瞬間を写真で捉えたような感覚が「別れ」には多いように思えて、それを書けたらいいなと思ったのですがいかんせん書き方がわからない。どうしよう。
でも書けない書けないと喚いていても仕方がないので、自分にできるだけの形に仕上げてようやく完成に至りました。色々と悪あがきもしましたが、この物語の中にひとつでもそんな感覚をつかめる部分があったらとても嬉しいです。
また読んでくださった方に、嶋津さんに話してみたかったこともあったので書いておきます。
わたしはとても優柔不断です。今までいくつもの大切なことを誰かに決めてもらってきたような気がしています。
たとえばおもちゃを買ってもらえなかったこどもが癇癪をおこしたとして、それが「買ってもらうための手段」ではなく純粋に気持ちが溢れ出したものだったなら、彼がおもちゃを手にできるかどうかは両親に委ねられることになります。
ざっくり言うとこういう感じ。何かの決断を迫られらとき、こどもの頃は誰かが導いてくれていたような。でもおとなになれば何でも自分で決めるようになる。でも急にそれができるようになるわけじゃなくて、みんな少しずつ練習してきたんじゃないだろうか。
この物語の主人公もそうやって千明に手を引いてもらったんじゃないだろうか。その哀しみを経てひとりで立つようになっていくんじゃないだろうか。
そういう感覚が正しいのかどうか、わたしにはまだわかりません。わからないから書きたくなります。
*
なんだかんだと長くなってしまいました。
最後になりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。素敵なコンテストを開催してくださった嶋津さんに感謝です*
今年の冬は一段と寒くなるようなので、どうかお体に気をつけてお過ごしください。
作品を閲覧していただき、ありがとうございました! サポートしていただいた分は活動費、もしくはチョコレート買います。
