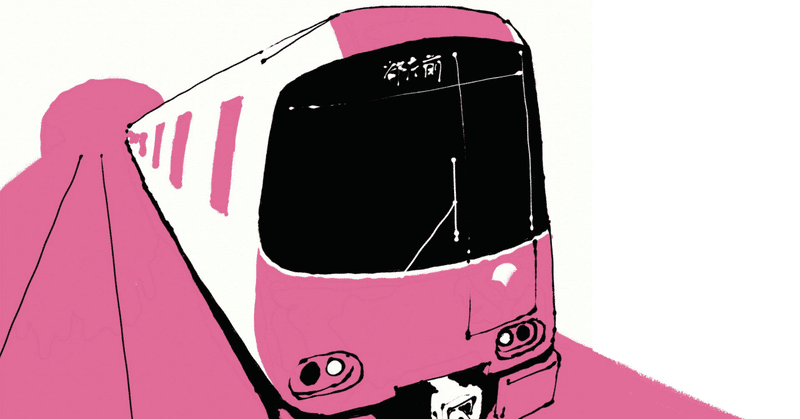
【短編小説】都営大江戸線
「恋人ではないの?」
右足にストッキングを通しながら聞いた、聞かないと勝手に恋人にしそうだったから。
「そうだね、恋人になってなかったね。」
靴下どこやったっけ?と探しながら答える。
「ここにあるよ。」
布団の中に隠れていたグレーの靴下を差し出してもう一度聞いた。
「恋人にはなれないの?」
「あ、どーも。」
彼は左足に靴下を通しながら言った。
「岡山と東京じゃ南極と北極みたいなものだよ。」
右足に靴下を通すと少しよろついた。
「遠いよなー。」
「じゃあ恋人になれないんだ。」
「ゆっくり考えようよ、これで終わりってことはないから。」
2回目のデート。食後のホテル。恋人になれないならこれで終わりにしたかった。「あんたさあ、いつも都合のいいデリヘルみたいだよね」って言われたことを思いだした。ああ、そういう感じなのかな。ピアスのキャッチをはめて、鏡を見ながら髪の毛を手櫛で整えた。鏡越しに彼と目が合う。
「フロントに電話して、9番。帰りますって。なんかそういうシステムらしい。」
きっとこれで終わり。返事はせずに電話をして、フロントのおじさんよりも低いトーンで帰りますと告げた。プツンと聞こえて、受話器を置いた。いつもの癖で電話は切れてから切ったけど、今日は先に切りたかった。
「ねえお金、ここは割勘にさせてよ。」
せめてもの反抗で。食事もご馳走してくれたし。デリヘルじゃないし。
「今日はいいよ、次払って。そうしたら次も絶対会えるから。ね、ゆっくりさ。」
恋人になれないならこれで終わりにしたいんだけど。とは言えなかった。
特別だけど恋人じゃないよと言った彼は、ホテルから駅までの帰り道、肩と腕が何度かぶつかった何度目かで手を握った。都営大江戸線はいい思い出がないんだよなーとぶつくさ言いながら。
「1年前に別れた彼女がさ、住んでたんだよなー。13年付き合っててさ。」
どうでもいいのに、どうでもよくない感じで呟く。やきもちを焼かせたいのか、彼女にはまだ到底適わないからと言いたいのか。深くは聞けなかった。13年の月日に終止符をつけるってどんな気持ちなのか。線香花火みたいな恋ばかりしてきた私には分からない。生きた心地がしなかった1年とSNSで投稿していた彼の記事を思い出す。
時節は弥生。杉だか檜だかのアレルギー反応で、くしゃみを5回続けてした。それと同時に電車が目の前で停まった。ガラス越しに映る目が潤んでいる。目を閉じる前に拭かないと流れそうだ。「離れてお待ちください」という車掌のアナウンスで手が離れた。流れずにすんだ。最終電車、勝どき行きの電車に乗り込む私を見送る彼が小さくなっていく。
37歳の彼。32歳の私。私たちのゆっくりはたぶん違う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
