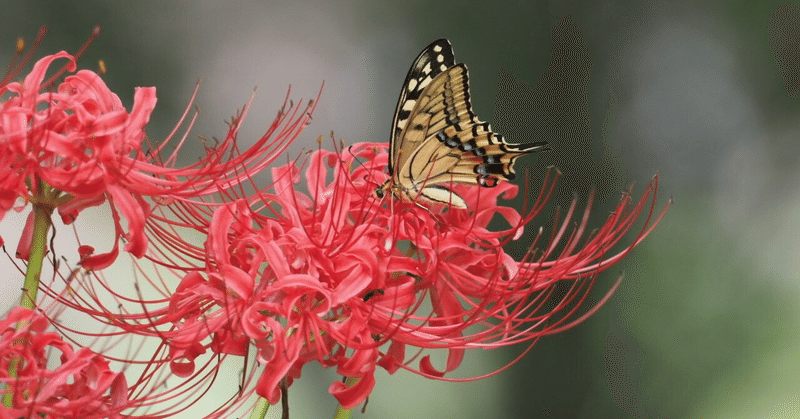
「SFマガジン 百合特集」読書会レポート試し読み(『ますく堂なまけもの叢書⑥平成の終わりに百合を読む 百合SFは吉屋信子の夢を見るか?』所収)
「SFマガジン」が導く
「百合」に満ち溢れた世界
益岡
開始の時間になりましたが、この読書会に並々ならぬ情熱を燃やしておられた銀河さんがちょっと遅れておりまして……
ティーヌ
銀河さんは、この「SFマガジン 百合特集」の担当編集者である溝口力丸さんが登壇した「書泉百合部ミーティング」(二〇一九年一月二十五日、書泉ブックタワー秋葉原にて開催)にも参加されていましたし、「この特集号には言いたいことがたくさんある!」と折に触れておっしゃっていましたから、気合いが入っていると思います(笑)
益岡
そんな事情もございますので(笑)この読書会に先んじて行われた吉屋信子『屋根裏の二處女』読書会の様子など振り返りながら、到着をお待ちしたいと思います。
今回は二つの読書会レポートを併録することで「百合」について考えようという趣向です。吉屋信子読書会については、その仕事を百合小説の「祖」と捉えて読み込んでみようという意識で僕は臨みました。課題作はごくごく初期のものでもありましたし、かなり古典的な少女小説風味の作品だと予想していたので、今話題になっている百合作品とはかなりの断絶があるのではないかと、そういう覚悟を持って読み始めたのですが……読み終えてみるとですね、これは『少女革命ウテナ劇場版 アドゥレセンス黙示録』だった。
美夜日
『ウテナ』だったの!?
益岡
まあ、『屋根裏の二處女』が『ウテナ』なのではなく、『ウテナ』の制作陣が百合の歴史をよく踏まえていたと受け取るのが順当なわけですが(笑)
『屋根裏の二處女』は、主人公の女の子二人が、女性としての全く新しい未来を目指して二人きりで歩んで行こうと決意するラストシーンがとても印象的なのですが、これが「ウテナ劇場版」のラストシーンと酷似しているというか、響きあっていて、「これはまさしくウテナじゃないか!」と盛り上がった(笑)
だから、思ったより断絶はないな、と個人的には感じられたんです。こうした「百合特集」の雑誌が出ると、必ず「作品ガイド」が用意されますが、その中で『少女革命ウテナ』という作品は非常に大きな役割を担わされています。今回の「SFマガジン」でもアニメの部の筆頭格にあげられていますから、アニメ界における百合代表というか、百合アニメの古典と考えても良い作品だと思います。現在の百合ムーブメントは、活字よりも、コミック・アニメなどの視覚・映像メディアから派生した部分が大きいと思いますので、ここでまず、百合小説の祖と現代の百合ムーブメントの祖は繋がったと言ってよいだろう、と。
この「百合特集号」が現代の百合ムーブメントの象徴で、最先端なのだとすれば、これはすごくいいかたちでバトンが渡ったな、と嬉しく感じました。
駄々猫
「百合ブーム」が来ているという実感は、個人的にはそれほど大きくないんですけど、この「SFマガジン」は、本当に、そんなに売れたの? 刷り部数が少ないから増刷になったんじゃなくて?
益岡
もちろん、そうした面があるのは事実です。この雑誌を取り巻く状況はそもそも、決して良くはないという認識です。
「SFマガジン」は元々、月刊誌でした。それが隔月刊になったのは二〇一五年。同じく月刊誌だった「ミステリマガジン」も隔月刊になり、交互に刊行されることになった。これは僕には結構ショックで……いわば、二つの雑誌が一つになったというか、月刊誌を半減させたというのに等しいわけです。ともに歴史のある媒体ですし、特にSFは新しい国内作家がたくさん出て来て「夏の時代」を迎えているという印象があったから余計に出版界の厳しい状況を感じざるを得なかった。これが、「専門小説誌を紙で刊行する」という事業の現実なんだな、と。
ただ、それでも、この雑誌の普段の水準から考えればずば抜けて売れたということは間違いないと思います。発売前からネット書店は軒並み売り切れでしたし、発売後もしばらく、リアル書店でも品薄な状況が続きました。創刊以来初の三刷というのは大きな記録だとは思います。
駄々猫
たしかに、普段通り刷ったら全然足りなかったというのは間違いないもんね。
益岡
それだけ「百合」というテーマが注目されていることの証明ではあるのかな、とは思いますね。
ただ……この特集で、意外というか、驚いたのが、ボリュームの少なさ。実際には、特集に割いている誌面は一〇〇頁もないんですよね。
神崎
うん、私も意外に思った。たとえば「ユリイカ」が特集を組むときは、ほとんどまるまる一冊が特集ページだよね。
美夜日
はい。私はBL好きで、「ユリイカ」は何度かBLを特集していますが、頁も内容もかなり充実していて、毎回満足しています。金田淳子さんや三浦しをんさんなど、論客も豪華。それぞれ本当に詳しい人たちが自身の得意分野について寄稿したり対談をしたりしているので、記事のバリエーションも豊富で面白い。それに比べると今回の特集は些か淋しい印象を受けました。
益岡
「ユリイカ」は既に「百合特集号」も刊行しています。こちらは二〇一四年十二月号ということなのでちょっと前なんですけど、百合の金字塔である『マリア様がみてる』(集英社)に関する著者インタビュウなど、確かにコンテンツが豊富で充実しているという印象です。
たた、当時この「ユリイカ」が出たときも思ったんですが、作品リストはなんだか淋しいというか、あっさりしている印象は持っていたんです。
ティーヌ
私も、この「ユリイカ」の特集号は読んだと思うんですが、あまり印象に残っていない。ただ、「百合特集号」に限らず、最近の「ユリイカ」には若干、そういう印象は持っていて、広く浅くというか、バリエーションはあるけど、特集全体としては、そんなに強く記憶に残らないというか……
益岡
まったく同感。個人的には、これは「ユリイカ」の問題というよりは、「百合」をとりまく言説全般にいえることなんじゃないかと思っているのだけれど、みんな「百合」について語るときに、なんか当たり障りないことを言って終わっているような気がするんですよね。
ティーヌ
わかる。なんか、ショックなことが何も起こらないっていう感じ。
益岡
たとえば、今回の「SFマガジン」においても、「〈コミック百合姫〉編集長インタビュウ」なんか、そつなくまとまっているというか、「百合」に関する認識については、特に反発を感じるところもないわけですよ。もちろん、これは「入門編」を企図しているから「易しく入っている」という見方は出来るわけだけれど、この「初心者が読むから易しく入ろう」というコンセプトというか、雑誌の空気は「ユリイカ」とも共通している。つまり、二〇一四年からずっと、「百合」は易しく、優しく語られ続けてきている。それでいいのか、という。
美夜日
益岡さんにとってカルチャーショックを与えられるような言説は、「百合」からは何も生まれていない、ということですか。
益岡
全体的な印象としては、その通り。ただ、今回の「SFマガジン」を読んで、「百合」を感じるセンサーみたいなものが自分の中にも備わっていて、且つ、それに気づかず生きて来たんだなと実感できる場面は増えてきたように思っています。
例えば、最近までTBSの「日曜劇場」枠で放送されていた「グッドワイフ」。
常盤貴子演じる主人公は、結婚をして一線を退いていたのだけれど、唐沢寿明演じるエリート検事の夫が闇献金疑惑で逮捕されたことをきっかけに弁護士として復帰する。そのきっかけを作ってくれたのが事務所の上司で研修生時代の同期である小泉孝太郎。この作品は一話完結の法廷ドラマでありながら、夫の不正を巡る検察組織の対立を描いた長篇サスペンスでもあり、夫と上司、二人のイケメンが美人の主人公を取り合う三角関係の恋愛ものでもあるというてんこ盛りの内容なのですが、それが最終盤に一転して、百合ドラマになるんです。
駄々猫
ちょっと、情報量が多くて何を言っているんだかわからない(笑)
益岡
うん。自分でもちょっとよく分からないんですが(笑)、常盤貴子には仕事上のパートナーというか、事務的なことをアシストしてくれるアソシエイトがいるんですね。この女性を水原希子が演じているんですが、彼女は凄腕の情報屋でもあって、違法すれすれの方法で裁判に有利な情報をとってきてくれる。最初は冷たい、無愛想な人物として描かれるんですが、常盤貴子が主人公らしく頑張るのを見て、だんだんと距離が近づいていく。
慣れない仕事に加えて、逮捕されているのに存在感を示そうとちょっかい出してくる唐沢寿明や、好きだけど、そんなには好きではない小泉孝太郎にお疲れ気味の常盤貴子にとって、水原と二人きりで食事をする時間は、「唯一の幸せ」になっていく。
ティーヌ
なんか、怪しくなってきた。
益岡
そう。ただ、そんな二人の友情が壊れざるを得ない水原の秘密が、そこで明かされるんです。それに向き合わされる二人のシーン。本当にお互い、大好きなんです。でも、許せない。許すわけにはいかないと心を鬼にする常盤貴子。二人は決定的な断絶を迎えて、でも、それぞれひとりきりになったときに、激しく泣き崩れるんです。もう、号泣。なんだ、これは、大変なことになったと視聴者である僕は思う。そして、気付くんです。これ、完璧に「百合じゃん」と。
一同 (笑)
益岡
でもね、この「SFマガジン」を読んでいなければ気付かなかったかもしれない。テレビドラマでは昔から、かなり踏み込んだ女の友情が描かれてきているわけです。こんなね、お互い好きすぎて、でも別れなきゃいけなくて、それで大号泣、なんて場面を観てもね、僕は今まで通り、「激しい女の友情もの」として処理していたかもしれないんです。これが男同士の、しかも四十歳超えたおじさんと二十歳代の青年が離れ離れになるのが嫌で号泣していたら、「大変なことが起きている!」とちゃんと騒げると思うんですが、女性同士だとね、「こういうこともあるのかなあ」で終わってしまっていた可能性がある(笑)
そういう「百合センサー」を意識して、過去、自分が好きだった作品を振り返ってみると、「あれもこれも百合じゃねえか」という思いが湧き上がってくるんですよ(笑)
特に驚いたのが「29歳のクリスマス」というフジテレビのドラマ。テレビドラマ黄金期である九〇年代、ヒットメーカーだった山口智子の代表作にして、テレビドラマ通史においても名作の一本に数えることに反対する者はいないであろうというほどの傑作です。
ひとことでいえば、アラサーを迎えた男女三人の友情物語。そして、それにそれぞれの抱える不器用な恋愛が絡んでくる。
山口智子と松下由樹、そして柳葉敏郎という女二人、男一人のトライアングルはとても安定した友情関係で結ばれていて、恋愛関係に発展することなどありえないというような結びつきがありました。本人たちもそれを信じていた。だから借金にあえぐ松下は、柳葉がひとりで暮らす一軒家に間借りすることになります。でも、最終的には、この二人は肉体関係を持ってしまう。それでぎくしゃくした空気をおさめるために、後に山口も加わり、三人が一つの家に暮らすという状況になる。それなりに関係を修復していく三人。各人の恋愛問題もあり、二人の一夜の関係が落とす影は薄まっていくように思われました。
しかし最終盤、この関係は急転する。柳葉は自分の恋が成就して、高嶺の花と目されていた水野真紀演じる恋人と結婚することになり、仙台へ旅立っていきます。家はそのまま、松下と山口で使うことに。そこで松下は、「実は柳葉との子がお腹の中にいる」と山口に明かします。しかも、柳葉にはそれを告げず、ひとりで産んで育てるという。驚いたのは山口智子。「そんな大事なこと、伝えないわけにはいかないでしょ!」と激怒です。それでも松下の決意は固い。何も知らない柳葉は旅立つ直前、晴れ晴れとした表情で、「ずっと生きて来て、今、一番、自分の人生が好きだ」と言い切る。その表情を観て、山口智子は決意するのです。
「しょうがないな、私が父親になってやるよ」
ティーヌ
え! 百合じゃん!(笑)
美夜日
めっちゃイケメンじゃないですか、山口智子!
益岡
そうなのよ。でも、こんな物凄い展開がありながら、僕はこのドラマが「百合」としても解釈出来るだなんて、これっぽっちも思っていなかった。これは一九九四年の放送ですから、もう四半世紀が経っている。四半世紀のあいだ、こんな問題発言を見過ごして来たのかと自分の鈍感さに慄いたわけです。
ただ、一方で、この解釈に至るにはかなりの無理というか、技術が要ることも確かなんですよ。このドラマはほぼ「異性愛」のいざこざで出来ているし、主題歌はマライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」。いまやクリスマスソングの定番で、ハッピーな異性愛ライフを全力で彩ってきた名曲です。この作品は、そんな一曲を全国に知らしめたドラマなわけです。まさかそれが、最終回に至って「百合」に転じていたとは、普通は思わない。それが可能になるのは「百合センサー」が、「百合受容体」が、機能してこそなわけです(笑)
そう考えてみるとね、今まで、ただの「女の友情もの」として整理してきた作品にも多くの「名作百合」があったんじゃないかと思えてきた。
もう一つテレビドラマの例を挙げれば、恋愛の神様と謳われる脚本家・北川悦吏子の実質的なデビュー作にあたる「素顔のままで」(一九九二年、フジテレビ)は、安田成美、中森明菜をダブル主演に据えた女の友情ものですが、最終回で安田が病に倒れ娘を遺して命を落とした後、その娘を育てているのは、親友だった明菜なんです。離婚したとはいえ、この娘の父親である東幹久は存命なのにもかかわらず(この作品でも女たちは男に内緒で子どもを生んでしまうんですが)、売れない俳優である明菜が親友の娘を育てるんです(後にダンサーとして成功はするんですが)。これ、おかしいよね。
ティーヌ
おかしい。そして、これはまさに百合です。
益岡
そう。さすがにこの作品は当時の僕もちょっとおかしいと思っていましたが、それでも、安田と明菜のあいだに恋愛関係は見出していなかった。やっぱり「女の友情もの」だったんです。でも、今、最終回で娘と散歩をしていた明菜を思い出すとき、これは完全に、友情を超えた何かが二人のあいだには走っていたし、この義理の母娘のあいだにも何か特別な思いが生れていくのだろうと感じてしまう。それは僕が、この「百合特集号」によって、百合受容体に目覚めたということなんだろうと思うんです。
しかもこれはフジテレビドラマの看板枠、「月9」の大ヒット作です。恋愛ドラマの代名詞と謳われたこの枠の、名作中の名作が「百合」であったというのは、百合作品の歴史においてもっと大きく取り扱われるべきトピックであると思うのですが、残念ながら誰も触れていない。逆に言えば、そういう発見・発掘をしていくための機能がまだ、あらゆる人々の中に眠っているというのは、とても愉快なことだと感じる。
だから、そういう作品との出会いというか、再会を得られたこと、それを可能とする機能に気づかせてもらえたことについては、僕は率直に「SFマガジン」に感謝したいと思っています。
ティーヌ
今の話で私が思い出したのが「やっぱり猫が好き」(一九八八~一九九一年、フジテレビ)。これ、年配のレズビアンにものすごくファンが多いんです。三姉妹の話なんですが、女性だけの朗らかな生活を扱った緩い描写の中に、レズビアンたちはしっかりと官能的な空気を読み取っている。異性愛を介在させないところにあるエロスが感じられるというのが人気の理由なんです。
益岡
そういう視点で「やっぱり猫が好き」を捉えたことはまったくありませんでした。
ティーヌ
もちろんドラマだしフィクションなんだけれど、ちょっと、ドキュメンタリータッチな雰囲気もある。三姉妹という設定なんだけれど、女子三人の共同生活を描いているという色合いが濃くなっていて、レズビアンの視点から捉えるとときに色っぽく見える。
神崎
紹介されている作品で意外に思ったのが、月村了衛さん脚本の「ノワール」というアニメ。女子高生と暗殺者の女性、さらにもうひとりの謎の少女が中心の話なんだけど、これまでずっとこれを百合とは捉えていなかった。
あと、私は今まで、BLと百合は対極にあるものというか、対になるものだと思っていたんです。でもこの「〈コミック百合姫〉編集長インタビュウ」を読んで、セックスを伴う恋愛関係を必須としている「BL」と、何かしらの強い、濃い感情が二人の間に流れているという時点で成立する「百合」とは対ではないんだな、と認識を新たにした。
BL研究のマスターピース
「よしながふみ対談集」と「百合SF」
美夜日
ここちょっと、柴田さんと梅沢さん、許せないですね(怒)
一同 (笑)
美夜日
この、BLへの偏見に満ちた解説は許せないです(怒)
益岡
僕もこの部分のBLへの認識については違和感があった。ただ、この点について触れるにあたって紹介しておきたい本があって、それが、よしながふみさんの対談集『あのひととここだけのおしゃべり』(白泉社文庫)。この一冊はBLという表現を考えるにあたってマスターピースになる作品だと個人的には思っています。
僕自身のBL観というものも、この本にかなり影響を受けているんですが、その中でも重要だと思うのが三浦しをんさんとの対談です。
ここでよしながさんが「やおいという関係とBLは違う」ということを明確に打ち出す。「やおい」という関係は男同士だけに限ったものではない。女同士でも、異性間でもあり得る関係なんだというんですね。
「やおい」は恋愛とは限らない、なにか「同志」的関係というか……
美夜日
なんらかの関係性があれば、熱い関係性が感じられさえすれば「やおい」であるという……
益岡
それは常に一緒にいるとか、べたべたいちゃいちゃしているとか、そういうことでは測れない。ここでは、テレビドラマ「きらきらひかる」(一九九八年~二〇〇〇年、フジテレビ)が取り上げられているんだけど、鈴木京香演じる法医学者と松雪泰子演じる警部補が普段は特に仲が良くも見えないんだけど、鈴木京香がピンチになったとき、松雪泰子がぱっと来て助けたりする。鈴木京香は「なんで助けてくれたの、仲良くもないのに?」って顔をするんだけど、松雪泰子が「わたしたち友達じゃない」と言って去っていく。つまり、これが「やおい」だ、と。
美夜日
この連帯関係というか、そこに妄想の余地があって、受け取り手の創作欲を刺激していく、そんな関係ですよね。だから、たとえ、ヘテロ間でも「やおい」関係が成立しうる。
ティーヌ
その関係はフェミニズム的にも正しいというか、好ましいもののように思う。自立した個人と個人だからこそ成立しうる関係ってことでしょ。なんか、「やおい」という言葉が一気に好きになった。
益岡
「フェミニズム」という言葉についてもこの対談集では大きく取り上げられていて、「フェミニズム」という言葉やその言葉の持つイメージが作品に出てしまうと、それだけで拒絶感というか、読者が身構えてしまうので、よしながさんは自身がフェミニストであると名乗ることも、フェミニズムについて語ることも出来なかった。でも、三浦しをんさんとの対談を通して、「自分がフェミニストだ」といえるようになった。ただ、「私が考えているフェミニズムはどんなものか」とまず示さなければ、その先が聞いてもらえない、伝わらないという実感はある、と。これはつまり、セクシュアリティをめぐる作品というか、ジャンルについて語るにあたっては、前提として、自身にとっての語の定義というか、世界観を示していかなければならないということでもあって、実際、「BL」というジャンルを語るにあたって、二人は「自分にとってのBL」について議論して明らかにしていこうとするわけです。
ここにおいて出てきたのが「やおい」という概念についての……いわば新解釈ですよね。少なくとも僕にとっては「やおい」というのは男の子同士の極端な恋愛物語を示す言葉であって、語源は「やまなし おちなし 意味なし」であるというのが定説だった。それがこの二人の対談によって革命的に塗り替わり、さらにこの関係が男性同士に限定されなかったがゆえに、僕にとって現状、「百合」として受容されている多くの強い感情は、「やおい」に包括されてしまっているようにも思う。僕の「百合受容体」が鈍感だった一因は間違いなく、この一冊にあると思うんです(笑)
それでね、美夜日さんが憤った百合男子たちのBL観に話を戻すと、このよしながさんと三浦さんの素晴らしい対談の中にもね、残念ながら、今回の柴田・梅沢間のやりとりに近い図式が感じられる箇所がある。
それが、女がBLを愛でるとはどういうことかについて語った箇所。よしながさんが「女がBLを愛でるということと男がレズが好きっていうこととは違う」と断言する。その一言だけで片付けられて、三浦さんも特にその点に反応はしない。このばっさり置き去りにされてしまった「男がレズが好き」には、柴田・梅沢の「BLは肉体が必須」という切り捨て方に似た構図を感じるんです。ちょっと、これは重要な問題だと思うので、後でじっくりお話をしたいと思います。
一方で、今回、こだわりたいと思っているのが、「ちゃんと創作について語りたい」ということなんです。「百合とは何か」とか、BLやフェミニズムとの関係とか、そうしたジャンルに関わる概念的な部分についてはすごく面白い議論だし、出席者も読書サロンに縁のある方が多いので盛り上がってしまうと思うんですね。でも、この特集はかなり創作メインというか、「百合SF」という新しいジャンルを実作によって示そうという意欲が高い誌面になっていると思うんです。そういう点でも、ちょっと作品論というか、実作への検討はしっかりやっていきたいと思っています。
個人的には、この特集で初めて伴名練というひとを知ったんですね。この「彼岸花」という作品、僕の中では、「何もかもが良い」と(笑)
美夜日
絶賛じゃないですか(笑)いったい、どうなさったんですか?
益岡
そんな、僕が誰かの小説を褒めたらおかしいみたいな……僕は結構、褒める方だと思うんだけど(笑)
いや、それまでの作品がね、先鋭的というか、「百合SF」という新しいジャンルを成立させるためにいろいろな研究成果を一生懸命発表しているという気負いが感じられたのに比べて、最後のこの作品がどっしりと、「百合の伝統」みたいなものを踏まえたウェルメイドな存在として鎮座していてくれたので、なんか安心したというか(笑)
神崎
私は正直、掲載作品を順番に読んでいっても、なにひとつピンとくるものがなくて、半分くらい読んだところで、この読書会への参加もやめようかと思った。でも、それをわが家でこぼしたら、相方の益岡に「最後に載ってる作品がとてもいいから、とりあえずそこまで我慢して読んでみて」と力説されて、最後の作品を読んでみたら「ごめん、良かった」と。わが家では盛り上がりました。
美夜日
たしかに、他の作品は異色作というか、「不在系百合」という感じですよね。
神崎
不在系百合……そんな言葉が……
美夜日
だって、いないじゃないですか。冒頭の宮澤伊織「キミノスケープ」なんて、登場人物自体がいない。
※この先、かなり議論は過激になってまいります(笑)
ご興味頂けた方は、文学フリマ東京などのイベント、大阪阿倍野の「古書ますく堂」や神田神保町の「PASSAGE」で直接手に取ってご覧いただけますので、是非、お出かけください。
通販はこちら⇒https://ichizan1.booth.pm/items/1693873
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
