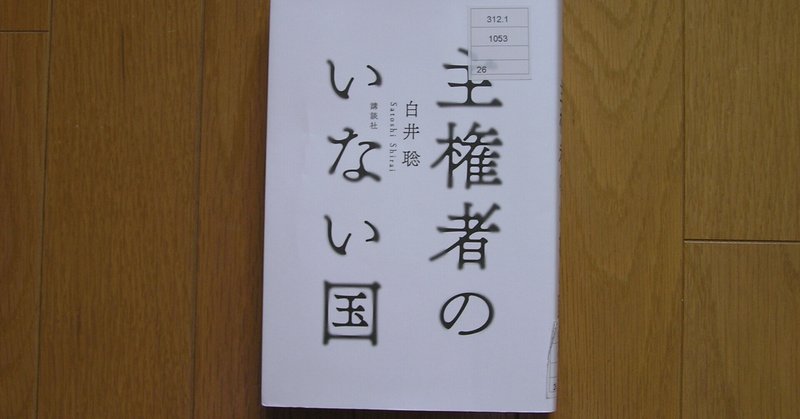
「この国は、10年前にすでに滅んでいた」ことにいまさら気づかされた! 白井聡著『主権者のいない国』を読む 1 序章 未来のために想起せよ
白井聡さんの近著『主権者のいない国』の冒頭を読んで、心から「私たちは運がよかったのだ」ということを痛感させられた。2011年3月11日の大震災に際して、F1(東京電力福島第一原発)の1~3号機の水素爆発が「水蒸気爆発」でなくて運が良かったと思っていたわたしのあさはかさを思い知らされた。以下、本書から引用する。
破滅の淵を想起する
本書が店頭に並ぶ頃、あの3・11からちょうど10回目の春を私たちは迎える。この10年は、私個人にとっても、日本という国にとっても激動の歳月であった。本来政治思想史の研究者である私は、3・11をきっかけとして『永続敗戦論 戦後日本の核心』(2013年、太田出版/2016年に講談社+α文庫に収録)を書き、それ以降、現代日本政治に関する時事的な発言に踏み込むことにたった。それは、研究者・文筆家として思いがけない成り行きであったが、私を駆り立てたのは、「何とかしてこの国の崩壊を止めなければならない」という思いだった。
10年前、日本を襲ったのは、文字通りの激震だった。巨大津波による被害だけでも筆舌に尽くしがたいものかおるが、経験したことのない種類の惨禍をもたらしたのは福島第一原子力発電所の過酷事故だった。
当時の不安な気持ちを思い起こすだけでも胸苦しさすら感じるが、それでもやはり振り返っておくべきだろう。私たちが東日本壊滅という事態を避けることができたのは、ひとえに《運がよかった》からであった。
多くの危険きわまる事象のうち最も危険であったのは、4号機の核燃料プールの件だった。そこには1331体の使用済み核燃料が納められ、うち548体はつい4ヵ月前に原子炉内から引き抜かれたばかりの、高温の崩壊熱を放つものだった。そのプールに注水できなくなった。注水できなければ当然、プールのなかの水は核燃料の崩壊熱によって蒸発し、燃料がむき出しになる。アメリカは懸念を深め、原子力規制委員会のグレゴリー・ヤツコ委員長は「プールの水は空だ」と発言した。
使用済み核燃料は、劇物中の劇物である。もしそれがむき出しの裸の状態で置かれていたら、周りの人間は即死するほどの高線量を放つ。ゆえに、4号機の核燃料プールの水が空になり、むき出しになった使用済み核燃料が溶け出すということは、誰も福島第一原発に近づけなくなるということ、したがって、メルトダウンの事故処理も全くできなくなること、を意味した。だから、当時の菅直人政権は、最悪のシナリオとして、首都圏を含む東日本全体の壊滅を想定したというが、それは何ら大袈裟なものではなかった。この事態は、東日本壊滅というよりも、日本壊滅と考えたほうが適切であろう。また、日本にとどまらず、世界全体の自然環境に対する影響の観点からすれば、文明の終焉すらもたらしかねない事態だった。
この危機を救ったものは、《偶然》だった。三月12日の夕刻、4号機上空を飛んだヘリコプターからの撮影により、核燃料プールに水があることが確認される。なぜ、ないはずの水があったのか?
それは、核燃料プールに隣接する「原子炉ウェル」という部分に張ってあった水と、原子炉ウェルにつながる「ドライヤー・セパレーター・ピット」という部分の水が、プールに流入したためだった。原子炉ウェルとプールの間には仕切り板かおるのだが、地震の振動などにより仕切り板がずれて流入したとみられる。そして、われわれがとりわけ「幸運だった」というのは、原子炉ウェルは、通常水が満たされる場所ではないからだ。なぜそこに水があったのか?
事故前年の末に、4号機では原子炉の「フンユラウド」と呼ばれる部分の付け替え工事が始まっていた。このシュラウドは、長年の使用により放射化しているために、それを通過させる原子炉ウェルには水が張られていた。しかも、その水は、2011年3月7日に抜き取られるはずだった。そうならなかったのは、シュラウドを切断する際に使用する治具に設計ミスが発見され、そのために付け替え工事の工期が延びていたためであった。
もしもシュラウド交換工事が2011年3月11日に重ならなければ、そして工期延長がなければ、あの最悪のシナリオが招き寄せられたのである。私たちは、文字通りの破滅の間際にいた。このことは、どれほど強調してもし足りない。
かつ恐るべきことに、この状況の深刻さをその当事者たる東京電力の上層部は、全く理解していなかった。3月13日昼過ぎの時点で原子炉に注入する淡水がなくなり、吉田昌郎福島第一原発所長は、海水を注入するほかないと報告した。その直後の東電本社と現場とのテレビ会議の模様が後に報道されるが、そこで東電幹部から発せられた言葉は耳を疑わせるものだった。
「いきなり海水っていうのはそのまま材料が腐っちゃったりしてもったいないので、なるべくねばって真水を待つという選択肢もあるというふうに理解して良いでしょうか」
この幹部が懸念したのは、海水を注入された原子炉が使用不能になることだった。吉田所長は「理解してはいけなくて、(中略)今から真水というのはないんです。時間が遅れます、また」と即座に返しているが、この会話は狂人と正常人のやり取りに聞こえる。メルトダウンはもう間近に迫っていた。そんな原子炉を二度と使えるはずがない。
そして何よりも、この瞬問は、日本が破滅するかどうかの瀬戸際にあったのだった。東電幹部の言葉からは、そのような認識と切迫感が一切感じられない。「原子炉が使えなくなると我が社に何百億円も損が出る」という懸念かおるだけだ。要するに、この人物は、「日本が終了してしまうこと」と「東京電力という会社が何百億円か損失を出すこと」とを天秤に掛けてどちらが重大であるのかを判断できなかった。否、東電の損失すら考えていなかったかもしれない。大失態を犯してしまった原子力部門に属する自分の出世の困難を思っていたのかもしれない。かかる人物を形容するにあたり、「狂人」以外に適切な言葉を私は知らない。
危機を適切に認知できない人々には、同時に責任感もモラルもない。ただひたすら空っぽである人だちからなる集団が、この国の「選良」として君臨してきた挙句に、あの事故を起こした。なぜ、日本はこんな国でしかないのか、こんな社会でしかないのか。
その根源を見定めようとするならば、「あの戦争(第二次世界大戦)の未処理」という問題にまで遡らなければならないという確信に基づいて、私は『永続敗戦論』を書いた。あの事故における東電幹部や経産省関係者(原子力安全・保安院)、さらには「原子カムラ」の御用学者たちの姿は、丸出員男が昭和のファッショ体制を指して述べた「無責任の体系」そのものであったからだった。
だから、福島第一原発の事故は、未曾有の経験であったのと同時に、見慣れたものでもあった。つまるところ、3・11が暴いたのは、「戦後日本はあの戦争への後悔と反省に立って築かれてきた」という公式史観の虚偽性だった。私たちの社会が本当に後悔・反省しているのなら、「無責任の体系」は克服されていなければならない。しかし現実には、それは社会のど真ん中で生き延びてきたことを3・11は明らかにした。ならば、なぜかくも無反省でいられるのか。その根源的な理由は、日本人があの戦争で敗北したことを本当は認めていないというところにあることを私は『永続敗戦論』で主張し、かかる歴史意識を「敗戦の否認」と名づけた。
歴史観や歴史意識は、その社会の質に関わり、ひいては私たちの生き死にに関わる。3・11が突きつけたのは、私たちの社会は解体的な出直しを必要としているという事実にほかならなかった。最近やたらと増えている分断批判業者の連中は認めたがらないようだが、この時以来、日本社会は真っ二つに分裂した。それは、この事実を受け止める人々と何としてでも受け止めない(否認する)人々との分裂である。
どちらが多数派であるかは言うまでもない。ちょうど『永続敗戦論』の原稿を書いていた2012年12月の総選挙で第二次安倍晋三政権が成立し、そこで出来上がった権力構造が現在にまで続いていることは、まさにこの「敗戦の否認」という歴史意識から日本人全般が脱していないばかりか、そのなかにさらに深くはまり込んでいることの証明である。というのも、安倍音三こそ、政治の世界で「敗戦の否認」の情念を代表する人物にはかならないからだ。
ゆえに、この期間が日本史上の汚点と目すべき無惨な時代となったのは、あまりにも当然の事柄である。虚しい歴史意識は、社会を劣化させ、究極的にはその社会を殺し、場合によってはそこに生きる人間を物理的に殺す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
