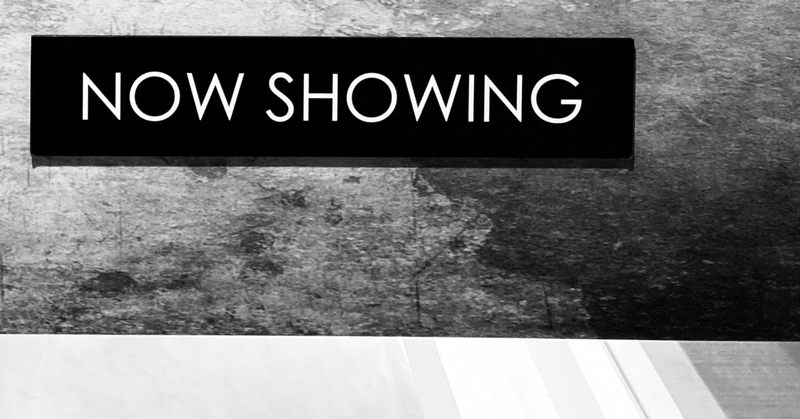
映画の思い出 (20代)
映画を観るようになったのは20歳を過ぎた頃からだった。大学3年生のとき、新入生に紛れてバンドサークルに入った。俺はそこでバンドや音楽の話だけしていればいいとばかり思っていたのだけど、音楽だけしか興味がない人間はほとんどおらず、むしろ音楽の話にはいい加減飽きた人間たちが映画やアニメの話で盛り上がっていることの方が多かった。俺はその話にまったくついていくことができず、カルチャーショックを受けたのだった。
映画ならまだしも、アニメは子どもが見るものだと思っていた。そしてアニメは、人気のある漫画をアニメ化しただけのものだと思っていた。俺の中では、アニメは漫画の二番煎じでしかなく、まだ漢字を読めない子どものために作られているのだと思っていた。
そもそも、深夜にアニメが放送されているという事実を知らなかった。深夜に放送されているということは大人が見るのだろうし、大人が見るということは「ドラゴンボール」とはワケが違うのだろう。そういえば、「すごいよ!マサルさん」がアニメ化されたときは、なんでこんな遅い時間に…と思いながら録画予約したのを覚えている。そしてそのときも、やっぱり漫画の方がいいやと思ったのだった。
あの世界をまさか、大学に入って知ることになるとは思ってもみなかった。日本中から集まった若者たちが熱くなってその話をしているのだから、きっと何か価値があるのだろう。そしてようやく人生で初めて、アニメや映画をちゃんと観てみようと思ったのだった。みんなの話題についていくというよりは、遅れを取り戻すために、自分もそれくらいのことは常識として知っていましたよと後から言うために。
ちょうどその頃、バンドメンバーがレンタルビデオ屋で働いていて、スタジオのついでに毎週立ち寄るようになった。どれから観ればいいのかもわからないまま手当たり次第借りていき、忘れないようにノートにメモをとった。鬱を経験したあとだったことも大きかったかもしれない。基本的に疲れていて、これまでのようには動けなくなっていたので、じっとしているだけで物語が進んでいく暇つぶしが俺にうってつけだった。たしか中原昌也がどこかで「疲れている人間じゃなきゃ映画は観れない」という内容のことを言っていた覚えがあるのだけれど、そのことをたまに思い出す。何をやってもうまくいかない最悪の日々を迎えて、俺は映画を観れるようになった。
観れるようにはなったが、それを楽しめるようになるのはさらに時間がかかった。100本くらい観たあたりでようやく、好きな映画と嫌いな映画のラインが明確になってきた。俺にとって一番重要だったのは、作っている人間の個性が映像や物語に現れていることだった。「監督=作品」、言い換えれば、「いくつかの作品の中に一貫した偏りを持っている監督」が好きだということだ。映画自体を観たことがなかった俺にとって、その偏りを感じるためには基礎訓練が必要だった。何がおもしろいのかわからないまま耐える。そして観れば観るほど見えるようになる。そんな訓練の中で好きになったのは、北野武、ソフィア・コッポラ、デヴィッド・リンチなどだった。
もう一方で、アニメに対する俺の了見の狭さを改めさせてくれたのは今敏だった。友人が「パーフェクトブルー」をオススメしてくれて、それを観てとても衝撃を受けた。しかし、「パーフェクトブルー」はあくまで実写可能なドラマという感じがするので、アニメの凄まじさを本当に感じたのは「妄想代理人」かもしれない。「ドラゴンボール」と同じ30分アニメシリーズでありながら、天下一武道会も人造人間も登場しなかった。かといってドラマとも違う。現実のトレースではなく、映画とは別のリアリティがあった。そこには、デヴィッド・リンチと似た感触があった。そしてその感触は音楽とも切り離せなかった。何を今さらそんなこと。さんざん遅れた俺は、陰鬱な日々と味気ない訓練を続けていくのだった。誰ともその話をすることもなく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
