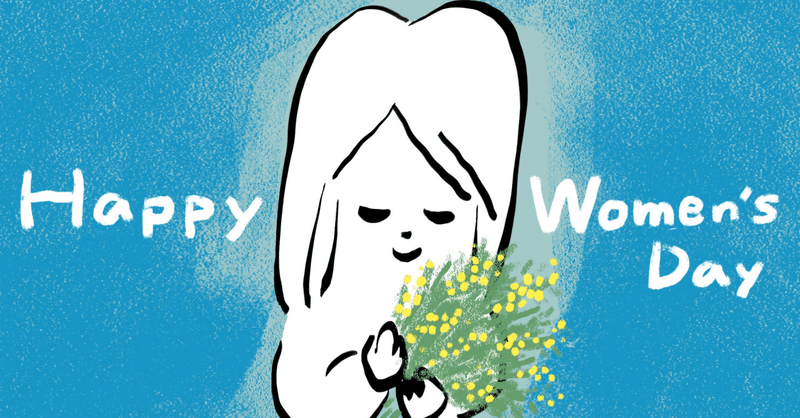
山口真由「世界一やさしいフェミニズム入門 早わかり200年史」
フェミニスト、というと、女性の権利を感情的に振りかざす人、というイメージが強いようで、本の中でも、そういう女性を揶揄した男子の話が出てきたりします。私も女性だからこその不遇を感じる時もありながらも、少しずつ良くなってきた状況の中で、男女平等について主張するのはやぶへびみたいな感覚がありました。つまり、何も言わなければそれほど嫌な思いをしない、けれど話題に出せば、やっぱり女性は家庭を第一に考えるべき、仕事は……みたいな話をされ、イヤな気持ちになるだろうと思っていました。だから、積極的にこの本を読んでみようと思ったわけではありません。
先輩女性から、「これ、読んだ方がいいよ」と言って手渡されました。正直すぐに読む気が起きなかったのです。
新人として入った頃は、女性職員は、仕事以外に毎日のお茶入れを課せられました。当時いた課はとても大きく40人以上に昼食時にお茶を淹れなければなりませんでした。不満を口にしたら、男性だって重いものを運んだり、高いところのものを取ったりしている、と返されました。それって毎日でしたっけ?
お茶淹れはその後、女性の多い職場に異動すると全くやっておらず、それから20年以上経過し、特に女性だからと差別されると感じることはなくなりました。特に育休・産休を取得していない女性の中は男性と同じように昇進している人もいます。
むしろ今は女性というよりは、母親である女性に対する差別があるように感じることがあります。差別というか、母親はこうすべき、という価値観です。私自身も父親である夫より、日常の中で多く負担していることがあると感じますし、サポートしてくれる実親には感謝しているものの、母親である私がやらないから代わりにやっているという考えを言葉の端々に感じます。身近な範囲だけでなく、社会全体にもそういう意識を感じます。そのため、働き続けることを辛く思う瞬間がないわけではありませんが、私も女性の一人として、子を育てる母親の立場として、組織の一部となり、個人として咀嚼しながら、組織のすることが、女性にも母親にも受け入れられるような働きかけをしたい、と考えています。
社会の半数は女性であり、少子化を憂いているわけですから、女性にも母親にも受け入れられなければならないのです。でもそれを真っ向から言うのではなく、仕事の裏にそういう想いを込めていたいと考えてきました。
だから、敢えてフェミニズムについて考える必要はないと思ってきました。
でも、この本、読んで良かったと思います。この本は、フランス革命以降の世界各地での、フェミニズムに関する様々な活動や著書について、系統立てて紹介しています。
第二次世界大戦後はその動きも急激になり、フェミニズムという大きなくくりで議論される活動も、よくその内容を見てみると、考え方が違っていることが分かります。さらに、LGBTQの議論が加わると、男と女だけでどうこう議論すれば事足りるわけではなくなってきます。
もちろんこうした話も興味深かったのですが、本の中では日本におけるフェミニズムについても、欧米に影響をされつつも、独自の発展をしたということで、1つの章を割いて詳しく語っています。
わが国のフェミニズム論争は、常に、母性を中核として展開されてきた。
最初の論争の事例として挙げられているのが、平塚らいてうと与謝野晶子の論争です。
母性が重要であるがゆえに、子どもの養育という母の仕事に対して、家計ではなく、むしろ政府が支給を行うべきという論を展開する。この母性保護が晶子とらいてうとの間の論争の主題となったのだ。
らいてうは支給を行うべきとし、それに対して
晶子は、今でいうところの新自由主義的であり、自助努力の有無による格差を肯定していた。だからこそ、晶子はその努力によって、男性も女性も経済的かつ精神的な自立を手にすることができると考えたのだ。
14人の子どもを、夫が収入がない時期も育ててきたという与謝野晶子の言葉の重みは大きいです。
またその他紹介されているものとして、アグネス・チャンが楽屋に子どもを連れて仕事をしていたことに端を発した論争があります。
子ども給付金(それよりは給食無償化などの現物給付の方がよいのではないかという議論も含め)、子連れ出勤など、今の時代でも結論が出ていないことをたどっていくと、この時代までさかのぼるのか、と思ってしまいます。
その他、本の中で興味深かったのは、カルチュラル・フェミニズムです。主流といわれるフェミニズムは、男女に生物学的な差異があるもののジェンダーにおける次元の差異はモラルやイメージによって作り上げられたとして、それをなくそうとしているものです。けれどもカルチュラル・フェミニズムは、男女の文化的な差異までも、”本質的”なものだと考えるのです。
1982年にキャロル・ギリガンという心理学者が『もうひとつの声』を出版しました。正義感の発達に関する研究をしている中で、既存の研究は男児を対象としているものが多く、そこに疑問を呈したのです。
ギリガンは、何が正しいかを語る女性たちの声の響きに、男性とは根本的に異なる特異性を見出して、それを「もうひとつの声」と呼んだ。
本の中で「ハインツのジレンマ」の話を聞いた11歳のジェイクとエイミーの反応が出てきます。「ハインツのジレンマ」とは、末期がんの妻を抱えるハインツは、薬剤師が開発した特効薬が高額であるため入手できない、盗むべきか、という話です。
ジェイクは迷わず盗むことを選びます。ですが、エイミーは、薬剤師を説得できないか、お金を工面できないか、もし盗んで自分が捕まったら誰が妻の面倒をみるか、といった具合に態度を決めることができません。従前の研究では、抽象的な思考から普遍的な正義へたどりつくことを評価するため、エイミーのような態度を低く評価します。でもこれは本当に低く評価されるべきなのでしょうか。
この状況をギリガンは「正義の倫理」とは別ベクトルで「ケアの倫理」という基準が存在するはずだと指摘します。「正義の倫理」はジレンマ問題を権利の衝突と捉え、誰かの権利のために他の権利が犠牲になっても仕方がないと捉えます。ですが、「ケアの倫理」においては、誰かが別の誰かに踏みつけられることそのものが目的の未達成だと考えるのです。なので、決して抽象性が低いわけではないと主張しています。
抽象性に関しては自分自身ではまだ解釈できていませんが、ただ、思い当たることがあります。私が子どもたちのケンカを仲裁するときに、自分の主張をさせた後に、すぐに相手の気持ちを類推させようとしてしまいます。まあ原因はどちらか一方が作ったとはいえ、それを上回る報復の繰り返しでどちらが良いとか悪いとか超えている段階が多いのですが。
この女性は「ケアの倫理」というベクトルがあるという考え方は、女性は家庭の中でケアを担うべき、という理論の補強に使われがちで、実際レーガン政権時の家族政策に利用されたといいます。
カルチュラル・フェミニズムが目指しているのは、その先にあります。
ケアの職業が、この社会において不当に低く評価されていると、このフェミニズムは主張するのだ。
なぜ看護師の給与は医師よりもずっと低いのか。
なぜキャビン・アテンダントの仕事の対価はパイロットよりもあがらないのか。
介護士は? 保育士は? 秘書は?
端的にいえば、”この世を支えるケアの役割=女の子たちのゴール”を正当に高く掲げるべきだというのが、格差を解消するためのカルチュラル・フェミニズムの方策となる。
著者は、日本のフェミニズムの根底を理解するにはカルチュラル・フェミニズムを理解しなければいけないと言っています。それは、日本のフェミニズムもやはり「母性」を大切に考えているからです。「母性」は「ケアの倫理」とかなり重なります。
一方で、日本の組織内のことを考えると、「根回し」のようなケアの倫理に近いこともあるようにも感じます。業務内容で本当にコミットする人間はもちろん事前に協議するのは必要ですが、本当にコミットする余地のない、無関係だけれど重鎮の顔を立てる、的な感じで話をしておかなければいけないことがあるのは、合理的とはいえないけれど男性特有のケアの倫理と考えると、まあやっていくしかないのかな、とも思ったりもします。
それにしても、介護士も保育士も不足が深刻です。さらに結婚を考えない人も増え、少子化も進んでいます。
もしかしたら、カルチュラル・フェミニズムの考え方に従って社会を変えていけば(単に給与の問題だけではなく、意見の尊重といった部分まで含めて)、看護師不足も保育士不足も介護士不足も、そして少子化も、変わっていくのではないかと思ったりもしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
