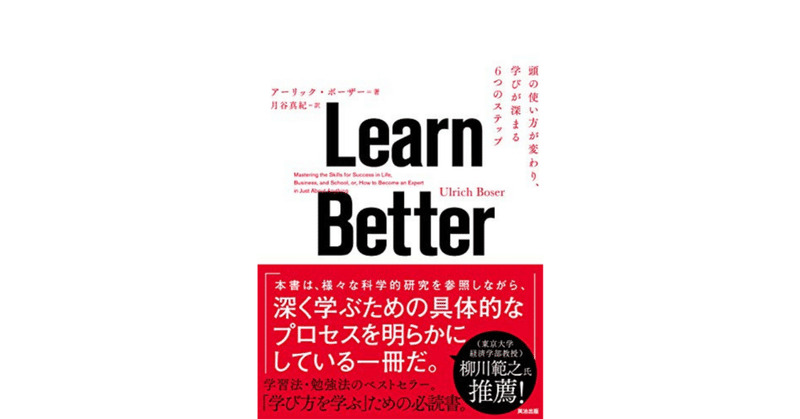
【お薦めの一冊】 学校では教えてくれない「学習の方法」 / 「Learn Better」 アーリック・ボーザー
今まで多くの本を読んできました。
その中には、私の人生に良い影響を与えてくれた本が沢山あります。
そんな本の感想を書き留めておくことで、私自身の備忘のためにも、また、これを読んで下さった方の本選びにも、少しでもお役に立てばと思っています。
1.学校では学習の仕方は教えてくれない
私たちは、小学校や中学校で当然のように毎日多くの授業を受けてきました。
国語・算数・理科・社会・数学・英語・・・
科目ごとに教わる内容自体は異なりますが、これら全てに共通することは、いずれも学習であるということです。
では、そもそも「学習」とは何でしょうか。
教科書を繰り返し読むことでしょうか。方程式や歴史年表を丸暗記することでしょうか。または、漢字の書き取りを10回行うことや、教科書に蛍光ペンで線を引くことでしょうか。
実は、私たちは今まで莫大な時間を学習に割いてきたにも関わらず、そもそも「学習」とは何なのか、また、「学習の正しい方法」について学んだことはほとんどありません。
本来であれば、私たちは、多くの科目を勉強する前に、その前提となる「正しい学習法」について学ぶ必要があり、そうすることで、より効果的に学習がてきたはずなのです。
本書では、そんな正しい学習法について、6つのステップで分かりやすく説明してくれます。
2.著者 アーリック・ボーザー氏とは
著者のアーリック・ボーザー氏は、学習についての研究を専門としている方で、ワシントンDCにある米国先端政策研究所(Center for American Progress)の上級研究員です。
また、学習に関するコンサルタントサービスを企業等に提供するThe Learning Agencyの創設者兼CEOでもあります。
このように、学習について、学術面だけでなく、そのノウハウを実践的に社会に提供するという活動も行なっています。
3.なぜ同じ授業を受けても人により理解度が異なるのか?
私たちは、小学校や中学校、人によっては大学まで、多くの授業を受けてきました。
同じクラスの同級生は、みな同じ教室に座り、同じ授業を聞いていたはずなのに、なぜ人によって理解度が異なり、テストで異なる点数を取るのでしょうか。
確かに、一部の生徒は塾に行っていたり、家で家庭教師に教わっていた生徒もいたでしょう。
しかし、同じ塾に通っている生徒でもテストの点数は異なりますし、家庭教師を付けなくてもテストで良い点数を取る生徒がいるのはなぜでしょうか。
これに対する一部(もしかすると大部分)の方の意見は次のようなものかも知れません。
遺伝的・先天的に生まれもった知性という才能があり、それにより、人によって理解が早い人もいれば、遅い人もいる。
世の中には、天才と呼ばれる人たちがおり、その人たちは学習を難なくこなせる生れつきの能力を持っている。
このような考えに基づけば、才能の無い人はいくら学習しても理解度は遅いままであり、才能のある人は大した学習をしなくても知識・スキルを習得できることになります。
しかし、本書では、このような考えを明確に否定しています。
このような「才能」といった考え方を否定し、天才と呼ばれるような人たちも、生まれ持った才能ではなく努力によってその能力を身につけていることについては、以下の書籍でも明確に述べられています。
私たちが、同じ授業を聞いても、つまり、同じことを勉強しても、その理解度・習得度に違いが出るのは、意識的か無意識的かにせよ、学習の方法を理解しているか否かによるのです。
学習の方法を知っているか否かで、習得の度合いと効果は大きく異なるのです。
4.学習とは授業を聞くだけや、テキストを読むだけでない。 自らの頭を働かせる「活動」である。
本書では、学習とは、講義を黙って聞くような受動的な受け身のプロセスではなく、主体的・能動的に頭を働かせる活動であると述べています。
つまり、学習とは、教科書をただ繰り返し読むことや、教科書にただ蛍光ペンで線を引くことではないのです。
5.学習の6つのステップ
それでは、上記で述べた「学習」=「主体的・能動的に頭を働かせる活動」の具体的な方法とはどのようなものでしょうか。
本書では以下の6つのステップで説明しています。
(1)価値を見いだす
(2)目標を設定する
(3)能力を伸ばす
(4)発展させる
(5)関係づける
(6)再考する
それぞれの内容を簡単に解説すると以下の通りです。
6.価値を見いだす

私たちは、どのような学習対象であっても、学習対象に価値があると思えないと、それを学ぶことは困難になります。
学習対象に価値を感じられなければ、そもそも、それを学習するモチベーションも湧きません。
では、この学習対象への価値はどこから来るのでしょうか。
それは、自分の生活・人生との関連性をどれだけ感じるかによります。
例えば、学校で古文や微分・積分を学習することについて、当然に価値を感じられる人はどれだけいるでしょうか。
そう多くはないはずです。
それは、数学や古文を学習することが、自分の生活・人生に関連すると感じられることが多くないからです。
同様に、統計学やプログラミングや英語など、現代社会では重要と言われているような知識・スキルでも、その学習に実際に取り組み、継続する人は多くないのはなぜでしょうか。
それは、統計学やプログラミングや英語についても、当然習得していれば「一般的には」役立つとは思っていても、今の「自分の」生活・人生においては、それを学習することが本当に役立つと関連性を感じられないからです。
当然、外資系企業に就職・転職して英語が会社で必須となれば、英語を学習することが「自分の」生活・人生に関連しますので、自然とそこに価値を見いだすことになります。
このように、学習するに際しては、まずその学習対象に価値を見いだすことがスタートとなりますが、一方で、私たちは、自分で価値があると当初から思えることだけを学習できる訳ではありません。
学校や会社などでは、自分にとって価値があると感じられない対象についても学ぶ必要が生じます。
そのような場合でも、まずはその対象の価値を探すことから始める必要があります。
本書では、そのような場合における価値の見いだし方についても具体的な方法を紹介しています。
7.目標を決める

学習対象に価値を見い出した後に、実際に学習に取り掛かる前に、学習の目標を決めることが必要となります。
つまり計画を立てることです。
その際のポイントは以下の通りです。
(1)習得する目標について、その内容を細かく具体的に分割する
(2)日々習得する目標は、コンフォート・ゾーンから少し出たものにする
(1)習得する目標について、その内容を細かく具体的に分割する
習得する目標については、具体的に設定することが重要です。
また、その際、具体的な行動を目標とすることも効果的です。
例えば、「英語を上達させる」といった目標よりも、「月曜日と水曜日に、30分英語の勉強をする」といった目標の方が学習に取り組みやすいです。
そして、それをより細分化させていき、日々の学習に際しても、習得する内容を明確にすることが重要です。
例えば、「今日は、英単語を20個覚える」といったようにです。
そのため、授業が始まったら、いきなり教科書を読み始めるような学習では正直効果はありません。
まず、その日の学習を通じて何を習得したいのかを明確にする必要があります。
(2)日々習得する目標は、コンフォート・ゾーンから少し出たものにする
上記の通り、最終的な目標を細分化して、その日に習得する内容を明確化する必要がありますが、その際に重要な点があります。
それは、学習する内容が、自分の知識・スキルより少し背伸びしたレベル(知っていることや出来ることの少し上のレベル)であるようにすることです。いわゆるコンフォート・ゾーンから出る必要があるのです。
私たちは、一般的に「既に知っていること」や「自分にとって難しすぎること」から学習を始めてしまう傾向があります。
例えば、英単語を学習する際に、ほとんど知っている単語が掲載されいている1ページ目から勉強を始めて、新しい単語が出てくるページに辿り着く前に飽きて止めてしまうといったことや、難しい単語しか載っていない単語集を買ってきて、すぐに挫折してしまうといったことが頻繁に起きます。
目指すスキルが今のスキルレベルとかけ離れていると、学習していても途方に暮れてしまいますし、一方、簡単すぎても学びがありません。
そのため、今の知識・スキルより少し難しいレベルを日々の目標として設定する必要があります。
8.能力を伸ばす

具体的な計画・目標を立てることが分かったら、それを踏まえて学習に取り組むことになります。
つまり、知識やスキルを伸ばす具体的な取り組みです。
この知識やスキルを伸ばす際に重要なポイントは以下の通りです。
(1)フィードバックを受ける(モニタリングをする)
(2)ミス・失敗に対する心構えをする
(1)フィードバックを受ける(モニタリングをする)
私たちは、学習に取り組む際、何を向上させるべきか明確にわかっていないため、同じ練習を繰り返して時間を無駄にしているだけのことも多いです。
例えば、英語の発音についても、ネイティブの発音を聞いて、それを真似して発音練習を繰り返していても、実際にそれが正しいのか、また、改善するポイントはどこなのか分からず、全く向上していないこともあります。
そのために、外部からのフィードバックが重要性となります。
この場合、ネイティブの講師に、自分の発音に間違いがないか、また、間違っている場合はどこを直せば良いかを確認することになります。
しかし、人によっては外部からのフィードバックが受けられない場合も考えられます。
その場合、練習を記録する=モニタリングするたけでも効果があります。
この場合、自分の発音を録音して聞き直すことになります。
学習中、自分のパフォーマンスを記録するだけで、そのパフォーマンスに意識が向き、集中が増すことになります。
そして、モニタリングした結果を自分で見直し、「自分は正しくやっているだろうか」「ミスをしなかったか」「どうすればもっとうまくできるか」と自問するだけでも、ただ練習して終わりといったスタイルと比べると、大きな効果があります。
(2)ミス・失敗に対する心構えをする
また、特に初期の学習において、必ず訪れるものがミスや失敗です。
私たちは、日々、コンフォート・ゾーンを少し超えたレベルの内容に挑むことになりますので、ミスや失敗が起きるのは当然のことです。
そのため、ミスや失敗に対する心構えをしておくことが重要です。
何ら心構えができていないと、ミスや失敗をするたびにそれを恥ずかしく思い、自信をなくすこともあり得ます。
失敗やミスは、決して正しく学習出来ていないことの証拠ではありません。
むしろ、コンフォート・ゾーンを超えた取り組みを行なっている証拠でもあります。
そのため、ミスや失敗は当然に起きるものと心得て、ミスをした際に、「今度はどうすれば良くできるのか」と考える心構えを意識する必要があります。
9.発展させる
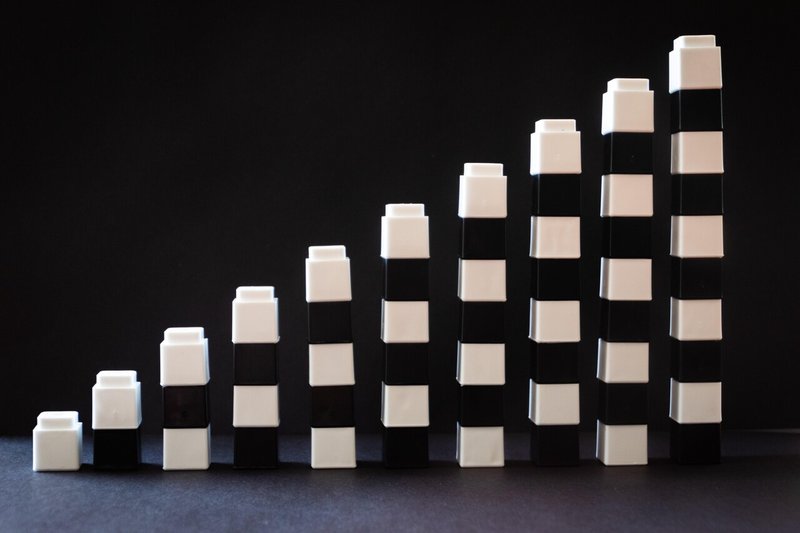
ある程度、特定の領域における基本的な知識・スキルが身についてきたら、それを発展させ、知識・スキルの領域を広げていくことになります。
つまり、基礎をベースとして、知識・スキルを発展・応用させる段階です。
例えば、英語の発音・文法・単語をある程度覚えてきたら、それらを踏まえて実際に英語を話してみる段階です。
このような基本的な知識・スキルを発展させる方法はいくつかありますが、本書でも多くの具体例を挙げて説明しています。
(1)自分自身への問いかける
(2)議論を行う
(3)人に教える
(4)視覚的にイメージする
(5)アナロジー(対比)を行う
それぞれの具体的な方法については、是非本書で確認してみて下さい。
10.関係づける

個々の基本的な知識やその応用が分かってくれば、最後は、関連する知識やスキルの関わり合いを知り、その根底にある体系を理解することを目指します。
学習効果を上げるにはそれぞれの知識・スキルを独立して捉えるのではなく、その関係性を知り、体系を理解することが効果的です。
例えば、複数の分野を混ぜ合わせて練習したり、様々な事例を織り交ぜて学習することによって、その根底にある関係性への理解を深めることができます。
例えば、法律であれば、民法と民事訴訟法をそれぞれ独立して理解するにではなく、その関係性を体系立てて学ぶ方が理解が深まります。また、刑法や刑事訴訟法との関係も理解することで、民法や民事訴訟法に対する理解も深まることになります。
一つの分野に通じた専門家は、その分野の物事の関係性を理解しているため、一見すると混沌として複雑な状態であっても惑わされず本質を掴み取ることができるのです。
このように、知識・スキルの根底にある体系を理解するための方法として、本書では以下の方法が挙げられています。
(1)システム思考
(2)復元抽出
(3)仮定思考
11.再考する

ここまでの手順を踏んで学習をしてくれば、その対象についてかなりの知識・スキルを得ており、その根底にある体系も理解しているはずです。
ただ、このように学習を進めてきたからこそ、私たちが陥ってしまう誤りがあります。
それが過信です。
私たちは、ある程度物事を学習すればするほど、実際以上に物事をよく知っていると勘違いしてしまう傾向があります。
そして、自分では十分知っていると思っていることでも、往々にしてその知識が間違っていることや、十分でないことがあります。
何より、私たちは、もうそれについては十分知っていると思ってしまうと、それ以上、学習しなくなってしまいます。
しかし、そもそも、世の中は常に変化・進歩し続けており、私たちは常に最新の情報を学習する必要があります。
つまり、どんなに学習しても終わりはなく、常に最新の内容に知識・スキルをアップデートしていく必要があります。
10年前の知識しかない弁護士に、私たちは自分が今抱えている問題を相談できるでしょうか。
そのため、私たちは、一度学んだことであっても、定期的に再考する必要があります。
その再考の手助けとなる方法として、本書では以下の方法が挙げられています。
(1)自分に対する問いかけ
(2)外部からのチェック
(3)小テストの実施
(4)分散学習
12.「学習の方法」を身につけること=社会を生き抜くサバイバルツールを得ること
本書は、今まさに学習やスポーツに取り組んでいる学生の方はもちろん、社会人の方にもお薦めの一冊です。
学校を卒業して社会人になってからであっても、私たちは学習が求められる機会は多くあります。
特に、これからの社会は変化のスピードが早く、今後どのような知識・スキルが必要とされるのか予想もし難くなっています。
そのような社会で必要なことは、どのようなスキル・知識が必要とされても、それを早く・効果的に学ぶことであり、そのための前提となるスキルが、本書で紹介されてる学習の方法です。
なお、本書の巻末には、その内容を学生・講師等に向けて纏めた「ツールキット」というものがあり、それを定期的に読み返すだけでも、本書の内容を効果的に復習することができ、非常に効果的なツールと言えます(本書でも、定期的に学んだ内容を繰り返すことで記憶の定着を図ることを進めています)。
本日も最後まで読んで頂きありがとうございました。
記事に関する質問など、何でもご遠慮なくコメント頂ければ幸いです。まだまだ勉強不足の身ですが、できる限り回答させて頂きます。
