
【文芸、音楽批評】大槻ケンヂの変遷 「私」の不在と「私小説」(前編)
大槻ケンヂの変遷 「私」の不在と「私小説」
執筆者:航路 通(@satodex)
先にすこし自分のことについて書きたいと思う。
大槻ケンヂについて話したいという欲求が以前からずっとあった。だけれど、僕が大槻ケンヂについて何を言っても、何を書いても、何かしらウソになるようなそんな気がしていて書くのがためらわれていた。なぜなら、大槻ケンヂというミュージシャンは多くの人間の人生を狂わせていて、僕もその狂わされた一人に違いないからだ。
以前も批評を書いたように、プログレなど、ある種の構造的で叙情的な音楽を聴いている僕は、その批評に関してはいつもドライであるように心がけている。洋楽をよく聞く人間ならわかるかもしれないが、CDのライナーノーツというものは、たまに、音楽を聴いた感動をすごく主観的にのみ書くような執筆者がいる。だが、「語りえないような素晴らしさ」こそを語りえるように批評し解説するのがライナーの役割なのであって、少なくとも僕はそこに、執筆者の主観的な感情を求めていない。
そういったものに対して僕は反発があるから、僕はある程度の客観情報=歴史を書くことから、その音楽の周辺事情を書くことから批評を書き始める。だけれど、大槻ケンヂは僕が初めて聴き、はまり、初めてライヴを観に行ったミュージシャンだ。僕の生き方とものの見方を根本からねじくれさせた張本人だ。批評を書くかどうかはともかくそういう人は多いと思う。大槻ケンヂにはそういう能力がある。だからこそ、彼を語る上で、単なる愛情以上に、彼のスタイルを分析していく必要があると思っている。
しかし、オーケンを語る上で僕の自意識のようなものは、いかにして焼却処理できるだろうか。他でもなく大槻ケンヂによって言及される僕らリスナーの自意識は、すべて大槻ケンヂによる一つの恣意的「コンセプト」のもとに回収されてしまう。大槻ケンヂは、自らのリスナーの自意識をわざと歌い上げるような、そんなやり口を使う。それが気になって、何年も書き始めては捨てを繰り返していたのだ。
ではなぜ今書くのか。それは、僕の中である程度大槻ケンヂという存在が相対化可能なものになったから、であることは確かだ。大槻ケンヂから出発して様々な音楽を聴いた僕は、そして入れ込み具合もましになった今なら、おそらく僕はこの大槻ケンヂという一人のひねくれものに対してある程度のドライな批評をすることができる。
けれどももう一方で、今の僕はある諦念も持っている。どれだけ自意識を文章から追い出そうとしてもそこには他でもなくひとつのテクストを選び批評しているという点で僕の恣意性であり自意識は介在している。だから僕は大槻ケンヂを好きなように批評する。というか、歴史を語る。大槻ケンヂの歌詞には、大きく分けて四つの時期の変遷がある。すべてを語ると長くなるので、恐らくは前半のふたつについて重点を置いて書いていくことになる。
だからといって僕はここで自分が大槻ケンヂのどこに惹かれたかを語るつもりは一切ないが、どうせ何を書いても僕の像はここに現れてしまう。それを読むのはあなたの勝手だ。だからその結果として何らかの情報が、伝わればいいと思う。勝手に読めばいいと思う。それが批評ってもんじゃないのか。

大槻ケンヂ
大槻ケンヂという人を知らない人もいるかもしれないが、もしあなたがある程度「サブカル」や「オタク」「ネクラ」と否が応でも呼ばれる界隈に生きている人間なら、大槻ケンヂの影をどこかに見ているはずだ。基本的にはロックミュージシャンでありながら、それに留まらず小説を書き、また作詞者としてもアイドルや声優やアニメ楽曲も手掛けている彼の存在感は、幅広い射程に及んでいる。それは、一人のミュージシャンとしては比較的膨大なWikipediaの記事を読めば理解できるだろう。
彼は筋肉少女帯(筋少)なるバンドで80年代に活動を始め、ケラ率いるインディーズレーベル・ナゴムレコードで自主製作盤を制作するなどして水面下の活動を続けた後、80年代後半のバンドブーム期にデビューし、いまなお活動を続けているミュージシャンである。
まず、彼自身が「表現できれば何でもよかった」と言う通り、彼のスタイルは音楽的ではない。そもそも、彼は筋肉少女帯結成当初こそベースを兼任していたが、数か月ともたずボーカルに専念するようになっている。その後もまったく楽器を弾くことができず、ボーカリストとして30年近く活動を続けてきた(最近になってギターを始めたが)。彼の作曲した曲も存在するが、それはほとんどが大槻ケンヂの鼻歌をもとに他のバンドメンバーが編曲したものであって、彼が楽曲のインストゥルメンタルな部分に実際に関わっていることはほぼない。最近でも、レコーディングでは歌入れ以外はほとんど録音現場に行かないなど、ドライな距離を保っている。
ファンの間でも、とくにロックリスナーではなく、他の音楽は聴かないが、大槻ケンヂの歌詞の文学的な側面や不条理な側面が好きで聴いているという向きも少なくないだろう。少なくとも僕の場合はもともと音楽をまったく聞かない人間であり、ロックも苦手だったが、大槻ケンヂの歌詞はそういった「音楽」を聴くのとはまた別の気持ちで聴いていた。
のちに触れるが、音楽をし続けながらも、音楽に対して微妙な距離感で接する大槻ケンヂの態度は、彼のスタイルを理解するうえで実は重要である。それはジャンル自体、あるいはロックをするということ自体に対しても同じような距離感があるからだ。
音楽をし続け、と書いたが、大槻ケンヂは休みなく活動しているミュージシャンである。90年代後半の筋少が活動凍結した際には、特撮というバンドを結成し、筋少が復活した今も同時並行で活動している。ソロの活動もさることながら、そのほか空手バカボン、電車など様々な別働隊も不定期で活動を続けている。彼は休みなく常にステージに立ち続けてきた。
一方、彼は小説家・エッセイ作家としても多数の著作を持ち、作詞家として、その言葉の影響力には多大なものがある。「電波系」という言葉の生みの親であるし、たとえば『NHKにようこそ!』など、「ネクラ」な若者の気持ちを代弁するような作品には、つねに大槻ケンヂの影が見え隠れする。彼のスタイルには、60年代~80年代の「裏側」のカルチャーがほとんど濃縮され放出されている。具体的には寺山修司、プログレ、ガロ系、アングラパンク、ニューウェーブ等である。いまや僕たちは、そういったカルチャーを大槻ケンヂというフィルターを通して理解していると言っても過言ではない。
そういった「アングラ」の要素を持ちながら、彼が90年代バンドブームで世に出てからは、一種のポピュラーな「文化人」的な立場として、少なくとも10年程度テレビに出演し続けていた事実もまた興味深いものである。後述するが、そこには大槻ケンヂの、何者も相対化してしまうような一つの冷めた批評眼が関係している。大槻ケンヂは、「アングラ」に笑いを足すと「サブカル」になる、と発言したことがあった。その発言の通り、大槻ケンヂの歌詞にはある種のコミカルさやシュールさが付きまとう。
そうして日本の「サブカル」シーンの中を象徴的に表す一人のスターとしての大槻ケンヂだが、その歌詞のスタイルの変遷を追うような批評は少ないと言っていいかもしれない。彼のスタイルは実はかなり大きく変わっている。本稿ではそれを明確に区別していくことを目的とし、さらに、それを「一人称の出現」というコンセプトで批評していこうと考えている。そしてそれは紛れもなく、先ほど僕がうだうだと書き連ねた自意識の問題ともつながっていると思う。
そのスタイルは具体的には、それは4つにわけることができ、それは単純に言ってナゴム時代→90年代の筋肉少女帯(メジャーデビュー後の筋肉少女帯)→特撮→現在である。
実際に批評するにあたっては、90年代の筋肉少女帯をさらに細かく分類する必要があるだろう。それは具体的に言えば1st『仏陀L』~6th『断罪!断罪!!また断罪!!!』:前期、7th『エリーゼのために』~9th『レティクル座妄想』:中期、10th『ステーシーの美術』~12th『最後の聖戦』:後期である。区分の仕方は色々あるだろうが、本稿ではこのように分ける。後にそれぞれを見ていく。
先に言っておくが、変遷をすべて追うことは本稿ではしない。特撮期の歌詞はハッキリ言ってやや不条理なものが多く解釈に困る。また、現在の大槻ケンヂは(後述するように、これは今までのスタイルをすべて総括するものなのだが)、ライヴにおける観客とのコミュニケーションを意識した歌詞、あるいは本人が自身のスタイルを自覚し、ある路線を決定して歌詞を書くことが多いと思われる。これも(変遷を語るという名目で)批評するには、とっかかりが少ない。そして、ナゴム時代に関しても、有頂天のケラとのユニットであった空手バカボンについては、特に触れない。
よって本稿では、ナゴム→90年代における、筋肉少女帯での大槻ケンヂの歌詞に限定して、変遷をたどる。それは大きな時代の流れのパラダイムシフトと捉えることもできるだろう。そして本稿の場合、それは「一人称の出現」というテーマで批評されることになる。
では、順を追ってみていこう。ナゴム時代、すなわちインディーズ時代、80年代の筋肉少女帯である。
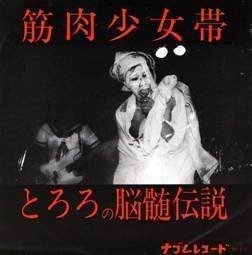
ナゴム 「筋肉少年少女隊」
80年代インディーズ・ブームとはいかなる現象だったのか――それは後追いのファンにとってはなかなか捉えづらい。
当時、大きくとらえれば、ニューウェーブ、テクノの流れを汲んだナゴムレコード(有頂天、筋肉少女帯、空手バカボン、ばちかぶり、人生(後の電気グルーヴ)、たま、カーネーション等)と、ハードコア、ゴス、プログレ、アヴァンギャルドの流れを汲んだトランスレコード(YBO2、ZOA、ゲロゲリゲゲゲ、ボアダムス等)という二つの潮流があり、ナゴムは有頂天のケラを中心に、トランスはYBO2の北村昌士(『フールズメイト』初代編集長)を中心にそれぞれ集まっていた。前者はコミック寄り、後者はアヴァンギャルド寄りだと考えても差支えがないだろう。
有頂天は、P-MODELやヒカシューなど80年代前半のニューウェーブブームに影響を受けたバンドであり、そこからナゴムもニューウェーブ寄りの音楽性のバンドが多く集まった。
筋肉少女帯は当初「筋肉少年少女隊」として、大槻ケンヂと内田雄一郎(Ba)を中心に結成され、他のメンバーはかなり流動的だった。特にギターは、90年代に固定されるまで十数名のメンバーチェンジを繰り返している。大槻ケンヂはまったく作曲能力がないので、内田雄一郎と、後にサポートから正式なメンバーとなる三柴江戸蔵(Pf)の二人が音楽的な根幹となっていた。その音楽性は、ハードロック、パンク、プログレなどが混在したカオスな様相を呈している。ナゴムでは、どのバンドもライブパフォーマンスがアヴァンギャルド(といってもほとんど不条理なおふざけ)だが、筋肉少女帯もまた、身体中にトイレットペーパーを巻き付けて観客にダイブしたり、顔を小麦粉で白く固めたりなど、とにかく意味の分からないことをしていた。

後に、長い髪と割れ目を施した見た目からヴィジュアル的な人気も多少は博すようになる大槻ケンヂだが、この頃は逆立てた髪に眉毛を強調したメイク、黒縁の眼鏡に、血まみれの白衣という格好をしていた。

内田雄一郎とケラとの関わりから、ナゴムレコードに所属することになった筋肉少女帯は、ナゴムで『とろろの脳髄伝説』(1985)『ノゾミ・カナエ・タマエ』(1987)の二枚のアルバム、『高木ブー伝説』(1987)の一枚のシングルをリリースしている(いわゆる自主製作盤)。
ここでは、メジャーデビュー後ではあるが、インディーズとの密接なかかわりがあると考え、1st『仏陀L』2nd『シスター・ストロベリー』も批評の対象としよう。
この時期の筋肉少女帯の歌詞は、大槻ケンヂの不条理さ、厭世観を放出したものとなっている。その特徴はパロディとストーリーテリングであろう。
何曲か聞いてほしい。
これはどれもナゴム時代の楽曲である。フレーズを繰り返すひねくれたベースと鋭角なパンクめいたギターの上に、三柴江戸蔵のピアノが乗り、大槻ケンヂの「怪鳥ボイス」、もしくは語り、が合わさるという基本線の音楽性は、前述のとおりハードロック的でもあり、パンク的でもあり、プログレ的でもあり、どのバンドにも似ていない独特の音楽性を持っている。
不条理なストーリーテリング
そして、「釈迦」「最期の遠足」「外道節」…これらに通ずるのは、不条理なストーリーテリングだ。釈迦は、屋根から落ちる少女の死について、最期の遠足は子供たちの死について、外道節は「赤子で人間パズルをする男が島に流される」話について。
この路線はこの三曲だけではない。「キノコ人間になったタマミちゃん」についてのストーリー「マタンゴ」、ララミーが小学生に凌辱される「ララミー」、ゴムマニアの姉が死んでその恋人に嫌な距離感を詰められるストーリー「いくぢなし」、など、映画マニア・文学マニアだった大槻ケンヂの語彙が発揮され、それらはすべて「不条理な物語」として描かれる。物語でないものは、「ラッシャー木村はえらい」という叫びから始まり、レスラーの名前を連呼する「オレンヂ・ペニス」くらいだろう。
さて、このうち、特に僕が注目すべきと考えるのは、先ほども挙げた「外道節」だ。歌詞を詳細に見てみよう。
「ちょいとそこ行く皆様方よ ボクの話を聞いては行かぬか/お代はいらない聞くだけ得だよ/猟奇漂う妖しい話じゃ/名乗り遅れた私の名前は猫神博士と申す者です
時は昭和のベービーブームに ちょいと生まれた三角野郎は/ガキの頃から悪知恵きいて トボケた顔して巨万の富を/作りついでにたてた計画が 人を外れた外道のイカサマさ
貧乏なお宅の赤子を引き取り 手足外して人間パズルじゃ/どんどん出来るよ即席奇形児 そんな子どもを大量に作って/廉価献売!お安く売ります 心の友達貴方も如何かな?
『えー、もはや東京は阿鼻叫喚、パニックシティとなりました/年端もいかない子ども達に、一体なんてことを/極悪非道もここまでくると気持ちがいい!よかねえか
ともかく、この男の言い分が呆れます/綺麗は汚い汚いは綺麗、朱に交わればなんとやら/なぜみな同じ形でなければならないのだ、異形を拒む心こそが間違いだなどと/自分で奇形児作っといてよく言うよ
ま、ともかく/これがけっこう需要があるんだってんだから困ったもんだ/売る方もなんだが、買う方も買う方だね/時の総理も困り果て、ついに、/とある政府の黒幕にお伺いを立てましたところ、/「そんな連中は、船にでも載せて、どこか遠い異国に流しておしまいなさい」/と申されました。
あー チャカポコチャカポコ』
船は出て行く東京湾から 溢れんばかりの子どもを乗せて/どこへ行くのか誰も知らないんだ 行方しれずの気ままな旅だよ/もしもどこかで出会うことあれば どうぞよろしく伝えてちょうだいよ」
先述の通り「奇形児を作って売る男の話」というダークなストーリーだが、しかしこの歌詞の重要な点は、「猫神博士」の無関係さだ。
このストーリーは猫神博士なるキャラクターによって語られている。途中の長い語りの部分も猫神博士によるものだ。しかし、このストーリーは別に猫神博士には直接関係がない。途中の長い語りでも、猫神博士は不条理な一連のストーリーに対して「この男の言い分が呆れます」「自分で奇形児作っといてよく言うよ」「困ったもんだ」などと、「ツッコミ」のような冷静な立場から注釈を加えている。奇形を愛するサイコな男に対して、猫神博士は「それを語る」立場でしかなく、ほとんど正常な判断を下しているのである。
これは奇妙である。なぜならこのストーリー自体が大槻ケンヂによって考えられているのにもかかわらず、それに対してほかならぬ語り部=大槻ケンヂがツッコミを入れているからだ。ただ男の話を語るだけではなく、一段メタな語り手の視点を入れることによって、この歌詞はより奇妙さを増している。道端で話を聞かせる怪しい人間が、入るのである。
この物語と語り手の関係は落語にも通ずるだろうが、ともかく、僕が「不条理なストーリーテリング」と表記した際、むしろ軸足は不条理さではなく、「テリング」にある。大槻ケンヂはあくまで語り部であって、不条理そのもの、サイコではない。物語に寄り添う立場、より踏み込んでいえば、サイコを面白がる立場なのである。そしてこのスタンスが、「パロディ」に通じている。

当てこすりとしてのパロディ
大槻ケンヂを貫くもう一つの大きな指標はパロディである。これは、どのような形であれ、どの時代の大槻ケンヂにもある手法で、手癖といってもいいだろう。意識的にか無意識的にか、歌詞のなかに小説のタイトルや印象的なフレーズ、他人の歌詞を混入させるという手法である。先ほどの「外道節」にも『ドグラ・マグラ』のパロディがあったが、こういうささいなレベルから全編にわたるものまで、とにかく大槻ケンヂの歌詞はパロディずくめである。大槻ケンヂの場合パロディの語彙が広すぎて、すべてのパロディ元を確定できないが、ナゴム時代~メジャーデビュー直後は、一種のパンクとしての批評性、すなわち「悪意のパロディ」を発揮していたと言える。これはニューウェーブ全体にも通ずる手法であり、大槻ケンヂの出自にニューウェーブがあることもわかる。
これに関しては1stの楽曲のほうがわかりやすい。
「イタコLOVE~ブルーハート~」を聴いていただきたい。
(当該の楽曲は9:20頃~)ライブ映像しかなかったが、このタイトルは明らかにブルーハーツに対するあてこすり、パロディだ。このライブの2分頃にも「リンダリンダ」を歌ったりしていたが、大槻ケンヂはとにかくブルーハーツのような一種の「泥臭さ」「真摯さ」「カッコよさ」に対して斜めの視点を持っている。↑の画像も、布袋寅泰モデルのギターであり、「カッコいいロッカー」の像である。
長くなるので引用は避けるが、「キミはもういない だから心呼んでもらおう そしてそのままイタコと暮らす」というイントロ前の歌がすべて言ってしまっているように、「イタコLOVE」は、「死んだ恋人の魂をイタコのおばあちゃんに降霊させてそのおばあちゃんと暮らす」という内容であり、オリジナル版の途中では長い語りが入る。この歌詞は、「いくら恋人の心が好きと言ってもイタコに降ろした恋人を愛せるのか?」という、プラトニックな恋愛に対する攻撃であるが、それをブルーハーツに対する当てこすりとして書いているのが特徴的だ。
他に、1stでは「モーレツア太郎」における歌詞「狂えばカリスマか?/吠えれば天才か?/死んだら神様か?/何もしなけりゃ生き仏か?/そんなロックで子供が踊るよ/モーレツア太朗/ひとつものを教えてあげて下さい/モーレツア太郎 /啓蒙してくれよ」で、パンク的な言い方によってパンク(ロック)に対するあてこすりをしている。『仏陀L』の歌詞は、基本的にこのパロディ的な想像力と、前述のストーリーテリングによってできている。
そしてそれを最もよりよく表しているのが「高木ブー伝説」である。
「俺は高木ブーだ/まるで高木ブーだ/俺は高木ブーだよ
一人で生きろよ/つらくとも死ぬな/また合う日まで/御機嫌よう
苔のむすまでに/愛し合うはずの二人が/予定調和の中で/離れ離れになる/何も出来ないで/別れを見ていた俺は/まるで無力な俺は まるでまるで高木ブーのようじゃないか
俺は高木ブーだ/まるで高木ブーだ/まるで高木ブーだよ」
この曲はインディーズ時代からのレパートリーであり、ナゴムレコードからシングルカットされた楽曲であるが、高木ブーを揶揄しているとして、訴訟の噂が立ち、自主回収になっている。デビュー後も「高木ブー」を「鼻血ブー」に変えて歌うなど色々と物議をかもした楽曲である。インディーズ~デビュー期の筋肉少女帯を有名にし、高木ブー本人の許可を得て楽曲が録音されるとオリコンにランクインするなど、筋肉少女帯といえば「高木ブー伝説」という印象も強い。
ドリフにおける高木ブーの「なにもしなさ」と、自らの無力さを重ね合わせるという歌詞だが、いかにも技巧的であることがわかる。この歌詞は、何かを何かに例えるというやり方をまず自覚して、その「例え」の方法論自体のパロディとして提示されている。
この楽曲はスターリンの「テンプラ」の歌詞「天ぷらお前だ空っぽ」から発想されたらしい。大槻ケンヂ本人が語ることだが、ロックに限らずポップミュージックの歌詞、ならびに詩の方法論は、例えば恋人を、例えば自分自身を、何かに形容する、比喩で語るというクリシェがある。この楽曲は、それをあえて「高木ブー」という斜め上の比喩によって語ることで、このクリシェ自体をパロディしているのである。
さらにこの楽曲は、もう一つパロディとしての意味を持っている。それは「自意識を語ることについて」のパロディではないだろうか。たとえばパンクに限って言ってもたとえばセックス・ピストルズは「アイ・アム・ア・アナーキスト」、「アイ・ワナ・ビー・アナーキー」と歌った。先ほど挙げたブルーハーツも、「ドブネズミみたいに美しくなりたい」と歌った。これらは「私」の物語なのである。
そして町田町蔵の場合、「メシ喰うな」で、「お前らは全く/自分という名の存在に/耐えられなくなるからと言って/メシばかり喰いやがって」(メシを喰う、はパンクの隠喩である)、という形で「自意識=パンク」に対して皮肉を飛ばし、だからこそ「俺の存在を否定してくれ」と歌っている。
大槻ケンヂの場合も町田と同じく何かと「俺」「私」を歌う、「自意識」としての「俺は○○だ」を皮肉っているが、より意地が悪いと言えるだろう。その対象を「高木ブー」にしてコミカルにしてしまうのだから。
「私」を大槻ケンヂは語ろうとしない。それを語ること自体がクリシェだからだ。要するに大槻ケンヂはクリシェ認識の人なのだ。何でも、たとえば「時代」「ジャンル」の方法論の「ありがちなやり方(自意識)」を認識し、それを皮肉るという仕方で歌詞を書いてきた人間なのである。それは、最近の歌詞においてもそうである(「S5040」等多数)。大槻ケンヂは初期以降の楽曲でも頻繁に「人間とは何だ」「人生とは何だ」という言葉を歌詞や叫び声として楽曲に入れ込むが、それは「問うこと自体」へのパロディなのである。
そしてここに不条理なストーリーテリングとパロディの共通点が見えてくる。それは「私」の不在である。
もちろんこれらに大槻ケンヂの自意識を読み込むことは安易だろう。しかしここでは後半との対比を考え、あえてこう記述したい。
たとえば「釈迦」や「外道節」に見られるストーリーテリングには、大槻ケンヂ本人の「私」語りは一切登場せず、不条理な物語を語る不気味な「語り部」としての立ち位置から動こうとしない。そして「イタコLOVE」「モーレツア太郎」「高木ブー伝説」に見られる手法では、何かの方法論自体を、クリシェとして認識し、それをひたすらパロディする。ここでも、「私」を語るというやり方は、あくまでパロディの手法のためのものであり、ではそのパロディをしている自分自身は何なのかという問いは一切発生していない。
大槻ケンヂはまったく、自分自身を語らず、不条理な物語世界や、過剰ともいえるクリシェ認識によるパロディ、すなわち批評だけで歌詞を成立させているのだといってよい。これを仮に「私」の不在としよう。
では、ここから、90年代の筋肉少女帯において大槻ケンヂの歌詞はどう変わっていくのか。それはむしろ対照的に、「私」だけの世界、すなわち「私小説」とこの批評において呼ばれるものへと没入していくと考えられる。この「私」の不在は、大槻ケンヂ自身によって自覚され、そして本人が意地悪くパロディしていた問いの世界へ、大槻ケンヂは精神的な病とともに落ち込んでいく。私の不在から私の世界へ、いかにして大槻ケンヂが変化するのかは、後編で書く。
(続く)
