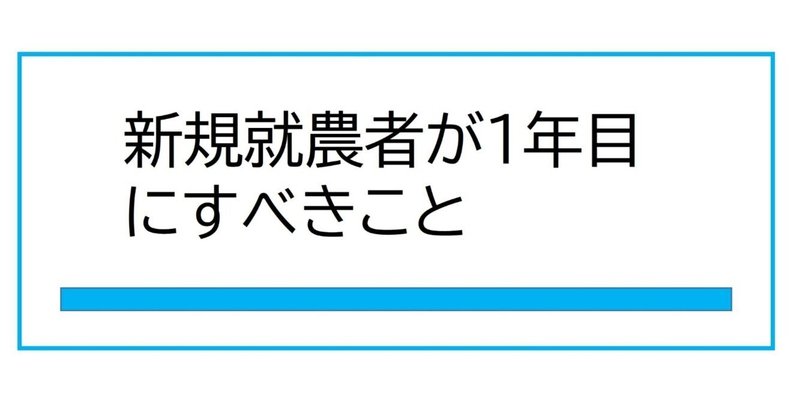
新規就農者が1年目にすべきこと
最初の1、2年は準備の時期と心得、畑と作物のクセを知るとともに、土づくりに重点を置いた出費の少ない栽培を心がけることが大切です。
就農希望者にとって、研修先とは
新規就農後に安定した経営ができるかは、当事者である研修生と受入農家の研修内容が大きく影響します。
新規就農者がどのような経営を目指すのかによって、営農スタイル、主な栽培品目、販路まで多くのことを身に付ける必要があります。
就農したい(住み続けたいと思える)地域を選ぶことはもちろんでですが、誰のもとで研修を受けるかがその後の就農状況を決定すると言っても過言ではありません。
目標とする営農スタイルにあった研修受入農家の技術力とそれを伝える力、さらに研修生の学ぶ意欲や勤勉さが欠かせません。
「土佐自然塾」1期生、就農1年目の成果は?
有機のがっこう「土佐自然塾」の1期生が研修を終え、新規就農1年目の出来事。1年間、栽培から出荷・販売まで学び、借りた農地で新規就農した1期生。近隣で就農後、学んだことをそのまま実践。畑を耕耘し、野菜の種を播種。野菜苗も入手し定植。
しかし、畑のクセ(土壌の養分、排水性など)も分からずに始めた栽培では、野菜はまともに育たず、病害虫の被害にもあい、収穫は皆無だったとのこと。
労力、耕耘に要した燃料代、肥料代、種代などかけた経費は回収できませんでした。
研修で栽培についてある程度分かったとは言え、学んだことを実践するだけでは成果が得られませんでした。研修時と同じように栽培しているようでも、塾長の指導のもとで行っているときとは、勘どころが違っていたのでしょう。
この反省に立ち、2期生からは借りた畑にまず緑肥作物を栽培し、畑のクセを知ることから始め、いろんな作物を小面積で試しながら、畑にあった作物を選定するようにしたそうです。
そして、本格的な栽培は、病害虫の被害の少ない秋作から開始するようにしました。
有機のがっこう「土佐自然塾」
高知県と民間が協力して立ち上げた有機のがっこう「土佐自然塾」では、授業を受けるだけでなく、実技を通して、一年間有機農業について学ぶことができ、多くの新規就農者を輩出しました。塾長の山下一穂さん(1950-2017)は、有機農業参入促進協議会の代表理事として、有機農業の普及にも尽力されました。
三重県伊賀市に新規就農した村山邦彦さん事例
就農1年目には、研修先で学んだ契約出荷を土台にした計画的栽培・販売を可能するための準備から始めました。
10月から5月までホウレンソウを切らさずに一定量を出荷できるように、9月から4月まで播種時期をずらし、収穫に必要な日数、栽培面積を確認しました。
9月初旬には38日で出荷できるまでに生長しましたが、10月下旬播種では出荷まで138日を要しました。
これらのデータをもとに、翌年から毎週契約量を出荷できるように、播種日と栽培面積を策定しました。
新規就農者が、最初にすべきこと
栽培を始めるにあたり、畑に労力と経費をかけても、作物が収穫・販売できなければ、農業は継続できません。
目標とする営農スタイルに向けて、最初の1、2年は準備の時期とし、畑と栽培作物のクセを知るとともに、土づくりに重点を置いた出費の少ない栽培を心がけるべきだと思います。
参考資料
村山邦彦(2011)「野菜の有機栽培・安定生産へ向けた取組」第10回有機農業公開セミナー 資料集:26-38, 有機農業参入促進協議会.
山下一穂・千葉康伸(2016)「研修受入先の心得」『有機農業をはじめよう!研修生を受け入れるために』:4-5. 有機農業参入促進協議会.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
