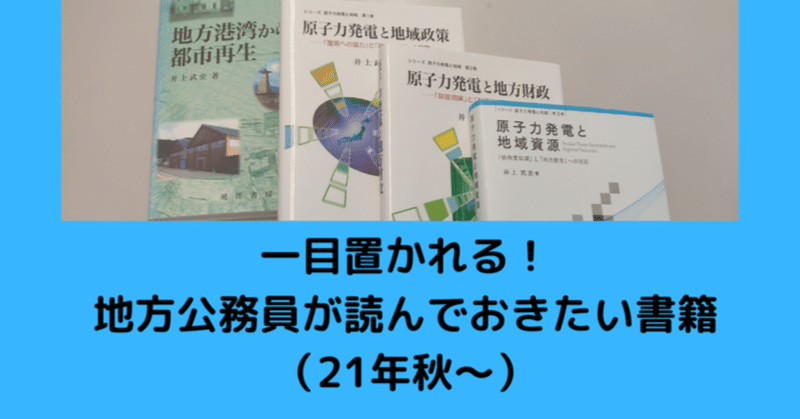
地方公務員が読んでおきたい書籍の紹介:久松達央「農家はもっと減っていい-農業の常識はウソだらけ」光文社新書、2022年
本書のタイトルが刺激的で興味をひかれたので、購入しました。農業は日本の大切な産業であることは言うまでもありません。ただ、零細・兼業の形態が多いため、それをいかに維持するかに主眼が置かれてきたように思われます。つまり、補助金等による財政的な支援で、市場による競争では淘汰されてしまうのを防ぐ形で農業が維持されてきました。本書は、そうした既存の農業政策からの脱却を訴えています。
ただ、いわゆる市場原理主義の立場にあるかと言えば、そういうわけでもありません。農業は、大規模・低コストの農業と小規模・高コストの農業に二極化していると筆者は述べています。当然ですが、前者の立場は市場原理主義による競争によって優位に立つことができ、後者が財政支援で対抗することを訴えることになります。しかし、筆者は後者の小規模・高コストの農業経営者なのです。問題は、農業政策がいずれの形態に対しても同じ方策で持続を図ろうとしているため、適切な形になっていないことにあります。そこで、筆者はそれぞれに合った政策への転換を訴えているのです。
特に、私が印象に残ったのは、「最愛戦略」です。筆者独自の用語ではなく、あるコミュニケーションデザイナーの方の言葉を紹介しているのですが、他社との競争のなかで、機能面でのダントツの優位性をめざす「最高戦略」や、他より1円でも安くする「最安戦略」を取るには、相当な覚悟と体力が必要とされ、そのような戦いを続けられるのは一部の強者に限られます。多くはそれができないので、機能でも価格でもなく「個性」で消費者の信頼や愛着を獲得する「最愛戦略」に向かうべきではないか、ということです。自分の作りたい作物を作りたいように作り、それを受け入れてくれる消費者に販売する、というのは農業のやりがいにもつながってくると思います。
もう1つ興味深いのは、有機農業への疑問です。後半のほとんどはこの点を力説しています。「有機農業」と聞けば、私たち消費者は「自然に優しい」「健康に良い」といったイメージを持ちます(私もそうです。つい先日、「有機栽培米」と大きく書かれた米が売られているのを見かけました)。しかし、有機農業でなければ自然に優しくなく、健康にも良くないのかと言えば、そんなことはない、と筆者は述べています。つまり、有機農業は1つの形態に過ぎず、その点が誤解されているのです。
高く売られている有機農業の産物をありがたく購入する我々は、認識を改める必要があります。私は、これが「風評被害」の逆パターンと言えるかもしれない、と感じました。根拠のない評判が商品の価値を不適切に下げてしまうのが風評被害だとすれば、不適切に上げてしまうのが有機農業ということになるでしょうか。「新機能〇〇を追加!」「性能〇〇%アップ!」など、宣伝によく使われる謳い文句も、根拠はあるけれども不必要に価値を上げようとしているのかもしれません。有機農業に力を入れている筆者から見れば、それで高く売れてもやりきれない面があるのではないかと思います。
最後に、本書は農業だけでなく地方そのものに当てはめてみても面白い、と思いました。「地方はもっと減っていい」のではないか?本書に書かれている農業の記述を地方に置き換えてみても、意外に筋が通るような気がします。しっかりと考えたわけではありませんが、農業について学ぶだけでなく地方のあり方を考える題材として読むと、もっと面白い。本書が地方創生のイメージトレーニングや思考実験につながる可能性を指摘して、今回の紹介を終えたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
