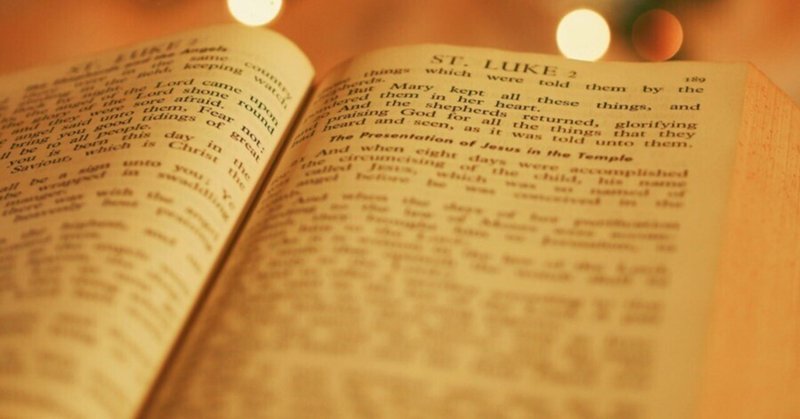
ステイントン・モーゼスの『霊訓』を読む
スピリチュアリズムのバイブルとも呼ばれる名著、ステイントン・モーゼズの『霊訓』。
世界三大霊訓の一つとしても名が挙がります。
モーゼズ(1839-1892)はイギリスの超大物スピリチュアリスト。かのSPRの創設にもかかわり、副会長をつとめています。
『ベールの彼方の生活』の著者オーウェンと同じく、もともとは国教会の牧師でした。
やはり初期のうちはキリスト教の教義に従順であり、スピリチュアリズムの運動を完全に無視していたといいます。
変化が起きたのは主治医の奥さんにすすめられて降霊会に出席したこと。
これがきっかけになって、モーゼスの身の回りにさまざまな霊的現象が発生するようになります(シルバーバーチの霊媒も同じようなルートをたどったことが思い起こされる)
もっとも重大な現象は自動書記でした。インペレーターと名乗る霊が統率する、49名から成る霊団がメッセージを送り、モーゼスがそれを記録するという活動がはじまります。
メッセージの中心は現在のキリスト教への批判でした。既成宗教がいかに歪められているかを指摘し、そのかわりにスピリチュアルな真実を提示していくという内容。
当然、元牧師のモーゼスは内容を受け入れられず、随所に反対意見を書き込みます。
それに対してまた霊団からの批判的応答が届き…というふうに、モーゼスの『霊訓』は白熱した宗教的議論になっているのが特徴。
以下、とくに印象に残ったシーンをいくつか紹介してみましょう。なお日本語訳は近藤千雄のものを使用させていただきます。
魂の成長、および善と悪について
人間は霊界へ来たからとて、地上時代といささかも変わるものではない。その好み、その偏執、その習性、その嫌悪をそのまま携えて来るのである。
変わるのは肉体を棄てたということのみである。低俗なる趣味と不純なる習性をもつ魂は、肉体を棄てたとてその本性が変わるものではない。それは、誠実にして純真なる向上心に燃える魂が死と共に俗悪なる魂に一変することが有り得ぬのと同じである。
汝らがその事実を知らぬことこそ、われらにとって驚異と言うべきである。考えてもみるがよい。純粋にして高潔なる魂が汝らの視界から消えるとともに一気に堕落することが想像できできようか。
然るに彼らは、神を憎み善に背を向け肉欲に溺れし罪深き魂も、懺悔一つにて清められ天国に召されると説く。前者がありえぬ如く後者も絶対に有り得ぬ。魂の成長は一日一日、一刻一刻の歩みによって築かれるのである。すぐに剥げ落ちる上塗りではない。
魂の本性に織り込まれ、切り離そうにも切り離せぬ一部となりきること───それが向上であり成長である。そうして築かれたる本性がもしも崩れるとすれば、それは長き年月にわたる誤れる生活によりて徐々に朽ちるのであり、織物を乱暴に切り裂くがごとく一夜にして崩れることはない。ない、ない、断じてない! 習い性となり、魂に深く染み込みて個性の一部となりきるのである。
これはけっこうハッとする発言だと思う。
なんとなく、死んであの世にいったら本当の自分が目覚めるような感覚があると思うんですよね。
しかしインペレーターによるとそれは違うと。霊性の上昇も、いわば「習慣が織りなすもの」だと言うんです。
背後霊について
──背後霊のことですが、どういう具合にして選ばれるのでしょうか。
背後霊は必ずしも指導する目的のみでつくのではない。そういう場合がいちばん多いのではあるが、時には背後霊自身にとっての必要性から付くこともある。が、その場合でも人間を教え導くという傾向は自然に出てくる。
また時には特殊な使命を帯びた霊がつくこともある。性格に欠けたものがあって、それを補ってやるために、その欠けたものを豊富に有する霊が選ばれることもある。反対に霊の側に欠けたものがあり、それを身につけるために適当なる人間を選ぶという場合もある。
これは高級なる霊が好む手段である。己の霊的向上のために、敢えて指導が困難で不愉快な思いをさせられる人間につくことを自ら希望する霊もいる。
その人間と苦労を共にしつつ向上していくのである。中には霊的親和力によって結ばれる場合もある。地上的縁の名残で結ばれることもある。何ら特殊な使命を帯びていない人間の背後霊は、魂が向上するに従い背後霊が入れ替わることがしばしばある。
なぜ死刑制度が害悪なのか
霊にとって、その宿れる肉体より無理やりに離され、怒りと復讐心に燃えたまま霊界へ送られることほど危険なるものはない。いかなる霊にとっても、急激にそして不自然に肉体より切り離されることは感心せぬ。
われらが死刑を愚かにして野蛮なる行為であるとする理由もそこにある。死後の存続と進化についての無知が未開人のそれに等しいが故に野蛮であり、未熟なる霊を怨念に燃えさせたまま肉体より離れさせさらに大きな悪行に駆り立てる結果となっているが故に愚かというのである。
確かに、あの世や転生の全体像を考慮すれば、死刑制度は非合理的といえます。
死刑制度を支持する時点で、そのひとが唯物論的な迷信にとらわれていることがわかってしまいますね。
夫婦の絆について
〔しばしば交霊会に出現していた夫婦の霊が、別の仕事の境涯へ向上して行ったと聞いていたので、夫婦の絆は永遠のものかどうかを尋ねた。〕
それはひとえに霊的嗜好の類似性と霊格の同等性による。その両者が揃えば二者は相寄り添いて向上できる。われらの世界には共通の嗜好をもつ者、同等の霊格をもち互いに援助し合える者同士の交わりがあるのみである。われらの生活においては魂の教育が全てに優先し、刻一刻と進化している。同質でなければ協同体は構成されぬ。
したがって当然互いの進化にとって利益にならぬ同士の結びつきは長続きせぬ。地上生活において徒らに魂を傷つけ合い、向上を妨げるのみであった夫婦の絆は、肉体の死と共に終わりを告げる。
逆に互いに支え合い援助し合う関係にあった結びつきは、肉体より解放されたのちも、さらにその絆を強め発展していく。そして二人を結ぶ愛の絆が互いの発達を促す。かくの如く両者の関係が永続するのは、それが地上で結ばれた縁であるからというのではなく、相性の良さゆえに、互いが互いの魂の教育に資するからである。
かくの如き結婚の絆は不滅である。ただしその絆は親友同士の関係程度の意味である。それが互いの援助と進化によって一層強化されていく。
そして互いに資するところがあるかぎり、その関係は維持されていく。やがてもはや互いに資するものがなくなる時期が到来すると、両者は分かれてそれぞれの道を歩み始める。そこにはなんの悲しみもない。なぜなら相変わらず心を通じ合い、霊的利益を分かち合う仲だからである。
もしも地上的縁が絶対永遠のものであるとすれば、それは悲劇までも永遠であることを意味し、向上進化が永遠に妨げられることになる。そのような愚行は何ものにも許されていない。」
これを聞いて安心する人は少なくなさそう。
夫婦だけでなく、あらゆる家族関係に当てはまる話ですね。
神について
われらは怒りと嫉妬に燃える暴君の如き神に代わりて愛の神を説く。名のみの愛ではない。行為と真理においても愛であり、働きにおいても愛を措いてほかの何ものでもない。最下等の創造物に対しても公正と優しさをもって臨む。
われらの説く神は一片のおべっかも要らぬ。法を犯せるものを意地悪く懲らしめたり、罪の償いの代理人を要求したりする誤れる神の観念を拒否する。況や天国のどこかに鎮座して選ばれし者によるお世辞を聞き、地獄に落ち光と希望から永遠に隔絶されし霊の悶え苦しむさまを見ることを楽しみとする神など、絶対に説かぬ。
われらの教義にはそのような擬人的神の観念の入る余地はない。その働きによってのみ知り得るわれらの神は、完全にして至純至誠であり、愛であり、残忍性や暴君性等の人間的悪徳とは無縁である。罪はそれ自らの中にトゲを含むが故に、人間の過ちを慈しみの目で眺め、且つその痛みを不変不易の摂理に則ったあらゆる手段を講じて和らげんとする。
われわれ現代日本人からすると、至極まっとうなことを言っているように聞こえると思います。
しかし当時のモーゼスはイギリス国教会の教義を信奉していた人間。だからインペレーターの説く神や啓示の教えと衝突する場面が多々あるんですね。
それが本書の見どころのひとつになっています。
啓示について
いかなる教派にも偏ってはならぬ。理性の容認できぬ訓えに盲目的に従ってはならぬ。一時期にしか通用せぬ特殊な通信を無批判に信じてはならぬ。神の啓示は常に進歩的であり、いかなる時代によっても、いかなる民族によっても独占されるものではない。神の啓示は一度たりとも〝終わった〟ことはないのである。
その昔シナイ山にて啓示を垂れた如く、今なお神は啓示を送り続けておられる。人間の理解力に応じてより進歩的啓示を送ることを神は決してお止めにならぬ。
またこれも今の汝には得心しかねることであろうが、全ての啓示は人間を通路としてもたらされる。故に多かれ少なかれ、人間的誤謬によって着色されることを免れないのである。いかなる啓示も絶対ということは有り得ぬ。
信頼性の証は合理的根拠の有無以外には求められぬ。故に新たなる啓示が過去の一時期に得られた啓示と一致せぬからとて、それは必ずしも真実性を疑う根拠にはならないのである。いずれもそれなりに真実なのである。ただその適用の対象を異にするのみなのである。正しき理性的判断よりほかに勝手な判断の基準を設けてはならぬ。
啓示をよく検討し、もし理性的に得心が行けば受け入れ、得心が行かぬ時は神の名においてそれを捨て去るがよい。そして、あくまで汝の心が得心し、進歩をもたらしてくれると信じるものに縋(すが)るがよい。いずれ時が来れば、われらの述べたことが多くの人々によってその価値を認められることになろう。われらは根気よくその時節を待とう。
啓示というのは要するに神や霊からの知らせのこと。今風にいえばチャネリングによってもたらされるメッセージです。
・神からの啓示に終わりはない
・啓示は人間という通路に媒介されているので必ず歪みがある
・啓示が正しいかどうかは理性によって判断せよ
聖書について
われらに言わしむれば、バイブルを構成するところの聖なる書、及びその中に含まれていない他の多くの書はみな、神が人間に啓示する神自身についての知識の段階的発達の記録に過ぎぬ。その底流にある原理はみな同じであり一つである。
それと同じ原理がこうした汝とわれらとの交わりをも支配しているのである。人間に与えられる真理は人間の理解力の及ぶ範囲にかぎられる。いかなる事情のもとであろうと、それを超えたものは与えられぬ。人間に理解し得るだけのもの、その時代の欲求を満たすだけのものが与えられるのである。
さて、その真理は一個の人間を媒体として啓示される。よって、それは大なり小なりその霊媒の思想と見解の混入を免れぬ。と言うよりは、通信霊は必然的に霊媒の精神に宿されたものを材料として使用せざるを得ぬ。つまり初期の目的に副ってその材料に新たな形体を加えるのである。その際、誤りを削り落とし、新たな見解を加えることになるが、元になる材料は霊媒が以前より宿せるものである。したがって通信の純粋性は霊媒の受容性と、通信の送られる際の条件が多いに関わることになる。
バイブルのところどころに執筆者の個性と霊的支配の不完全さと執筆者の見解による脚色のあとが見られるのはそのためである。またそれとは別に、その通信が意図した民族の特殊なる必要性による特有の色彩が見られる。もともとその民族のために意図されたものだったからである。
啓示と神の観念について
それは時代や霊媒の限界を超えることはありえないと説かれます。
改めて述べるまでもなく、神の啓示はいつの時代にもその時代の人間の受容能力に応じたものが授けられ、それがさらに人間の精神によって色づけされている。言い換えれば、神の観念は鮮明度の差こそあれそれを受けた霊感者の考えであったとも言える。
精神に印象づけられた霊示がその霊感者を取り囲む精神的環境によって形を賦与されていった。すなわちその霊感者の受容度に応じた分量の真理が授けられ、それが霊感者の考えによって形を整えたのである。
真理の全てを授かれる者は一人としておらぬ。みなその時代、その民族の特殊なる要請に鑑みて必要なる分量のみが授けられた。今も引き合いに出せる如く、神の観念が種々様々であるのはそのためである。
神の観念は人間がこしらえたものだ、という考えがあります。ある意味では、そしてある程度は、それは当たっているということ。
とはいえ神や宗教を「根拠のないフィクションだ」とまで見なすようだと、それ自体が不健康な迷信になってしまうのですが。
悪霊について
自ら悪霊を招くような悪しき生き方をしているのでなければ、悪霊やら低級霊やらに取り憑かれることはない、と明言されています。
魂が悲しみと懊悩の暗雲に被われ、罪の重荷に打ちひしがれるやも知れぬ。すなわち、あたりに見る不幸と悪に己れの無力さを感じ、良心の呵責に苦しめられることもあろう。が悪魔が彼らを囚(とりこ)にし、あるいは地獄へと引きづり下ろすなどということは絶対にない。
そうした懊悩も悲しみも良心の呵責も、所詮は魂の経験の一部であり、その体験の力を摂取して、魂は一段と向上して行く。それは進歩の手段として守護霊が用意せる試練であり、故に細心の注意をもって悪の勢力から保護してくれているのである。
悪を好み、霊性の発達を欠き、肉体的欲望に偏れる者のみが、肉体を棄てたのちもなお肉体的欲望を棄て切れぬ同質の未発達霊を引き寄せるのである。悪の侵入の危険に曝されているのは、そうした類の人間のみである。その性壁そのものが悪を引き寄せる。
招かれた悪が住みつくのである。そうした人間が、地上近くをうろつきまわり、好きを見ては侵入し、われらの計画を邪魔し、魂の向上のための仕事を挫折させんとする霊を引き寄せるのである。さきに汝は軽率にも霊界通信なるものがいい加減にして益になるとは思えぬと述べたが、それは全てそうした低級なる邪霊の仕わざである。
メルキゼデクについて
これよりわれらは古き時代においてわれらと同じく人間を媒体として啓示が地上にもたらされた道程について述べんと思う。聖書に記録を留める初期の歴史を通じて、そこには燦然と輝く偉大なる霊の数々がいる。
彼らは地上にあっては真理と進歩の光として輝き、地上を去ってのちは後継者を通じて啓示をもたらしてきた。その一人──神が人間に直接的に働きかけるとの信仰が今より強く支配せる初期の時代の一人に、汝らがメルキゼデク①の名で知るところの人物がいた。
彼はアブラハム②を聖別して神の恩寵の象徴たる印章を譲った。これはアブラハムが霊力の媒体として選ばれたことを意味する。当時においては未だ霊との交わりの信仰が残っていたのである。彼は民にとっては暗闇に輝く光であり、神にとっては、その民のために送りし神託の代弁者であった。
メルキゼデクはイエスに連なる系譜の最重要人物。
逆にアブラハムは霊界から見れば脇役にすぎないと説かれています。
なお、聞き手がキリスト教徒のモーゼスなのでこの系譜が解説されていますが、聖書以外の系譜にも多くの霊的存在がいたとインペレーターは注意しています。
モーセについて
メルキゼデクは死後再び地上に戻り、当時の最大の改革者、イスラエルの民をエジプトより救い出し、独自の律法と政体を確立せる指導者モーセを導いた。霊力の媒介者として彼は心身ともに発達せる強大なる人物であった。
モーセは実在し、出エジプトも本当にあったこととして語られています。
そしてモーセの後ろにはメルキゼデクの霊がいたと。また、モーセも死後に霊として地上に戻ったようです。
メルキゼデクがモーセの指導霊となりたる如く、そのモーセも死後エリヤの指導霊として永く後世に影響を及ぼした。
モーセ五書について
あの五書はエズラの時代に編纂されたものである。散逸の危険にあった更に太古の時代の記録を集め、その上に伝説または記憶でもって補充した部分もある。モーセより以前には生の記録は存在せぬ。「創世記」の記録も想像の産物もあれば伝説もあり、他の記録からの転写もある。天地創造の記述や大洪水の物語は伝説にすぎぬ。
エジプトの支配者ヨセフに関する記述も他の記録からの転写である。が、いずれにせよ現在に伝えられる〝五書〟はモーセの手によるものではない。
エズラとその書記たちが編纂したものであり、その時代の思想と伝説を表しているに過ぎぬ。もっとも、モーセの律法に関する叙述は他の部分に比して正確である。何となれば、その律法の正確な記録が聖なる書として保存され、その中より詳細な引用が為されたのである。
今の聖書は、ペルシア帝国の支配を受けていた時代に、「モーセ五書」をコアとしてまとめられたものです。それを指導したのがペルシア帝国の高官エズラでした。
やはりフィクションが多い模様。
ただしモーセの十戒は実在したものとして本文中で解説されています。メルキゼデクらの霊団がモーセにそれを授けたと。
もちろん十戒はプラグマティックな性質のものであり、その時代のその場所でのみ効果を発揮するもの。後世の人間が文字通りにありがたがる意味はないと指摘されています。
神の観念の発達について
重ねて言うが、啓示とは時代によりて種類を異にするものではなく、程度を異にするのみである。その言葉は所詮は人間的媒体を通して霊界より送り届けられるものであり、霊媒の質が純粋にして崇高であれば、それだけ彼を通して得られる言説は信頼性に富み、概念も崇高さを帯びることになる。
要するに霊媒の知識の水準が即ち啓示の水準ということになるわけである。故に、改めて述べるまでもあるまいが、初期の時代、たとえばユダヤ民族の記録に見られる時代においては、その知識の水準は極めて低く、特殊なる例外を除いては、その概念はおよそ崇高と言えるものではなかった。
人間創造の計画の失敗を悔しがり、悲しみ、全てをご破算にするが如き、情けなき神を想像せる時代より、人間は知識において飛躍的に進歩を遂げてきた。より崇高にして真実に近き概念を探らんとすれば、人間がその誤りの幾つかに気づき、改め、野蛮的創造力と未熟なる知性の産み出せる神の概念に満足できぬ段階に到達せる時代にまで下らねばならぬ。
野蛮なる時代は崇高なるものは理解し得ず、従って崇高なるものは何一つ啓示されなかった。それは、神の啓示は人間の知的水準に比例するという普遍的鉄則に準ずるものである。故に、そもそも過ちの根源は人間がその愚かにして幼稚きわまる野蛮時代の言説をそのまま受け継いできたことにある。神学者がそれを全ての時代に適応さるべき神の啓示としたことにある。その過ちをわれらは根底より改めんと欲しているのである。
・啓示はそれを受ける人間の精神レベルに制限される
・人間の精神レベルが上がれば質の高い啓示が可能になる
・だから人間の進歩にしたがって神の観念も発達していく
・古き野蛮な時代の神観念をいつまでも有難がるのは無意味
これは凄く説得力があります。きわめて重要な発言。
インドの哲学・宗教が他の地域に与えた影響について
今の汝の信仰の底流となっている宗教的概念の多くはインドにその源流を発している。インドに発し、太古の多くの民族によって受け継がれてきた。その原初において各民族が受けた啓示は単純素朴なものであったが、それにインドに由来する神話が付加されていったのである。
救世主出現の伝説は太古よりある。いずれの民族も自分たちだけの救世主を想像した。キリスト教の救世主説も元を辿ればインドの初期の宗教の歴史の中にその原型を見いだすことが出来る。
インドの Manou(まぬ) はキリストの誕生より三千年も前の博学な学識者であり、卓越せる哲学者であった。いや実は、そのマヌでさえそれよりさらに何千年も昔の、神と創造と人間の運命について説かれたバラモンの教説の改革者に過ぎなかった。
ペルシャのゾロアスターの説ける真理も全てマヌから学んだものであった。神に関する崇高なる概念は元を辿ればマヌに帰する。法律、神学、哲学、科学等の分野において古代民族が受けたインドの影響は汝らが使用する用語がすべてマヌ自身が使用した用語と語源が同一である事実と同様に間違いなき事実であるとの得心がいくであろう。」
インドにマヌという名の哲学者がいたことは初めて聞いた気がする。
一見したところ世界の宗教はバラモンの伝承的学識のなかに類似性を見出だせぬかに思われるが、実はマヌが体系づけ、マーニー Manes がエジプトに摂り入れ、モーセ Moses がヘブライの民に説いた原初的教説から頻繁に摂取しているのである。
哲学及び神学のあらゆる体系の中にヒンズー(インド)的思想が行き渡っている。たとえば、古代インドの寺院において絶対神への彼らなりの純粋な崇拝に生涯を捧げたデーヴァダーシーと呼ばれる処女たちの観念は、古代エジプトではオシリスの神殿に捧げられる処女の形を取り、古代ギリシャではデルポイの神殿における巫女となり、古代ローマではケレース神の女司祭となり、後にあのウェスタ―リスとなって引き継がれていった。
エジプトの宗教について
当時のエジプト人は霊の存在とその働きについて今の汝より遥かに現実味のある信仰を抱いていた。
死後の存続と霊性の永遠不滅性について、現代の地上の賢人より遥かに堅固なる信仰をもっていた。彼らの文明の大きさについては汝もよく知っていよう。その学識はいわば当時の知識の貯蔵庫のようなものであった。
まさしくそうであった。彼らには唯物主義の時代が見失える知識があった。ピタゴラスやプラトンの魂を啓発せる知識、そしてその教えを通して汝らの時代へと受け継がれて来た知識があった。古代エジプト人は実に聡明にして博学なる哲学者であり、われらの同志がいずれ汝の知らぬ多くのことを教えることになろう。
モーセの教義もエジプトの宗教から借用したものばかりだったといいます。
そういえばピタゴラスやプラトンもエジプト文明から大きな影響を受けていたんですよね。当時の地中海世界はエジプトが中心地であり、ギリシアは辺境にすぎなかった。
とはいえ宗教的にはやはりインドが先達で、エジプト人はそこから影響を受けたそうです。
エジプト宗教はインドへのある種の反動であり、精神的・瞑想的な方向を極めたインド文明に対して、エジプトでは物質的・日常的なもののなかに神を見出すモードが発達しました。
生活のすべてが宗教の一環としてあったエジプト人の世界を、インペレーターは称賛しています。
イエス・キリストについて
イエスは常に霊界と連絡を取っていた。その身体が霊の障害とならなかっただけ、それだけ自然に天使の指導を受け入れることが出来たのである。
地上の救済のために遣わされる霊はその殆どが肉体をまとうことによって霊的視野が鈍り、それまでの霊界での記憶が遮断されるのが常である。が、イエスは例外であった。その肉体の純粋さ故に霊的感覚を鈍らせることが殆どなく、同等の霊格の天使たちと連絡を取ることが出来た。
天使たちの生活に通じ、地上への降誕以前の彼らの中における地位まで記憶していた。天使としての生活の記憶はいささかも鈍らず、一人の時は、殆ど常時、肉体と離れて天使と交わっていた。長時間に亙る入神も苦にならなかった。
イエスは一般民衆とは和やかな関係にあったようです。
しかし聖書にはそのような記述が欠けている。インペレーターはそこに憤っています。イエスと敵対したエリート知識人たちのことばかりが書かれていると。
なおイエスは幼少期にエジプトに退避していたとインペレーターは述べています。
イエス・キリストの磔刑について
その聖なる生活は人間の無知と悪意とによって、その半ばにして終焉を迎えた。キリスト教徒がイエスは地上人類の犠牲となるために降誕したと述べる時、彼らはその真実の意味を理解していない。確かにイエスは人類の犠牲となるために来た。
がその意味は熱烈なるキリスト教徒の説く意味とは異なる。カルバリの丘でのあの受難のドラマは人間の為せる業であり、神の意図せるものではなかった。
使命遂行に着手したばかりの時点においてイエスを葬ることは、神の悠久の目的の中には無かった。それは人間の為せる行為であり、邪悪にして憎むべき、且つ忌まわしき出来ごとであった。
イエスの磔刑は、本人にとっても霊界にとっても、予期せぬアクシデントだったというんですね。
もしイエスが予定通りにその生涯をまっとうしていれば、人類にとっての恩恵は計り知れないほど大きなものになっていただろうとインペレーターは述べます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
