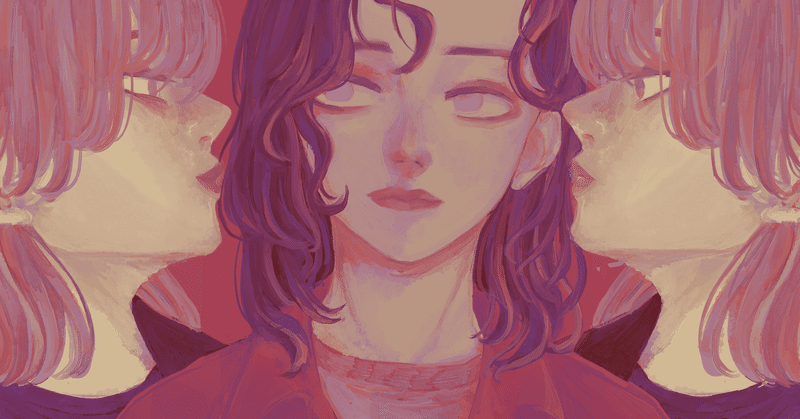
雑文(79)「日替わり亭主」
私には七人の亭主がいる。
月曜日には月曜日の、火曜日には火曜日の、という具合に、日ごと違う亭主と私は暮らしている。
元来の飽き性なので、こっちの方が私の性に合っており、喧嘩すらない。というか、喧嘩しそうになっても、次会うのが一週間後だから、その頃にはなぜ怒っていたのか、どちらも覚えていない。
というわけで、私は七人の亭主と代わり番こで生活しており、毎日楽しく日々を送っていて、むろん七人の亭主たちにも違う家庭があるだろうけど、その辺りは干渉しない決まりだ。
私たちの家庭には関係ないことで、そんなことを考え出したら、いまの家庭が崩れてしまいかねないから、お互い気にもしないように接している。
「マイハニー」と、カタコトの亭主が戸口から、当然のように家にあがって、居間にいる私に声をかけてきた。
水曜日の亭主である。
出会ってすぐにハグを交わすと私たちは小さなソファに収まって、恋人たちみたいに仲睦まじく初々しさを共有する。
「寂しかったよ」と、水曜日の亭主。
「私もだよ」と、私。
このような社交辞令を交わした後、黎明期を過ぎたテレビ番組を、お互い意見を言い合いながら小一時間観て、互いの近況報告をして、夜の別れを惜しむ。
くり返し行われてきた儀礼であり、夫婦生活だった。
冷めてはなかったが、けれど熱くもなかった。
傍目には熱々に映るかもしれないが、本心はやはり社交辞令で、役を演じているのが強い。
だけれども、居て楽しいから、苦痛はない。
それはたぶん彼もそうで、心底嫌なら、遠に別居だろう。
こうして毎週水曜日の自宅訪問を欠かさないから、私はまだ彼に愛されている。
別れ際にまたハグをして、戸口から出て、彼の後ろ姿を見送り、名残惜しそうに私は戸を閉めて、明日来る亭主に備え、感情をリセットする。
夫婦関係が長続きする秘訣はなんですか? と誰かに訊ねられたら、私はこう答えるだろう。
それは、新鮮な気持ちで亭主に接することです、と。
私みたいに色とりどりな亭主に囲まれて家庭生活を送る夫婦は世間にはあまりいないだろうが、あえて私は提言したい。
飽き性な私でも日替わりで亭主と接すれば長続きするんだと、誰でもない誰かに胸を張って伝えたい。
誰かのある日の亭主であっても、私には彼が今日の亭主なのだ。
いつでも女性扱いで、間違っても、オカンなんて言う、卑劣な言葉を私に吐かない。
母親であるのと同時に、私は一人の女であって、そう願われればいつまでも若くいられる。
亭主たちに望まれる理想の女で居続けられるのだ。
木曜日の亭主は無口な方だった。
年上で、寡黙な性格の男性だったが、無駄なことを喋らなくてよかったので、一緒に居ても疲れない。
落ち着いた時間が、彼と共に過ぎていく。
訊かれることも些細な確認ぐらいで、薄暮のテレビなんか点けずに、ずっと隣で私の肩を抱いて、肩に寄りかかった私の頭をやさしく撫でてくれる。
そこに言葉はないが、言葉以上の感情が彼から伝わってきて、私の胸底からじんわり熱が上がり、幸せな気持ちに包まれる。
水曜日の亭主のような賑やかさもよいが、彼のようなシックな扱いもよい。乙女心がキュンとなるのが私にはわかる。
帰り際も、なにも言わずに戸口でそっと口づけをして、別れを惜しみもせずに出ていき、戸口から覗く私の顔を一度も見ずに、振り返らずに廊下奥の左に消える。
戸を閉めて、余韻に浸り、私は心の準備を整える。
金曜日の亭主は形容しがたい。というか、形容できるが、形容したら誤解される。
普通のサラリーマンではない。といって、完全に社会性がないといえば嘘になる。
いずれにせよ、彼は酔っ払っていて、来るなり、酒を要求した。
要求どおり熱燗を差し出すとそれを一気に飲み干し、さらに要求する。
グラスを差し出された腕は若干震えており、止めなよと、いくら言っても一切聞かず、酒だけを要求する。
状況だけ描写すれば最低の亭主だと、賢明な読者は思うだろうが、それは違う。
彼は悲しいのだ。
悲しさを忘れるために、それを紛らわすために酒を飲む、そんな男なのだ。
そうすることでしか、感情を整理できない、悲しい男なのだ。
そこに私の母性がくすぐられる。
救いたいと、相談に乗りたいと、私の母性がそれを私に要求する。
入れ替わった亭主の中で新参の彼だからか、まだ彼の全貌を私は把握していない。
職業すらまともに知り得ていない。
どんな素性の男なのか、私にすら話さない。
彼の奥さんではあるが、彼のことはなにもまだ知らないのだ。
会うなり酒を要求し、ぐでんぐでんに酔って帰るまで、一日中自宅で酒を飲み、時折嗚咽を零しながら、私の顔なんか見ずに、泣きじゃくっている。
むろん衰退期のテレビなんか消したままの、男の泣き声だけが響く静寂の中で、私は彼を静かに見守り、酒を注ぎ、彼が心を開くのを待つ。
彼に肩を貸して、千鳥足の彼を戸口まで運ぶと、その千鳥足で彼は別れも言わずに去っていく。
酒臭くなった戸口で私は、彼に想いを馳せながら、明日を想うのだ。
土曜日の亭主は、昨日一昨日とは打って変わってよく喋る男だった。
といっても、訳ありの職業の男で、男らしいが、包容力は他の六人の亭主とは比べようがないが、危ない橋を渡っていた。
借金取りというか、闇金融で働く男で、腕っぷしが強く、その腕には龍の刺青が彫られてある。
立場もそれなりで事務所のナンバーツーだと自称し、見た目はかなり怖いが、私にはとてもやさしく、喋っていて楽しい彼だった。
赤裸々な愚痴だって、私にはざっくばらんに話し、夜逃げした負債者を追っているとか、職を仲介した不法滞在者が行方不明になったとか、とにかく金がらみで毎日、てんてこ舞いだそうだ。
お金ならあるでしょ? と私は言うのだが、彼は、それは別の話だと、取り合わない。
七人の亭主とは貯金は共有してあるから、別に彼が必死に働かなくても生活は困らない。
他の誰かが稼げば賄えるのだ。
それでも彼は大黒柱のように、まさに大黒柱なのだが、懸命に働き、汗を流して、私を愛してくれる。
「今日もきれいだね」とか、「なにかあったら、俺が守ってやるからな」とか、とにかく私を心配し、その太い腕で私をやさしく抱きしめ、大切に想ってくれる。
夜遅くまで家に居てくれて、彼が帰るのはいつも日が変わるぎりぎりだった。
長居して、すまないねと、別れを惜しむように私を抱きしめると、何度も振り返って私の顔を見て、階段を降り、その姿が消えた。
戸を閉めて、彼の立派な肉体を思い出しながら私はしばらく恍惚に浸るのだが、さらにしばらくして正気に戻ると、思い出したように居間に戻る。
日曜日の亭主は警官だった。
交番に勤める巡査で、本庁からの通達で最近、悪徳な消費者金融を取り締まる、非合法な団体を撲滅する職務に忙しいという。
被害者が年々増え、会う度に、まったく世知辛い世の中だよと、私に愚痴をこぼす。
制服姿ではないが、背筋は伸びて、まさに警察官という感じで、利発そうな表情には正義感があふれていた。
普段、拳銃を所持していないが、特別な時には所持することがあるらしく、最近物騒だからと、冗談で彼は、もしかすると拳銃を撃つこともあるかもなと、上機嫌に笑い、私の笑いを誘う。
真面目な男だったから、自宅でいちゃいちゃしないが、世事を交えた会話は私の知的好奇心を満たしてくれる。
それは彼も同じで、私が聞き手で真剣に聞いてくれるから、疑問を忖度なして私が訊ねるから、新たな視点に感心を示し、彼もやはり満足しているようだ。
七人の亭主の中では、いちばん頼りがいのある男性だった。
むろん昨日の亭主も頼りがいはあるが、見ていて危なっかしいところがあるので、安定を望めば彼一択だろう。
軽い夕飯を一緒に食べて、夫婦団らんの時間を過ごすと、律儀にお礼を述べて、夜勤明けの、そう、彼はあまり寝ていないのだが睡眠時間を削って私の元に来てくれたのだが、そんな疲れの色は一切見せずに笑顔で最後、帰っていく。
戸を閉めて、精かんな顔つきの彼をぼんやり頭の中に浮かべると、私は明日からの週明けに備え、少し早い眠りにつくのだ。
月曜日の朝、いつもなら来ている時刻なのに、亭主が現れない。
時間には厳格な男だから、遅刻するなんて、厳密には遅刻ではないが、私は嫌な予感に包まれ、台所で支度していた朝食を置き去りに、居間のソファに座って震える。
なにげにリモコンを操って、栄枯盛衰のテレビを点けると、報道番組では大々的にニュースを報じていた。
迫真の表情で男性のキャスターが原稿を、カメラ目線で読み上げ、一語一句間違わずに視聴者に伝える。
なにか昨夜未明、銃撃戦があったという。
違法な消費者金融の事務所でのことで、警官が一人殉職したらしい。警官は拳銃を構えて、同じく拳銃を構える組合員と対峙したらしいが、手元が狂ったのか、警官の撃った弾丸は全て外れ、正しくは最後の一発は跳弾して、警官に致命傷を与えた組合員の男の額に当たり、その男も亡くなったそうだ。
当時事務所には撃たれた組合員の他に五人の男がいて、一人は夜逃げした多額の借金を抱えた男で、一人は国籍不明の外国人の男で、一人は借金をしに来た会社員の男で、残り二人は事務所の事務員の男たちで、いずれも銃撃戦に巻きこまれ、亡くなったという。
物騒な世の中だなと、私は台所で淹れたコーヒーを居間のソファに座り直して飲みながら、深刻な表情で事件を伝えるニュースキャスターの低いトーンの語りに耳をすませ、静かな居間でコーヒーをすする。
最後に画面に、被害に遭った男たちの顔写真がテレビ画面いっぱいに映って、私は思わずカップを手から滑らして絨毯の上にこぼしてしまった。
絨毯の染みよりも、私は動揺してしまった。
画面に映し出されたのは紛れもなく、私の七人の亭主たちだった。
写真映りの違いはあるものの間違いはない。
誰もが私のよく知る男たちだったのだ。
くり返し、ニュースキャスターの男が伝える。
全員、銃撃戦に巻きこまれて亡くなったと、そればかり何度もカメラ目線で、視聴者の私に伝えてくる。
カップを拾い上げるとそれを私はなにも考えずに画面に投げつけた。
それで、過渡期をすぎたテレビは壊れてしまった。
散らばるカップの破片なんか気にせずに、私はまたソファに座り直すと、あふれる涙を止められない。
私は一夜にして、七人の亭主たちを、手のひらの砂をこぼすように失ってしまったのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
