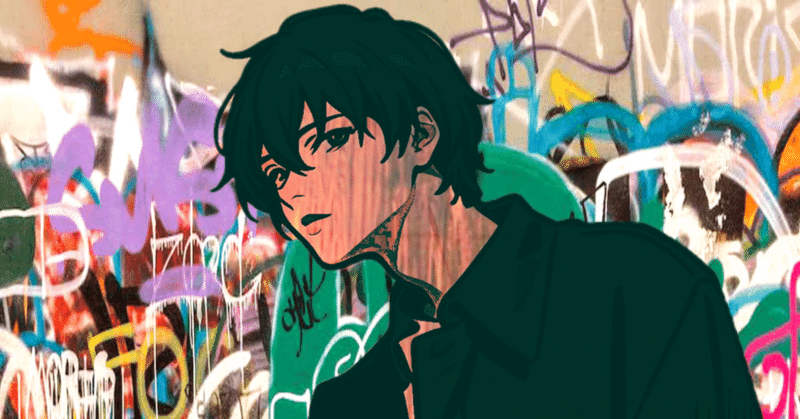
雑文(02)「兄貴は姉貴で、姉貴は兄貴」
「薄々だけどさ、気付いていたよ」
実弟が、実兄にそう言って、実兄は、驚いた容子で、「驚かないのか」と、実弟の冷ややかな態度に驚いた。
「有名私立大学卒で、スポーツ万能でルックスもいい。なのに四十すぎても今まで誰とも付き合ったことがないなんて弟目線の甘々で見ても有り得ないだろ?」
「そういうもんかな?」
「そういうところだよ」
実兄は、実弟をぼんやり眺める。
「それはね、僕からしたら、友だちに自慢できるいい兄さんだけどさ、兄さんがそれでいいなら僕は全然構わないんだけどさ、兄さんが幸せなら」
「幸せだよ。こんな可愛い弟がいるんだから」
「そういうところも。仕事もできて貯蓄だってけっこうあるのに、兄さん、言い寄ってくる女性を皆んな、兄さんを狙っている女性をさ、きっと」
「そんな金目的の奴らなんか、俺は目にないさ」
「そういうところだよ、兄さん。そういうところが駄目なんだって」
「駄目なのかな」
実弟は実兄にわかるくらいあからさまな深めのため息を吐いた。実兄はあからさまなため息の深さの意味がわからず、仕事大変なんだな、と、暢気な空想に浸って、実弟に微笑んだ。
「笑い事じゃない」
「そうだな。おまえも仕事大変なんだろ?」
「何の話だよ」
「いいからいいから、きょうはリラックスしろよ」
実弟は話の合わない実兄に苛立ち、実兄にわかるくらいあからさまな舌打ちをしたが、実兄は、ストレス溜まってんだな、と、暢気な空想にまた浸って、実弟に微笑んだ。
「で」実弟が痺れを切らした。「大事な話って何の話? 兄さんのことだから、付き合ってる女性がいるとか、有り得ないだろうけど」
「そうだな」と、実兄は一言置いて、実弟に、鬱陶しそうなその瞳をのぞき込んで話しはじめた。「まあ、だな。俺は」
「なんだよ。まどろっこしいな」
「率直に言うとだな。つまりアレだ」
「岡田監督かよ。古いよ、そのネタ」
「結婚する」
実弟は悲鳴に近い叫び声を上げた。余りに予想外だったからだ。叫んでしまった。大の大人が。
「あした大地震が来るのか」実弟は身体を震わして続ける。「おめでとうと言っていいのか、よくないのかわからないけど、おめでとう。やっと兄さんも腰を」
言いかけた実弟に実兄は補足する。「いまはできない。当分は無理だろうね、いまの政権じゃあ」
「何言ってんの?」
「まあ、そのだな。俺に好きな人ができたが、いやずっと好きだったんだが」
「ああ」勘のいい実弟は短く唸った。「いまは結婚できない。いまの政権じゃ、将来不安だからな。将来のこと、ちゃんと考えていて、ちょっと安心したよ、兄さん」
「いや、まあ」
「誰? 昔からっていうと、顔馴染み?」
「まあ、そうだな」
「俺は知ってるのかな?」
「よく知ってると思う」
「教えろよ、兄さん」そう言って実弟は、実兄の広い肩に肩を寄せて、言い詰める。
「ずっと好きだった」
「なんだよ、いきなり。いきなりステーキは店舗を急拡大した経営者の誤った判断で今潰れかけだぜ。それと原材料費の高騰と、物価高による人件費賃上げの影響で」
「違う。好きだった」
「おいおい」実弟は全身から汗を噴き出した。「そろそろ出ようぜ、暑くなってきた」
実兄が柄杓を手にすると、掬った桶の水を中央の焼け石にかけた。焼け石の熱で蒸発した水分で部屋の中はちょっと温度が高くなった。
「どうだ?」実兄が実弟を見つめたが、実弟は耐えきれず目を逸らした。「どうって? 何がどうなんだよ」
「国は法律で認めてないが、大丈夫だ」
実弟が首を捻った。
「血縁関係だから今は結婚できないが、だから付き合ってもいいはずだ」
「どういう解釈だよ」
「そういうことだよ」
実兄が実弟に身体を寄せて詰め寄る。「だからどうなんだ? 返事は」
「返事も何も」
実弟は過剰な汗で眩暈がした。「おい、どうした」と繰り返す実兄の薄れる声かけが最後の意識だった。
次に目覚めたとき、実弟はサウナ室の外で仰向けに天井をぼんやり眺めていた。
「よかった、よかった」と数人の声がして、しばらくして実兄の声がした。「よかった、意識を戻したか」
「俺は」と言いかけて実弟はぞっとした。見逃さなかったのだ。実兄のその動作を。
実兄は手の甲で口許を拭って、口角を上げて微笑んだのだ。
「何をしたんだっ」と、実弟は叫びたかったが眩暈の後遺症でうまく呂律が回らない。
「負ぶってやるから」実兄は言う。「きょうは泊まっていくといい。安心しろ、ずっと付いててやる。なんせおまえは俺にとって大切な弟なんだから」
実弟は喚くように叫んで、気をまた失った。
次に目覚めたとき、実弟はベッドの上に寝かされていて、仰向けに天井をぼんやり眺めていた。
逃げなくちゃと思ったが、手足が言うことを利かない。なぜか気力が削がれていた。まさかと思ったが、考えるのを止めた。
聴覚を戻った。聴覚はシャワーが止まるのを捉えた。ドアが開き、吐き出された蒸気で室内の温度がわずかに上がった。湿った足音がフローリングの床にへばり付き、着実にそれは近付いて来ていた。
寝室のドアがゆっくり開いた。
白いバスローブを着た、兄貴。いや、実弟は、「姉貴」と、つい思った本音が口に出て、言われた兄貴、いや姉貴は、困惑する実弟に微笑んだ。
「いつからだよ」弱々しく実弟は言うのみだ。
「この日を逆算してだな」
元々がモデル並みに整った顔付きだから、拒否はできたが拒否しなくてもいい気分に、実弟はなぜかなっていた。「いいのか」
「それがおまえの答えだな?」実兄は実弟に確認した。実弟は小さく肯いた。実兄は笑って、ベッドの端に腰掛けた。「法整備はされていない。だから大丈夫、血縁関係があっても付き合っていいはずだ。合法だ。違法じゃない」そう言って、実兄は、いや姉貴か、姉貴は実弟に覆い被さり、実弟はいい匂いのする実兄に、いや姉貴に抱かれ、遠い日に空想した、思春期初頭に妄想した、兄貴が姉貴だったらどんなにいいだろう、が、遠い歳月を経て、その妄想は実体化して、四十すぎの実弟を襲った。
兄貴は姉貴で、姉貴は兄貴
実弟は心の中でそう呟いて、兄貴、いや姉貴、いや兄貴か、抱かれて妙に清々しい気持に包まれ、実兄もまた、実弟に呼応した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
