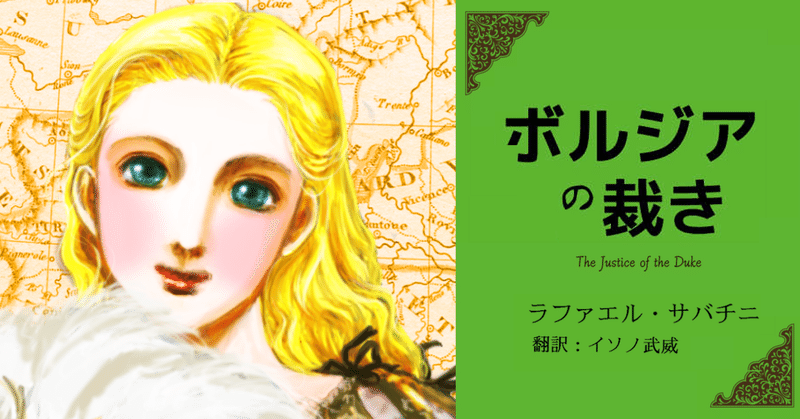
Ⅰ ヴァラーノの名誉
ⅰ
ヴァレンティーノ及びロマーニャ公爵チェーザレ・ボルジアは、ゆっくりと椅子から立ち上がると、悠然とした足どりでイーモラの城塞内にある広々とした部屋の窓に向け歩んでいった。秋の日差しの中で窓辺に立ち、天幕が張られた草原とその向こうの川、そして、かの一筋の長い道、いにしえのヴィア・アエミリア(エミーリア街道)を見下ろす。それは遠くに幾つかの建物がかすんで見えるファエンツァの町へと消えるまで、完全な一直線を描きながら続いていた。
イタリア北部を斜めに横切るその道――かのルビコン川からピアチェンツァまで百里にわたる、ほぼゆるぎない直線――は、およそ1500年前にはマルクス・アエミリウス・レピドゥス【註1】の誇りの源であったかもしれないが、この秋の日に同じ街道を見つめるチェーザレ・ボルジアにとっては苛立ちの源――あえて招集せずにいる援軍が通って来るはずの南北を往来する道に過ぎなかった。
そして再び、彼の視線は街道から、川の側に広がる草原に設営されている包囲陣へと移った。其処では皆がせわしなく動き回り、人馬の絶え間ない活動は蟻の群れさながらに勤勉だった。手前では工兵の集団が、彼の本拠への突破口を開かんと大砲を設置していた。その向こうには武具をきらめかせた複数の人影が周囲を行き来している大きな緑の天幕があり、その中に納まっているのが大胆不敵なるヴェナンツィオ・ヴァラーノなのだ。更に西へと目を転ずれば、半裸の男たちが鶴嘴とシャベルを振るい、川から水を引き込むための溝で作業をしている。あれは彼らが包囲している砦内からの奇襲に対して、塁壁の役割を果たすものであった。
この一連の作業により発せられる騒音のかすかな反響は、高所にある砦にも届いており、彼は蔑みと怒りの狭間でそれらに呪詛を吐いた。蔑み、それは自分が指一本上げさえすれば、頭上の青空に雄飛する一羽の鷹に気付いた雀の群れが散り散りになるがごとくに、あの大層な軍は四散するであろうという考えによる蔑みだった。怒り、それは手の内を見せることによって、現段階では未完成な別の大きな計画に支障をきたす可能性があるゆえに、あえてその指一本を上げずにおかねばならぬという深慮からの怒りだった。更にまた蔑み、それはこのヴァラーノという名のうつけ者自身に向けられたものであり、チェーザレ・ボルジアは万策尽きて、ヴァラーノが編成したような少数の――軍事市場で雑にかき集めた――傭兵たちの餌食となるであろう、などと想像するような、浅はかな蛮勇に対する蔑みなのであった。そしてまた怒り、一日といえ、一時間といえ、ヴァラーノがそのように考え続けるのを許さねばならぬことに対する怒り。この無反応なイーモラに対し、そしてマスキオ塔にひるがえる牡牛の紋章が描かれたボルジア家の旗の下、晩秋の日差しを浴びながら静かにまどろんでいる茶色の城塞に対し、あのカメリーノのうつけ者は、一体、どれほどの思い上がりから包囲を命じたのであろうか。
背後の部屋で忍ばせた足音が立てられたが、公爵は気付かなかった。それは彼が如何に集中していたかの証明であった。何故ならば、彼のように鋭敏な感覚の持ち主は他におらず、彼のように鋭い知性と野生動物のような優れた身体能力を併せ持つ人間も他にはいなかったからだ。彼を眺めてみれば、そのような一切は全て納得できるだろう。若さの盛り、二十七歳の彼は、長身で姿勢がよく、鋼のようにしなやかだった。彼の父である教皇アレクサンドルⅥ世は、青年期には同時代で最も容姿に恵まれた男といわれていた。その美貌は女性たちに対して磁石のように作用し――それは聖職者に求められる高潔な道を歩む助けにならなかったのだと。その美はチェーザレに受け継がれ、それのみならず、彼の生母であるローマの女性、マドンナ・ヴァノッツァ・デ・カタネイの優美によって洗練され、更なる輝きを与えられていた。絹のような黄褐色の髭に半ば隠された朱唇は官能的であったが、その印象は淡い眉の威風によって改められていた。鼻は流麗な曲線を描き、その鼻孔は繊細であり、そしてその目――一体、このハシバミ色をした目の輝きを言葉で表現し得る者がいるであろうか?その真意を正しく読み取り、冷ややかな無表情の下に隠された、その意志を、知性を、おぼろな憂愁を、言葉によって描き得る者がいるであろうか?
その全身は黒で装っていたが、天鵞絨の上衣の切れ込みからは金布地のシャツの豪奢な黄色が鮮やかに光り、ウエストにはルビーをちりばめた帯を締め、腰には精緻な細工がほどこされた金の鞘に納めた金柄のピストイア製短剣を下げていた。彼の黄褐色の頭は無帽だった。
再び背後で忍び足のきしみが立てられたが、それはまたしても気付かれなかった。それとは別に、よりはっきりとした足音が彼の部屋へと続く階段に聞こえたが、尚もチェーザレは身動きしなかった。彼は張りついたようにヴァラーノの陣を観察し続けていた。
扉が開き、また閉じられた。何者かが入室し、彼に向って歩み寄ってきた。それでも彼は身じろぎひとつしなかったが、姿勢はそのままで口を開き、新来の者に名指しで話しかけた。
「それで、アガビト」と彼は言った。「私の召喚状は、ヴァラーノめに送ったのか?」
秘書であるアガビト・ゲラルディほどにはチェーザレの流儀に慣れていない者にとって、これはほとんど奇怪にすら思われたかもしれない。しかしアガビトは主人の異常な鋭さを熟知していた。その知覚は盲人並みに鋭敏で、余人ならば姿を目にするまでわからない足取りも判別できるほどであった。
チェーザレが振り向くと、アガビトは一礼した。彼は中背で恰幅のいい男性であり、表情豊かで諧謔味のある口と鋭く黒い目をしていた。年の頃は四十歳あたり、書記という役職から膝まである黒い上着をまとっている。
「既に先方に届けております」と彼は答えた。「されど、あのカメリーノの紳士が招きに応じるとは思えませんが」
アガビトは自分を見透かして、更にその向こうまでを見つめているような公爵の視線を観察した。沈思と無為、主人の眼差しは、そのように見えた――既に述べた通り、この秘書は主人について熟知していたが、その親密さをもってしても尚、チェーザレの不可解な視線の意味を測りかねていた。公爵の両目は物憂げな見かけに反して慎重かつ油断なく観察し、その後ろでは結論を導き出すべく高速で頭脳が稼働していた。精緻な彫刻がほどこされた書きもの机の向こうに吊るされているアラス織が、かすかにではあるが揺れている。これをチェーザレは――傍からは、もの思いにふけっているように見えたが――観察しており、室内の空気が静止している以上、通風ではその現象を説明できないと考えていた。しかし彼が口を開いた時、その観察も結論も一切表には出さなかった。
「そなたは悲観主義者か、アガビトよ」と彼は言った。
「ご慧眼恐れ入ります」秘書はチェーザレが彼に許している打ち解けた調子でそう応じた。「とはいえ、彼が来ようと、来るまいと、問題ではありますまい?」アガビトは目の周りに皺を寄せて微笑んだ。「常に裏口というものは存在するのですから」
「お前のいまいましい悲観主義のお陰で、またも思い出してしまったではないか。裏口は存在するが、ただ存在するだけだ」
アガビトは両手を広げ、とばっちりを受けたとでもいうように顔をしかめた。
「その裏口を開こうとする者が、何処にいるというのだ?」公爵は問うた。
「同盟に裏口の存在を知らせて掛け金を外してやったとて、その音が聞こえただけで奴らは震え上がり、皆が私を避けて逃げ出すだろう。裏口、よく言ったものだ!耄碌したな、アガビト。あの浅はかな愚か者を退却させる策を示してみよ、私がここで対処できるような手段でだ」
「残念ながら」秘書は絶望的な溜息をついた。
「まったく、残念至極だ!」公爵は鋭く言い放つと、秘書の脇を通り部屋の奥に歩み入った。彼は其処で現状を思案しつつ、しばし歩きまわり、アガビトはそのような主人をじっと見守っていた。
この問題よりも険しい難所というのも他にはなかったであろう。これはオルシーニ一族が、チェーザレに反旗を翻した傭兵隊長のヴィッテリとバリオーニ両名と手を結び、彼に対抗する同盟を形成した時期のことであった。この一万の軍勢からなる反抗勢力は、彼を破滅させんと決意し、彼に死をもたらさんと誓っていた。この者たちは抜け目なく網を広げて彼を囲い込み、無害化し、その力を搾り取ったと信じていた。そしてチェーザレは、彼のために編まれた網で反抗勢力が自縄自縛に陥ってくれれば好都合という理由から、チェーザレ・ボルジアは力を失い備えもできていないという思い込みを正さずにおいた。その錯誤を更に助長するために、彼は意図的にフランス槍兵隊――まさに彼の軍隊の基幹である――のうち三部隊を解雇し、それがヴァレンティーノ公爵と仲をたがえた隊長たちに率いられて自主的に去ったかのように吹聴させた。かようにして、チェーザレの終焉を告げる鐘の音が鳴り響いたかと思った同盟軍は、早くも彼を自らの獲物とみなすようになっていた。何故ならフランスの槍兵隊を失ったボルジアの兵力など、恐るるに足るものではないのだから。しかし彼らはナルドがチェーザレのために編成したロマーニャ兵部隊について全く把握しておらず、ましてスイス歩兵や、ロンバルディアで彼の士官たちが確保しているガスコーニュ傭兵については知る由もなく――いざ、その時が来るまでは、そのような兵力の存在を察知することはないはずであった。チェーザレが指一本上げさえすれば、たちまち同盟諸国の心胆を寒からしめるだけの軍勢が出現するのだ。それまでの間、誤った安心によって動きを鈍らせた同盟軍には、彼を捕らえる罠の準備をしていて欲しかった。彼は悠々と、その罠に足を踏み入れるだろう。だが――神のお陰をもって!――その中で動じるようなことは一切ない。そのバネ仕掛けは跳ね返り、奴らを捕らえ、粉砕するのだから!
綿密に策を練り、王手をかけるために必要となる動きを緻密に計算し――そして気付いてみれば、甚だしい思い上がりゆえに足元にある火山を一切気にかけずに居座り続けるカメリーノの愚か者の軽挙によって、かえって膠着状態に陥っているのが現状なのだ!
経緯はこうである。カメリーノの支配者の座を追われた僭主のひとりであるヴェナンツィオ・ヴァラーノは、同盟軍の停滞に焦りながらも迅速な行動をうながすことができず、自ら武力をもって事態の解決に臨んだのである。様々な国から流れて来た向こう見ずな食いつめ傭兵たちをかき集めると、推定千人程度の手勢を率いてイーモラに進軍し、ヴァレンティーノ公爵の砦を包囲し――双方の作戦計画にいらぬ干渉をしたことによって、同盟からもチェーザレからも呪詛されたのであった。
「恐らく」ややあってアガビトは発言した。「同盟がヴァラーノに与すれば勝算ありと認めたならば、この地で彼に合流しようとするでしょう。さすれば我が方に勝機が生まれるはず」
だがチェーザレは苛立たしげに手を振った。「どうやって、ここに網を張ればよいというのだ?」彼は問うた。「奴らの手勢を敗走させることはできようが、それが何だというのだ?私が望むのは、その頭だ――それも一撃で刎ね落としたいのだ。話にならぬ」そして結論した。「ともかくも、この招きにヴァラーノめが如何なる返答を寄越すか、何が起こるかを確かめてみようではないか」
「何も起こらなければ、こちらから打って出るのですね?」アガビトはうながすように言った。
チェーザレは顔を曇らせつつ思案した。「まだだ」と彼は答えた。「何らかの機会に望みをかけて待つ。好機――我が勝運にだ、心せよ」彼は大きく精巧な造りの書きもの机に向かうと、其処で一通の封書を手に取った。「フィレンツェの僭主に宛てた手紙だ。既に署名してある。どうにかして、それを届けるのだ」
アガビトは包みを受け取った。「かなりの工夫が必要になりましょうな」そう言って彼は唇をすぼめた。
「任せたぞ」と告げた上で、チェーザレは彼を下がらせた。
秘書が扉を閉め、その足音は石の階段を下っていき、やがて聞こえなくなった。それから部屋の中央に立つチェーザレは、アガビトが退出していった出入り口で微動しているアラス織と対した。
「さあ、姿を現すがよい、間諜よ」至極おだやかにそう告げた。
ここから先は
英国の作家ラファエル・サバチニによるチェーザレ・ボルジアを狂言回しにした短篇集"The Justice of the Duke"(1912…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
