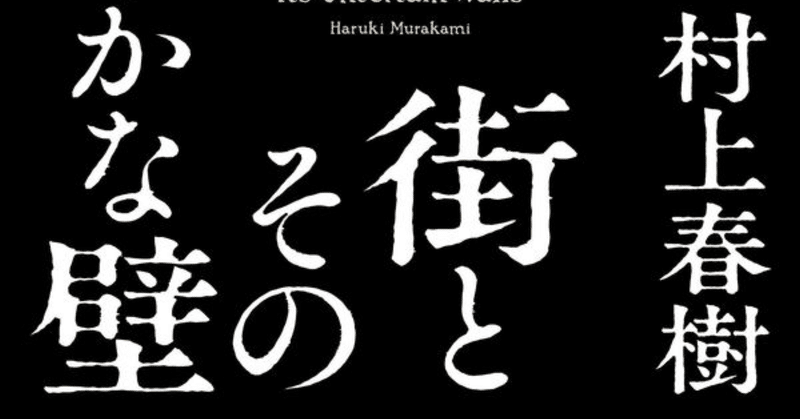
村上春樹はスマホで読め──『街とその不確かな壁』感想
村上春樹の新作『街とその不確かな壁』(講談社)を読んだ。大変よかったので、その理由について書く。なお、私はキンドルで購入してスマホを横向きにしながらこの小説を読んだ。この読書形態がかなり評価に影響していると思うので、それを考慮しながら読んでほしい。以下あらすじ。
*
物語は、17歳の〈ぼく〉が16歳の〈きみ〉と仲睦まじく過ごしている場面からはじまる。2人はセックスこそしないものの、恋人に近い、非常に親密な関係を1年近く続けた。やがて〈きみ〉は、〈ぼく〉に〈街〉の話をするようになる。現実社会に居場所のないように見える〈きみ〉は、自分の存在は影で、本体はその〈街〉にあるのだと語る。そしてある日を境に、〈きみ〉は〈ぼく〉の前から姿を消し、〈ぼく〉の心には深い傷が残った。
一方、45歳の〈私〉はその〈街〉に迷いこんでいた。そこには16歳の姿のままの〈君〉もいる。〈私〉は17歳の頃に負った深い傷を癒すことができず、45歳になっても独身のまま過ごしていたところ、気がつくと〈街〉にいた。〈街〉では、現実での居場所を失っていた〈私〉にも〈夢読み〉という仕事が用意されている。その街には時間がないので、永遠に〈君〉と共に暮らすこともできる。
だが、その〈街〉に居続けるためには、〈私〉は代償として自分の〈影〉を失わなければならない。〈影〉は世界に対する批判精神のような、心の暗い部分のような何かだ。〈私〉から切り離された〈影〉は、〈街〉を出て外の世界に戻るべきだと〈私〉に忠告する。〈街〉には時間の概念がなく、猫もおらず、音楽もなく、固有名詞も存在しない。テーマパークのような美しい〈街〉を維持するために、犠牲になる存在もいる。やはりここは「本当の世界」じゃないのだと、〈影〉は言う。
選択を迫られた〈私〉は、一度は迷うが、結局〈街〉に残ることを選ぶ。外の世界に戻ることの意味がどうしても見いだせなかったからだ。戻ったところで、自分はますます孤独になり、深い闇に直面するだろうし、幸福にもなれないだろう。この〈街〉はたしかに矛盾の上に成立しているが、ここにいれば少なくとも孤独にはならないし、やるべき仕事もある。〈私〉を置いて外の世界へと脱出していった〈影〉を見送って、第1部は終わる。
第2部では、〈街〉を選んだにも関わらずいつのまにか外の世界へ戻っていた〈私〉のその後の物語が描かれる。〈私〉はふしぎな流れに導かれて、それまで勤めていた取次の会社を辞め、福島県にある私営図書館の館長へ転職する。その図書館の先代館長である子易さんは、死者であるにも関わらず霊魂として〈私〉と会話することができた。
対話を重ねるうちに、〈私〉は子易さんの人生を追体験していくことになる。若い頃文学青年としてフラフラと過ごしていた子易さんは、35歳で運命の女性と出会い、結婚し、産まれた子どもへの継承を考えることで、人生を幸せに送れるようになった。しかし、ある時子どもを交通事故で失い、それをきっかけに妻も自死してしまった。子易さんは二人を失った傷を癒すことができず、その後の人生を独身として過ごした。だがその後、子易さんは子どもの代替のようなもの、「失われた心を受けいれる」ための図書館を作り、70代半ばで亡くなるまで人生をまっとうしたという。
一方、その図書館には、17歳の少年もいた。少年はサヴァン症候群で、現実に居場所を持たず、読書に耽溺している。そして〈私〉の一人語りを盗み聞きして、〈街〉の存在を知り、そこへと行こうと決意してしまう。〈私〉は困惑する。まだ若い彼を外の世界から〈街〉へと送り出す、それはモラルとして許されることなのだろうかと。
悩む〈私〉は子易さんに相談する。その少年にどう向き合うべきか。子易さんは、〈私〉が思い悩む必要はないと諭す。〈街〉の存在を少年に伝えることで、〈私〉はすでに何かを少年に継承した。少年はそれをきっかけに、自分の人生を自分で選ぶことになる。そして〈私〉もまた、自分の人生を自分で選んでいけばよい。そう言い残して子易さんは消え、二度と戻らなかった。少年は〈街〉を求め、誰にもわからない方法で失踪した。
残された〈私〉は、もはや自分に〈街〉へいく資格がないことを嘆きながら、ある女性と交際する。しかし、女性と交流する中で〈私〉に浮かび上がってくるのは、あの頃の「きみ」の面影ばかり。ある程度幸せだが、かつてのような100%の体験はできない。やがて〈私〉は現実感覚を失い、どこか分からない場所にいく。そこで再び〈きみ〉と出会って、第2部は終わる。
第3部はわずかしかない。〈街〉に残っていた〈私〉のもとへ、少年がやってくる。それをきっかけに、〈きみ〉は〈彼女〉になり、少女からひとりの女のようになる。〈私〉はこの〈街〉に自分の居場所がなくなっていることに気づき、少年に「夢読み」の仕事を引き継いで、〈街〉を出ることを決める。少年は言う。「あなたの分身の存在を信じてください」。それが自分を信じることになり、この〈街〉から〈落下〉した〈私〉を助けてくれるのだという。〈私〉が〈街〉を捨てるために、ロウソクを吹き消して暗闇に包まれたところでエンド。
■〈街〉と〈影〉の意味
この小説が描いている物語は、具体的には何を伝えているのか。本作において鍵となる言葉は〈街〉と〈影〉だ。物語の中で、「私」はつねにこの2つのどちらかを選ぶよう迫られている。そして、これを何のメタファーとして捉えるかで、小説の内容はまったく変わってしまう。
たとえば、〈街〉を他者のいない幸福なディストピア、〈影〉を他者と関わろうとする社会的な意識とする。するとこの小説は、いかに自己と他者の折り合いをつけて社会に関わるか、という思春期的な(おそらく中年の危機も老年の危機もそうなのだろうが)悩みを描いたもの、『新世紀エヴァンゲリオン』を筆頭に90年代以降のアニメで執拗に描かれてきた物語になる。そこでは、〈街〉からの脱出は社会復帰を意味する。この視点を採用すれば、本作は「中年男性の自分探し」と表現できるようになる。
しかし、村上は団塊世代で、全共闘やその残滓があった頃に大学に身を置き、過激派とも近い場所にいた元・新左翼だ。そう考えると〈街〉は、社会が安定すると同時に進歩や体制変更への期待(つまり時間的概念)も失われた1980年前後の(犠牲者を伴うテーマパークとしての)日本であると捉えることもできるだろう。この場合、〈影〉とは左翼的批判精神のこと、〈街〉からの脱出は「日本社会、または80年代的停滞からの脱出」を指すようになり、先ほどのそれと正反対の意味を帯びてしまう。
また、本作は1980年に発表された中編小説「街と、その不確かな壁」を書き直したものである。その中編の最後の章で村上は「僕はかつてあの壁に囲まれた街を選び、そして結局はその街を捨てた」と書いている。私小説的に読み解くと、村上がその時点で〝捨てた〟であろうものはベタな左翼性くらいだから、〈街〉は大学や左翼的精神であり、〈影〉とは健全な社会性ということになる。こう読めば、本作は(無関係の大学生がリンチ被害に遭い殺された)川口事件など当時の学生運動への反省を含んだ作品ということになるだろう。
■45歳にもなって、フィクションに耽溺していていいのか?
これらの読み解きはいずれもそれなりの説得力を持っていて、「正解」とも「不正解」とも言いがたいかもしれない。文章は、意識的にどれともつかないようなものとして描かれているようにも見える。しかし私は、〈街〉をフィクションとして、〈影〉を社会の中の自分として読んだ。この場合は、「物語についての物語」としてこの小説を読んだことになる。
なぜそう読めるのか。それはたとえば、以下のようなシーンの存在による。小説から直接抜粋しよう。第2部、物語後半で交際することになるコーヒーショップの店長と〈私〉が、初めて会話する場面だ。
雪の舞う月曜日の朝のコーヒーショップには、私の他に客は一人もいなかった。いつもの女性──髪を後ろでぎゅっと束ねた、おそらくは三十代半ばの女性──がカウンターの中で働いているだけだ。そしていつものように小さな音で古いジャズがかかっていた。ポール・デズモンドがアルトサックスを吹いていた。そういえば最初にこの店に来たときデイヴ・ブルーベック・カルテットがかかっていて、そこでもデズモンドがソロを吹いていた。
「ユー・ゴー・トゥー・マイ・ヘッド」
と私は独り言を言った。
女性がマフィンをオーヴンで温めながら、顔を上げて私を見た。
「ポール・デズモンド」と私は言った。
「この音楽のこと?」
「そう」と私は言った。
「ギターはジム・ホール」
「ジャズのことは私、あまりよく知らないんです」
と彼女は少し申し訳なさそうに言った。
そして壁のスピーカーを指さした。
「有線のジャズ・チャンネルをそのまま流しているだけだから」
私は肯いた。まあ、そんなところだろう。ポール・デズモンドのサウンドを愛好するには彼女は若すぎる。(中略)
そしてそのときふと思った。そういえば、あの街では音楽というものをまったく聴かなかったな、と。
さらりと書かれているが、このシーンでの「私」はあまりにも醜い。〈私〉は、よく行くコーヒーショップの店主の若い女性に好感を持っている。そこではいつも渋めのジャズが流れていて、ジャズが好きな〈私〉は、好みの女性と好みの音楽が合わさって若干興奮している。興奮しすぎてつい、「ユー・ゴー・トゥー・マイ・ヘッド」と曲名を口に出して言ってしまう。これを「独り言」と認識しているのはひどい。店内に二人きりの状況で言っているわけだから、実質的には話しかけている(つまり女性にアプローチしている)ようなものである。なのに、その事実が恥ずかしくて自意識の中では予防線を張っている……しかも予防線を貼っていることを自分では意識できていない。そのように描かれているように見える。
「ユー・ゴー・トゥー・マイ・ヘッド」「ポール・デズモンド」と、赤の他人にしたり顔で固有名詞を連呼している45歳のおじさんに対して、店主の女性は「この音楽のこと?」と返す。疑問で返しているのだから、女性はジャズに詳しくない。この時点で、女性が最初に〈私〉が想定していたであろう「若い娘なのにおじさん的趣味に精通している(萌え4コマ漫画に出てきそうな)理想の女性」でないことははっきりしているわけだ。にも関わらず、この期におよんで〈私〉は「ギターはジム・ホール」とさらにマニア的固有名詞を続けてしまう。
結果、「ジャズのことは私、あまりよく知らないんです」となぜか女性の側が申し訳なさそうにする。客相手だから、こういう厄介コミュニケーションにも丁寧に接しなければならない。ふつうなら、そんな対応をさせてしまったことを反省して「いやすみません、ジャズが好きなもんでつい……」とでも謝罪する。が、〈私〉は何も言わずに肯いて「まあ、そんなところだろう。ポール・デズモンドのサウンドを愛好するには彼女は若すぎる」と勝手に(失礼に)納得する。本当は好みの女性との会話に失敗して明らかにガッカリしているのに、そのガッカリした感情を自分で認めようともしない。さらには自分の思い通りにいかない現実を離れて、〈街〉について考えはじめる──なんとも情けないが、この小説の主人公は、そういうタイプの人種として、空想に耽溺しがちで対人コミュニケーションが苦手な中年男として意識的に描かれているのだ。そしてこの場面において〈街〉は、他者のいないディストピアや、学生運動や、80年代の日本としては使われていない。それは明らかに、物語やフィクションの同義語として扱われているように見える。
〈私〉もまた、自分がフィクションに耽溺してばかりのダメ人間であることを、本当のところは自覚している。そこで、人生の先達である子易さんにこう相談する。自分は、30年前の恋愛にいまだ囚われ続けている。その恋愛は「純粋ではあるけれど、どう見ても未熟」で、「時の検証も受けていない、様々な現実的障害にも出会っていない、十代の子供たちの甘い恋愛ごっこ」にすぎない。そして〈私〉は、既に中年の域に足を踏み入れている。「そんな人間が失われた少年時代の想いを求めて、こちらの世界とあちらの世界を往き来する──それは果たしてまともなことなのでしょうか?」。
会話のテーマは恋愛のようにも見える。だが、恋愛を扱いたいなら今の恋愛の話をすればいい。わざわざ30年前の恋愛について語っているのは、それがフィクションの比喩的な表現であるからだ。「いい歳をした人間が失われた少年時代の想いを求めて、こちらの世界とあちらの世界を往き来する」のは村上春樹作品の特徴であり、またフィクションを読むという行為そのものを表しているともいえる。中年にもなってフィクションを読み、耽溺する。それは真っ当なことでありうるのだろうか? これがこの小説の一つの主題である。
■物語を読むことについての物語
この主題を念頭に置くと、物語は一気に明快になる。〈街〉でも現実でも〈君〉が〈私〉とセックスしてくれないのは、その恋が現実ではなくフィクションの比喩だからだ。〈きみ〉の本体が〈街〉にあるというのは、辛い現実から逃れてフィクションに耽溺しているということの言い換えだ。夢を読むことが仕事の謎の職業〈夢読み〉とは、フィクションを読む読者のことであり、〈街〉に入る時に分離する〈影〉とは、自分の中の社会的な側面のことである。
第1部では、フィクションに耽溺する中で、現実感覚を失い、社会の中で生きることの意味を見出せなくなった〈私〉が現実への帰還を断念する様子が描かれる。ここで描かれているのは「フィクションを読んでいる私」こそが本物の〈私〉で、「社会の中で生きている私」はかりそめの姿にすぎないという──わりあい多くの人が陥っていそうな──状態が生まれる様子だ。
そうは言っても社会生活はしなければならないので、第2部では社会の中で生きる〈私〉が描かれる。が、その生活は大半がフィクションについての思考で埋め尽くされている。しかも、自分に影響された少年まで同じことに巻き込もうとしている。こんなことでいいのだろうか、この歳でフィクションに耽溺するのは真っ当なことだろうか、と人生の先輩・子易さんに相談すると、子易さんは「自分の人生は自分で選びとるもの」だとアドバイスして消え去ってしまう。現実の女性との交際はイマイチうまくいかない。が、少年のように全てを捧げてフィクションに浸ることももはやできない。最後の場面で、〈私〉は想像の中の〈きみ〉にこう言われる。「ねえ、わかった? わたしたちは二人とも、ただの誰かの影に過ぎないのよ」。つまり、〈私〉は第1部と同じように、かつての〈きみ〉──現実に居場所がなく、フィクションを読んでいる時だけが真実に思える人──と同じ状態に陥ってしまったのである。
だが、その状態から抜け出す道もある。作家志望の子易さんがこの世から消えたのは、〈私〉と少年に図書館というフィクションを受け継ぐことができて満足したからだ。同じように、〈私〉も〈街〉の存在というフィクションを少年に受け継いだ。そしてフィクションの世界に読者としてやってきた少年の助けを借りて、〈私〉は現実に帰還する。〈落下〉とは、何らかの理由でフィクションに熱中できなくなる瞬間を意味する。そんな時、〈私〉を受け止めてくれるのは、まがりなりにも社会生活を送っている分身=〈影〉の自分である。〈影〉の自分は、人生の充実感こそないものの、先輩である子易さんの遺したフィクション=図書館を受け継ぎ、それを後輩に伝えた。フィクションに耽溺してばかりのダメ男は、ダメだからこそフィクションを通して(同じく現実に居場所のない)他人と関わることもできた。フィクションに耽溺した自分の実人生を、それそのままで信じてみようではないか──。これこそ、この小説が描いたメッセージである。
■つながりすぎる世界への拒絶
ここまででいったん話は終えられるのだが、この小説にはフィクションに関連してもう一つの主題が描かれているから、そちらについても書いておこう。それは、フィクションよりも現実を尊ぶ、別の言葉で言えば、すべてを合理的な言葉として表現しようとする人々への反発であり、それをしないことの尊重である。
たとえば、この小説には「スマートフォン」という言葉が登場しない。「赤いプラスティック・ケース」に入った「画面をタッチして」使う「携帯電話」は登場するが、それを「スマートフォン」と呼ぶことはない。また、第2部の舞台となる福島県の田舎町の駅前を、〈私〉は「中に入りたいという気持ちになるような店」が全くないと切り捨て、「地元の人々はおそらく無個性なワンボックス・カーや軽自動車に乗って郊外に出かけ、無個性なショッピングモールで買い物をしたり、食事をとったりするのだろう」とわざわざ攻撃的な言い方をする。そこにあるのは、世界がつながること、普遍化すること、均一化されることへの忌避感だ。次のような一節にも、それはよく表れている。
〔筆者注:サヴァン症候群の少年には、生年月日から一瞬でその曜日を割り出せる特殊な能力があるが、〕しかし自分の誕生日が何曜日だったのか、グーグルを使って調べれば、今では十秒もかからず誰にでも簡単にわかってしまうのだ。少年はそれをたった一秒で言い当てることができるわけだが、西部劇のガンファイトではあるまいし、十秒と一秒との間にどれほどの実利的な差があるだろう? 私は少年のために、少しばかり淋しく思った。この世界は日々便利に、そして非ロマンティックな場所になっていく。
ここで主張されているのは、情報通信の発達によって世界がつながり、ロマンティックな部分がなくなっていくことへの反発だ。〈私〉の先達である子易さんもまた、いまどき図書館の本の管理にコンピュータを使わないという異常なこだわりを持っていた。〈私〉や子易さんは、そんなあらゆるものがつながりすぎた合理的な世界に苛立ちを感じているのだろう。その苛立ちはさらに「ポストモダニズム」へと飛び火する。
「そういうの〔筆者注:ガルシア゠マルケスの作品に見られる現実と非現実のシームレスな描写〕をマジック・リアリズムと多くの人は呼んでいる」
と私は言った。
「そうね。でも思うんだけど、そういう物語のあり方は批評的な基準では、マジック・リアリズムみたいになるかもしれないけど、ガルシア゠マルケスさん自身にとってはごく普通のリアリズムだったんじゃないかしら。彼の住んでいた世界では、現実と非現実はごく日常的に混在していたし、そのような情景を見えるがままに書いていただけじゃないのかな」
(中略)
ガルシア゠マルケスの小説についての話は、私に子易さんのことを思い出させた。彼女なら子易さんと会っても、彼が既に死んでしまった人であることを、そのまますんなり受け入れてくれたかもしれない。マジック・リアリズムやらポストモダニズムみたいなものとは関係なく。
ここで拒絶されているのは、「マジック・リアリズムやらポストモダニズム」そのものではない。〈私〉は、「マジック・リアリズムやポストモダニズム的なものを、マジック・リアリズムやポストモダニズムと名付けること」に違和感を持っているのである。
これらの描写によって示される合理的なもの、言葉にすることへの嫌悪感がもっともよく示されるのは、少年が失踪した後、その原因を探るために〈私〉のもとへやってくる少年の父や兄との会話シーンにおいてだ。少年は〈街〉へ行くために誰にもわからない方法で失踪した。ところが、少年の二人の兄(弁護士と医者という、きわめて合理的な職業についている)は、確実な原因を突き止めるために〈私〉に次のような質問をする。
〈街〉の存在については、「それはつまり、あなたの想像の中で生み出された空想の街なのですね?」。〈夢読み〉については「特殊な書物とはいったいどんなものなのですか?」「なぜそれを読むことが、街にとって重要な意味を持っているのですか?」と言った具合だ。彼らは〈私〉曰く「常識に括られた世界で生きている人」であり、そのためすべてを合理的に解釈しようと試みる。弟の方は、精神医学を駆使して〈街〉についての精神分析まで始めてしまう。これは(この文章自体もそうなので言いにくいのだが)フィクションをすべて現実と結びつけた社会反映論で語ろうとする、無粋な批評家・読者を象徴しているといえる。
そんな兄弟に対して、私はため息をつく。そして少年は〈街〉に行って失踪したのだという真実について、あえて言葉にせず黙っておく。兄弟は少年が「比喩的にか、象徴的にか、暗示的にか」はわからないが、精神医学でいう非意識の世界に入りこんでしまったのだろうと分析する。〈私〉はそれを聞いてこう考える。「いや、それは比喩でも象徴でもなく暗示でもなく、揺らぐことのない現実なのかもしれない」。〈私〉や少年や子易さんにとって、フィクションとはもう一つの現実であり、それは合理的な思考で行動する人々には決して理解しえない聖域として機能しているのだ。
■村上春樹はスマホで読め
以上に引用したのは、すべて第2部の文章である。だが、あとがきにもあるように、第2部以降はそれ単体として完成し、しばらく寝かされていた第1部に「やはりこれだけでは足りない」として付け加えられた部分である。つまり、第1部が80年当時の村上の問題意識を反映しているとすれば、第2部には現在の村上の問題意識が反映されている。70代の老人の死や若者への継承が描かれているのもその一環だろうが、とくに目立つのはやはり、上記で触れたような、インターネット・SNSの普及や(国内外の)グローバリゼーションによって進んだ、言うなれば「世界の普遍化」といえる現象への反発だ。
村上の作品は、かつて「コミットメントからデタッチメントへ」という言葉で語られていた。それまで社会から遊離した作品ばかり書いていた(社会からのデタッチメントを重視していた)村上が、震災やオウムについて書くようになった(社会にコミットするようになった)ことを自らそう言及したからだ。その転向の背景には、90年代以降の現実──政権交代や、インターネットの普及、冷戦の終結──に基づく、世界の普遍化が世界をより良くするのではないかという期待があったのだろう。だが、2010年代後半には、それらの期待はすべて失われ、あとには自由主義と資本主義がより普遍化された虚しい現実だけが残った。冷戦が激化し、インフレが起き、進歩への希望も無い。世界は、文化的な余白を失った上で80年代初頭に巻き戻ってしまったといえる。そんな世界で、村上の問題意識もまた80年代に回帰したのかもしれない。
「ただフィクションを読む」という無益な行為は、世界の普遍化によってとても難しくなった。世界が標準化された結果、そこに残ったのはシンプルな功利主義だ。本書を読みながらスマホで違うタブを開き、インターネットを覗いてみる。すると、そこにあるものの9割は自己啓発書かビジネス書かポルノか社会正義に分類できる。共通するのは実益があるという点だけだ。かつて「ポストモダン」と呼ばれていた思想は、そういう現実社会へのアンチテーゼだったはずだが、その後継者たちは今やSNSで建設的で現実的で政治的に正しい話ばかりしている。オタクやマニアと呼ばれる比較的フィクションを好む人々でさえ、今や「ただフィクションを読む」ことを継続できなくなり、作品を単なるポルノとして扱ったり、推し活のメリットについて話したりして日々を過ごさざるをえない。
だが、この小説は違う。2023年の世界に1980年の世界観を持ち込むことで、そんな現実に「NO」を突きつけている。現実的で建設的で人間的なことの尊さ(人間讃歌)ではなく、「ただフィクションを読む」こと、「フィクションを通じて会話すること」を信じるフィクション讃歌。今の社会でもっとも難しいテーマの一つであるそれを、いい歳こいて現実と空想の区別がつかなくなった45歳のダメ男を主人公に描ききった、紛れもない傑作だ。
評論家の宇野常寛は本作を、コミットメントが消失した性搾取的な駄作であると評していた。それも仕方のないことだろう。これは、現実的で建設的なことの重力に絡め取られてフィクションへの信頼を失ってしまった健全な〈僕〉たちのための作品ではなく、現実に中指を立てがちなダメ人間である〈私〉や〈俺〉のための傑作なのだから。そしてこの「非現実的」な傑作には、いかにも「人間性」や「社会性」の宿っていそうな仰々しい紙の単行本ではなく、しょうもないSNSと同じ画面こそがふさわしい。村上春樹はスマホで読め!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
