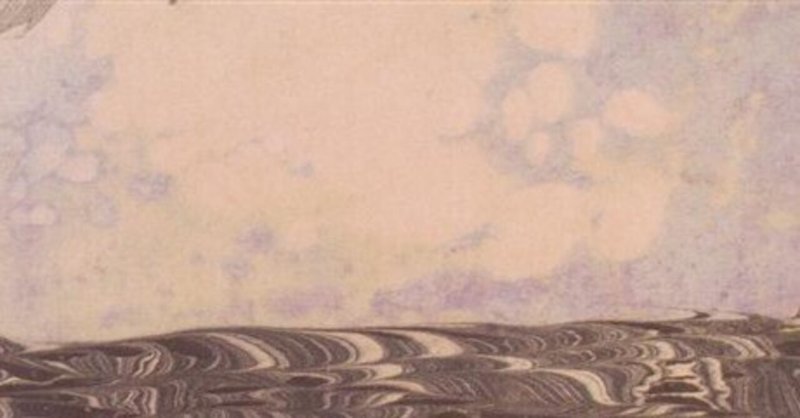
連作から落とした歌①(1×10首)
お世話になっております、丸田洋渡と申します。
昨年頃から特に短歌連作に力を入れて、まだ誰にも言及されていないのに次の50首、次の30首、次の50首……とがむしゃらにハイスピードで書いてきました。
この辺りでひとつ、今まで読んできてくださった方へのボーナス・トラック的な記事が必要だと思い、今まで公開した連作を組み上げる上で、最終的にそこから落とした歌たちを紹介したいと思います。
今まで歌のみを大量に出すばかりだったので、この記事では作者として、創作秘話的な、小話を挟みつつ書いていきたいと思います。
○
連作から落とす、というと、ハズレの低クオリティの歌のように聞こえてしまいますが、実際、そうです。でも、そうでない場合もあります。
私は出す場所によって推敲の方法をやや変えるよう意識しています。たとえば参加しているネットプリントのユニット「第三滑走路」だと他の二人の連作と同じ紙面に載るので、やっぱり二人に圧倒されてはいけない。むしろ二人の作品を呑んでしまうくらいのパワーで行きたい、と心がけているので、''87点以下の作品はそもそも下書きの段階から落とす''的な篩にかけています。
ふだんのnoteに上げる分には僕の作品だけが載って、告知も僕だけがして、すべての責任が僕に返ってくるので、そういう推敲はしません。
連作全体の雰囲気と展開を意識していて、特に最初と最後の作りと、途中のキーになる歌とその加速や失速に重きを置いています。なので、ちょっと弱くても、歌の展開上欠かせない、というものは残しています。
ということで、これから紹介する歌は、「全体の強さを上げるために落とした平均点以下」のものか、「連作の雰囲気や展開からはどうしても逸れる」もの、になります。
一応補足しておくと、平均点以下と言っても、内容に愛着があれば一首の推敲に一週間くらいかけて連作のトップになれるくらいの強さに生まれ変わらせる、こともします。これはこれ以上推敲出来ないだろうし、したとしてもこの連作では浮くかも、というものを落としています。
○
強い弱いで話すとなんだか、弱い歌が可哀想に聞こえてきます。でも、強いことがすなわち良いということでは決してなく。
最近よく思いますが、「言われたこと」よりも、「言おうとしたこと」の方が絶対大事だと思うんですね。たとえば、相手があきらかに何かを閃いたか思い出したかして、自分の顔をパッと見たその時、一瞬間があって「何でもない」と言ってきたら、''本当に何でもない''わけが無い。何かを 言おうとして、その上で自分の何かの要素がそれを言うことを阻んだ。「何でもない」という言葉自体よりも、その後ろにあるものの方が大事。
言い淀む、とか、言い換える、とか、言い直す、とか、そういうのが全部、大事な「言おうとしたこと」のために行われている動作だと思うわけです。で、短歌は、そういう動きをあまり見せない。''もともと初めからそう言いました''という雰囲気で立っています。どれだけ作者が、作中主体が、言い換えた結果であったとしても。(佐久間慧の〈僕は幾度となくそれを誤記して、訂正して、お詫びします。〉のように、この辺りを攻めている作家もいて、そのことはとても安心しています。)
随分脱線してしまいましたが、つまりは、言われていることの強さ、だけで選んでいるのではなくて、言おうとしたことが肝心なもの、を優先的に残しています、ということです。
もし今後、私の作品を見かけることがありましたら、それを思いながら読んでいただけたらより面白がれるのではないかと思います。
○
それでは紹介していきます。全部で何首になるかは決めていません。美術館でやたら隣に来て説明してくる学芸員のようなしつこさで、当時のエピソードも入れながら書いていきます。
○
1
盗賊は打ち合わせほど綿密に 看板の昭和のレタリング
──2022.3 第三滑走路13号「顛末」の頃。盗賊によって主人公がいる館が崩壊する、という展開で、その補強のための歌。交通事故で突然運命が変わった、みたいな世界にはしたくなくて、盗賊側の映像を増やした方がいいかと思って作ったものの、主人公の時間と軸を考えたときに、ただ邪魔になるだけだなと思って落としました。(アンパンマンの生まれてからこれまで、を聞きたいのにバイキンマンが家でくつろいでいる映像は要らないな、という。)
おそらく「看板の昭和のレタリング」発進で、レトロな一首にリメイクすると他の連作で使えたかと思うんですが、自分の歌に''看板''で他に気に入っているものがあり(〈ずるずると人の流れを見ていたい 巨大な看板に腰かけて ね〉、〈貸看板に貸看板と書いてある 助手席のあなたは夢の中〉の二つ)、あまり気乗りしませんでした。
2
どこに居ても想いは通じる 全国のテレビに映るシリアルキラー
──2021.9 「HorrororroH」の頃。僕の作品に頻出して現れるテーマ①''想い''はどこにいてもどこにでも届く(特に悪い意味で)、②誰でも殺人犯になりうる、の二点がくっついた歌。HorrororrHはホラー連作で、「恐怖」そのものが持つ不条理さを描きたかったので、こういう人っぽい俗っぽい感じは浮くな〜と思い。あと、この歌は、「テレビに出たかったら悪いことすれば一瞬」みたいな、メディア批判を暗に込めていて、そういうのはまとめて他でやろう、と思ったのもあります(これは後の「Empathize」でやりました)。
3
マヒャドよりザラキよりザキで倒したい 一途な愛を信じていたい
──2021.3 「GHOSTS」「FRIENDS」の頃。これはゲームの、ドラゴンクエストの呪文を入れすぎていて、説明が無いと面白がれないだろうと思い落とす。
マヒャド、は氷系の呪文で最強(マヒャデドス等は除く。)で全体魔法。ザラキ、は全体(グループに効く)魔法で、相手を確率で呪い殺す呪文。死ぬかもしれないし、死なないかもしれない。どれだけ体力がある強い敵でも、もしザラキが効けば即死する。ザキ、は、ザラキの単体バージョン。たった一人に向けて、呪い殺せるかどうかを試す魔法。
ドラクエにおいて呪文は進化します。氷だとヒャド→ヒャダルコ→ヒャダイン→マヒャド。死だとザキ→ザラキ→ザラキーマ。ザキを覚えたあとでザラキを覚える。
基本的に、進化した方が強いから、マヒャドを覚えているのにヒャドを使うことは無い。でも、ザキ系だけは特殊で、ザラキーマやザラキよりも、ザキの方が成功率が高い。つまり、一人のことを想って呪い殺そうとした方が、皆を呪うよりも力を発揮する。呪いの性質をよく分かっているなと思います。
モンスターが出てきては殺し、モンスターが出てきては殺す、インスタントなゲーム。その中でもザキだけは、相手を殺すということに強い思いを馳せている。それはもちろん、プラスの方向ではないけれど、ただ殺すよりもずっと愛があると、子どもながらに思っていました。
……という前提で、この歌ができています。なので、説明すれば「一途の愛」がベタベタな付き方をしていることに気づいてしまうし、説明しなければ全く分からないという、どっちに行っても……な歌でした。ちなみにドラクエだと、ザキの他にニフラムという、相手を光の彼方にぶっ飛ばす呪文もあります。いつか使うかもしれません。
4
口を開けて電気プラグを差し込んであなたに光る充電のサイン
──2020.10 第三滑走路10.5号「hymn/last dance」の頃。この頃は、小さい連作単位で書きまくる、という方法で作っており、ロボット系の7首を4つくらいストックしていました。結局分解しましたが。
この歌も、「あなた」はロボットである、という展開です。hymn/last dance も、最後ロボット化の展開にする予定でしたが、あなたとの世界の崩落、という形になったので、ロボットの話はまた後で、と思って落としました。
自分で言うのもあれですが、初句「口を開けて」が、読んでいくうちに自分の行為ではなくて「(人の)口を開ける」という他人への行為であると裏返るのが上手いなと思います。はい。
5
内臓が邪魔なんだよなあ……最新の恋愛ドラマを見ながら捌く
──2021.3 「GHOSTS」の頃。グロ要素と恋愛の取り合わせです。魚を捌く、野菜を切る、肉を食べる、人がする殆どの行為にはグロテスクさがまとわりついています。この歌でも、「内臓が邪魔-捌く」というラインのグロさが目立っていますが、実際はもっと、「最近の恋愛ドラマ」の方がグロいです。それは恋愛そのもの、という意味でもあるし、ロマンチック・ラブ・イデオロギー的なものの押し付け(「運命」とかいうやつ?)でもあるし、放送局の維持のために人気俳優を使ったザコ脚本の王道恋愛ドラマをやり続けるしかない、みたいなグロさでもあるし……。これは言い過ぎたかもしれません。
GHOSTSでは、テレビへの批判を〈Televisions 彼は半世紀も前のドラマのことについて怒った〉、〈誰に聞いても彼はそういう子でしたと言われて テレビか と思った〉にして出しました。グロさは後の「Eerie」に。

Koloman Moser〈Landscape with cloudy sky〉1904
6
空へ墜ちる魚のような飛行機の婚姻色の翼を拾う
──2022.1 短歌研究新人賞に応募しようと作っていた頃。(見事落選。また後日公開します。)題名は「Acceleration」で、その題名の通り加速を意識して、乗り物から思考まで、色んなものの加速に思いを馳せる連作でした。その中で、「飛行機」も登場させていて、この歌も飛行機パートに入れようとしました。ただ、やや審査員層を意識しすぎて硬いし媚びているので落としました。のちのち公開したとして、寄せてるな〜w とは思われたくなく。
ちなみにこの「婚姻色」は、僕がものすごく好きな歌、〈婚姻色の魚らきほひてさかのぼる 物語のたのしさはそのあたりまで/齋藤史〉を意識しました。本来なら「婚姻色」は齋藤史のもの(これ以上のものを僕が作れる気がしない)ですが、チャレンジしたく作った記憶があります。この齋藤史の歌は、下の句の鋭さも凄いですが、「きほひてさかのぼる」がおかしいくらい迫力があります。この「きほひて」を思い付いて書くには、僕だと数年かかるなと思います。
7
砂糖どろどろ桃ジュース陽炎が常態化しそうな半世紀
──2022.3 第三滑走路13号「Ephemerality」の頃。この100首連作は、はっきりここに書いておきますが、現代短歌社の2021年9月の例のアンソロジーの件に苛立って書き始めたものでした。最終部に宝石の名前が登場していることで数人は気づいてくれたかと思いますが。なので、構想からもう半年は寝かせていたことになります。本当は、9月のうちに100首連作を出してやろうと思っていたのですが、第三滑走路の二人から勿体ないと止められ、13号に合わせて出そうという話になり、結局長引いて関係ない時期の関係ない100首になりました。推敲しまくって半分以上見違えるほど良くなったので、これで良かったと思っております。
この歌は最終部〈Ephemerality〉にいれるつもりでした。ただ全体を見渡すと、あっさりしながら刺す、というのが魅力だなと思ったので、こういう苛立ちからくる漫然としたどろどろした歌は暑苦しくて浮くなあと思い下げました。結果〈暑さで何も読めなくなった小説に液体の栞をさしておく〉という塚本邦雄の液化するピアノリスペクトの歌になりました。
ちなみに僕はこの塚本の液化するピアノ、のリスペクトを定期的に行っていて、以前は〈水になったピアノを弾いて少しずつ元のピアノに戻してあげる/「水天」第三滑走路8号、2019.8〉を作りました。好きな歌に固執する、というのも大事だと思ったりしています。
8
雨という字の点四つ 傘という字の人四つ カフェの向こうに
──2021.11 「Stir/Scarlet」の頃。この連作は、うたとポルスカの歌会でも出した〈季節考 後ろからコーヒーが来て前から紅茶が来た 窓に風〉に始まる季節とズレとカフェ、のパートから始まります。この一首もそこに入れこもうと思って作っていました。別に入れても良かったなと今は思いますが、ちょっと理知に走っているというか。最序盤から文字の面白さという引いた面白は、読者を冷静にしてしまうかなと思って下げました。
傘、の、人人人人、ちょっと気持ち悪くないですか? 爽、とかもそうですが、書いていてちょっと引くときがあります。
9
嬉しくて誰も止めすらしなかった映画館のみずいろの暴走
──2021.4 第三滑走路11号「awkward」の構想の頃。awkward、自分の中でも相当お気に入りの連作で、ほぼ全ての歌に愛着がある、相当''強い''作品です。というのも、下書き50のうちから10にして、プラス30して15にして、みたいな作業を繰り返しまくって、推敲も細かくしまくったので。濾過、みたいな作業でした。
awkwardの前段階は、「ラウンドアバウト」という連作でした。最初は、あの回転する円形の交差点(?)のラウンドアバウトをモチーフにした交通系(?)の連作にする気で、これも20くらいの形にしてはいたのですが、途中で完全に解体しました。この歌はその「ラウンドアバウト」期に作っていたものです。
今、車を運転していてよく思うのは、誰かひとりが、運転中にぐいっとハンドルをきれば、容易に大事故が引き起こせるということです。みんなが、良心に基づいてまっすぐ進んでいることで何とかなっていますが、誰かがいたずらでハンドルを回した途端にバグります(本人も死ぬことになるでしょうが)。こんな脆弱なシステムで国が回っているのが不思議な話です。
人が、何かが、暴走するってとっても簡単なことで、なのに、暴走してしまえば、止めるのはなかなか困難です。そういう思いを込めた歌でした。映画館が暴走しても、観客は映画だと思って止めないんじゃないか。止めようと思っても止められないだろうし。近作「Fluffy Bullet」の〈沸騰の薬缶が発狂しはじめてはじめて中断した大富豪〉も同じシステムで作りました。薬缶の沸騰、あれが発狂した声だったとしても、もはや止められないし、そもそも発狂だと認識していない。
暴走って、身近だし、容易に起こるし、起こってからじゃないと気づかないし、起こったら止められないし、もっと考えられるべきだよなあと思います。人が鬱になったり殺人したりしたときに、突然あの人は狂った、みたいな言い方を無責任にする人がいますが、いやいや……と思います。
10
改名まで考えていた夜のこと息の長い幽霊を見ました
──2021.9 歌壇賞応募「雪の洞窟へ」の頃。結構好きな歌でした。名前、というものに対して一家言あるというか、語りたいことが山ほどある私として、「改名」ってものすごく重い行為なんですね。読者としてはそんなこと知ったこっちゃない、とは思うんですが。「改名まで考えていた」は、決してTwitterのユーザー名を変えるようなライトなものではなくて、全人生を消去するような重い行為としてあります。
その上で、「息の長い幽霊」を「見ました」。ここをどう読むかは読者の皆様に託したいですが、「見ました」は僕なりの天秤の両皿の平衡をとった結果の表現です。重い表現に対する、ライトな口ぶり。でもこれは、重いものを持ちきれなくなったからこそ出る、嘘の軽さで、おどけて言っている訳では無いんですが……。
落とした理由は、谷川由里子『サワーマッシュ』のせいです。せい、というと良くないのですが。『サワーマッシュ』、現時点で全ての歌集の中で一番好きな歌集なんですが、その中に〈ひとつだけ台詞が言える夜のおばけ いい天気だねー おばけは言います〉という歌があり、なんかお化けに関する歌はもうこれに敵わないな、と思ってしまい、やめました。これは完全におどけの歌なので、方向性が違うから別に気にする事はないんですが、この頃はちょっと過敏でした。
幽霊、または幽霊的な存在、も、僕の中ではかなり重要なテーマです。
○
読んで下さりありがとうございます。
②に続きます。
────────
GHOSTS
HorrororroH
Stir/Scarlet
hymn/last dance
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
