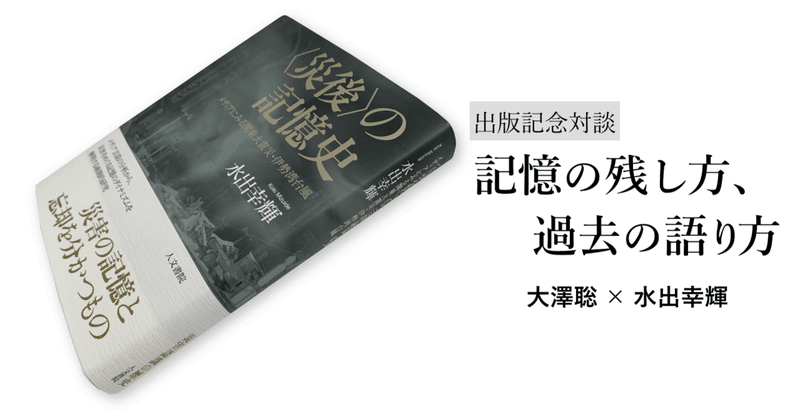
【対談】記憶の残し方、過去の語り方――大澤聡×水出幸輝「データベースの罠」〈第4回〉
2019年に人文書院から発売された『〈災後〉の記憶史――メディアにみる関東大震災・伊勢湾台風』をめぐって、批評家で、メディア史研究者でもある大澤聡さんとの対談が実現。歴史と記憶について、たっぷり語っていただきました。前回はコチラ。
収録日:2019年12月13日
4 データベースの罠
大澤 忘れられた忘れられたと語り続けることにおいて、語る行為が持続するという本書の指摘もおもしろいですね。
水出 関東大震災の記憶語りについてですね。語りが定着する一方で、それまで指摘されていたはずの「忘れられている」という事実そのものが忘れられてしまう。
大澤 そうした言説のねじれというか逆説がある対象を延命させていく。たとえば「論壇」も似た構造で、論壇がなくなったなくなったと語られ続けることによって、論壇は延命した面があります。それはもう「論壇」という言葉の発生時点からそうでした。そうしたねじれを解きほぐすのが、メディアの言説をたどっていくおもしろさのひとつですよね。
水出 通時的に追いかけたからこそ気づける変化です。
大澤 この本について、言及記事を機械的に大量に集めてきただけと見る人はいるでしょうね。けれど、実態はまったくそうではない。語られたことだけではなくて、語られていないこともこの本では扱おうとしているわけだから。そのあたりが伝わるといいんですが……。
水出 伝わらないと「頑張ったで賞」で終わりですからね(笑)。
大澤 もっとひどいケースだと、データベースの検索に引っかけて、結果をパッチワーク式に並べただけといったように誤読する可能性もある。
水出 大澤さんが『批評メディア論』(2015年)でやられた、論壇や文壇の実態そのものではなくて、形式やシステムを見ていく作業はメタ視点こそが可能にするものですよね。この本も手法的にかなり影響を受けています。データベース検索ではけっしてメタ視点にたどり着けません。
大澤 私の場合は雑誌が主な資料で、執筆当時はもちろん現在も詳細なデータベースはないから、誤解されることもないでしょうけど、新聞だと『朝日新聞』と『読売新聞』のデータベースが充実しているぶん、検索結果を集めただけだと誤解されかねない。もちろん、データベースの恩恵を受けてはいるんだけど、それだけではどうしてもたどりつけない部分があるということをどう伝えるかですね。とりわけ、これからやってくる研究者に対して。
水出 後輩の院生から「○○新聞の分析だけでは弱いですかね……」といったタイプの質問を受けることがあります。明らかにしたい事象に応じて扱う資料が変化することを理解していないんですよね。複数紙分析したところで見当外れの比較参照項を持ってきたならまったく意味がないし、反対に一紙の検討で十分な論理を展開できる研究も当然あります。
大澤 水出さんの研究の場合は、「空間的な拡張」やナショナルな同質性を描くうえで比較が不可欠だった。なぜ『朝日新聞』なのかという問題はどう答えますか。
水出 たしかに『朝日新聞』は地域面を含めてデータベースが充実していますが、そのことは『朝日新聞』を軸にした決定的な理由ではありません。最大の理由は研究の出発点が伊勢湾台風だったことです。この時点で、名古屋で圧倒的部数を誇る『中日新聞』はまず欠かせない。それとの比較対象を考えた場合に適当なのが『朝日新聞』だったというわけです。伊勢湾台風当時のメディア状況としては、1955年に『朝日新聞』と『毎日新聞』が名古屋エリアの支社を本社に格上げして、部数拡大に向けた攻勢を強めていました。『読売新聞』は『中部読売』を発行しますが、これはかなり後のこと。ですから、この時点で対象からは外れます。こうしたメディアの情勢に加えて重要なのが各社の性質でした。調べていくなかで、朝日新聞名古屋本社が伊勢湾台風と深い関わりを持つことがわかってきたんです。
大澤 前提にたどりつくまでのプロセスがまたあるということですね。
水出 そうです。名古屋の各種図書館に赴いて調査しないとわからないこともたくさんありました。他紙や他の資料を読んでいないわけではない。むしろ、軸にしない資料をいかに漁るかが重要でした。名古屋南図書館には伊勢湾台風資料室が設置されているんですが、そこには一般の方の寄贈資料も多くおいてあって、新聞の切り抜き帖なんかもあります。ずいぶん助けられました。
大澤 なぜその資料を使うのか、そこにいたるまでの調査も必要なんですよね。それは本に記述されないレベルのことです。自身の研究を「基礎研究」と位置づけてらっしゃるけど、まさにこの「基礎研究」にいたるまでの「基礎研究」がさらに必要。もう一点は、データベースだけではたどりつけない問題があるのだという当たり前のこと。キーワード検索で可能なのは氷山の一角にすぎませんから。
水出 そもそも『朝日新聞』のデータベースだと古い大阪版や名古屋版ってうまく検索に引っかからないんですよね。基本的な設定を理解せずデータベースを妄信している人が意外と多い。それから、データベースに依拠しすぎると、おのずと資料は東京中心になって地域間の比較にならない。
大澤 ふだんから地道な基礎作業をしている人だと、その本が検索だけで済ませたかそうでないかがすぐにわかる。
水出 奥行きが見えないというか、資料の位置や語りの重みを測り損ねてるというか。
大澤 そう、資料の奥行きね。データベース単体だとそれがフラット化してしまう。
水出 検索して満足してしまう研究者だと、逆に「記念日」という設定をせず、いろんな記事を幅広く扱ったんじゃないかと思います。データベース的な発想で、書かれたものの重さを考慮せずに集める。
大澤 質的な意味づけができない。
水出 でも、ぼくは「記念日」に照準をあわせたのでそれ以外の記事はかなり捨てました。捨てた理由は簡単で、記念日という設定のなかに含まれないからです。通時的な強弱を見るには、ある設定を用意して、その設定のなかで定点観測しなければなりません。記憶の問題だけでなく、忘却の問題を範疇にいれたこの研究では、むしろ、記事として存在しないことをいかに描くかが重要でした。忘却を描くには書かれている資料を網羅的に集めて並べるスタイルではダメなんです。それだと外れ値を外れ値として評価できません。「例外的な事例」を「決定的な事例」と誤読し、「ある」ことを強調しすぎてしまう。
大澤 そこは重要ですね。私も『教養主義のリハビリテーション』(2018年)の第四章でそのことに触れました。
水出 検索結果の一覧を「全体」と錯覚してしまう問題ですね。
大澤 そう、「ニセの全体性」問題です。キーワード検索は「ある」ということしか証明できません。「こんなおもしろい記事があった!」という達成なら検索でも同じことができなくはないんだけど、その「ある」の負荷がまったくちがいます。遠近感を見誤って、偶然の事象を必然として扱うなどしてしまう。それから、「ある」ことの位置価にも言及できません。「ない」ことも語れない。けれど、この本は「ない」ことを指摘したり、ひとつひとつの言説の位置価を測定したりしています。そのために、これだけの通史が必要だったわけでしょう。この本の物理的な厚みは必然性がある。
〈つづく〉
※本連載は全5回、6月15日(月)より毎日掲載しています。
- - - - - - - - - -
略歴
水出幸輝(みずいで・こうき)1990年、名古屋市生まれ。関西大学大学院社会学研究科博士課程後期課程修了。現在、日本学術振興会特別研究員。専門は社会学、メディア史。共著に『1990年代論』(大澤聡編、河出書房新社)、『一九六四年東京オリンピックは何を生んだのか』(石坂友司、松林秀樹編、青弓社)。
大澤聡(おおさわ・さとし)1978年生まれ。 東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。 現在、近畿大学文芸学部准教授。専門はメディア史。著書に『批評メディア論――戦前期日本の論壇と文壇』(岩波書店)、『教養主義のリハビリテーション』(筑摩書房)、編著に『1990年代論』(河出書房新社)など。
#水出幸輝 #大澤聡 #人文書院 #対談 #人文書 #本 #批評 #歴史
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
