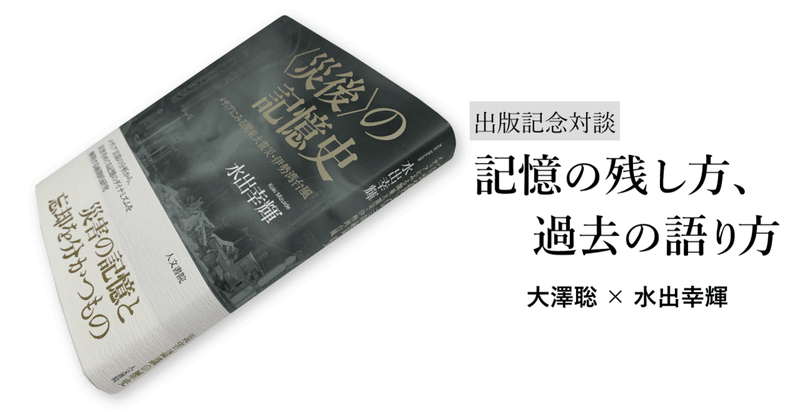
【対談】記憶の残し方、過去の語り方――大澤聡×水出幸輝「フィクションと科学」〈第3回〉
2019年に人文書院から発売された『〈災後〉の記憶史――メディアにみる関東大震災・伊勢湾台風』をめぐって、批評家で、メディア史研究者でもある大澤聡さんとの対談が実現。歴史と記憶について、たっぷり語っていただきました。前回はコチラ。
収録日:2019年12月13日
3 フィクションと科学
大澤 そうした東西の空間的な偏差の問題に加えて、誰が語るのかという偏差の問題も重要ですね。
水出 清水幾太郎がそれを指摘しています。関東大震災の被害を受けたのが下町ではなくてインテリの住む山の手だったなら、もっと多く書き残され、忘れられなかったんじゃないかといっている。
大澤 最近、私は1938年7月の阪神大水害について調べているんですけど、これも甚大な被害をもたらしたのにいまでは全国的にはほとんど忘却されています。
水出 神戸地区ではかなり書き残されていますが、教科書レベルの記述にはなっていないですね。
大澤 たとえば、谷崎潤一郎は長篇小説『細雪』のなかで阪神大水害を描いているでしょう。新潮文庫の分厚い三巻本なんだけど、その第二巻の、しかも古い文庫だから活字がぎゅうぎゅうの組み方で、その50ページ分ほど費やして、どんどん拡大する水害の現場に登場人物たちが巻き込まれていくその時間的経過をひたすら描写している。谷崎自身は芦屋に住んでいてそんなに被害を受けたわけではなかったらしいんだけど、被害を受けた人の証言や体験記、小学校の文集なんかを執拗に読み漁って、地の利を生かしながらリアルに描写することに成功している。
水出 ジャーナリズム性の高い創作なんですね。
大澤 そう。これなんかは当事者語りと新聞的な報道語りとの中間にあるんじゃないでしょうか。ただし、そうした記憶がフィクションとして残されたことをどう位置づけるのか。「戦争の記憶」研究ではこうした問題についても最近、ようやく考えられるようになりましたね。福間良明『「反戦」のメディア史』(2006年)や山本昭宏『核と日本人』(2015年)などはそうした流れに位置付けられる成果だし、10年ほど前に発足した戦争社会学研究会の会誌の第二号は『戦争映画の社会学』(2018年)でした。そういえば、水出さんの本にも、小松左京『日本沈没』(1973年)が登場しますね。
水出 Popular Culture of Disaster(災害のポピュラーカルチャー)と呼ばれ、災害研究でも資料として見直されつつあります。関東大震災でいうと、吉村昭『関東大震災』(1973年)が広く読まれてきました。文学研究の方面ではそういった作品の分析の蓄積もありますね。ただ、第二次大戦でいうところの野坂昭如『火垂るの墓』(1968年)や中沢啓治『はだしのゲン』(1975年)に相当するような作品はなさそうです。伊勢湾台風だとさらにない。
大澤 その不均衡の要因自体もまたメディア研究の課題となる。
水出 戦争と災害の不均衡、それから地震と台風の不均衡が存在します。前者はナショナルな体験かどうかという条件、後者は作り手が東京に集中しているという条件がそれぞれ関係しているのかもしれません。
大澤 戦争と災害の不均衡というと、阪神大水害は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』(1985-86年)の序盤にも描かれていて、あれは第二次世界戦争とセットになっている。戦争に埋もれて消えてしまいがちな災害の記憶を残すという手塚の意志が垣間見えます。伊勢湾台風も主題的にではなくても、時代背景として描き込んだ創作があるんじゃないかなと思ったんですけども。
水出 そこは網羅的に調査したわけではないので正確なことはいえませんが、多くない印象です。文学作品だと井上靖『傾ける海』(1968年)、三輪和雄『吠える海』(1982年)があります。それから、全国的なインパクトをもったものに、TBS系のテレビドラマ『赤い運命』(1976年)がある。これは記憶を残すという要請ではなくて、主演の山口百恵が生まれた1959年前後の出来事をドラマの背景として設定したためでした。ですから、伊勢湾台風の記憶が同時代の社会で要請されたわけではない。もう一つの背景として、こちらの方が重要だと思うのですが、台風による大量死にリアリティを感じなくなっていくという時代背景があります。終戦から伊勢湾台風までの期間は千人単位で人命を奪う風水害が続発して、「戦後大水害の時代」と表現される。水害の死者数を数百人規模におさえられるようになるのは伊勢湾台風以後。伊勢湾台風ほどの規模で人命が奪われる体験はなくなっていくので、災害対策が成功しているという感覚が人びとのあいだにあったのだと思います。
大澤 ちょっと残酷に響きますが、死者数に規定されてしまう側面もあった、と。
水出 より正確に表現すると、死者の実数ではなく死者数が減ったという感覚です。人びとが恐れた地震よりも風水害で奪われる人命の方が多い時代なので。
大澤 三木清は1935年3月から40年9月までの5年半のあいだ、『読売新聞』夕刊に週一の時事コラム「一日一題」の連載をもっていて、そのなかに災害を書いた回があるんですよ。1938年9月6日の「天災の教訓」と題された回もそうなんですが、こうはじめているんですね。「ことしは天災が多いやうである。尤も今頃には毎年台風の襲来を受けるのであるが」……と書き起こす。9月6日のコラムだから、直前にあった阪神大水害や台風のほかに、関東大震災の「9月1日」もここでは意識されていたはずです。続けて読むと、「ことしはそれが特に深く人心に印象されるのは事変中だからであらう。飛行機の襲来に備へる訓練は近来年毎に行はれてゐる。しかるにこの防空演習に対するほどの熱意を政府も国民も天災の防止に示してゐるであらうか。しかも自然の災害に対する予防と戦争の災害に対する予防とは決して無関係ではないのである」とある。ようするに、自然対策と戦争対策が重ねられている。
水出 関東大震災の直後には、第一次世界大戦で欧州が体験した空襲火災と重ね合わせ、防空の必要性が指摘されています。震災火災と防空の関係については、土田宏成『近代日本の「国民防空」体制』(2010年)が詳しい。もう少し時代が進むと国民精神総動員運動のなかで震災の記憶が動員されるようになります。『東京朝日新聞』の記事では「震災と空襲の構えは同じだ」書かれたりする。
大澤 ポイントはそこですね。新聞でそういう指摘がなされる。三木は、科学の力で対策せよと結論します。国民の「科学的精神」の養成につとめよと。この議論は1930年代後半に三木や戸坂潤が「科学的教養」や「科学精神」を打ち出す流れに位置づけられるんだけれど、こうやって自然災害対策を戦争対策へとスライドさせるフォーマットがあったからこそ、自然災害について語りやすかったんじゃないかと思うんです。さきほどの『アドルフに告ぐ』の構図はその延長線上にある。他方、戦後の伊勢湾台風の時代になると、戦争というフックがもう使えませんから、自然災害を単体で語らなければならない。ローカルな現象だとどうしても言説化が弱くなってしまう。
水出 それに付け加えておくと、伊勢湾台風の時代は科学への期待値がまだ高かったということも指摘できます。公害が本格的に社会問題化する前で、科学の力でなんとかなるみたいな雰囲気が社会全体にあった。
大澤 逆に、三木の時代は科学の重要性を国民にセットアップする段階なんですよね。
水出 2冊目に書く予定のテーマに関係するんですが、台風の場合は富士山気象レーダーや気象衛星といった技術の発達のおかげで、実際に「見える」ようになっていきます。そうした科学技術の進歩に伴って人びとが体験した変化は、台風について語り続けなくてもよい社会を用意したのかもしれません。
大澤 なるほど、それはおもしろい指摘ですね。ちなみに、戦前戦中、三木や中野重治をはじめ、大杉栄、荒畑寒村、小林多喜二といった治安維持法で捕まった思想犯を多数収容したことで知られる豊多摩刑務所が中野区にありましたが、その跡地は1985年に「平和の森公園」として再生しているんですね。それから、その近くの「電信隊の原」という軍用地があった場所には2012年に「中野四季の森公園」が開園しました。戦争の記憶がみっちり刻印されているはずの場所に、「平和」なり「四季」なりといった新しい物語が上書きされ、しかもいざというときには防災施設として機能する広域避難場所として再生する。戦争という有事は、戦後には災害という有事へとシフトし、まさに国防国家から防災国家へというシフトした。そのことを象徴しているんじゃないでしょうか。こういう土地の記憶も掛け合わせることでさらに議論は立体化するはずです。
〈つづく〉
※本連載は全5回、6月15日(月)より毎日掲載しています。
- - - - - - - - - -
略歴
水出幸輝(みずいで・こうき)1990年、名古屋市生まれ。関西大学大学院社会学研究科博士課程後期課程修了。現在、日本学術振興会特別研究員。専門は社会学、メディア史。共著に『1990年代論』(大澤聡編、河出書房新社)、『一九六四年東京オリンピックは何を生んだのか』(石坂友司、松林秀樹編、青弓社)。
大澤聡(おおさわ・さとし)1978年生まれ。 東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。 現在、近畿大学文芸学部准教授。専門はメディア史。著書に『批評メディア論――戦前期日本の論壇と文壇』(岩波書店)、『教養主義のリハビリテーション』(筑摩書房)、編著に『1990年代論』(河出書房新社)など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
