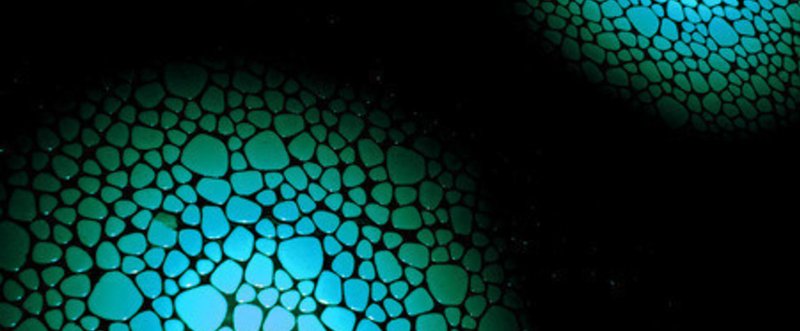
<賢者の石>を求めて
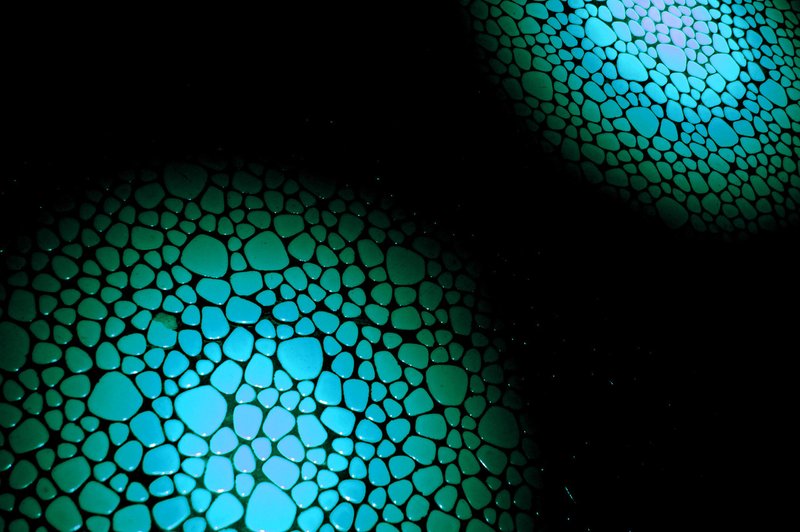
『いのちを“つくって”もいいですか?』では、すでに私たちの生活に入り込みつつあるエンハンスメントの諸事例、出生前診断を軸とする「いのちの始まり」と現代科学の関わりに続いて、第3章では現代生命科学の最前線とも言える「再生医療」について取り上げています。
2012年、京都大学の山中伸弥先生がノーベル生理学・医学賞を受賞したことで一躍世間にその存在を知られることになったiPS細胞。お茶の間レベルで「再生医療」ということが語られるようになったのは、やはりこのiPS細胞が現れたことが大きいのではないでしょうか。「きょうの健康」の読者アンケートのお便りにも、「再生医療についてもっと知りたい」という声がしばしば寄せられます。
また、「あの日」からまだ1年ちょっと、というのも何だか信じ難いくらい遠い昔のように感じてしまいますが、ちょうど昨年の今頃、STAP細胞騒動がワイドショー的なネタとして消費されることになったのも、やはりiPS細胞の存在あってこそのことでしょう。でも、実際にiPS細胞(とそれによる再生医療)とはいったいどんなもので、どんな点が優れていて、結局それで何ができるのか。その知名度、人口に膾炙している度合いに比べると、正しい理解はまだまだ進んでいないのではないでしょうか。
iPS細胞とは何なのか。またそれに先行するES細胞、またヒトクローン胚などを含めた再生医療について、基本的なところから学ぶための本としては、『いのちを〜』の参考文献にも挙げた田中幹人編『iPS細胞―ヒトはどこまで再生できるのか』(日本実業出版社、2008)をまず紹介します。生物学的な基礎情報から、その革新のポイント、そして技術が進んだ先にある社会的な課題などにも触れている、守備範囲の広い1冊です。
もっとも、現代科学は日進月歩。情報の鮮度が落ちるのは非常に早いので、より新しい本で情報の更新をするには、iPS細胞だけではない、「幹細胞」による再生医療の全体の見取り図を描いたものとして、中辻憲夫『幹細胞と再生医療』(丸善出版・サイエンスパレット、2015)はコンパクトながら非常に内容の厚い1冊。とかく話題性ばかりに関心が集まってしまっている再生医療について、科学的に最先端の状況を知ることができます。
とはいえ、詳しいことを学ぼうとするとやっぱり難解なこのテーマ。「で、結局長生きできるようになるの?」という素朴な疑問は、私自身も持っています。そんな疑問を専門家にストレートにぶつけてみたら――八代嘉美・海猫沢めろん『死にたくないんですけど iPS細胞は死を克服できるのか』(ソフトバンク新書、2013)はそんな問いをストレートに扱ったユニークな対談本。再生医療、生命科学の基本知識をわかりやすく理解しながら、これから先、いのちをめぐる科学がどういう方向に進んでいくのかについて、そのイメージを掴むことができます。
1996年に誕生した「クローン羊のドリー」や、その後のES細胞、ヒトクローン胚などの万能細胞的なものに対して、生命倫理においては、主として「受精卵=人のいのちの始まりを壊す」という観点から批判がなされてきました。そして、新たに登場したiPS細胞はその問題をクリアした点が革新的なのだ、とも主張されています。しかし、真の問題はそこ(だけ)ではなく、「人工的にいのちを創り出してしまう(そして、そこから何ができるかはわからない)」という点こそが問われるべきでは、というのが『いのちを〜』における島薗さん独自の主張です。
全く新しいいのち、生命を創り出す、というのは科学が目指す究極の地点の一つでしょう。現在の学問分野としては「合成生物学」にあたるでしょうか。岩崎秀雄『〈生命〉とは何だろうか―表現する生物学、思考する芸術』(講談社現代新書、2013)では、合成生物学とはどのような科学であり、何を志向しているのか、またその歴史的な変遷と意味についてわかりやすくまとめられています(一方で、後半では、生命科学と芸術、美学、と大きくベクトルの異なる議論が展開されます)。
「複製技術時代の人間」の回でも触れたように、現代科学としての合成生物学的なものが構想されるよりもはるか昔から、人間は自らの手で生命創造・付与の技術を得ることに熱意を燃やしてきました。以前にも挙げたゲーテの『ファウスト』にも描かれた「ホムンクルス」は、それを象徴する存在といえます。
ホムンクルスとは、主に西洋における錬金術でその創造を追究された人造人間のこと。ルネサンス期の錬金術師パラケルススがその作製に成功していたとかいないとか、彼の「物の本性について」という論文によれば、人間の精子を蒸留器に入れて40日以上かけて腐敗させるとやがて人のかたちをした透明のものが生じて、これに毎日人間の血を与えて馬の胎内と同じ温度でさらに40週間保つと、普通の人間と同じ存在になる(ただし、かなり小さい)、とされているそうです。
実際にその創成を目指した錬金術師は数多くいたことでしょう。またこのような不可思議な話は、人々の間で広く語り継がれていきました。ゲーテもまた、パラケルススの伝承に着想を得て、『ファウスト』においてホムンクルスを描きました。『ファウスト』のホムンクルスは、つねに透明なガラス器のなかにとどまり、非現実と現実の境界にあるような、なんとも印象的な存在です(はかないほのかな光を放っているようなイメージが浮かびます)。
人間が全く新しい人間(のような存在)を創り出す。いのちの神秘性に触れる、ある意味で厳かなことなのだとも思いつつ、秘儀・秘術的なその方法も相まって、どこか背徳的・官能的な雰囲気が感じられないでしょうか。それこそが、ホムンクルスという伝承が私たちを惹きつける本質なのかもしれません。(無機的な物質から生命を生み出す、という錬金術自体がもつ妖しい魅力なのかもしれませんね。藤田和日郎『からくりサーカス』や荒川弘『鋼の錬金術師』のようなモチーフは、時代を超えて私たちを魅了するものだと思います)
さて、ホムンクルスと並び知られる、人が秘術によっていのちを与える存在に「ゴーレム」があります。いにしえのユダヤ教の伝承によるもので、ヤハウェの神が土塊から人間を創造したように、人間が土塊にいのちを与え、それを使役したとされます。その創成の儀式において、額にヘブライ語で「emeth(真理)」の文字が記されることで動き出し、mの文字を消すと「meth(死んだ)」となり土塊に返る、とされています(エコですね)。
このゴーレムも、ユダヤ教の秘術という要素もあり、民間伝承、またグスタフ・マイリンク『ゴーレム』をはじめとして、ゴシック小説などで非常に好まれたモチーフです。現代のファンタジー小説やRPGゲームなどにおいても、すっかり定番のキャラクターとなって生きています。
※ただし、マイリンクの『ゴーレム』は、ゴーレムそのもののは主テーマではないのですが。
ここまで来ると、「人間のいのちを人工的に創り出す」ということからはちょっと乖離してしまっているかもしれません。上に述べたように、ゴーレムは「神による人間創造」の模倣であり、モノへのいのちの付与、人というよりは「亜人」的な存在ですね。金森修『ゴーレムの生命論』(平凡社新書、2010)は、この「亜人」という観点を重要なカギとして、生命倫理の問題にユニークな視点で迫っています。はじめはゴーレム、およびゴーレム的なものの変遷、特にゴシック小説等で描かれるその存在の意味を論じていて、「ゴーレムの文化論」としてだけでも非常におもしろいのですが、終盤では私たちの内面にも亜人、ゴーレム的なものがある、ということを分析することで、一気に生命倫理の問題に読者を引き込んでいきます(それこそ見事な魔術のよう!)。
だいぶん遠くまで脱線しましたが、では実際に「人間のいのちを人工的に創り出す」という状況を、いわゆるSFの悪役的な感覚?で、ナイーブに欲望する人はいるものでしょうか? 全くゼロとは思いませんが(妄想として、等)、少なくともサイエンスの分野においてはあまり現実味がない話のように思います。
むしろ現在の関心としては、「人工知能(AI)」が可能か、それが人間の知性や処理能力を超えられるのか、という問題に注目が集まっているのではないでしょうか。先日、Googleが開発したAlphaGoが韓国のプロ棋士に圧勝(4勝1敗)して大きな衝撃をもたらしました(参考記事)。AI研究の発展スピードは驚異的で、出版業界でもここ数年、人工知能をテーマとする本が山のように刊行されていますが、次々と情報が新しくなるので、「定番」といえるものがなかなか見定められないのが難しいところです。
※個人的に読んでみたものとしては、松尾豊『人工知能は人間を超えるか』(角川EPUB選書、2015)、小林雅一『AIの衝撃 人工知能は人類の敵か』(講談社現代新書)、「現代思想」2015年12月号(特集:人工知能 -ポスト・シンギュラリティ)など
先の囲碁の件(チェスや将棋でも既に行われていますね)でも、また上に挙げた書名などを見てもわかるように、この手の話題はつい「人間vs人工知能」「人工知能が人間を超える」「人工知能が人間を脅かす」という、割と単純な対立構造および脅威論として語られる(少なくとも、そのような装いで示される)ことが多いですね。わかりやすくまた耳目を引きやすいからなのでしょうけれど、そもそも人間と機械・AIはその基本的な構成も、存在の意味も全く異なる土台に立っていますし、また価値判断のポイントは無数にあるわけで、そもそも「対立」とか「超える」という基準の立て方自体がナンセンスではないか、と思っています(もちろん、前述の囲碁等での対戦のように、比較のポイントを絞ったうえでの勝負、というのは非常に興味を引かれます)。
「ロボット」の言葉の発端であるカレル・チャペック『R.U.P』以来、映画などでは「人間vsロボット(機械、人工生命体)」という、ある意味わかりやすい設定が定番のように用いられていますが、現実のテクノロジーの発展はもっと先に、そしてより複雑な状況に進んでいっているのではないでしょうか。(現実はフィクションよりも奇なり?)
現時点ではiPS細胞に最も大きな期待が集まっている再生医療研究ですが、今後の目標のひとつとして、「生殖細胞(卵子・精子)をつくる」ことが目指されています。目的としては、より基礎的なところでは生命発生の仕組みを解明すること、そして実臨床的には不妊症や遺伝性疾患の機序の解明、さらに具体的な治療法の発見を、ということがあるようです。
それぞれiPS細胞から作られた卵子と精子、これを受精させれば、理論上は胚を形成して新しい個体が誕生します。もしそれが現実にできたとして、その「親」は誰になるのでしょうか。そして、人工的なiPS細胞由来、ということだけでも複雑な問題ながら、さらに「誰」のiPS細胞由来で、かつそれをどのように組み合わせるのか、ということでさらにこんがらがった問題になりますね。タイトルどおり、まさに「いのちをつくる」領域に踏み込むことで、想像するだけでも頭がクラクラします。
これはすでにES細胞やクローン胚の頃から指摘されてきた倫理上の根本的な問題で、自然由来でない生殖細胞を受精させて新たないのちをつくることについては、ほぼ世界中で原則的に禁止されています。しかしその一方で、「研究目的であれば、受精卵をつくるところまでは許容する(そして、その受精卵を用いて研究を行うことは許容する)」という主張があり、先進諸国ではそちらの方向に舵が切られつつあるようです。
とりあえず現在のところ、iPS細胞からつくられた生殖細胞による新しい個体の発生は、もちろん人間では行われていませんが、マウスでは既に成功しています。
※ただし、「iPS細胞×iPS細胞」ではまだ未達成で、「ES細胞×iPS細胞(どちらかはES細胞由来)」とのこと。:2015年7月時点。
「いのちをつくる」という事態について、それが人間についてのことならば、誰もがそれに何らかの不安や不快感のような感覚を抱くのではないかと思います。でも、それが動物だとしたら? 今述べたように、実験マウスのレベルでは既に実現している。今まではただ知らなかっただけで、知ったうえで「全く許容できない、あり得ない!」と感じる人もいるでしょう。でも、それは人でもマウスでも(あるいはほかの動物でも)、同じように感じるのでしょうか? また、「人とマウスでは違うレベルの問題だと思う」と感じるのだとしたら、その違いは何なのでしょうか。人と動物は違う? では実験に用いられるのがマウスではなく、犬や猫だったとしたら?(あなたは愛犬家・愛猫家かもしれないし、あるいは全くそうではないかもしれない)
人工的に「いのちをつくる」ような営為はいっさい断固拒否すべき、という意見もあるかもしれません。では、許容されることとされないことの間にはどのように線が引かれるのでしょうか? 医薬品の開発などはその典型例ですが、医療を含めて、現代科学においてはさまざまな領域で動物を用いた実験が行われており、その成果は多方面に活用されています。そしてそれは私たちが意図する・しないにかかわらず、私たちの日常生活に浸透してきているのが現実です。
つい先日、中国で「ゲノム編集」という新たな遺伝科学の技術・研究にが実施された、という報道がありました。ゲノム編集とは、受精卵以前の段階で、特定の疾患や特性などに関わる遺伝子に手を加えて、それらの発現を抑えたり、逆に伸長を目指すような遺伝工学技術。明らかに「いのちの始まりに介入する」技術なので、現時点ではおおむね批判的な目が注がれています。
でも、これは簡単にいえば人間における「遺伝子組み換え技術」。その目的や程度はさまざまながら、遺伝子組み換え技術自体は、植物はもちろん、動物に対しても既に広く応用されています(実験室で用いられるハエやマウスから、畜産応用を目標とした羊や豚なども)。「遺伝子組み換えは認めたくない」と感じるとき、その対象が人でも動物でも(あるいは植物でも)、その感覚は全く同じものなのでしょうか、それとも違っているでしょうか?
そんな問いを考えていて行き当たったのが、伊勢田哲治『動物からの倫理学入門』(名古屋大学出版会、2008)。上に述べたような問いをはじめ、私たちは、時に相互に矛盾する多様で複雑な対応を、ひとくくりに「動物」と呼ばれるものに対して取っています。それぞれの差は、そして私たちと動物とを分けるものは何なのか(あるいは分けるものはないのか)。そのような観点をきっかけに「倫理学」という学問へ誘う本で、平易な書き方で幅広く、それなのに専門分野の教科書たり得る深さをもった、とても読み応えのある1冊です。
「倫理(学)」というと、なんだか道徳的正しさみたいなものを押し付けてくる感じがあって、つい遠ざけられがちなもの、という印象を抱かれる気もします(個人の感想です)。でも実際には、「現実に起こり得る、決して簡単には答えの出ない問題」について、きちんと正面から向き合うのが倫理の課題であり、やや語弊があるかもしれませんが、知的な探究心を強く刺激されるものではないか、と感じています。
今回は扱うトピックが全くバラバラで、あっちへ行ったりこっちへ行ったりな記事になってしまいましたが、「動物の問題を通じて考える倫理学」という観点は、先に触れた今後社会に間違いなく広がっていくAIやロボットなど存在に、私たち人間がどう向き合っていくのか、という問題を考えるうえでも非常に興味深く、また有効なものだと思います。こちらのレビューで言及されているウェンデル・ウォラック(共著)の『Moral Machines: Teaching Robots Right From Wrong』は、機械倫理・機械道徳・人工道徳といったテーマを扱っているとのことで、本には大いに興味を惹かれます。が、とりあえずは邦訳のある、その共著者であるウェンデル・ウォラック『人間VSテクノロジー:人は先端科学の暴走を止められるのか』(原書房、2016)を読んでようと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
