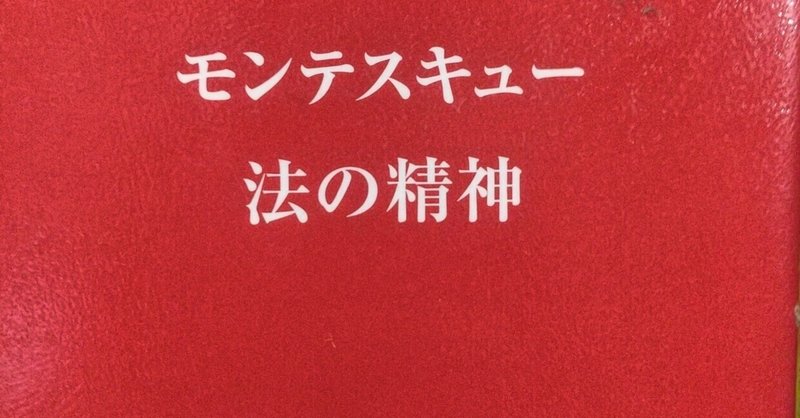
秋の夜長の一冊(モンテスキュー 『法の精神』井上 堯裕 訳 中央公論新社)
1748年出版。原題『De l'Esprit des lois』。
普段あまり、直接かかわることがない法律。「法」って、そもそも何なんだろうという疑問から読んでみることにした、タイトルだけよく知っていた、本です。
「Esprit」 は「精神」と訳されていますが、他にも(それがもつ固有の)「知性」、「才気」などの意味があるようです。つまり「法」というものが持っている特性について考察した政治哲学の本ということだと思います。全て理解できたわけではないですが、興味をもって読み進められました。
三種の政体の比較によって事象の説明がされている箇所が多くあるのですが、とても簡潔に書かれています。
三種の政体がある。それは、「共和制」「君主制」「専制」である。その本性を見いだすには、もっとも教育のない人々が、それらについてもつ観念で十分である。私は、三つの定義、というよりも事実を思い浮かべている。第一に、共和政体とは、人民全体、あるいはたんに人民の一部が主権をもつ政体であり、第二に、君主政体とは、唯一人が、しかし定まった制定法に則して統治する政体であり。第三に、これに反して、専制政体においては、唯一人が、法も準則もなく、おのれの意志と気まぐれにより、すべてをひきまわす。
(選挙と投票について、ローマやアテナイを例にとって述べている箇所)
術策は、元老院においては危険である。それは、貴族団においても、危険である。だが、その本性が、情念により行動することにある人民においては、それは危険ではない。人民がまったく統治に参加していない国々においては、人民は、政治に熱狂するように、俳優に熱狂するだろう。共和国の不幸は、もはや術策のないときだ。それは、人民を金銭により堕落させたときに生じる。人民は冷血となり、金銭には執着するが、政治には執着せず、統治に、またそこに提案されることに関心をもたず、黙然として、報酬をまつ。
もっとも自然な従属的中間権力は、貴族の権力である。貴族身分は、いわば君主制の本質のなかにはいりこんでおり、君主なくして貴族なく、貴族なくくて君主なし、が君主制の基本的な格率である。貴族なくしては、専制君主が出現する。
(格率=論理の原則などを簡単に言い表したもの。)
君主政体や専制政体がおのれを持し、おのれを保つには、清廉篤実は多くを要さない。前者では法の力が、後者ではいつもふりあげられた君主の腕が、すべてを処理し、抑制する。しかし、民衆国家には、いま一つの発条が必要であり、それは「徳性」である。
私の述べることは、歴史の全体により確証されており、事物の自然にきわめて適合している。
なぜなら、法を執行させる者が自身を法の上にあると考える君主制においては、法を執行させる者が自身もそれに服しており、その重みを担っていると感じる民衆国家よりも、徳性を必要とするところが少ないのは明らかだからである。
さらにまた、悪しき助言や不注意から法を執行させることをやめた君主は、容易に誤りをただすことができることも明らかである。君主は顧問会議を変えるか、この不注意自体をただせばよい。だか、民衆政体において法が執行されなくなったときには、そのような事態は共和国の腐敗からしか生じないから、国家はすでに失われている。
(発条=ばね。行動を起こすきっかけ。)
共和制においては徳性が、君主性においては名誉が必要であるように、専制政体においては「恐怖」が必要である。そこでは、徳性はなんら必要ではなく、名誉は危険であろう。
徳性とは、共和国においては、きわめて単純なことである。それは共和国への愛である。それは感情であって、もろもろの知識の帰結ではない。国家の最下位の者も、最上位の者も同様に、この感情をもつことができる。民衆はひとたびすぐれた格率をもつと、いわゆる育ちのよい人々よりも長きにわたってそれに執着する。腐敗が民衆から始まることはまれである。しばしば、民衆はその知力の中庸から、既存の事物へのより強い愛着をひき出す。
祖国愛は習俗を善良に導き、習俗の善良は祖国愛に導く。われわれは、個別の情念を満たすことができなければできないほど、よりいっそう普遍的な情念に身をささげる。
じっさい、いたるところで見られるように、専制政体の変動のさいには、人民は自分自身に導かれ、ものごとを行きつくかぎり遠くまで運んでしまう。彼らの犯す秩序の破壊は、ことごとく極端である、それにたいし、君主制においては、ものごとが過度にまで推し進められることはきわめてまれである。首領は自分自身のために不安になる。彼らは見捨てられることをおそれる。従属的な中間権力は、民衆が強くなりすぎることを望まない。国家の諸身分のすべてが腐敗することはまれである。君主はこれらの諸身分に依存している。したがって、不穏分子は、国家をくつがえす意志も希望ももたないから、君主を倒すことはできもしなければ、望みもしない。
このような状況では、知恵と権威にめぐまれた者が調停に立つ。人々は、妥協案をとり、和解し、誤りを正す。法律は力をとりもどし、ふたたび遵守されるようになる。
哲学的自由は、おのれの意志の行使、あるいは、すくなくとも[あらゆる哲学の体系にしたがって、話らねばならないとすれば】人がもつ、おのれの意志を行使しているという意見にある。政治的自由は、安全、あるいはすくなくともおのれの安全について、人がもつ意見にある。
公的あるいは私的な告発以上に、この安全をおびやかすものはない。だから、市民の自由は主として刑法のよさに依存する。
刑法は一挙に完成されたのではい。人々がもっとも自由を求めたところにおいてさえ、自由はつねに見いだされたわけではない。
(大国にとりかこまれ、様々な産業が妨げられ貧困に陥っている小国の、人民に対する賦課(税金などを割り当てて負担させること。)について書かれた箇所。)
一国の豊かさの効果は、万人の心に大望を抱かせることにある。貧しさの効果は、そこに絶望を生ぜしめる。大望は労働によりかき立てられ、絶望は怠惰により慰められる。
自然は人間にたいして公正である。自然は人間の労苦にむくいる。それは、より大なる労働にはより大なる報酬を結びつけているから、人間を勤勉にする。だが、もし恣意的な権力が自然の報酬をとり去るならば、人々はふたたび労働をいやがり、無活動が唯一の善と思われるようになる。
多くのものが人間を支配している。風土、宗教、法律、統治の格率、過去の事例、習俗、生活様式。それらからそれらに由来する一般精神が形成される。
各国民においては、これらの原因の一つがより大きな力をもてばもつほど、他の原因はそれに譲歩する。
したがって君主が、その国民に大変革を行なおうとするときには、君主は法律により確立されたものは法律により改革し、生活様式により確立されたものは生活様式により変えねばならない。
そして、生活様式により変えるべきものを法律によって変えるのは、きわめて悪い政策である。
引用ばかりになってしまいましたが、自分のためのメモとして気になった個所を載せさせてもらいました。
250年以上前に書かれたにもかかわらず、日本の国政だけでなく、会社や部署など、今現在の、「集団」に起きていることに通じるものも多々あると思いました。
私は、この先も、「政治」(立法や執行)に近い場所でかかわることはきっと無いでしょうが、「人民」のひとりとして、徳性と本能に基づいた(生活のなかでの)actionは大事なのではないかと感じさせられました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
