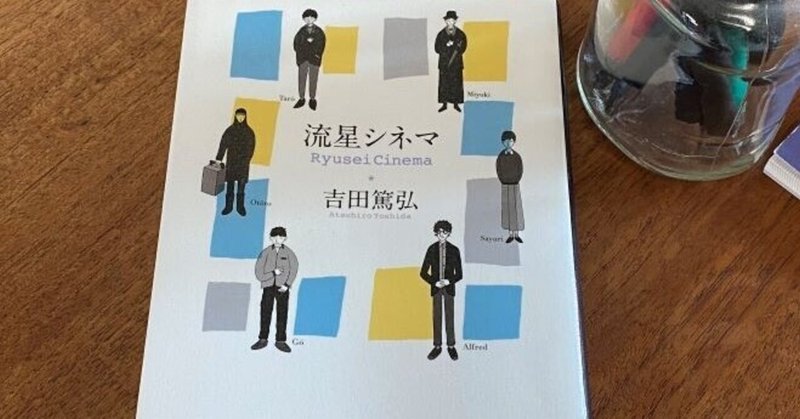
忘れた頃に、忘れる前に読みたくなる吉田篤弘さんの物語。
吉田篤弘著『流星シネマ』(2020年5月18日/角川春樹事務所)
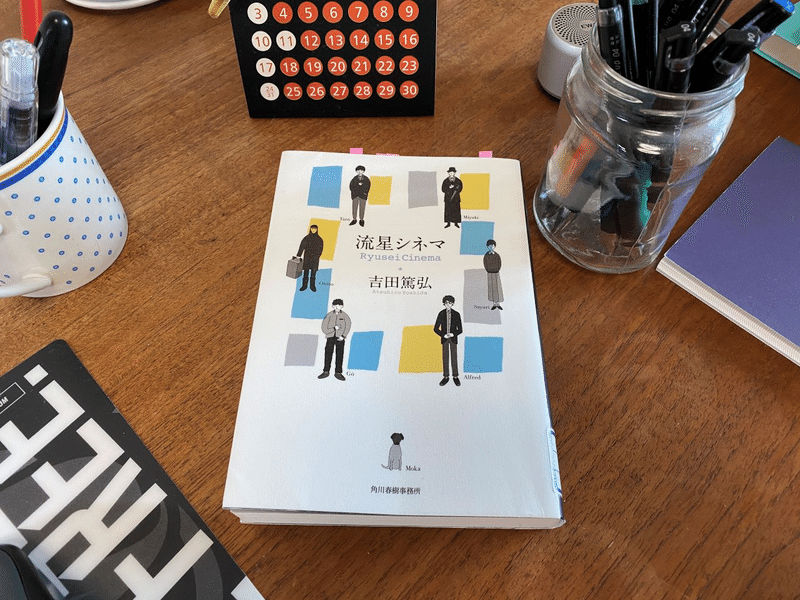
<やじろべえ>ってあるでしょう。長い両手をのばして、一所懸命均衡を保ってるやつ。
ぼくにとっては<やじろべえ>みたいなものかな。
片方が重くなって、ちょっと拙いなぁって気配がし出すと、すぐに吉田さんの物語をもう片方にぶら下げる。
どの物語もズシンとは来ない。 だから片方にぶら下げても反動で落っこちたりしない。
『流星シネマ』に登場する人たちがいい。
吉田さんが作り出す人物はみんな好ましいのですが、本書の表裏紙に描かれているキャラクター画が、まさに“本人そっくり”?と言いたくなるほど似ている?
書き出しにこうあります。
― この世界はいつでも冬に向かっている。 いくつかの明るい空の下で起きたことを思い出しながら、四つの季節のいちばん終わりへ向かって地球は回りつづける。
そう思うと、少しばかり怖ろしくなって、僕は下手な歌を歌ってごまかす。
明るい空の下で起きたことを思い出しては、夢や希望を織り交ぜ、胸の奥にしまってあったものとひとつにして、声を出さずに歌っている ―
物語の舞台は、私鉄電車の急行が止まらない町のガケ下の“へこんだ”ところ。
<流星新聞>というタウン誌発行人のアルフレッドによれば、
― この町のへこんだ地形は「気がトオクなるくらい歴史的な大ムカシ」に大きな流星が落ちてきて出来たもの ーだそうだ。
主人公は、アルフレッドの下で編集人をしている太郎君。
『つむじ風食堂の夜』や『レインコートを着た犬』、『台所のラジオ』などを読んだことのある方なら解るでしょう。
この物語にもさして大きな事件は用意されていない。
いや、ぼくが思っているだけで、他の方が読めば違っているかもしれない。
ひとつだけ。
町に流れる川に大きな鯨が迷い込んだことがあったそうです。それでこの町の人はガケが鯨の形に見えることから「鯨塚」と呼ぶそうです。鯨は二百年も前にも昇って来たとか。
“鯨”はキーワードのひとつですね。
物語ですから当然紆余曲折、起承転結、序破急あるのですが、それは置いておいて、いいなぁと思った文節を。
ガケ上の洋館に住んでいるカナさんは、超ヘビースモーカーで、“おばあさん”と言えるお歳。詩集を出版している書肆を営んでいる。
カナさん曰く。
―「同じ響きを持った言葉は、どこか底の方でつながっているじゃない?わたしはそう思っています。詩はいつでも、その背中に死を背負っている。そうじゃなかったら、ただの茶番にしかならないもの。わたしはそう思っている」ー
こんなところも。
― 冬にもまた、こうして終わりがくる。冬が終わって春がめぐってくる。春の暖かさは命を持つものすべてを励ますようにつくられている。たぶん、きっと、おそらく。
(もういちど、最初からはじめよう)
そう云われているような気がした。
人生の四つの季節は否応なく冬に向かっているけれど、こうして小さな(もういちど)は何度でも繰り返される。何度でも再生して、何度でもやり直せる。ー
吉田篤弘さんの物語。
堪能してもらえるといいのですが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
