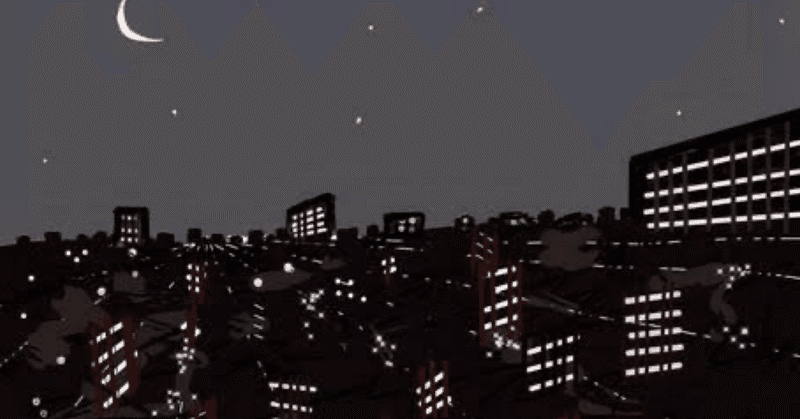
私が私であるために
リストカットは数年前に辞めた。と言うより辞めさせられた。
止血が間に合わずどくどくと止めどなく溢れ出す血液を親に見られてしまった。それがいけなかったのだ。もともと鋏やナイフではなくカッターでしか上手く皮膚を切り開けない性分だったので、当然のように廃棄を言い渡されたことで、私は泣く泣く手首を切り開く手段を手放すこととなった。
いざ辞める時は思い切って、カッターを新聞紙とセロハンテープで包み込んでごみ箱に捨てたものだが、自身の左手首の上にかつて鋭利な刃物を血管に沿って縦に滑らせた快感が忘れられずに今でも轍のように跡が残された左手首を見つめてしまう時がある。
自身で自身を傷つけることの何がいけないのか、私には到底理解出来なかった。他人からの否定を抜きにすれば、簡単に自責も雑念も全てを闇鍋に混ぜ込んで頭から被ることが出来る。私をこの世に存在たらしめる靱やかな糸のような、私という存在の輪郭がぼやけていく中で線を書き足して明確にするかのような、私とこの世を繋ぐ鎹を私は手放したくなかった。
「美冬ちゃん、終電大丈夫?」
「えっ、ああ」
スマホの電源を付けてそこに表示されたのは22:42という文字。
「終電は23時30分だから…もう少しかな」
「おっけおっけ、次何飲む?」
そう言ってドリンクのメニュー表を開いて見せ、一緒に見るかのように距離を縮めてくる男性。実際この男性とはサークルの新歓で出会ってまだ2回目なのだが、私が今年の数少ない1回生だからやけに目をかけてくれている。
アルコールは良い。簡単に不安を飛ばせる。度数の低い酒でも何杯も飲めば積もって体内を侵食していくし、高い酒なら尚更一撃だ。リストカットをやめた今、これが最もコストパフォーマンスよく快感を得られる方法ではないかと思う程だ。グラスを呷って喉に流し込む度に、脳に直接届くような幸福感が私の思考を麻痺させて舵を取り始める。やがて視界をも眩ませる麻薬に、私は依存しきっていた。
「じゃあコカレロ飲みましょうよ、一緒に」
私はそう言って男性の膝に手を置いた。もともと距離が近かったからか、更に体は接近し、胸元が腕にくっつきそうなのが見て取れる。
「強いの飲むねー、いいよ、飲もうか」
男性は微かに笑いながら私の腰にゆっくりと手を回した。赤子でも撫でるかのように生暖かい手つきで骨盤から回って腰を掴み、私を更に自分の体へと引き寄せた。互いの体は密着し、とても会って2回目とは思えない。
堪らない。
運ばれたコカレロを一気に呷ると、私の視界は夢の世界のようにぼやけ、脳内に綿をぶちまけたかのように靄がかかっていくのが感じられた。明らかに体にも心にも悪いことは分かっているのに、やめられない。身を削って得られる世界から、抜け出せない。
「何時だと思ってるの」
どうやら終電で帰るのは母のお気に召さなかったらしい。
「ごめんなさい」
「何なのまた謝って、謝ってばかりじゃない!何、私がいけないって言うの。ねえ美冬、私はあなたをこんな風にするために大学に入れたんじゃないわよ!」
「はい」
「頼むから私の言うことを聞いて頂戴。ねえお願い、遊びになんて行かないでちゃんと勉強して。美冬は偉いから分かるでしょ?」
「ごめんなさい」
「どうしてまた謝るの…私の事嫌いなの!?」
このような押し問答を一体何時間繰り広げたか、時計の短針が一周した辺りから数えるのを辞めた。私が生半可な返事しかしないからか母の激情は比例していくかのように加速していき、いつしかまともに話が成立していない水掛け論へと発展していた。
目の前で大粒の涙を流してへたり込む母を見下すようにじっと見つめる。そして如何に自分が卑劣な人間であるかを理解し、まるで散らばったパズルピースを元に戻すかのように脳内に展開される思考を組み替えた。
私の存在が母を苦しめている。母は私が生きている限り金銭でも心理面でも永遠に苦しみ続け、その身に絡みつく呪縛から逃れることが出来ない。そう思考した途端に母がぶつぶつと発している言葉が全て私に向けた恨み節のように聞こえて仕方がなかった。その声帯から絞り出される罵詈雑言を私はこの身で一身に浴びた。呷ったコカレロも、肺に溜め込んだ煙も、何もかもを覆い尽くしていく数多の呪詛。私という存在が黒く塗りつぶされていくような、深い蒼に覆われた深海に押し込められていくような、気味の悪い感覚が私を襲っていく。
どうして私は生きているんだろう。平気で人を傷つけて、なのに決められたマニュアルを読み上げるかのような謝罪を述べることしか出来ない。私という存在がこの世から切り離され、乖離していく。母は私の存在に傷ついているというのに、私は何も傷ついていない。
罰を求めた。不出来な私を罰し、私が存在することの許しを乞うた。早くこのぐちゃぐちゃに入り混ざった脳内を何とかしたかった。痛みで、辛さで、私の輪郭を書き足したかった。視界が眩み、頭がふらふらする。だがその程度じゃまだ足りないのだ。明確な痛みがないと罰にならない。私を傷つけるものが欲しい。そしてそれを罰とし、私は存在が許される。私にとって私を傷つけるものは罰であり救いなのだ。
「お願い美冬、もう勝手に遊びに行ったりしないで」
罵詈雑言の羅列が句点を打つ頃には、時刻は3時を回っていた。母はその場で気を失うように眠り、私は適当にクローゼットから引き出したブランケットを母の肩にかけてそのまま玄関へ向かった。
スマホの電源を付けて表記を確認した。3:21という時刻表示の下には、同じサークルの同回生の男性からのメッセージが表示されていた。「美冬ちゃん今どこ?今から飲み来れたりする?w」という軽薄なメッセージを尻目に、私は同じ服のまま、黒いロングコートのみを羽織って厚底のブーツを履いた。
今この家を出発することで後にまた同じように思考を繰り返すことなど私にはとっくに分かりきったことだった。だがそれで良かった。それが狙いだった。物理的に自身を傷つける手段が封じられた今、私はこうして私を追い詰めて私の存在の輪郭を書き足す。
恐らく明け方、私が無断外出したことに気づいた母は顔面蒼白の後に睡眠薬を机にばらまいてはかき集めるように喉へ流し込むに違いない。そして私はその様子を見てまた思考する。私が母を追い詰めた、私の存在がいけなかった、私には罰が必要だ、と。それだけ分かっていて尚私がこの行動を辞められないのは、これが私とこの世を繋ぐ鎹であるからだ。
私は私の精神を傷つけて存在する。そうして生きていると実感する。私によって傷つけられた精神の中藻掻き苦しみ罰を与えるために私は私を傷つける。物理的手段ではなく、それが精神的手段に変わっただけである。
こうして私はこの世に存在していることを客観視することが出来る。そうして得たピースを繋ぎ合わせて、私はこの世に私を形作る。
身を削って得られる世界から、もう抜け出せない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
