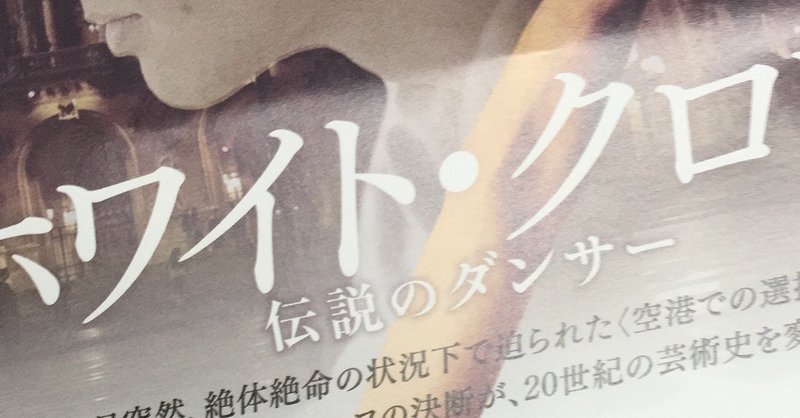
アウトプットする身体、インプットの自由──映画『ホワイト・クロウ』
ダンサーの身体の説得力は、すごい。
踊るシーンがあるから、ではない。主人公を演じるオレグ・イヴェンコの身体性は、むしろダンス以外のパートにおいて圧倒的な存在感を放つ。ダンサーならではの筋肉の厚みとしなやかさ。その彫刻のような迫力を宿した肉体が、美術館で裸体の彫刻をのぞきこむ。なんという説得力。
もう承認するしかない。喜んで受け入れよう。信用しよう。
スクリーン上にいるこの青年が、ルドルフ・ヌレエフであることを。
映画は20世紀を代表するバレエダンサー、ルドルフ・ヌレエフの1961年の亡命劇を描く。キーロフ・バレエ団初のヨーロッパ遠征の飛行機の中から物語ははじまる。到着したパリで、若きヌレエフはさっそく異端児ぶりを発揮する。勝手きままに散歩する。英語を話して現地のダンサーたちと交流する。鉄道模型に夢中になる。美術館でレンブラントの絵画や彫刻を見る。それと同じ目でセクシーなショーを観る。外界と触れ合う経験が自分の踊りの糧になると彼は強く信じている。だからこそ彼はバレエ団のお偉方やKGBの連中に逆らってでもパリの街に出ていく。鍛えられた身体を惜しげもなく解放して。なにげない、無意識の佇まいにこそ凄みが出る。これはダンサーを演じるダンサーでなければ絶対に出せない存在感だ。
この映画は徹底して「インプットするダンサー」を描く。ダンスのシーンは決して多くない。バリバリ踊れる現役のダンサーをヌレエフ役として起用しているのに、である。それに対する不満の感想もちらほら見かけるが、ダンスの妙技だけを観たければライブビューイングでいい。「物語」であることにこの映画の意味はある。いみじくも監督自らが演じるヌレエフの師プーシキンが言うように。「テクニックにこだわるな。物語を語ることが重要なんだ」──
自由なインプットなくして、アウトプットする身体は存在しえない。この映画は繰り返し繰り返しそれを描き続ける。だからこそ、当局の抑圧の本末転倒ぶりがだんだんと浮き彫りになり、それが空港での重大な決断の動機となる。椅子から立ち上がった彼は、ソ連側のすべての人間に背を向け、ひそかに待機していたフランスの空港警察官の方へ、一歩一歩、力強い早足で歩き出す。抹殺の危機にさらされた自由と身体が、この瞬間に一体化し、よみがえる。緊迫感と輝きに満ちたクライマックスだ。
世界的バレエダンサーの人生はここから幕を開け、映画はここで終わる。彼の体内のインプットとアウトプットの循環は、観客ひとりひとりに引き継がれる。「特に政治的なメッセージをこの映画に込めたつもりはありません。私にとって興味があるのは、人間の内なる精神の発露といったようなものです」──そんな監督の意図が適切に反映された映画である。
