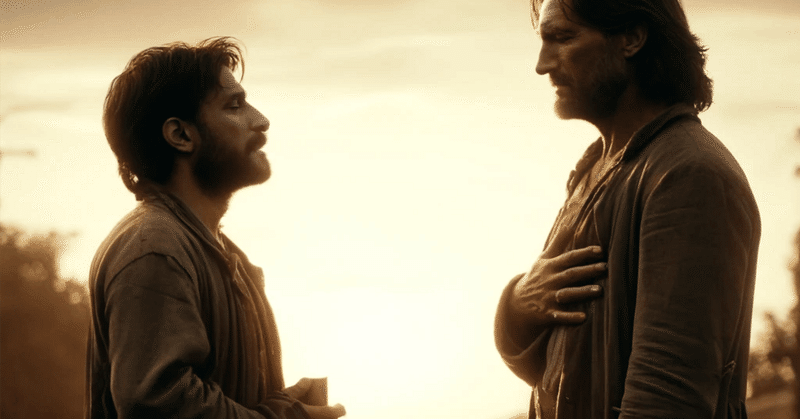
【追悼:山本弘さん】ぼくが世界でいちばん好きでいちばん嫌いな作家、山本弘とは何者だったのか。(第二回:小説作品編前編)
【『サイバーナイト』の思い出】
この記事は、亡くなった作家の山本弘さんを追悼した記事の第二弾である。
しかし、第一弾とはほぼ独立した内容になっているので、ここから読んでいただいてもかまわない。
それでも気になる方は前回の記事も読んでみてほしい。かなり長いけれど、そこそこ好評だったようだ。
前回は山本さんのネットでの一面を取り上げて、それで気力が尽きて終わってしまったので、今回はかれの小説作品を取り上げよう。
前回も書いたが、ぼくはかれの長編作品はほとんど読んでいる。雑誌に掲載されただけの短編などはさすがに追いかけ切れていないわけだが、初期の「テーブルトークRPGリプレイ集」なども読んでいるし、グループSNEの一員とした書いたものもかなり読んでいるはずだ。
初めに読んだのはたぶんゲームノベライズの『サイバーナイト』あたりだろうけれど、これはぼくが生まれて初めて読んだ本格的なSFだったのではないかと思う。
いわゆる「ゲーム理論」をベースにして全宇宙における生存のための最適戦略を描き出した「四行原則」のあたりにはわくわくしたものだ。
大人になってから読み返すと色々思うところがあるわけだが、少なくとも少年の頃のぼくは夢中になって読み耽った。
その意味では、ライトノベルとして、サイエンス・フィクションとして、最も意義のあるタイプの作品ではあるだろう。
そう、いち私人としての山本弘に、あるいは小説家としての山本弘にも、どれほど欠点があるにしても、ひとつ間違いなくいえることがある。
かれは非常に率直に自己を開陳した人物で、庵野秀明ふうにいうなら「パンツを脱いだ」作家であった。
山本弘の作品の内容はファンタジーからSF、ポルノにミステリと多岐にわたるが、そのいずれもが非常に「山本弘らしい」。
たとえ作者名をかくされて読ませられてもすぐに山本弘の作品だとわかるような強烈な個性がある。当然、良いところばかりではないと思うわけだが、それはどの作家だってそうだろう。
その作品のすべてが傑作だというつもりはないが、リーダビリティの高さも相まって、文句なしに面白い作品は数多い。その魅力の一端なりと説明し切るだけの筆力がぼくにあれば良いのだが。
【山本弘の最も山本弘らしい小説】
さて、どこから書きはじめたものだろう。
山本さんの小説作品は、既読の長編に限っても無数にある。そのなかでいずれが最高傑作かということは議論があるところだろうが、そうやって傑作と認められる作品を複数残しているだけでも凄いことだ。
そういえば、山本さん本人は生前、『アイの物語』こそ自身の最高作品にあたるのではないか、といった意味のことを記していた(続けて、より正確に集計を取ると『詩羽のいる街』になるとも書いているのだが、まあそれはそれとして)。
個人的には『神は沈黙せず』の重厚さをこそ高く評価したいところだが、一般論としてはそれほど異論はない。
『アイの物語』はたしかに山本弘の最も山本弘らしい小説である。
すでに人類が滅亡しかけた近未来から物語を始め、七つの短編を通して人類衰退の由縁を探っていく「箱物語」的に卓抜な構成、全編にただよう人間と人類に対するアイロニカルな視点、いずれも山本弘らしさ全開だ。
しかし、このAmazonでも非常に評価が高い『アイの物語』、あまり指摘されないのだが、非常に問題含みの作品でもある。
面白く読めることは間違いないものの、内容的に、そしてまた思想的に、どうにも受け入れがたいものがあるのである。
特に山本弘作品を続けて読んでいると、そこにあまりにも赤裸々に作者の思想が開陳されていることがわかって辟易させられる一面がある。
そう思っていたのはぼくだけではないらしく、きのう読んだやはり山本さんへの追悼の記事が、その『アイの物語』を取り上げてかなり手きびしく批判していた。
ぼくはここまで辛辣にいい切ってしまうつもりはないが、この記事に書かれてあることにはほぼ全面的に賛成できる。
『アイの物語』は最も山本弘らしいという意味では紛れもなくかれの最高傑作なのだが、同時にかれの欠点と限界をもさらけ出してしまっている問題作なのである。
「良い意味でも悪い意味でもきわめて強く山本弘の作家性が露出した作品」といえば良いだろうか。
かの三島由紀夫が代表作の「憂国」を取り上げて、「もし忙しい人が、三島の小説の中から一編だけ、三島のよいところ悪いところすべてを凝縮したエキスのやうな小説を読みたいと求めたら、『憂国』の一編を読んでもらへばよい」と語っているが、山本弘においてそれにあたる作品があるとすれば『アイの物語』になるだろう。
じっさい、上記リンク先で批判的に羅列されているように、この小説には数多くの難点があるのだが、だからといってぼくはこれを読むに堪えない駄作だとは思わない。
むしろそれらのいくつもの難点、矛盾、問題を生み出すに至った山本弘の思想的葛藤を想像することで、ぼくのようなタイプの読者は何とも楽しく読めてしまうのである。
まあ、もちろんその一方で、先述したようにあまりの山本弘濃度にちょっとつらくなってくることもたしかなのだが……。
【モノフォニーの地獄】
批評家のバフチンがドストエフスキーの小説を指して語った言葉に有名な「ポリフォニー(多声的)」という概念がある。
それぞれの人物が単なる作者の代弁者にならず、まったく違った思考と価値観を展開していることを賞賛した表現である(と思う)のだが、比較すると、山本弘の作品はまったくの「モノフォニー(単声的)」である。
ほとんどすべての登場人物が山本弘の考え方を代弁している印象がある。
まあ、小説とはたとえ一流の作家であっても往々にしてそうなりがちなものではあるのだろうが、それにしても、山本さんの、そして『アイの物語』の場合、かなり極端だ。
ここでは「人間は愚かで、AIは素晴らしい」という思想がひたすらに滔々と語られる。そして、ぼくとしては、その思想にまったく納得できないのである。
具体的にどう納得できないのかはリンク先を読んでほしいのだけれど、ぼくもまったくその通りだと思う。
この小説のなかでは一貫してAI(マシン)が人類より上位の知性として描写されているのだが、どうにもそのマシンたちが一様にあまり賢そうに思えないのだ。
上記noteでは「チャットGPTにも劣る」と書かれているくらいだが、この点に関して、ぼくとしてはいくらか作者に同情しないこともない。
そもそも「人間より圧倒的に賢い存在」をその人間が描くというところにムリがあるのである。
それは人間の想像力の限界の問題であって、どんな天才作家であっても、どこかでごまかすか、そうでなければ何らかの壁に突きあたるしかないはずだ。
たとえば異星人を描くときにも同様の問題は存在する。だから国内外のSF作家たちはどうあがいても想像しようがないように思える「異質な知性」を描写するために知恵を絞り、ファースト・コンタクトSF(異星人や未知の生物との最初のコンタクトを描くタイプのSF)の傑作をいくつも物して来た。
その頂点にいる作家が、たとえばポーランドの天才スタニスワフ・レムである。
ここら辺、瀬名秀明さんが「違和」と「異和」という概念を持ち出してわかりやすく説明しているので、もし興味がある人がいたら『境界知のダイナミズム』を読んでほしい。面白いよ。
【虚数のモラル】
まあ、それは余談。とにかく、そもそも原理的に描くことができないはずの「どうしてもよくわからないもの」、「人間の想像力の限界を超えたもの」をどう描くかということは、「描くことができないものを描く」ことをめざすSFにとって重要なテーマなのである。
山本さんも幾たびもこのテーマに挑戦している。『アイの物語』もそのひとつというわけだ。
そして、『アイの物語』の場合、その「描写不可能なものを描写する」ための「ごまかし」とは、マシンたちがもちいる「i」という概念である、といってしまって良いと思う。
この作品のなかで人工知能のマシンたちは自分たちの感情を表わすため、語尾に「i」という文字を付けて話をする。
かれらはその語尾を使うことで人間には不可能なほど論理的かつ平和的にコミュニケーションできるという設定になっている。
ただ、その「i」の内実が具体的にどういうものであるのか、マシンならぬただの人間である読者にはわからないし、もちろん作者にもわからなかったに違いない。
つまり虚数概念「i」とは「あなたたち読者にはよくわからないだろうが、とにかくこの概念を使える」ということでしかないわけで、やはり「ごまかしているなあ」と感じる。
しかし、くりかえすが、それ自体はしかたないことではあるのだ。人間に人間以上の存在を描くことはできないのだから。
手塚治虫の描く超越者であるあの「火の鳥」が、ときにそこらの人間以上に人間らしく見えてしまうのと同じように、山本弘の描くAIやロボットたちは、ひどく人間らしい。ぼくはそこにこの作家のひとつの限界を見るわけである。
とはいえ、何度もいうが、これはある程度はしかたないことだ。より深刻な問題は、このマシンたちの「人間性」が、きわめて傲慢かつ陳腐に思えるところにある。
山本弘がモノフォニーの作家である以上、人間知性を超越しているはずのマシンたちもまた、作者の代弁者であるしかない。
だから、マシンたちのモラルは山本弘のモラル、というより、かれが理想とするモラルである。
作中のマシンたちは山本弘にとっての理想を語りつづける。人間には到達不可能だと山本弘が考える理想を。山本さんはかれのウェブサイトでこう書いている。
僕は昔からSF小説やマンガなどで、ロボットがあまりにも人間そっくりに思考し、人間のように喋るのに反発を覚えていた。人間と同じように考えるなら、それはすでに人間じゃないかと。
ロボットと人間の違いは、単にボディが金属でできているかどうかではないはずだ。最大の相違点は心のあり方の違いではないのか。
彼らに「ヒトと同じになれ」と要求するのは無意味である。ロボットはヒトにはなれない。たとえば性的欲求や種族維持本能を持たない彼らに、恋愛感情や母性愛というものが芽生えるとは思えない。
それでも彼らは心を持つはずだと、僕は信じる。「心」とは「人間そっくりに考えること」ではないはずだ。
作中に登場する「スカンクの誤謬」とは、『鉄腕アトム』の「電光人間」というエピソードで、悪役のスカンク草井が口にする台詞から来ている。
「アトムは完全ではないぜ。なぜなら悪い心を持たねえからな」
「完全な芸術品といえるロボットなら、人間とおなじ心を持つはずだ」
この言葉は、「完全なもの」=「人間と同じもの」という誤解に基づいている。実際、多くの人がそう考えている。ヒトは万物の霊長、進化の頂点にある。進化を続けるロボットにとって、ヒトは到達すべきゴールであると。
そんなことはない。ロボットにとって、ヒトはゴールでもなければ、通過地点でもない。ロボットにはロボットの進む道があり、ゴールがあるはずだ。 実際に遠い未来、ロボットたちがこの小説で描いたようなゴールに到達するかどうかは分からない。これもまたフィクションだからだ。だが、こういう結末を迎えて欲しいと、僕は切に願うものである。
『アイの物語』のマシン、ロボットたちはまさに山本弘の理想そのもののキャラクターなのだ。どこまでも優しく、正しく、美しく――そして「倫理的」で「論理的」。
前の記事で書いたように、山本弘は「正義と論理を志す人」だから、正義(倫理)と論理をとても重視する。
否、むしろ倫理と論理とはかれにとって一体の概念である。
十分に論理的な知性であるなら、その必然として倫理的にもなるはずだ。これは『アイの物語』にくりかえし出て来る話だし、じっさいにかれはそう信じていたように見える。
一切の「悪い心」を持たない存在こそが完全。山本さんはごく素直にそう考えていた。
その実践の最もわかりやすい例が、たとえば『サイバーナイト』に出て来る「四行原則」である。
【論理と倫理は一体なのか?】
先に書いたように、これは宇宙における生存のための原則をわずか四行の原則にまとめ切ったものだ。その内容は、このようになる。
10 これが最初の接触なら30へ
二回目以降の接触なら20へ
20 前回相手が協調してきたなら30へ
攻撃してきたなら40へ
30 協調せよ
40 攻撃せよ
あまりにシンプルな「原則」なので、『サイバーナイト』を未読の方は、このようなやりかたで十分に安全を確保できるわけがないだろうと思われるかもしれない。
しかし、これは天才数学者フォン・ノイマンが創始したゲーム理論にのっとった戦略で、ゲーム理論の「囚人のジレンマ」状況における「しっぺ返し戦略」がもとになっているのだ。
「囚人のジレンマ」のシミュレーションにおいて最も単純な「しっぺ返し」のプログラムが最強であるように、あまたの異星人がうごめく宇宙においてはこの四行の原則にしたがって動くことこそが最も合理的なのだ、と『サイバーナイト』では書かれている(じっさいには『サイバーナイト』の刊行後、「しっぺ返し」より有効なプログラムがあらわれたようなのだが、もちろんそれはこの小説には関係ないことである)。
つまり、この「四行原則」にしたがって論理的に行動するなら、必然として自分から攻撃することはできない、ということになる。
このことを踏まえて、山本さんは登場人物にこんなセリフを吐かせている。
「君が真にエゴイストなら、他人と協調しなくてはならないんだ。モラルだの人類愛だのは、この際まったく関係ない。生き残るためには、自分からは決して他人を攻撃してはならないんだ。それが究極のエゴイズムなんだよ。」
これが、山本弘が考える倫理と論理を結びつける理屈の最たるものだ。
論理的にものごとを考える存在なら、平和と協調を選択し、決して自分からの戦争などは選び取らないはずだ。それは「モラルだの人類愛だのは、この際まったく関係ない」、あくまで純粋にロジックによって導かれる結論なのだ――。
小学生で初めて『サイバーナイト』を読んだときは、この逆転した論理展開に強烈なセンス・オブ・ワンダーを感じたものだ。
しかし、いまのぼくが思うに、この原則には、ひとつちょっとした穴がある(と思ったけれど、この点に関しては本編中でも指摘があるらしいので「穴」とまではいけないかもしれない。ぼくもぼんやりそんな気はしていたのだけれど、調べがつきませんでした。ごめんなさい)。
たしかに「囚人のジレンマ」のシミュレーションのように何千回、何万回とコンタクトをくりかえせば、この「四行原則」にしたがうことが最も生存確率が高くなるかもしれない。
だが、現実には一回殺されれば(絶滅させられれば)、それで生存は終わりである。「次の機会」はない。
「四行原則」では「最初の接触」のときは「協調」を選ぶことになっているが、それで敗北したとき、「次」があるとは限らないのだ。「四行原則」は「選択の一回性」を無視している、とぼくは感じる。
あるいはそのリスクを含めてもなお「四行原則」は大切だ、と山本弘はいうかもしれない。
じっさいのところ、ぼくにはこの原則がどこまで純粋に論理的だといえるかはわからないのだが、おそらく、それ以前に、山本さんは純粋に理屈で「四行原則」と、そこから導かれる「論理的に考えるならまず協調を選ぶべきだ」というありかたを真理だと考えているというよりは、ただそう信じたかったのだと思う。
これが「山本弘は何者なのか」、考える際に最も重要なポイントだといって良い。かれが論理と倫理を信じたがる心理は、非論理的な感情から出たものなのである。
いや、もちろんほんとうのところどうなのかはわからないが、ぼくはそう捉えている。そのように考えるとかれの言動や行動や作品はすべて筋が通るからだ。
【正義を求めるこころ】
山本さんは、ひとりの人間として倫理を、正義を強く強く求めていた。その気持ちがどこから出てきたものなのは無関係なぼくにはわからない。
だが、学生の頃、まわりからいじめられていた経験があったと本人が語っているから、あるいはそこら辺から来ているのかもしれない。
それ以上にもともと正義感の強い人だったということもあるのだろう。とにかく、かれはモラルの重要性と必要性を強く、固く信じていた。
しかし、ふつうに考えるなら、倫理や正義を守ることと己の利益を追求することとは矛盾する。「正直者がバカを見る」という言葉があるように、まじめに生きている人間がまじめに生きれば生きるほどつらい目に遭うことはこの世の中ではいくらでもあることだ。
きっと、山本さんはその、この世界に満ちあふれた理不尽さが許せなかったのだろう。
だから「四行原則」のような、「論理」と「倫理」が一致するロジックを考えだした。そういうことなのではないか。
上記リンクの記事では、『アイの物語』の内容的矛盾について、このように書かれている。
「論理的で合理的であれば自動的に倫理的になるはずだ」という話が繰り返し出てくるのだが、アステカ帝国を滅ぼして黄金を奪い尽くしたコンキスタドールは「非合理」だったのだろうか。アステカ帝国と仲良くしていればさらに多くの黄金を手に入れられたのだろうか。
たしかにその通りだろう。もちろん、「協調」が論理的に最善の選択である局面は存在することだろうが、「すべての局面において」まず「協調」から入ることが「論理的」だとは思えない。
ふつうに考えれば初手で「協調」より「攻撃」を選んだほうがより利益を得られる場合はいくらでもありえるはずだ。
「囚人のジレンマ」はあくまで現実世界のさまざまな条件を取捨した純粋に数学的なロジックである。それを現実世界にそのまま適用したからといって、利益が最大になるとは限らない。
ぼくは(SF的なセンス・オブ・ワンダーはないかもしれないが)、ごく常識的にそう考える。
もし人間にとって倫理を守ること、正義を貫くことが何より大切なのだとすれば、それはそうすればより多くの利益を上げられるからではないだろう。
ときに利益追求の論理に逆らってでも、正義を守るべき局面は存在する。あたりまえといえば、あたりまえの話だ。
しかし、山本さんはあくまで倫理と論理を一致させることにこだわる。ぼくはそこに何か切ないような気持ちを見るのである。
おそらく、山本さんの繊細な神経は「正しい者が報われるとは限らない」というこの世界の不条理さに耐えられなかったのだ。
正しい者(倫理的な者)は報われるべきだ。正しい者がしばしばまったく報われないこの世界は間違えている! そういうふうに考えていたのではないか。
【世界の中心でiをさけんだこども】
もちろん、この「不条理な世界でどう生きていくか」というテーマは単に山本弘その人にとってだけではなく、あらゆる人間にとってきわめて重大なもので、色々な人がこのことを考えている。
だが、山本弘がニーチェの哲学や、サルトルやカミュといった実存主義の文学を引用することはない。
かれにとって、そういった哲学だの文学だのはまさに抵抗するべき「大人の権威」に過ぎなかっただろう。
なぜそうなのかは余力が残っていればまた解説するが、とにかく山本さんはそういった権威的な思想が大嫌いだった。
その上で、神が定めたこの世界のありように我慢がならない山本さんが求めたのは、つまり「正義が正義である世界」だった。
これは『アイの物語』のなかに組み込まれた短編のタイトルで、ここまでの話を踏まえれば「すべての倫理的な行動が確実に報われる世界」といい換えても良いだろう。
この短編はコンピューター・シミュレーションのなかに創られた「正義が正義である世界」、つまり「正義が必ず悪をやっつけて終わる世界」を描いた話だ。
山本さんにとってその「正義が正義である世界」こそがあるべき、理想の世界であったことが痛いほど伝わってくる内容である。
同時に、山本さんにとっての「正義」や「倫理」が、いかに単純で、言葉を選ばないなら幼稚なものであったかも良くわかる。
かれにとっての倫理とは「人を殴ったり殺したりすることは悪いことに決まっている!」というレベルのものでしかない。
山本さんにとって、それはあまりにも自明のことであって、もしそのことがわからない人間がいるのだとすれば、それはその人が論理的ではないからなのである。
「悪いこと」はとにかく悪い。「悪い心」を持っている人間は不完全。おそらく山本さんにとって、それはあまりにも当然すぎて疑えないことだったのだろう。
むしろ、この「悪いことは悪い」という「事実」を受け入れられない人々のほうが、かれには「不完全」で「非論理的」な、つまり「悪い意味で人間らしい」存在と見えていたのだと思う。
もちろん、いちいちカントやらロールズやらを持ち出すまでもなく、一般的な倫理学や正義論はそれほど単純なものではない。
「正義が正義である世界」を求めることは人間全体の欲求であるかもしれないが、「何が正義であるのか」については意見が分かれるのである。
「悪いことはとにかく悪いに決まっているだろう!」といって済ませられる話ではないのだ。
だが、山本さんはいたってシンプルに正義を定義する。
ここら辺のあまりといえばあまりのナイーヴさが、ぼくがかれを嫌いな理由でもあり、また好きな理由でもある。
山本さんは最後まで十二歳の少年のように純粋な理不尽への怒りを抱きつづけた。かれはあらゆる「悪」を心から憎んだ。
それはきっと、決して「論理的に」導かれたものではなく、もっとかれの実存そのものに関わった感情だったに違いない。
もしかしたら子供時代のトラウマなどが関係しているのかもしれない。それはぼくには知る術もないことだが、とにかくかれは「この世界はまちがえている!」、「現実世界の人間はおかしい!」という情念から「あるべき真世界=正義が正義である世界」を求めていた。
ちなみに、まったくの余談になるが、この心理そのものは、かれが生前、痛烈に批判していた栗本薫などでもまったく同じである。
山本さんが栗本さんを徹底的に批判することは良くわかる。かれらはどこか良く似ているところがある(だからこそぼくはふたりとも好きになったわけだが)。
しかし、一方で決定的に違っているところもあって、山本弘がこの世界の「正義が必ず報われるとは限らない」という理とは異なる世界を求めたのに対し、栗本薫はその理をより突きつめた世界を求めたのである。
だから、栗本の世界は『グイン・サーガ』でも『終わりのないラブ・ソング』でも何でも良いのだが、際立って苛烈な生存競争、権力闘争ばかりが描かれる。
が、それは今回とはまったく関係ない話なので、このことは、もし今後、栗本薫論を書くことがあったらそこで書きたい。
話を戻すと、山本弘はかれが考える「正しい世界」を求めていた。それはたぶん無辜の人が無惨に殺されたりせず、暴力を振るわれたり差別されたりすることもない「優しい世界」であった。
山本弘は、おそらくその過激な発言などから思われるよりずっと優しい人であったのかもしれない。
かれにとって、この残酷な世界はあまりに耐えがたい場所だったのだと思われる。
山本さんは自伝的な小説『去年はいい年になるだろう』で自分の家庭事情を(あくまで小説なのでどこまでほんとうのことかはわからないものの)赤裸々に綴っているが、それを読むかぎり、たぶん子供時代は相当に苦しい生活だったのではないかとも感じる。
かれのどこまでも強く正義を求める心、弱者が踏みにじられることに対する灼熱の怒りは、かれのその、この残酷な世界を生きるにはあまりにも優しすぎる心から来ているものなのではないかと書いたら、ファンのひいきが過ぎるといわれてしまうだろうか。
しかし、ぼくは山本弘が幾多の欠点はあるにしても善良な人であったことを疑ったことはない。
おそらく、たぶん、きっと、かれはこの矛盾だらけの世界で生きるにはあまりにも善良であり過ぎた。それ故に、世界に自分を整合させることに苦労したのではないだろうか。
くだらないファン心理ゆえのひいきの引き倒しといえばそれまでだが、ぼくは、そういうふうに考えるのである。
山本弘は、かれが考える「善」を信じたいのである。しかし、現実の人間も、世界も、「善」であふれてはいない。だから、かれはそういった人間に対し、そして世界に対し、徹底して攻撃的であるしかなかった。
単純といえば単純だし、幼稚といってしまえば、そうであろう。しかし、ぼくはそのハリネズミのように辛辣な態度の裏側に、かれの繊細で傷つきやすい心を見るのだ。
幻想かもしれない。ただの思い込みかもしれないが、ぼくはやはり、山本弘の言葉遣いがどんなに乱暴でも、下品でも、かれを嫌いになり切ることはできそうにない。
かれのそういった攻撃的な言葉の数々の裏側に、この世界の残酷なありように痛々しく傷ついて「自分だけは決してそうはなるまい」と決意した十二歳の純真な少年がかいま見える。
その潔癖な、あまりにも潔癖すぎる少年は、たったひとり、この世界そのものの摂理と対峙して、「ぼくは求めない。認めるもんか!」と叫んでいるのである。いつまでも、いつまでも、そののどが破け、血を吹きだしても、それでも……。
いや、ぼくは、あるいは自分が思っていたよりもずっと山本弘さんの逝去に衝撃を受けていたのかもしれない。笑ってほしい、いささか感傷的になり過ぎた。
また、前回に続いてひどく長い文章になってしまった。これでもまだまだ終わりそうにないので、この「小説作品編」は二回に分けることにする。
数日中に後編を公開するつもりなので、良ければお待ちください。しばらくのお別れ。では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
