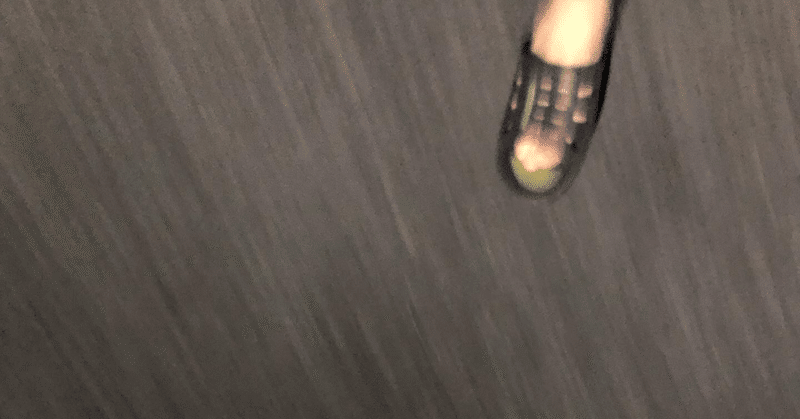
ある散歩について
いざ離れるとなると夕紅の色に映えたこの街の侘しさや、巷に漂う寂寥などが実に美しく眼に掛かる。春になって湿気を含んだ風が吹くので、嫌気がさして部屋に戻ろうとするのだが、もう少しだけと思いながらひと駅ぶん歩く。普段なら駅前の繁華な場所は避けて通るのだが、やはり今日が最後かもしれないと思いなおしてアーケードをくぐる。
部屋を出たときから聞こえていた虫の声が止んで、代わりに有線の音楽が流れる。歩くたびに存在がおおきくなっていく音楽と、窓々から漏れ聞こえてくる方言混じりの酩酊した声。泥酔の幸福感を帯びたビルの間隙を縫って歩く。
居酒屋の前で店のはっぴを着た下品な顔つきの男に話しかけられ、僕はこの街の全てが嫌になったような気分になって、曖昧な表情と返事をしてその前を通り過ぎた。
信号待ちをしながら、暗い路地を見つめる。このさきには、よく行った喫茶店がある。今は、営業時間外か。店主は僕の顔をよくしっている。僕もかれを知った気になっている。
何もかもがいつもどおりだった、だからこそ何を見てもなにかを思いだす。
ラーメン屋に入るとテレビから野球中継が流れていた。私に気付いた年寄りの店主が振り返って、いつも食べているものと同じでいいか尋ねた。私は短く返事をして、席につき、目線に困って興味のない中継に目を向ける。陶器の食器がぶつかり合う音がして、もうこの店にも来ることはないのだろうと思った。
中華麺を茹でる寸胴から立ちのぼる蒸気の臭い。旨味調味料の味が舌を痺れさせる不健康な幸福。洗いすぎて曇ったガラスのコップに油が浮かんで、汚らしい光を反射させていた。
「あんちゃん、ひさしぶり―――」
老いて硬くなった声帯の影響で、語尾は聞き取れなかった。「もう、ここにくるのは今日で最後かもしれません。」と、いうのは伝えなくていいことだと解っていたので、口の中で呟きながら麺を啜って、彼の仕事に敬意を示した。テレビの中継を見ている彼の背中をみつめながら。
東に向かって歩く。低い空に赤い月。夜気がゆっくりと満たしていくこの世界に一歩ずつ足を踏み入れて、足の甲で空気を掻きながら進む。煙草の煙を肺いっぱいに溜めたときのような不安が胸を圧している。ここはよく知っている街。しかし、ここでは歓迎されていないような。長崎や岩手に行けば歓迎される土地があるとも限らないのに。
映画のヒーローが守った街は、活字のヒロインが描いた夢は、すべて燃えないゴミになった。僕に才能があると言った女たちは、東京の民間企業に就職した。僕が帰る場所だったところには、駐車場ができた。
僕はもう部屋に戻りたくなくなって、商店街の外れまで歩いた。歩き疲れたところに、ちょうどコカ・コーラのベンチがあった。腰かけているうちに、だんだんとそれが憎たらしく思えて来、立ち上がって蹴り倒してやろうかという気になったのだが、白塗りの筆記体の文字を凝視することしかできなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
