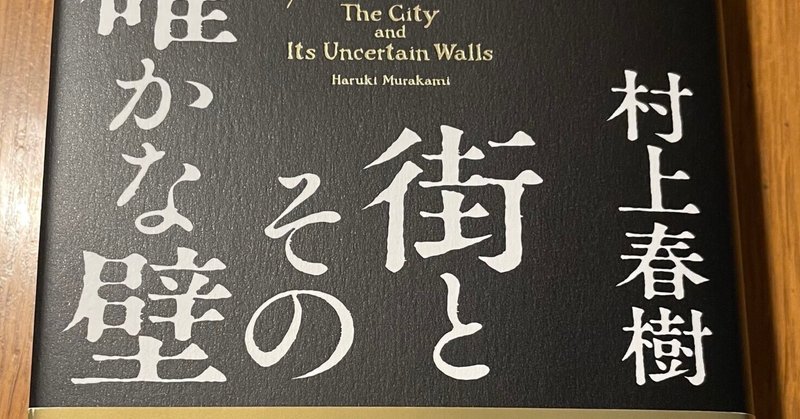
40年余の村上春樹との伴走と夢読み 村上春樹『街とその不確かな壁』レビュー
村上春樹の新作『街とその不確かな壁』を読了した。発売日の4月10日の朝、大船の駅ナカの書店で平積みされていた一冊を手に取り購入し、今春からの新たな環境の中で急がずゆっくりと時間をかけて、読み進めた。13日間の読書体験だった。
読み始めてからずっと、個人的に村上春樹の最高傑作と位置付け、愛している『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』と等しい読書感覚に小躍りしつつ、同時に、またも新味のないことにがっかりしていた。けれども、未だにその訃報の悲しみから脱け出せていない最愛の大江健三郎も常に同じような世界観の繰り返しだったし、その大江健三郎に導かれ出会った村上春樹の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を読み始めた時すぐに同じ構造の先行作品と受け止めた『野性の棕櫚』のウィリアム・フォークナーも舞台はいつもミシシッピ州の田舎町「ローアン・オーク」をモデルにした架空の土地ヨクナパトーファ郡ジェファソンだった。そう自分自身に言い聞かせ、それらと同じと思えばいいじゃないか、これはムラカミハルキ・サーガなんだ、と受け止め読み進めた。
読めば読むほど、これまで読んできたものに重なるアイテム、素材、イメージが次々とやってきた。プラトニックな彼女との愛の形、性的欲望、穴への落下、夢現(ゆめうつつ)の往来、少年、ジャズ、ビートルズ、ロシア5人組、スパゲッティ、スコッチ、etc.etc.そして何より堅牢な壁。嫌悪感も拒否感もない。沸き起こるのはただただ親近感であって、既視感溢れる作品世界に、1日のうち数十分、時に数時間浸ることは実に心地よい体験だった。
ある箇所で、漱石の『こころ』への村上春樹からの答えを聞いたように感じた。またある箇所では、東日本大震災という決して忘れてはならない歴史的事実への捉え方を示されたように思った。そして、655頁3部構成1200枚の大冊には、この3年間続く世界中を覆ったコロナ禍を読み取る手がかりが、そこかしこに満載だった。
読了直前の夜には、自分でも驚くようなリアルな夢を見て、それはまるで作品世界とほぼ同様な手触りの感覚の世界で、目覚めても忘れることのない映像として残るものだった。内容がこれまでの作品とどう似たものであろうと、そうした夢世界までもたらしてくれれば、読書体験としては、個人的には、それで十分。長く読み続けての最後の一行も完璧。余韻を深く湛えた結末だった。これまでなら、それで静かに全容を反芻するのが常だったように思うが、村上春樹は、珍しいことに「もともと好まないが」と注釈しつつ、大団円の次の頁に「あとがき」を付していた。
そこには、作品執筆の動機、経緯が記されている。そして本作が『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』と一対の作品であることが説明、いな、釈明されていた。心地良い読後感のまま、そうなんだ、とその釈明を読みつつ、自分の感覚の確かさに胸撫で下ろしながら、思いは、村上春樹の一読者としてのここに至る永い年月へと飛んでいた。
初めてその名を見た時、悪い冗談かと思ったことが忘れられない。群像新人賞の『風の歌を聞け』は、どう見てもカート・ヴォネガットの焼き直しのような印象だったし、筆名は、後に本名と知るまで当時一世風靡していた村上龍と角川春樹との混ぜ合わせた一種のパロディネームだなと勝手に決めつけていた。2作目の『1973年のピンボール』も、大江健三郎の『万延元年のフットボール』のもじりのようで、早稲田からまた小林信彦のような作家が現れたのかと片付けていたのだが、3作目のレイ・ブラッドベリのような雰囲気の『羊をめぐる冒険』を読んで、おやっと思わされるところがあって、これは真面目に読むべき作家だなと注視しようと襟を正すこととなった。また、同じ頃だったかその前後だったか、朝日新聞夕刊に連載されていたコラムの語り口に感心させられるところもあり、羊3部作として、あらためて先行2作も読み直し、SFタッチ、ハヤカワ系の読むべき作家として自分なりに再評価し大事にしようと自らの読書リストに定位させていた。
そして間を置くことなく出会った書き下ろしの長編『世界の終わりとハードボイルド・ワンダアーランド』。この一冊に、しばらくなかった読書体験としての衝撃を受け、感動し、自分自身にあっての村上春樹像が確立した。もはやハヤカワ系などではなかった。同書を読み終わると同時に「ダニー・ボーイ」が鮮明に聴こえてきて涙したことを忘れたことはない。
その後の、作家村上春樹の大躍進については付言も多言も無用。赤と緑の装丁が目にも鮮やかだった『ノルウェイの森』が大ベストセラーになり、その名は誰もが知るところとなって、どこぞのメディアは、村上春樹を「国民作家」などと持ち上げるまでになった。執筆世界も一挙に拡大し、ラブホテルやオリンピックのルポや、世界各地への旅行記、スコット・フィッツジェラルドやレイモンド・カーヴァーの翻訳などなど、活動範囲は瞬く間に多彩になった。
おそらく、その広がりの一環だったのではないかと思われるのだが、トルーマン・カポーティの『冷血』を思わせる地下鉄サリン事件の被害者へのインタビュー『アンダーグラウンド』が大きな画期となって、突如深く社会問題にも関与するようにもなり、内向的な作家から社会性に満ちた作家に変貌した。そして2005年に『海辺のカフカ』英訳版が米紙のベストブックに選出されて以降は、ノーベル文学賞の発表時期になるたびにハルキストと自らを呼称する愛読者たちが騒ぎ出すようになった。近年は新作上梓のたびにニュースになるし、個々の事象への発言も注目されている。本作もまた然り。その上、優れた読者が確実に増大していることも間違いなく、世界的に評価された映画『ドライブ・マイ・カー』の濱口竜介の原作換骨奪胎には、村上春樹の作品世界の典雅で想像力あふれる継承が明確に観て取れる。あゝ、村上春樹もついにこんなところまで来たんだな、と事あるごとに様々なことを思い今に至っているのだが、若い頃同じような時期に湘南地区に移り住んだらしいことや、もう随分と前の話ながら大磯に住んだ友人が自宅を売りに出した時、村上夫妻がその家を自宅を広げるべく買い増すようにして買い取ったということを聞いたことなど、自分とは何の関わりもないが遠からず感じるところがあったことまで思い返したりもした。そのように勝手な想いを馳せながら、作家は「限られた数のモチーフを、手を変え品を変え、様々な形に書き換えていくだけ」というこのたびの「あとがき」のくだりに深いところで合点し、納得させられつつ、デビュー以来ずっと自分は、その作家活動を伴走者のように追いかけ続けてきたのだなと捉える感慨をもった。そして村上春樹の本質はやはり『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』に尽くされていて、その後の広範な村上春樹ワールドは、その時一対のもとして書きかけていた本作に収斂されたものの変奏だったのだなと思った。
この40年とそれを少し上回る村上春樹の作家活動はあまりに広大すぎて、その全てを追いかけることは出来ていない。それでも、本作と「あとがき」とによって、村上春樹を読むことそのものが、村上春樹の処女作以降の夢のつづきを読む行為だったのだなと思い至った。村上春樹の新作『街とその不確かな壁』は、そのように読む者の来し方をやわらかに湧出させる作品である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
