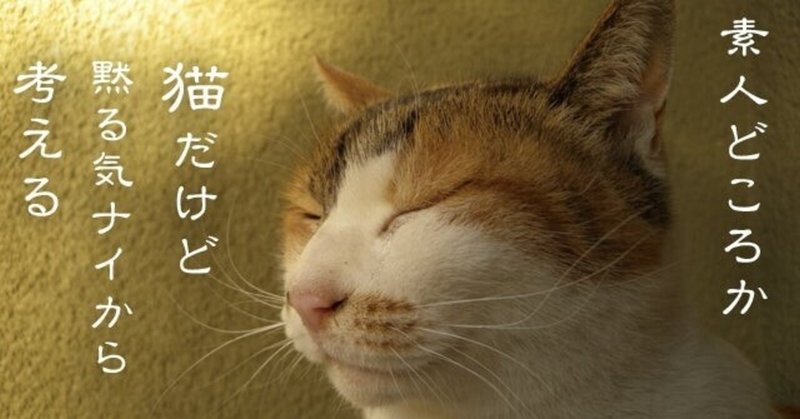
『矛盾』のすゝめ
「矛盾」という言葉を聞いて、ワクワクして喜ぶ人は、多分少数だと経験測から思う。僕の知人の中では、確かに一定数はいる。特に連続起業家(シリアルアントレプレナー)がそれにあたる。
世界的に見ても、連続起業家の割合は少数だから、そのような種類の人と一般の人を比べると、相当な比率で少数派とみなせるはずだ。
では「矛盾」を好まないのが大多数だとする根拠は、今の世の中での現代人の生活様式が確かな証左となっている。
「人間は基本的に怠け者である。仕事にも、その性質が表れてしまう。」
「考えることは最も過酷な仕事だ。だからそれをやろうとする人がこんなにも少ないのだ」
By フォード・モーター創業者 ヘンリー・フォード
この言葉が、端的に表しているような気がする。
僕たちは、考えるとき、判断を迫られるとき、課題にぶつかったとき、必ずこの「矛盾」に遭遇する。意識していなくとも、「矛盾」の定義とは、2つの事象のつじつまが合わないなど、何かが対立する場面のことだからだ。
判断がつかない時とは、頭の中で、行くか行かないか、話すか話さないか、会うか会わないか、実行するかしないか等々、行動や行為が伴う対立する
間で「うろうろ」「オロオロ」している状態を意味している。まさに「矛盾」の時、と云える。
そして「考えること」を避けたい人間の性は、疲労を回避するという本質的な理由もあるが、フォード氏の言葉を借りて、元々人は「怠け者」という仮説が一般なのだとしたら、「矛盾」という状態を、人生からできるだけ無くしたい、とするはずだ。
そんな何か耳障りの悪い「矛盾」を勧める題をつけたのは、なぜなのかといえば、古今東西、世の中は「矛盾」だらけだった、そして今もこれからも継続して「矛盾だらけ」は変わらないんだ、と個人的に常々感じたから。
今の政府が新型コロナウイルス感染症対策で発令している政策の「ダブルスタンダード」がまさに「矛盾」の代表例であるし、世界中が体験しているコロナ禍の「有事」状態の中では、「平時」のルールが全部ひっくり返され、良い悪い、行動の可否、言動の可否、開催の可否、発言の可否、などなど対立する事象が溢れてて、日常生活レベルでさえ世界中のみんなが右往左往している。
そしてこの「右往左往」→「矛盾」に疲れた人々が、何が正しくて正義なのか早く示してくれ、と誰かに、何かに縋っていることを感じ取ったマスコミが、それに対する消費社会上の力学として「業界の利益」を出すため、カタルシスの出口を偽装して示したような「政策批判」「揚げ足とり」の番組が多く散見されている。
途中だが、ここでちょっと脱線してみる。
僕はあまりTVを見ないが、定年後の65歳以上の世帯では毎日4時間以上TVを見る、と総務省がデータを公表している。なのでTVの番組からの高齢者への影響は多大だ。ちなみに10代、20代は1,2時間以下、ほぼ見ないという層も大多数だ。
加えて、日本の貯蓄の割合を年代別でみると、2015年のデータだが下記となっていた。
50代以上 日本全体の個人貯蓄総数の76%
60代以上 日本全体の個人貯蓄総数の54%
そして衆院、参院選の投票率では、2018年以前でみると50%を超えているのは常に50代以上だけだ。(総務省HP参照)
経済と政治のメインターゲット層が、50代以上に偏るのも上記のデータからすると必然のようにも感じる。でないと企業の利益も見込めないし、政治の票も得られないから。
現在の社会の状態は上記が示すデータの結果として、特に「矛盾」はなく、自明なものとしてそうなったのだ、と。
話を戻すと、今僕らは、そんな社会構造の中にいることを認識した上で、再度、題名でもある「矛盾」や「考える」ことを避けないように、と勧めるのは、これからの10~20年間くらいは、年代別人口分布的にはまだその社会情勢の中で翻弄され続けてしまう可能性をとても感じるから。
誰もが即効性のある解決策を求めている現状だが、真実は「急がば回れ」的な、民主的で落ち着いた状態をベースに、市民レベルでも科学的で平和的なプロセスが重要なのではないか、と。プラトンのイデア論やヘーゲルの弁証法に倣い、コロナ禍の「有事」の時こそ、現代に合わせてアップデートした本質的な「科学的」という状態を目指すことで、高次の「平時」にたどり着くことができるような、そんな気がしている。
内田樹氏が科学的とは何か、という定義を書かれていたのを思い出した。その科学的とはものすごく民主的で、わちゃわちゃと誰もが反証でき、透明性も高く、とても時間がかかるものだったと記憶している。
「知行合一」
突然の挟みだが、これは僕の一番好きな言葉。
ここには思想、思考と行動のバランスを是とする理念がある。
「矛盾」と上手に付き合るためにはピッタリだ。
そんなこんなで「矛盾」に落ち着いて、忍耐強く向き合うことが、僕ら現役世代の基本行動理念ではなかろうか。
と、僭越ながら問題提起をした次第でした。
▼ 参考文献
・プラトン入門 R・S・ブラック著、内山勝利訳
・国家-第六(「実相」に終るのである) プラトン著
・2016年国民生活基礎調査ホームページ
・総務省ホームページ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
