
小説『エミリーキャット』第78章・真昼の決闘
陸橋の階段を登りながら、彩は憂鬱な思いでそっと後ろを振り返った。
怒気を含み、尖った眼差しの慎哉が背後の階段を彩を見上げながらひたひたと登ってくるのを、まるで見てはいけないものを見てしまったかのような気持ちとなって彼女は思わず顔を背けた。
階段を登り切って暫くふたりは前後一列となり何事も無いように歩いていたが、やがて耐え切れないといった様子で彩が振り返り、ふたりは向かい合って対峙した。
『なんだよ?買い物に行くんじゃないのか?』
『独りで行かせてよ
子供のお遣いじゃないのよ』
『それは駄目だ、彩にはまだ単独行動はさせられない』
『酷いわこんなの!
私はこれじゃどこにも行くことが出来ないじゃない、
私にだってプライバシーはあるのよ』
『そんなことは解ってる、
彩が素直に入院にオーケーのサインを書いてくれさえしたら君はもう自由だよ、
少なくとも俺や山下さんからの五月蝿い監視の目からは逃(のが)れられるし俺だって有給使って仕事休むなんてことしなくて、すむ』
『どこが自由なのよ、
私を精神病院の隔離病棟に入れたいだけでしょう??』
『隔離病棟の何が悪い、
最初の1日か2日だけだと医者も言っていただろう?
病状がどんなものかよく個人観察する為だよ、万が一暴れられたら大変だからな、
ああいう病院へ入る人は最初は一応試験的、あるいは形式的にも大抵そういう風にされる、
それが過ぎたら一般病棟へ移されるんだ、君だって一度は鬱の入院で経験あるだろう?
…仕方が無いよ』
『でも今の私はどこも悪くないのよ、それなのに隔離室なんか入れられる謂(いわ)れは無いわ!絶対お断りよ』
『だったら俺の監視を断ることは出来ないぞ、
またふいに神隠しみたいに消えて半年後フラッと帰ってくるなんて真似、
もう二度とされたくは無いんでね!』
『あれは…』
と言いかけて彩はその先の言葉を飲んだ。

飲み込んだ言葉はどこまでも苦(にが)く、心の表面までをもまるで暗黒のビニールシートのように圧迫的に覆い尽くし息も出来ない、と彩は思った。
『私だって半年も経っていただなんて全然知らなかったんだもの…』

と、飲み込んだその言葉は夜の黒い水面(みなも)に銀いろの大きな波紋を拡げ続ける。
“そんなこと言ったってどうせ貴方は信じないでしょ?”
と彩はその波紋の中央で暗鬱な薄羽蜻蛉(うすば・かげろう)のように思った。
『独りで歩きたいのよ、
買い物じゃなくたって街を歩き回ってすっきりしたい時だってあるわ、外の空気に触れてリフレッシュしたいって誰にでもある気持ち…
シンちゃんにだって解るはずよ』



ほとばしるように、だが切々と彩は自分の想いを問いかけた。
だが慎哉には防水加工を施された固い布のように彩の言葉は浸透しない。
『だったら俺と一緒に歩いたらいいさ、
なんてことないだろう?
俺の存在なんて気にしなけりゃいいんだ、
独りで歩いてるように好き勝手にしたらいいさ、
リフレッシュなんて彩の意識次第でいくらでも出来るよ、
スタバ入って一服するなり、行きたがってたアーティゾン美術館のフォートリエ展へでも行ったらいいじゃないか、
そうだ、彩はバッティングセンターが好きだし行きつけのとこで、
思いっきりかっ飛ばしたらいいだろう?
何しようと君は自由だ、
俺は離れたとこから見てるからそんなの気にしなけりゃいいんだよ、
俺のことなんか空気みたいに思えばいいんだ』
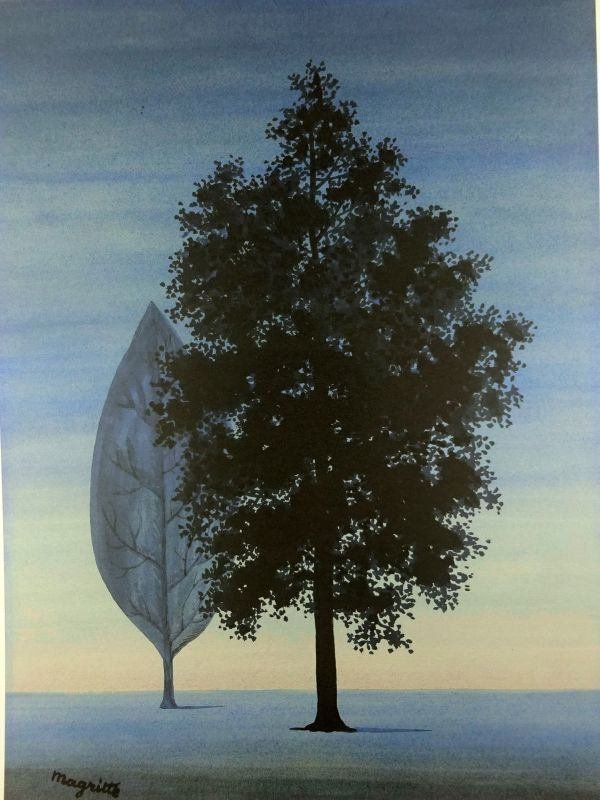
『思えないわよそんなの、
思えるわけないじゃない!
貴方は私の婚約者なのよ、
どうすれば空気みたいに感じられるっていうのよ?
ずっと尾行するように街中つけ回されて、意識したくなくたってしてしまうほうがむしろノーマルなんじゃないの??』
『へえそうかい?
今までずっとそうだったんじゃないのか?
彩にとって俺は一人の男というよりは、空気みたいな代替えのきく存在だったんだろう、
どっか俺の見知らぬ街へ行ってしまっても空気ならどこの街にだってあるもんな?』
慎哉の眼は怒りと今まで見たことのない嫉妬に燃え滾(たぎ)っている。
『……』
彩は追い詰められたように何も言い返すことが出来ず、
とうとう黙り込んでしまった。

彼自身、出どころ不明な“何か”や“、誰か”に対して持つ自分の中の焦点の定まらぬ嫉妬が不条理でならず、
そのことが彼のアイデンティティまでをも深く傷つけてしまいそうでどうしようもなく恐ろしくと同時に孤独だった。
にも関わらず今、彩を独りには絶対に出来ない、
なんで俺はこんなにもこいつにこだわるんだろう?
と慎哉は自分で自分の強い拘泥(こうでい)を憎んだ。

もう別れたほうがいいという気持ちがあるにも関わらず、そういう気持ちが芽生え始めた頃から彩に対する逡巡は何故だか全く無い、
発想だけがあり、それについてくるはずの瞬発力にも似た行動が心身共に彼には抜け落ちたように欠落していた。
何故ならそれに反する“絶対別れない、別れたくない”という気持ちのほうが圧倒的だったからだ。

“どうしてなんだ?
意地になってるのか?
彩なんかにそこまでの魅力があるとでもいうのか?
俺より歳上だし、三十路をとうに越えててもうさして若くもない”
遥香の言葉がふと頭を過った。
“お兄ちゃん、二十代のもっと若くて心身共に健康な女性だって周りにいくらでも居るでしょう、
なんで彩さんなのよ?
三十代にしても彩さんよりいい人はもっと他にも居るわよ、そりゃちょっと綺麗な人かもしれないけれどあの程度の美人なら幾らでもいるでしょう、ズルズルと婚約期間引き延ばして散々待たせた挙げ句、失踪だなんて、
あんなに非常識な人だとは思わなかったわよ!
お兄ちゃんは病気のせいって言うけれどそれだけじゃないような気もするの、
ねぇ、もういっそ誰か他の人にしちゃったら?
私、彩さんてお兄ちゃんを本当に好きじゃないような気がするのよね、
思い過ごしかもしれないけど、彩さんは全然違う何かを見てるのかもしれない、
それが他の誰なのか、
なんなのかは全く解らないんだけど…
彼女、ちょっと掴みどころの無い人だから…
施設で育ったり出自が不明な人って自分が解らないっていうか、そういう不安定なところがどうしてもあるのかも…。ねぇ、結婚相手なんだから、もっと“普通の人”にしたほうがいいわよ”

妹の言葉は確かだと慎哉は思った。
“彩の代わりになる女はこの世の中にはごろごろ居るに決まってる。
もっと身も心も健やかで無難な一緒にいて安らげる女のほうがいいに決まってる、
誰だってそう思うさ。
代替えが効くのは俺のほうじゃない、むしろ片方しか乳房の無いこの可哀想なメンヘラの彩のほうなんだ、
こいつを医者に頼んで精神科の独居房へ閉じ込めてもらって一年くらい絶対出てこれないようにした挙げ句、俺はいっそのことハワイにでも旅行へ行ってくりゃいい、
そこで健康的な小麦色の肌の女と知り合うんだ、
ナニジンだっていい、
どんな肌の色でもいい、
何もかも忘れて後腐れなく愉しい女ならどんなんだっていい、
何も結婚云々なんかそんなこと遊びがてらの女相手にどうだっていいじゃないか、
兎に角もうこんな目に遇いたくないだけだ、
彩なんぞいっそのことドブにでも叩きつけてやる!”
そう思うと慎哉は天を仰ぎたくなる想いになった。
“なんでよりにも因って俺はこんな女が好きなんだよっ!?”
腸(はらわた)が煮えくり返っているというのに彼から出てくる言葉は、途轍もなく冷静だった。
『だから買い物に行きゃいいじゃないか、
俺はなるべく離れて見るようにするからさ』
『行かないわ、
もう疲れたの…
こんな風に貴方とやり合うだなんて…そんな積もりは無かったのに…とても悲しい、
私今日なんだか上の空でうっかり履き慣れない真新しいヒールを履いてきてしまったから…
お蔭で足が痛いわ、
…もう家へ帰る』
慎哉の眼にはこんな時の彩は、なかなか言うことを聞かない気紛れで我が儘な、それでいて妙に可憐な小娘のように見える。
そこが慎哉は余計に腹立たしかった。
最初の頃のあの聡明でしっかり者の彼女は一体どこへ行ってしまったんだろう?
そう懐かしみ、昔を惜しむ気持ちがあるにも関わらず、慎哉は今の半分壊れかけたような彩を放っておけなかった。
芯から怒りも憎悪も感じているというのに彩を見ていると心配でならない、
『じゃタクシーを捕まえてくる、そこで待ってろ』
と苦虫を噛み潰したままの慎哉は言った。
『解った』
と彩が薄く安堵のため息をつくと同時にいきなり慎哉は彼女のバッグを乱暴に引ったくり、平板な、まるで全ての感情が消失してしまったかのような声でこう告げた。
『靴を脱げ』
『え?』
彩はその意味を飲み込めずに
鳩が豆鉄砲を喰らったかのような顔をしてその場に茫然と立ちすくんだ。
『靴を脱ぐんだよ、
どうせ痛いんだ、俺がその靴を持っててやるからそこで脱いじまえ』
慎哉はそう言いながらぽかんとする彩の目の前へ歩み寄ると急に膝まづき、自分の上着のポケットから今まで見たこともないような厚手で大判のハンカチを取り出すなり、
彩の足元へとそれを拡げた。

『靴を脱いでこの上へ立っとけ』
半分嗤ったような顔で彼は吐いて棄てるようにそう言い放った。
『何ですって?』
と彩は慄然とした顔を慎哉に向けた。
わけが解らず怯々と思い惑うその顔を見ても慎哉は全く憐憫(れんびん)を感じなかった。
むしろいい気味だと思った。彩はこういうことには羞恥が過剰に強いことを知っている慎哉は心の底から痛快だった。
ちょっとくらいは懲罰的に扱ってやれと彼は心の中で毒づいた。
『彩の靴は俺が持つ、
お前はこの上に立って俺をここで待て、いいな?』
『いやよそんなの!
冗談でしょう!?』
と、ようやく事態が飲み込めた彩は片眉を吊り上げ、慎哉が好きなあの形のいい唇が震えるほど怒っている。
『いいから早く脱げ』
『いやっ!』
一瞬彩はもしや慎哉が自分をおぶってくれるつもりなのか?と思ってしまった。
だが次の瞬間そんな自分の甘ったるい早合点を彼女は今更ながら激しく悔やんだ。
そして目の前に「とんだ自惚れ」と書いた紙を突き付けられたようで彼女は深過ぎる傷心と共にそんな自分を猛烈に恥じた。

孤独が彩の羞恥を強い酒のように撹拌し、高いアルコール度数を証明するかの如く深酒のように激しく揺らぐ悲しみの酩酊を彼女に与えた。
その中で彩は吐き気すら感じた。
『ふざけないでよ、
なんでそんな真似しないといけないのよっ』
彩は口調は強気だが折れそうな心持ちで慎哉に必死で抗った。
膝まづいた慎哉はそんな彩を無表情なまま見上げていたが、いきなり彩の花車(きゃしゃ)な足首を横殴りに掴むと半ば無理矢理、彼女のベージュのハイヒールをもぎ取るように脱がせてしまった。
荒々しく靴を脱がされた拍子に上半身のバランスを危うく失いかけた彩は思わず慎哉の肩にまるで武器のように鋭くその手のひらを突いた。
失いかけた我が身の均衡を辛うじてそこで保つと彩は絶望的なため息を彼の背(そびら)の上で、ひとつついた。

手を突いた勢いは強かったものの小さな彩の手のひらをスーツの肩越しに感じながら、慎哉は急に泣きたい思いとなった。
彼の肩から心臓にまで到達する彩の体温、
清水のように沁み通るその淫靡感、恐らくは慎哉の錯覚でしかないと、彼自身が思う彩という女の奥底に睡る艶めいた狡猾と小さく灯る卑劣と匂いやかな裏切り、
あるいは小動物のような危うい俊敏性、逃避への欲求と強い憧れ、
その癖、慎哉の肩から骨身にまで響き渡るような行き先不明の情熱を忌々しく、憎々しく、腹立たしく、毒々しく、
…そして愛おしく感じた。

と同時に思わず怒鳴りつけてやりたくなる衝動に彼は狂いそうになった。
その嵐のように荒れ狂う心を落ち着かせようと彼は心の中でわざとこう呟いた。
“男の革靴やスニーカーと違って女のパンプスと呼ばれるヒール靴など奪い取るようにすれば脱がせることはいとも容易(たやす)い”と…。
こんなもの妹があの細い眼につけてる似合いもしないエクステンションとかいう付け睫毛をひっぱがすより簡単だ、
見知らぬ男達の尻のポケットから自転車ですれ違いざま、無防備にはみ出す財布を素早く抜き取り、風のように逃げ去るより簡単だ、
今にも閉まりそうな電車のドアーの隙間へ身を斜(はす)にしてスレスレで滑り込むより簡単だ、
理髪店でシャンプー中『かゆいところはございませんか?』と問われて、そこではなく、こここそがかゆいのだっ!と言い放つより簡単だ、
林檎のなる木から林檎を捥ぐように簡単だ、
地面に落ちた小石を拾うみたいに簡単だ。
こんな簡単に脱がせることの出来る華奢造りで無防備な靴を履く女は本当に莫迦だと彼は思った。
しかしその莫迦な靴を履いている彩を見るのが彼は阿保ほど好きだったのだ。
そんな自分も亦、同類なんじゃないのか?と彼は思った。

彼の好みに合わせて平素、スニーカーが好きな彩も慎哉とのデート時はスカートだろうがパンツスタイルだろうがヒールの靴をわざわざ履いていてくれたこともまた事実だったが、彼はそのことについては今や考えたくもなかった。
更に彼は逃げるようにこう思った。
“莫迦な女が履く靴は全部、
莫迦だ!
男はあんな歩くのも危ういような莫迦な靴は履かない
増してや自分の脚を傷めてまで何故、女はあんなに装飾品的過ぎるゆえに脆弱な靴をわざわざ履いたりするんだ、
俺みたいな男が喜ぶからそうしてくれるとでも云うのか!?
いやいやそんなんじゃない!
冗談じゃない!
俺が悦ぶのはもっと、
そんなんじゃなくて、
嬉しく感じることはもっと…
欲していることはもっと…!”
と彼は思った。
“……なんだっけ?”

と彼は遠い空に真っ直ぐ伸びる飛行機雲を睨みつけて思った。

その瞳にはうっすら怒りの果ての少年じみた不条理な悲しみに涙が浮かんだ。
同時にいっぽかただけ慎哉に靴を奪われた彩も今にも泣き出しそうな惨めな顔となっていた。
慎哉はそんな彩の敗北者じみた顔を見て形ばかりの憐れみをかけるような言葉を故意にかけた。
『本当は両方脱いでもらうとこだがま、いいだろう、
そんなんじゃ危なっかしくてそう遠くへ行ったりは出来ないもんな、
そんなにそこに立つのが嫌ならそのままハイヒールの片足でずっと立ってたらいい、
ヨガみたいでいいじゃないかまぁずっとそうしてろよ、
出来るもんなら』
『……』
何がヨガよと彩の怒りは沸点に達したものの彼女はその反面いいわそんなに言うなら片足でこのままずっと立っててやるから!と決心した。
偶然ヨガを数年やっていた経験のある彼女は体の柔軟性とバランスにだけは自信があった。
だがそんなこと露ほども知らぬ慎哉は階段を前にこう言い放った。
『いいかそこで待ってろよ、タクシーつかまったらすぐ迎えにくるから、片足でもいいから転ばないよう
もしふらついたら欄干にでもつかまってそこでじっとしてろ』
悔しさに今にも泣き出しそうな顔の彩に向かってまるで更に溜飲を下げるように慎哉は唇の隅で嗤うと
『いい子でな?』
そう言い残し、彩のハイヒールを片手にぶら下げたまま軽快に口笛を吹きながら階段を駆け降りていった。

彩はひと気もなく、ただっぴろい陸橋の上で左足にハイヒールをはいたまま、白いトレンチコート姿で仕方無く右足をフラミンゴのようにすくめて立っていた。
だが1分経過し、だんだん彩は辛くなってきた。
何しろハイヒールでの片足立ちだ。
おまけにヨガを習っていたのはもう五年も前のことなのだ、と彼女は今更ながらその遠く流れた歳月を思い知った。
片足立ちを彼女はとうとう諦めて、慎哉が路面に敷いたハンカチの上へ渋々ハイヒールを脱いで立つことにした。
ハンカチの上へ立った途端、彩は慎哉に向かって降伏の白旗を挙げたような気持ちとなって情けなくなった。
が、それと同時に陸橋のタイルの感触を微塵も彼女の
足裏に伝わらせないほど、
分厚く幅広なハンカチの感触に彩は妙な感謝の気持ちが不本意にも泉のようにもくもくと沸いてくることが悔しかった。
彼女は羞恥と怒りと悲しみでぐるぐると回るように、ない交ぜになった心の中で呟いた。シンちゃんは私がどうすれば辛いか?
辱しめられるか?
その傷つきかたまでまるで私の生理の周期のように識っている、だからあんな風に巧みな意地悪をするのよ、
…それなのに私を見棄てようとはしないんだわ、
彩は唇を噛み締めた。
それが何故なのか、私は知っている、
今まで見て見ないふりをし続けてきた。
でももうこれ以上…
と彩は思った。
“だって私は違う!違うのよ”

しかしそうやって立つうち、やがて若いカップルやサラリーマン、子供連れの母親達が陸橋の上へやってきて、ハンカチの上で片方だけのハイヒールを手に下げて佇立する彩を“一体どうしたことか?”と揃って怪訝の眼を放つようになった。
彩はいたたまれなくなり、人々の視線から逃げるようにハンカチの上からおもむろに歩き出し欄干へ寄り添うと、人々の好奇の眼に背を向けた。
天気がいいので、てっきり陸橋の上は温かいであろうと思っていたが、ストッキングの彩の足の裏は冷たくざらついた、まるで磁器の上を歩くようだった。
おまけに取りすがった欄干までもが、塗料でなめらかなそのクリームいろの表面が意外なほど、冷ややかで、
桜の花時とはいえ、その強い春寒に彩は怖じ気づいた。
その癖、日光の照り返しが彩の鼻腔へ強く射し込むようで鉄の匂いがむっと立ち込める春の気候の矛盾に、彩は眼を瞑ってただ自分の躰が慣れるのを待った。

やがてカップルや親子は行き過ぎて陸橋の上は再び無人となり、彩は欄干に凭れ掛かり下方のアスファルトを見つめたまま小さくホッとした。
すると背後から慎哉ではない男の声が突然響き、彩は驚愕のあまりそのまま飛び上がりそうになった。

『あれ?吉田さん?
吉田彩さんですよね
こんなとこで何してんですか?』
ぎょっとして振り向いた彩の目の前に忘れたくとも決して忘れることの出来ない男が立っていた。
彩の顔から血の気(け)が音をたてて引いてゆくのが解った。
男はそれには頓着せずに、
むしろにこやかにこう言った。
『靴どうしたの?なんで履かないの?』
男は彩より若干年下風で更には慎哉より若く見えた。
丈の短い黒いピーコートに身を包み、やや長めの髪を後ろで一つに束ね、小さくて色黒の瓜実顔の周りには後れ毛がまるで若い女のように整えられつつふんわりとあった。
彩は欄干に寄りかかったまま、その指先に一足だけのパンプスを提げていた。

男は欄干にすがる彩のすぐ真隣りへ歩み寄ると真下のアスファルトの路面を陸橋から見下ろしてこう言った。
『間違って下にでも落っことした?』
下の路面に靴など落ちていないのを知ってて確認すると男はそらぞらしくこう言った。
『そんなわけないか
ねえどうしたのさ?彩さん久しぶりだね』
と言って男は彩のトレンチコートの肩に手を置いた。
その瞬間彩は激しく肩を揺すってまるで毛虫でも払い落とすような仕草をとりながら凍りついた声を上げた。
『私に触らないで!』
『そんなこと云わないでよ
冷たいなぁ、それにしても、こんなとこで逢うなんて、
またえらく奇遇だな、
俺また彩さんと逢えて嬉しいよ、一体何年ぶりだろう?』
男は自分から視線を背(そむ)け震える横顔の彩に問わず語りにとうとうと、立て板に水の如く話し出した。
『彩さんさぁドラッグストアの別の支店に俺のこと言いつけただろう?
お蔭で俺、あの後店長クビになったんだよね、
解任さ、
警察に言わないでおいてやるから辞任してくれって、
要するにクビになったわけ』
『貴方が悪いんでしょう私に関係ないわ』
彩は彼から顔を背けたまま、硬質の硝子をぴぃんと張り詰めたような声でそう言った。
『関係無かないでしょうよ、
そんな言い方しないでよ』
と男は彩の髪に触れようとしたが反射的にその手を鋭利な手さばきで払いのけた彩は燃え盛る呪詛とは反対に小さく口隠(ごも)るようにして叫んだ。

『だから触らないでって言ってるじゃない、
もうすぐ彼が来るのよ!』
と彩は周りには誰も居ないというのにまるで誰にも聴かれまいと努めるかのようにその声を潜めた。
『あの時も君そう言ったね?こんなことしたら私の父が黙っていないって、父は警官なんだから変な真似したら貴方は逮捕されるって』
『……』
彩は自分の口腔が薄いグラシン紙でも喉奥にまでびっしり貼りつけられたのではないか?と思うほどカラカラに渇き、吐き気すら感じた。
息が出来ない、と彩は思った。“苦しい、誰か助けて”
『あれ嘘だったんだろう?俺、店長クビにはなったけどさ逮捕なんかされてないもんね』
『……』
彼女は男を睨み返したが無念な想いはそのままに言葉は全く出てこない、
今何か話したら本当に吐いてしまいそうだ、と彩は思った。
『彩さんさぁ俺あのあと、
いろいろ君のこと調べたんだよ、君の後、尾けたり聞き込み調査とかしてさ、
近所の奥さん達、結婚相談所からの調査員だって言ったらベラベラなんでも喋ってくれたよ、彩さん当時ホステスさんやってたんでしょう?
夜遅く派手なメイクと服やドレスで帰ってくるのを見たことがあるって、
いろいろ苦労してそうだって…
彩さんが身寄りが居なくて、どうやら天涯孤独らしいって、警官の父親どころか独りぽっちなんだって』

彩は男から震える視線をそらした。
男は彩が興味も無いものを必死で見つめようと努めていることを見透かしたような気分となって小さく鼻で嗤うと彩の視線の先を辿り見た。
それを見ることに意識を集中させ、彩が今の苦境から逃げようとしているのだと彼は思った。
そんな彩の視線の先には遠い電柱に止まる一羽の鴉が居た。

『今もそうなの?
だったらさあの時の車まだ俺あるよ、
ちょうど下のガレージにね、
俺だったら彩さんの力になってあげられると思うよ、
奥さん連中言ってたの、
独りっきりで困ってそうな時もあるようだって、ね?
下、来ない?またドライブしようよ』
彼は彩の肩に手をかけると耳元で囁くようにそう言った。
『やめて』
彩は吐き気に耐えてやっとの思いでそう言った。
『あの時より俺優しくしてやるからさ』
そう言って男は再び払いのけられた腕を今度は彩の腰に回すと抱きすくめようとした。
『ちょっと!
ふざけないで!
私にこれ以上触ったら大声出すわよ!』
『もう出してるじゃない』
男は嘲笑った。
身をよじる彩の顔はどんどん血の気が引いてゆく。
慎哉はいつになったら来るのだろう?と彼女は思った。
もしかしてあのまま帰ってしまったのでは?
私への仕返しでこんなところへ置き去りにされたのでは?とあり得ない想像が彩の混乱する頭を駆け巡る。
だがそれに反するように、彩は目の前の男を殺気立つ焼けた鋼(はがね)の視線で睨みつけたが、男はただそれをせせら笑うだけだった。

と、階段を警戒と怒号の靴音をたてながら激しく駆け上がる慎哉の叫び声に彩ははっとして振り返った。
『おいっ!なんだお前!?』
慎哉は眼の色を変えてますます肩を怒らせながら大股で歩み寄ってきた。
『シンちゃんっ!』
彩は我を忘れてストッキングの爪先でタイル敷きの陸橋の上を走り出し、慎哉の腕の中へと緊張が一気に解けたあまり足を絡ませ崩れ落ちた。
『彩っ!大丈夫か??』
動揺した慎哉はそんな彼女の無事を確かめる為に、彩の顎を持ってその顔を診る為に上向かせた。
そして無事を確認するなり彩の前へその身を呈し、背後の彩にこう問うた。
『こいつ誰だ?知ってる奴か?』
彩は慎哉のスーツの背中にしがみついたまま無言で何故か
首を横に振った。
しかし男はまるで爽やかみたいに明るく言い放つ。
『おやぁそうかなあそんなことないでしょ?
吉田彩さんそれはないよ』
男は逃げも隠れもしないと言ったような陽気さを醸し出すことは巧かった。
『お前なんなんだよ何、馴れ馴れしく彩を抱き寄せたりしてんだよっ』
『彩さんこいつ誰?新しい彼氏か何か?』
自分の見知らぬ男が彩をフルネームで呼んだことに気が動転した慎哉は、思わず背中にへばりつく彩を振り返り、
つい詰問する口調となった。
『なんだ?彩、お前この男と知り合いなのか!?』
『知り合いも何も昔からの顔馴染みだよね?彩ちゃん』
と、あくまでも明るく人懐っこいみたいな口調の男を更に振り返った慎哉の顔は、激しい動揺に騒ぐ水面のように一瞬淀んだ。
『なんなんだよ?本当なのか??』
慎哉は恐怖に果てしなく近い狼狽に囚われ、思わず背中に止まる大きな蛾のような彼女を払いのけて問い質(ただ)したい思いとなった。
『違うわ!
この人シンちゃんと知り合うずっと前、私につきまとってた人なの、引っ越してもう遇わなくなってホッとしてたのに、
偶然また遭ってしまっただけよっ!』
恐怖に強張(こわば)った彩の声は平素から、か細く高いものの、今や不安定に甲高く春になると街角のそこここで聴かれる猫同士の縄張りを争うあの声にも似て異様にうわずり昂(たかぶ)っていた。
同時に男への憎悪と呪詛を孕(はら)み、その声は酷く振戦している。
また慎哉のスーツを背後から捻じ切ってしまうのではないかと危ぶむほど強く掴んで離さない彩は異常なほど怯え切っていた。
彩の云うことは紛れもなく事実だ、と、自分の傷を検めるように察知した慎哉は、
『じゃ何か?お前ストーカーなのか?彩は俺と今はもう婚約してるんだよ、
どうせ一方的に彩に思いを寄せてたんだろうが、彩にすりゃつきまとわれたりして迷惑千万だ、人の婚約者にこれ以上関わらないでくれ!』
『お前さん知らないだけで俺達けっこう深い仲だったこともあったんだよね?彩さん』
馴れ馴れしく笑いかける男のいとも簡単に陽気な笑顔を憎んで彩は泣き叫んだ。
『嘘よ!
そんなの嘘っ!!』
『いやぁ深い仲だったよ?』
『おい何言ってんだやめろ』
慎哉は解りやすい怒りと焦点の定まらぬ不安定な嫉妬とが自分の中へと両極端に突き上げてくるのを無理矢理、抑え込むとそう言った。
『俺と彩さんは車の中でカーセックスってやつ?』
『嘘っ!嘘よ!
そんなの嘘っ!!』
そう叫びながらも極限状態の彩は憤怒の余り、慎哉の背中から獣のように飛び出すと、いきなり真っ正面から男に挑みかかろうとした。
慎哉はあまりにも無謀な婚約者の腕を強く掴むと、そのまま振り回すような勢いで自分の背後へ戻すなり、
次の瞬間、男を殴り倒そうと遮二無二、渦中へと飛び込んでいった。
『いい加減なこと言うな彩はそんな女じゃないっ!』
しかし男は慎哉の明らかに優しく不慣れな拳が空(くう)を切る音すら立てないものであることを、軽く身を躱(かわ)す動作の中で、見抜いたのか、
次の瞬間思いもかけぬ素人離れした鋭いパンチを慎哉に向かって繰り出した。
みぞおちに男の拳が深く入り込むと次の瞬間、慎哉は顎を打ち抜かれるように突き上げられ、彼はそのまま陸橋のタイル敷きの上へ仰向けとなって倒れた。
倒れる瞬間、何故か慎哉は『あれっ?』と言うと同時に後頭部を打つガツッという鈍い音と共に気を失った。
『シンちゃんっ!?』
血相を変えた彩は倒れ込んだ慎哉の躰に駆け寄り、
『あぁなんてこと!
可愛そうに、大丈夫??』
と泣き震えながら慎哉の顔に震える両手のひらを当てた。
が次の瞬間、鬼の形相と化した彩は男を鋭く振り返った。
『ちょっとあんたっ!
なんてことするのよ!?』
彼女は慎哉のそばに落ちていた自分のハイヒールを男に向かって投石するかの如く思いっきり投げつけた。
ヒールが男の眦(まなじり)に激突し男は驚愕して彩を見た。
『何すんだよ』
男の目尻が華奢造りな女のヒール靴に当たって傷ついたのか、彼の頬骨から目尻にかけて裂傷を負い、流血していた。
『目に入ったらどうすんだ!?こんな尖った靴がさ、
危ないじゃないか!』
『近づかないでって言ってるでしょうっこれ以上近づかないで!もうほっといてよ』
そう言いながら彩は自分が持っていたもう一足のヒールを更に男へ投げた。が、男はそれをひょいとよけるものの、その顔は烈火の如く怒っている。
『お前なめてんじゃねえぞ!見ろ俺の顔をよ』
男は倒れたままの慎哉に取り縋る彩の腕を掴んで乱暴に立たせるとこう言った。
『怪我しちゃっただろうが、え!?』
『知らないわそんなの、
貴方が悪いんじゃない、
最初に暴力奮ってきたのはそっちよ!』
と彼女は言い放つと男の腕を振り払い、慎哉の傍に落ちた自分のバッグに駆け寄ると、その中を乱暴にまさぐり探し当てた携帯を彼に見せつけると、
『警察を呼ぶわ!
何もかも全部話すから!
シンちゃんにもし何かあったら私あなたを告訴してやる、
もう今度という今度こそ絶対許さないから!』
『ふざけやがってこの、
あま!』
男は彩の白いトレンチコートの襟首を両手で掴んだまま、欄干へとストッキングの脚のままの彩を大きな人形のように荒々しく引き摺っていった。
そのまま男は彩の肩甲骨と背骨が折れるかと思うほど激しく欄干へと叩きつけた。
彼は白いトレンチコートの襟首を掴んだまま怯えきった彩を何度も前後に揺さぶりながらこう叫んだ。
『てめえちょっと優しくしてやってたらつけ上がりやがってここから突き落とされたいのか?』
『やめて』彩はそう言った積もりが声にならない
『痛い目にあわされなきゃ反省出来ないってか?
俺に逆らって悪うございましたって気持ちちょっとでも俺に見せてみろよ?』
『シンちゃん』
彩は襟首を掴まれたままその背中ごと欄干から押し出され、彩の背骨は固い欄干に強力に押さえつけられて軋むように痛んだ。
『助けて』
彩は恐怖に掠れて出ない声を振り絞ったが事態は変わらない、それどころか悪化していく。
『あの坊やはのびてるよ、
倒れた時に床で頭を打ったんだろうおおよそ脳震盪でも起こしたに違いない、
頼りにならねえ男だな、
一発もかすりもしねえでノックダウンってさあんなのやめとけよ、なぁ彩さんあんた俺とより戻すって言うんなら俺、あんたのこと助けてあげたっていいん…』
しかし次の瞬間、膝で股間を蹴り上げられ男はその先の言葉を失った。
男は悶絶してくの字に身体を折り曲げたままその場に崩れるように膝を突いたものの、密接した互いの身体越しに蹴り上げた膝の力はふたつの肉体で吸収分散され、彩が思うような効を奏しなかった。
打撃を与えることは出来てもややあって当たった程度の中途半端な膝蹴りは男にダメージ以上の不穏な感情を煽り立ててしまった。
その為瞬時に立ち直った図太い男はまだ残る痛恨より上回る怒りに逃げる彩へとたちまち追いつくと、またもや欄干へ彼女の襟首を持って音を立てて激しく叩きつけた。
『舐めた真似しやがってこの女、もう許さないからな!』
彩に一切の隙を与えぬよう追いたてた欄干に自分の全身の圧力を使って、張り付けにすると男は彩の首もとを振り絞るように更に追い立てた。
とうとう上半身が欄干から、はみ出してしまった彩は欄干越しにその脇目を振って、
自分の真下に弧を描いて迫るその遠く硬い路面を見た。
『落としてやる!
落としてお前の首を折ってやる』
『やめて!』
と叫んだ積もりがその声は喉元を締め付けられて出てこない。
『無駄だよあの野郎はさっきからずっとおねんねしてらぁ』
『だれか…助けて』

かすれた声でようやくそう言いつのった彩はだんだん意識が薄れていくような気がした。
この時彩の脳裡に浮かんだ言葉は一つだった。
“やめてお願い
死にたくない!”
その瞬感、欄干からはみ出した彩の背を誰かがそっと、
だが同時に強く押し戻す力を彼女は感じた。
強く背後から彩はバネのようにしなやかに押し戻された。その衝撃により男は彩の身体に跳ね返されるように飛び退いて二、三歩よろめくように自分の背後を歩いた。
彼は惑乱した様子を見せたものの次の瞬間、彩に向かって猛突進してきた。
怯える彩の両肩を背後から目には見えない力がしっかりと捉えたまま男の目の前で滑るように脇へと瞬時に移動した。

男は欄干の前でつんのめったものの辛うじて立ち止まり、更に彩へ立ち向かおうと睨みつけた瞬間、彼の両足首はまるで目には見えない力で掴まれたかのように真上へ垂直に持ち上がった。
路面に両手を突いたまま、男は一瞬逆立ちをするような格好となり、やがてその背中が弓なりとなって欄干の上をさながらやじろべえのように静止した。背骨が音をたてて軋むほど激しい弧を描く一瞬の苦悶ののち彼は悲鳴と共に遥か下方のアスファルトの路面へと宙で何故か一回転した挙げ句、急滑降していった。
彩の切り裂くような悲鳴に覚醒した慎哉は必死で立ち上がろうと苦闘したものの、襲ってくる猛烈な吐き気と眩暈、そして頭痛に立つことも出来ないまま傍に落ちた彩の携帯で警察と救急車を呼んだ。
泣きながら慎哉に駆け寄る彩に彼は抱き上げられ、彩の膝の上で痛む頭を“あの男は何処へ?”とそっと巡らせた。
その朦朧とした頭で彼はふと欄干の隅に止まる一羽の鴉を見た。

鴉は、春の陽光のもと青光りする羽根を揃えてまるで置き物のように身じろぎせず留まっていたが、慎哉の視線を押し返すように見るその眼は片方だけが蒼くサファイアのように光ったように慎哉には見えた。
割れるように頭が痛む彼は朦朧とする中思った。
“なんだあれは…幻か?”
やがて鴉は黙って大きな翼を拡げたかと思うと一度も羽ばたくことなくまるでブーメランのように気流に乗って流れるように飛んでいってしまった。
やがてパトカーのサイレンが脈打つ頭痛のように近づいてくるその反響の中で、慎哉は何故かその鴉が泣いていた、と思った。



to be continued…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
