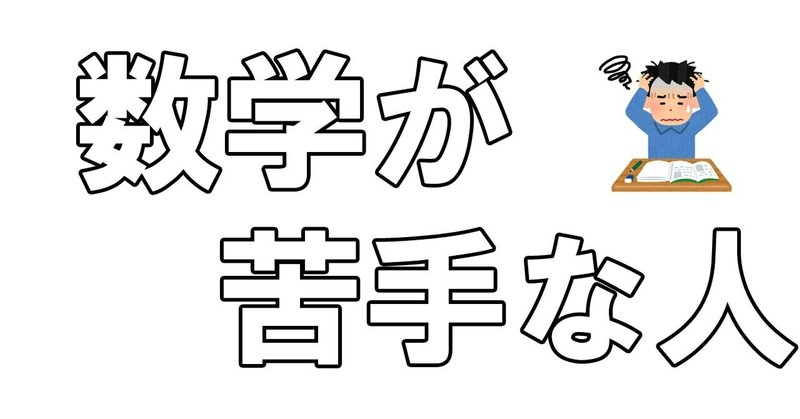
数学が苦手な人
私は中学生の頃、数学が苦手で、
基本の計算ならまだしも思考力を問われる応用問題になると、
さっぱり解き方がひらめかず、自分のセンスのなさを嘆いていました。
中学2年生のあるとき、
中1からの内容を振り返る数学のテストが実施され、
人生で初の0点
をとることになりました。
もちろん白紙ではなく、
問の1番から順に一生懸命考えて記入したのですが、
自分の名前以外1問も正解していませんでした。
テストを返却されたとき、脂汗が止まらず、
親にどう伝えればいいかと言い訳ばかりが頭の中をめぐっていました。
妙案が浮かぶわけもなく、
怒られるのを覚悟しながら答案用紙を渡しましたが、
いつもなら
「何、勉強してたんや!」
「あれだけ勉強しろっていったやろ!」
など、ガミガミ注意していた母が、
このときに限って無言で答案用紙を受け取るだけで、
何の指摘もしませんでした。
ホッとしたのと同時に、
失望させてしまったことに対する罪悪感が徐々に膨らみ、
(このままではダメだ…)
と本当の意味で自覚、反省しました。
改心した結果、
なんとか中学3年生になるころには
人並の学力が身についたように記憶しています。
母は、私が自立することを見込んだのか、
あきれてものが言えなかったのかわかりませんが、
今ではそっと見守ってくれていたことに感謝しています。
そんな数学が苦手な私は、
ひょんなことから中学校で数学を教えることになりました。
数学が苦手であるという気持ちを理解している私は、授業の際、
数学が苦手なオーラというか空気感を敏感に察知することができるようで、その周辺の生徒のフォローを重点的に行うことができました。
ただし、私の苦い経験は、
数学が苦手な生徒たちの共感にかなり有効に作用しましたが、
数学の苦手意識を払拭するという根本の解決には
あまり役立ちませんでした。
そこで次の段階として、
好き嫌いは別として数学を苦手とする生徒が
少しでも得意と感じられるようになる
または、
基本的な問題は解けると実感できるようになる
という状態になるにはどうすればいいかと考え、
研修を受けたり、
先輩の先生方からアドバイスをもらったり、
本を読んだりして、いろいろ試行錯誤を重ねました。
しかし、そう簡単にいかないことは自分の経験上よくわかっていたので、
大半のアイデアはボツとなりました。
そんなあるとき、私が授業改善のために良く参考にしていた
【脳科学者】池谷裕二氏の著書の1つ
パテカトルの万脳薬 脳はすこぶる快楽主義(朝日新聞出版)の中に
オハイオ州立大学のぺトリル博士らは昨年、600人以上の双子を調べ、
数学の得手・不得手の約40%が遺伝で説明できることを突き止めました。
という一文を見つけました。
そのとき私は目の前が開けたような気がしました。
それまで暗中模索状態で、
うまくいかなくてもあきらめず、
生徒の苦手を改善しようと努力してきましたが、
私のこの努力は何の影響も与えないのではないかと不安を感じていました。
しかし、
数学の不得手の約40%が遺伝で決まるということが事実であれば、
逆に約60%は
教師や保護者、友人、または、その他の環境(外的要因)で
どうにかなる可能性があるということになるので、
かなり勇気づけられました。
この約60%の可能性の中で100%の成果を出し、
少しでも数学の苦手を克服できるように研修していくことが
教員としての使命だと実感した瞬間でした。
(2022年3月末に退職するまでですが…)
ちなみに、この遺伝の話を他の先生方に話すと
「なぜそんな身も蓋もない話をするのか?」
「それでは我々がやっていることは一体なんなのか?」
と想像以上に批判され、驚いたことを覚えています。
遺伝の約40%を100%であるかのようにとらえているようで、
人によっては40%を多いと感じてしまう場合があるのだと発見でき、
違う意味で感心しました。
数学の苦手克服に向けて、
(遺伝の約40%も原因がある)と考えて、あきらめるのか?
(遺伝の約40%しか原因がない)と考えて、希望をもって前進するのか?
その考え方の差が生まれる理由を考えることも興味深いと感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
