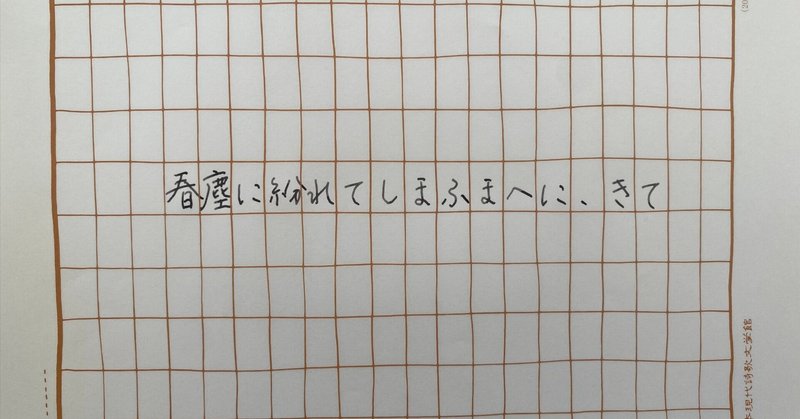
春の塵
昼ごはんにぶどうパンを食べてから、散歩へ出た。
わたしは運動のための運動がきらいだ。
運動のためではない運動は好きだ。
だから散歩は、散歩のための散歩ではなく、何かしらのちいさな用事を作って外へ出る。
今日の用事は、コーヒー豆を買うことだった。
とても天気のよい午後だった。
わたしの前を男の人が歩いている。革ジャンに深緑色のキャップをかぶっている。耳たぶには直径2センチほどの真ん中に穴の空いたピアスが嵌め込まれていた。
ぼっかり空いたピアスの穴から向こうが見えそうだった。
わたしはピアスの穴に気持ちを集中させた。
道路のアスファルトが見えた。穴の中のアスファルトが動いているように見える。
男の人はこのアスファルトを見ることができないのか、と思う。
もう一度穴に気持ちを集中させる。今度は少しだけ空が見えたようだった。
八百屋の前を通る。
この八百屋のおじいさんはいつもレジの横に座って、茶色くなった文庫本を読んでいる。八百屋を入って左側の棚の上には野菜ではなく、文庫本がずらりと並べられている。どれも古くて変色している。
本を読んでいない時には、並べられたみかんの中から傷んだものをよけたり、お客のおばあさんと話したりしている。
わたしが「70%のおばあさん」と呼んでいる人がいて、その人はわたしがその八百屋の前を通るとだいたい70%くらいの確率でいて、真ん中に穴の空いた背もたれのない椅子に腰掛けている。商品なのか商品でなくて持ってきたものかわからないくだものを食べていることもある。70%のおばあさんはたまにレジを打っていることもある。いつもくすんだ緑いろのエプロンをつけて、年中毛糸の帽子をかぶっている。
今日は70%のおばあさんではないあたらしいおばあさんがいて、真ん中に穴の空いた椅子に腰掛けておにぎりを食べていた。確かに別のおばあさんなのだけれど、70%のおばあさんと似ている。エプロンはつけておらず、ラクダ色のレッグウォーマーを履いて、むらさきの毛糸帽をかぶっている。おにぎりのご飯は茶色くて、白いご飯に何かを混ぜ込んだものか、炊き込みご飯か気になる。おにぎりを注視したのだけれど、判別ができなかった。
駅前のスーパーでコーヒー豆を買った。
レジで財布からお金を取り出していたら、レジの係りの人に爪のマニキュアの色合いを褒められた。
このスーパーのレジは、1秒でも早くレジを打たねばならないという切迫感がなくていい。切迫感に満ちたスーパーに行くと、早くお金を的確に出さなくてはとこちらまで切迫した気持ちになってしまう。
褒められたことに対して、「ありがとうございます」と言うと、さらに2回褒められた。
世の中にはとくによく思っていないのになぜか褒める風習があるけれど、これはほんとうによく思って褒めたのだとわかった。ほんとうの言葉は好きだ。
スーパーを出て、今度はお花を買おうと思いたつ。
20日前にいただいた花束の最後の一本のカーネーションが、今日ついに終わりの感じになっていた。
橘さんというお花屋さんへ向かう。
信号待ちをするわたしの前に、犬を連れた人がいた。
犬はダックスフントで、艶のない毛がおもたそうに下がっている。毛の先がアスファルトにつきそうで、でも犬はそんなことを気にしてはいないようだった。犬はどんなことも気にしてはいないように見えた。でもとくに楽しそうではなかった。
花屋さんで花を選ぶとき、いつも絶対にこれ、という花がかならずある。
いつも迷わずわたしはそれを選ぶ。今日の花はバラに見えないバラ一本と、グレイのスイートピー二本だった。
三本の花を、うすい白い紙にくるくると花を包んでいただく。
それを両手でそっと抱えて表へ出る。
花を抱えていると、何も持っていない時よりもかるい感じがする。わたしの体までかるい感じがする。
花といっしょに歩くと、いまわたしはいきものと歩いているという気持ちがきざす。
帰り道、八百屋にはもうおばあさんはいなかった。
おじいさんは茶色い新潮文庫を読んでいる。
花を抱えてわたしはゆっくり坂を上って家に着いた。
家に帰ると、陽の差しこむリビングの床にぺたりと座って17歳の子が新聞を読んでいた。
新聞を大きく開いて、じっくり読んでいる。この人はいつもそうなのだ。
陽はまよいのあるようにぼんやりと部屋に入る。あちらこちらがあかるい。ちらちらと部屋の中にほこりが光って見える。ほこりはふやふやと定まらず漂う。ほこりの中に子は背中を丸め、じっと新聞を読む。
買った花の茎を適切に切って、がらすの水差しに入れる。
食卓の上に置いたら、そこにもやはり春の塵は光っている。定まらず動く。

とてもしずかだ。
とてもあかるい。
すこしだけ、さみしいときの感じに、胸の下がきゅう、とした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
