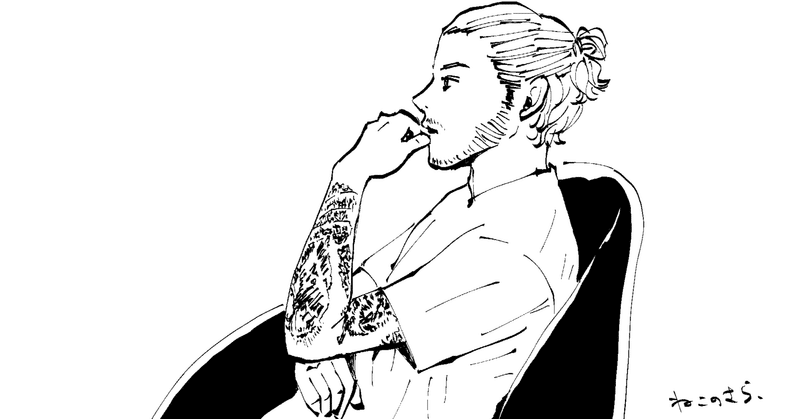
「見当違いの期待」感
重松清さんの短編集「季節風 春」を読んでいました。
この小説はすごく「懐かしい感じ」を感じることができます。
私自身が本でしばしば舞台となっている瀬戸内の出身であり、その土地の表現や言葉に溢れていることが、その理由かもしれません。
その上で、「春」という季節は出会いと別れ、目標に向かって飛び立つ季節で、自分の体験も重ねながらとても共感しやすい小説です。
しかしその一方で、どの短編にもどことなく不協和音が発信されていることを私は感じました。
おそらく、地方独特の閉塞感、屈折した思い、時の流れや時代の変化に逆らえない気持ちが個々の登場人物から滲みでていているからだと思っていました。
そして、それが何かがよくわからないままに読み進めていましたが、この全般に流れる不協和音の発信源は短編「お兄ちゃんの帰郷」の一節に現れていました。
人間は誰だって向き不向きがある。性格や根性もひとそれぞれで、見当違いの期待は、する方もされるほうも苦しめてしまうだけだ。
期待のずれ
「お兄ちゃんの帰郷」では、親の期待に答え、東京の大学に行ったお兄ちゃんをもつ妹の目線で語られています。
物語の中でそのお兄ちゃんは東京に馴染むことができずすぐに田舎に戻ってきてしまい、地元の大学に入り直したいことを親に伝えます。
そのときのお兄ちゃんの言い分が、親や祖父母の面倒みるから入り直したい、だったのです。
その様子に母親は「ひとのことを言い訳にするのはやめなさい!」と言います。互いに面食らった様子、失望感が爆発していました。
親子・身内だからこそ「わかっているだろう」とか「こういうものだ」といった、想定感や期待感のずれがそうさせることを感じます。
期待感の目線を合わせる
そういえば、会社でマネージャーをしていた頃、海外出張していたメンバーをサポートする意味でかけた言葉に、「そんなことはわかっている!」とキレられたことがありました。
ヒビが入りかけた傷はなんとか修正して今はむしろとてもよい関係になっていますが、お互いに想定する期待感は常にしっかり目線合わせしなければ破綻してしまうものです。そんなこと思い出しました。
仲間を応援するとき、あるいは親として子供に接する時、見当違いの期待をしていないかどうか、常に問う心がけが必要ですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
