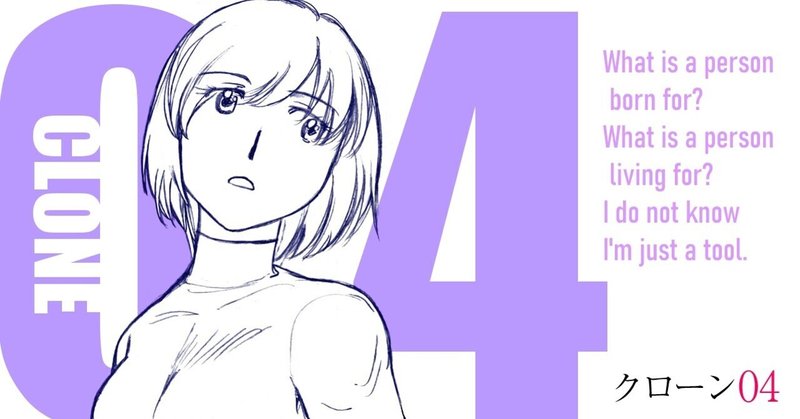
クローン04 第9話
九 それ以上の存在
「これが街頭センサーの記録だ」
壁の大型スクリーンに映し出されているのは、東京都市部の俯瞰図。そこに一本の赤い線が描かれている。線は、あるところではまっすぐ大胆に進み、あるところでは細かく向きを変えて、くねくねと動き回っている。
新宿近郊を動き回っていたその線は、急にその場をはなれる動きを見せる。公園内に侵入したのち、さらに離脱して海へと向かう。そして海沿いの地域で、ぶつぶつととぎれ、やがて消えていた。
「全域をカバーしているわけじゃないんだな」
クロサキは眉をひそめた。技術部門のスズキの元を訪れ、問題のクローンの行動解析結果を見ていた。
「これでもかなり微弱で不正確な信号まで復元したんだぜ?」
スズキは細面にかけた眼鏡のふちを指で押さえた。
眼鏡は入力デバイスになっている。眼球の動きを計測し、視線ポインターとして機能する。ふちを押さえる指の動きで画面が切りかわる。今ふれたことにより、線が切れ切れになっている地域が拡大された。
「単にテレメトリを取るだけなら、一般の通信帯域にデータを乗せればいいが、それではハッキングのリスクがある。そこで、警察のセンサーポストに便乗してるんだが、東側の湾岸域は水害も多いんで稼働率が低い。修理も進んでいないから百パーセントはカバーできていない。警察も予算ないしな」
「それでは、システムとして機能しないのでは? そちらの地域にも顧客はいるだろう?」
「通常時はそういう時には一般帯域に切りかえてるんだ。そちらは全範囲をカバーできている。ただ、問題の個体は隠密作戦行動中だった。セキュリティのモードが最高レベルに設定されていて、切りかえ機能は切っていた。作戦予定区域はセンサー網もきちんと機能していたからな。そこからの離脱は想定外だった」
スズキの操作でまた画面が変わった。今度は内陸部が映される。ポストの一つがクローズアップされ、そのわきに何本もの線が走るグラフが現れる。
「さて、見ての通り、戦闘行動時にはリアルタイムのテレメトリが入っていて、付近のセンサーポストが信号を拾ってる。犯行時刻と思われる所で、バイタルに大きなゆらぎ。ただし肉体に損傷があったとはデータからは読めない。簡単に言えば、ドキッとした、というところか。心理的動揺が見て取れる」
「戦闘型でか?」
「そう。刷り込みが低下したというお前の推測は、可能性がかなり高いな」
戦闘型クローンは、円滑な命令伝達と行動時の機能性向上のため、感情的な変化がほとんどないように設計されている。九十六号などはそれを極限まで推し進めたため、まるで人形のようだ。そのクローンが動揺したとなると……。
「やはり欠陥品か……。出荷チェックで引っかかっていないとは。このうわさが広まると、セールスにひびくな」
「それは必至だね」
「その後の足取りはわかるか」
スズキはまた画面を切りかえた。表示されている地図の縮尺が変わり、引いた図になる。
「このあと公園に寄り、湾岸方面に行って、そこからは不明だ。二日後にもう一度アクセスがあり、深夜、組織の本拠地にもどってる。お前さんが組織を壊滅させたあとだな。そこで取れているバイタルのデータはやはり不安定。そこからまた沿岸域の、データの取れない区域に引き返している」
「その後は?」
「アクセスは一度も。ただ、この次の日、SYRシリーズらしき遺体が都の保管所に運び込まれている。身元不明、身体データは一致。焼却処分寸前で気づいて、手を回してそのまま保管させてある」
「ふむ……高額なSYRシリーズが持ち主不明というのはあやしいな……。使いつぶした中古の不法投棄という線は?」
「データを見る分にはそう古くはなさそうだ。メンテナンスをうけおっていない中古までは把握できていないが、こちらから直でおろした比較的新しいもので行方不明になっているのは、問題の個体だけだ」
「なるほど。この遺体がそうなら、引き取って一件落着だな」
「お前さんの仕事はな。こっちはそこからだよ。刷り込み失敗の原因を特定しなけりゃ」
スズキはそう言って肩をすくめた。
クロサキは礼を言って部屋を出ると、九十六号と共に遺体保管所へと向かった。
荒川沿いにある都の遺体保管所は、外見からはそうとはわからず、倉庫付きのどこかの会社のビルのように見える。それは周囲の住民の反対運動に配慮したものだ。実際にそういう作りの建物が多くある地区で、目立たぬようひっそりと辺りにまぎれている。
身元不明の遺体を一時保管し、引き取り手がなければそのまま火葬する施設。確かに出入りするトラックにそんなものが積まれ、運び込まれていると知れば、付近の住民にいい顔はされない。この建物の中に、ずらりと死体が並んでいるのだ。
運ぶのは冷蔵トラックだし、遺体の保管も冷蔵倉庫だ。だから遺体の腐敗が進むようなことはないのだが、建物内にどれだけの数があるのかと考えれば、それだけで辺りに屍臭がただよっているような気分をさそう。
クロサキも、一瞬脳内にただよったそのにおいを、小さく首を振って打ち消し、建物へと入る。受付に会社名だけ告げると、話は通っていて、すぐに案内の者がやってきた。
この建物に充満する死の気配に染まったのか、死体のような青い顔色をした、やせぎすの男性職員が、薄暗い通路を案内する。
一時保管の間に身元を照合するのがこの施設の本来の目的だが、不法流入民の数が多く、国のデータベース管理もずさんなため、たいがいは身元不明のまま焼却処分される。問題の遺体も、連絡が三十分遅れれば焼却されていたそうだ。
「こちらです」
冷ややかな空気に包まれた、やはり薄暗い冷蔵保管所。一見ふつうの食品倉庫のようだ。だが立ち並ぶ天井まで届く幅広の大きな棚に、一体一体袋につめられ並んでいるのは、すべて人間の死体である。
案内してきた男は手持ちのタブレットを操作して場所を確認すると、フォークリフトに乗り込んだ。せまい通路にも慣れた様子で、少し高い位置のパレットを引き出し、手前に運び出してくる。
そしてリフトを降り、タブレットと遺体袋の記載を見比べる。クロサキに向かってうなずくと、袋を開いた。
その中の遺体をのぞきこんだクロサキが、顔をしかめる。
「これは調べるまでもないな」
保管されていたのはまったく別人の死体だった。SYRシリーズのクローンでさえない、見知らぬ顔。
「……ありがとう、焼却処分に回してくれ」
「わかりました」
部屋を出て廊下を歩きながら、クロサキは頭にかけたバイザーを操作する。
呼び出したデータをながめる。確かに、身長、体重、性別は一致する。しかし、他のデータには手が加えられている。
焼却処分寸前に押さえられたのは幸運だったな、とクロサキは思った。
この都の施設は処理数に対して予算不足におちいっており、まともな葬儀をあきらめてしまっている。産業廃棄物の焼却処理との唯一のちがいは、焼却炉の投入口のある部屋に、一応常に、読経の録音が流れていることぐらいだ。次から次へとどんどん燃やして、遺灰の分別もしない。
そうなると事後の鑑定はほぼ不可能だ。担当する職員も、ほとんど流れ作業で焼却しているから、大まかなデータが合っていれば些細な問題に気づくことはないだろうし、あとから思い出すのも難しいだろう。登録されたデータをいじられたら、確認のしようがない。
本人の手による偽装とも考えられなくもないが……。
バイザーをなおも操作。バックグラウンドデータを見る。
実物を見ればデータに手を加えたのは一目瞭然だが、データそのものにはその痕跡は見えなかった。クロサキの表情はくもる。
これだけのあざやかな手並みとなると、協力者の存在も疑われるな……。
「ここの前の痕跡は沿岸部の市場か……」
施設をあとにし、二人は次の目的地に向かう。都心をぬけて、開けた幹線道路へ。道幅のわりに車通りは少ない。しばらく進んで車を降りる。
そこはいつもの喧騒に包まれていた。人の波がとぎれることなく、客引きの声が威勢よくひびいている。ビル街をつらぬく広い幹線道路をせばめるように、ずらりと何重にも露店が並んでいる。沿岸域では一番の規模をほこる露天市だ。
クロサキはバイザーを操作し、テレメトリのデータを実際の風景に重ね合わせた。
この辺りのセンサーポストは五十パーセント程度の稼働率しかないとデータにある。その通り、生きているポストが視界の中には見えない。ただ、しばらく歩いても稼働しているポストに一つも出会わないとなると、話は少しちがってくる。区域の稼働率五十パーセントとはいえ、市場の辺りがくっきりぬけているとなると、地域の顔役と警察の癒着が考えられる。
自分たちが警察のセンサーポストを利用しているのも、警察の予算不足につけこんだ癒着なので、人のことをどうこう言える立場ではないのだが、それでも苦々しく思うのは止められない。ここのデータが不足しているせいで、追跡が難しくなっているのだ。
テレメトリ信号のかすかな痕跡を表示させる。どうやら自分たちと同じ側から来て、あちらにぬけたようだ。
「お前の嗅覚が警察犬なみなら、ここから追跡できるが、さて、そこまでたよれるかな……。とにかく行ってみるか」
九十六号に声をかけ、歩き出す。九十六号は相変わらずの無表情だが、感覚は研ぎすまされているはずだ。
この通りは、この先が押し寄せてきた海に水没していて通りぬけができない。街の真ん中にあるのに交通量がほとんどなく、露天商には格好の場所だ。
だがそれでも通る車が皆無というわけではなく、そういう時には車はクラクションを鳴らし、人波をかきわけて進むことになる。
今も一台の古ぼけたトラックが、騒々しく音をかき鳴らしながら、人々を押しのけていた。クロサキと九十六号もわきにのいて道を空ける。
その通り過ぎようとしたトラックの荷台から、奇妙なうなり声がした。
「う、うー!」
ほろのないむき出しの荷台から、一人の女が飛び降りる。SYRシリーズのクローンだ。
しかし神経障害があるようで、引きずるような歩き方だ。発声もおかしい。しゃべれないのかうなるばかり。
クロサキの目の前でべたっと倒れた。
それでもはいずってすがりつく。顔を見上げて声を上げる。
「う、ううー!」
破れかけた衣服によごれた顔。首輪をしていて、そこには縄がつながっている。
その瞳にはあふれんばかりの涙がたまっていた。
クローンを追って、男が車から降りてきた。筋肉質の身体。むき出しの太い腕には隙間なく刺青がほられている。ひとめでかたぎではないとわかる顔つき。
だが、見かけとは裏腹な意外な低姿勢で、クロサキに頭を下げた。
「すんません、ご迷惑かけて」
そしてクローンの襟元をつかむ。そこからのあつかいは見た目通りだった。首がしまるのもお構いなしに、乱暴に引っ張る。
「ほら、来い!」
「う、うー!」
しかしクローンは、クロサキの上着の裾を放さない。
その様子を見た刺青の男がクロサキの顔をのぞきこんだ。
「失礼、もしかして、こいつの元の持ち主さんで……? いや、こいつは中古で引き取った品なんですがね。もしや……」
クロサキはしがみつくクローンをじっと見つめた。
視線が合う。
よごれてはいるが、よく知る顔立ち。
常にクロサキのそばにいる顔。
だからこそ。
「……いや、知らんな」
クローンの表情がこおりついた。
「そうですか。おら、人ちがいだとよ!」
首輪についた縄で引きずられていく。
こちらを振り返る。
たまっていた大粒の涙が、ぽろぽろとこぼれ落ちた。
トラックの荷台には他に幾人かの女がいた。どれもクローンだ。SYRシリーズ以外の『暁里(シャオリ)生物科技』の商品、さらには他社製品もいる。
みな最低限の衣服。うすよごれた姿。
多分どのクローンも使いつぶされた中古品だ。男の風貌からして、安い売春宿の仕入れだろう。
トラックは走り出した。クローンは身を乗り出すようにこちらを向いて、悲しそうなうめき声を上げていた。
もしかしたら過去に使った個体かも知れない。
そうではないかも知れない。
神経がやられ、刷り込みも外れているようだ。認知障害があるかも知れず、クロサキをだれかと見まちがえた可能性も大きい。
あれではもう、他の使い道はない。
自分はあてがわれた個体を使い、使えなくなったら他の部署が処分する。
その後、道具として使い物にならなくなった彼女たちがどうなったかは知らない。
ただ、道具とその使用主の関係。それだけだ。
だが、彼女は涙を流していた。
彼女にとっては、それ以上の意味があったのだろうか。
彼女にとっては、それ以上の存在だったのだろうか。
今の出来事に考え込むクロサキの前方から、SYRシリーズのクローンが二体やってきた。スクーターに二人乗り。大きな荷物も抱えていて、明らかに重量オーバーだ。よろめきながら進んでくる。
ベストセラーだが、こういう時には困り物だな、とクロサキは思った。
どれが求めるホシなのか……。
「マリア、マリア、だいじょうぶ? 歩こうか?」
「平気だよー。それにバイクじゃないと間に合わなくて、おばちゃんに怒られるよー」
「マリアが、たのまれてないものまでこんなに買い込むから……」
「リンスゥだって、パフェ二つも食べてるから遅れるんだよ。最近リンスゥってば、あまいもの食べてる時、ほんとに幸せそうな顔するからさあ。せかそうかと思ったけど、できなかったんだよ?」
「そ、それは……」
スクーターが通り過ぎる。
九十六号がクロサキの袖をそっと引く。
「! あれか!」
クロサキは振り向いて、よたよたと去り行く後ろ姿を見つめた。
「これは僥倖……」
それはリンスゥにとっては奇禍。
小さく芽生えた彼女の幸せに、嵐がおそいかかろうとしていた。
ここから先は

銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE
2016年から活動しているセルパブSF雑誌『銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE』のnote版です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
