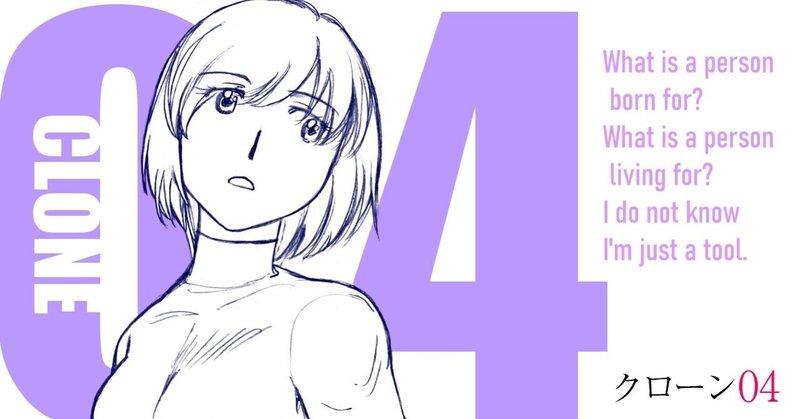
クローン04 第10話
十 私たちと同じ
「え、おばちゃん出かけたの?」
買い出しに行き、寄り道してすっかり遅れて、おばちゃんに怒られるとあわてたマリアとリンスゥ。しかし店にもどってみると、当のヤーフェイはそこにいなかった。
それを伝えてくれたのは夕方早くにやってくる常連の三人、ワン、グォ、チェン。いつもの席ではなく、奥のテーブルに座っている。小太りのワンが外を指さした。
「何か急用とかで、今出てったよ。二人を待ってたみたいだったけど」
「あれー、これはかなり怒られるね」
リンスゥと目を見合わせたマリアは、ぺろっと舌を出した。お茶目な表情。怒られると言いながら、マリアにはまだそういう顔をする余裕があるようだ。しかしリンスゥにはそんな心のゆとりはない。
怒ったおばちゃん、怖いからなあ……。
特に今日の大遅刻には、リンスゥの食い意地もからんでいるので、ひとごとではない。
ひとたび戦闘となれば、恐怖を感じず動揺もしないリンスゥだが、日常生活では最近すっかり抑制が外れてしまい、小動物的な小心者っぷりを見せている。特にヤーフェイにはずっと怒られっぱなしなので、びくびくしどおしだ。壊滅した組織に行った時に見たカタログにのっていた、あのクローンの元になった子から引き継いだ地の性格なのかなと思ったが、同じ遺伝情報を持つはずのマリアを見ていると、どうやらリンスゥ固有の問題のようだ。
「それより何か出してくれよ。すきっ腹に酒だけじゃこたえるよ」
リンスゥの憂いに割り込むように、チェンがその狐目を下げ、情けない声でひもじさをアピールしてくる。見るとテーブルにはビールしか出ていない。手際のいいヤーフェイがつまみ一つ出していないとは、本当に急用だったようだ。ますますやばいとリンスゥは眉をひそめる。
「はーい。ちょっと待ってねー」
それに対して、あまり怒られることを気にしていない様子のマリアが答える。すぐに厨房に入って、辺りを見回す。
「あれー、仕込みも途中だ。常備のお茶うけぐらいしか出せないよー。おまんじゅうでいい?」
「えー、ビールに合わないし、それに腹減ってんだよ。何かないの」
「しょーがない、じゃ私が」
そう言うと、エプロンを着け、髪を後ろにまとめる。包丁を手に取り、まな板の前に立つ。
「おおー」
新鮮なその姿に、テーブルから拍手がわいた。
「いや、待てっ!」
それを止めたのはチェンだった。いつも陽気で、こういう時には一番にはやしたてそうなものなのに、深刻な顔をしている。周りの二人はめったに見ないその表情に不思議そう。
「ん? どした? マリアの手料理だぞ。めったに食えんぞ?」
「そう、めったに食えん。だからみんなは味わったことがないんだろうが、わしゃ一度ある。この世の物とは思えん味だった! しかも火の通りがあまかったらしく、腹まで下した! マリア、あのあとちゃんと、料理覚えたんか?」
「……えへっ」
チェンの問いに、マリアはかわいらしく肩をすくめた。
「だー、だめだめ、絶対だめ!」
チェンはあわてて厨房へ飛び込み、マリアを引きずり出した。
「ええー、じゃあどうするんだよー」「大丈夫! お料理うまくなってるかもしれないよ?」「いやー、老いた体に、その賭けはきついかなあ……」「わしらで作るか?」「客が勝手に店の厨房使うのはどうなんだ?」
みんながもめてる、そんな騒動の最中。
店の戸口に新たな客の姿。
一人は背が高く、目元をおおうバイザー。
もう一人はクローンの女性。よく知った同じ顔。
クロサキと九十六号が店を探り当てた。
さわぎを横目に無言で店に入ると、入り口近くの席に着く。
「あ、いらっしゃいませー」
リンスゥが気がついた。二人のもとに歩み寄る。
「すいません、まだお時間前なので、メニューのこちら側のお料理は出せないのですが……」
「ああ、休憩するだけだから大丈夫。お茶を二つ」
「はい」
茶壷に茶葉を入れ、お湯を注いで、運ぶリンスゥ。さすがにこれぐらいの事には慣れてきた。茶壷、茶杯と、トレイから下ろして、二人の前にそっと置く。
九十六号の前に身を乗り出す形になった。
くん。
それとわからぬよう、においをかいだ九十六号。小さくうなずいた。
クロサキもうなずき返す。
かすかな動きだが、リンスゥも気がついた。何か他に注文かなとたずねてみる。
「他に何かございますか?」
「いや、これでいい。ありがとう」
あれ、じゃあ、なんだったんだろうと思ったところで。
「そうだリンスゥ」
「はい?」
チェンがリンスゥに呼びかけた。
「リンスゥはどうだ? 何か作れない?」
さわいでいたみんなの期待の視線が、リンスゥに集まる。
「なるほど、リンスゥはマリアみたいな大雑把な性格じゃないし、何かできそうな雰囲気だよなあ」
「なあ」
「何、大雑把って! ひどーい!」
「え、えーと……」
「なに、簡単な物でいいんだよ。ちょちょっと作ってみてよ」
新しい客の、ちょっと気になった様子のことは、この新展開でリンスゥの意識からふっとんでしまった。チェンに文字通り背中を押されて、リンスゥは厨房へ入った。
困り顔で辺りを見回していたが、やがてためらいがちに冷蔵庫を開けた。
肉を一切れ取り出す。フライパンに油を引き、火にかけて温める。トレイに置いた肉に、高い所から塩を振る。
「おっ、ちょっと! 予想以上に本格的な手つき!」
「おう!」
「耳濡れ目染まり、というやつか? 期待できるんじゃないか?」
肉を投入。じゃあっと威勢よく油のはじける音がして、フライパンの加熱ぶりを物語る。そのフライパンに蓋をする。
そこで止まる。
「む、どうした?」
「いや、あれは……聞いたことがある! 一流の料理人は、肉の焼ける音で火の通り具合を判断すると!」
「なんと!」
「ありえるわ! だってリンスゥの方が私よりずっと耳がいいもの! おばちゃんが焼く時の音を覚えているのかも!」
「おおおっ!」
みんなの期待がぐんぐん高まっていく。
その期待を裏付けるかのように、じっと動かないリンスゥ。
じゅうじゅうと肉の焼ける音がする。
まだ動かないリンスゥ。
こうばしいにおいがただよってきた。
さらに動かないリンスゥ。
だんだん煙が……。
リンスゥ脂汗。
今や蓋のわきから、もくもくとわき上がっていた。
「わー! 何していいかわかんなくて固まってるだけだー!」
「こげてる、こげてる!」
「なんだい、この煙!」
大さわぎになったところにヤーフェイがもどってきた。
「もー、何やってるんだい!」
火を止めてフライパンを水にさらし、ごしごしとこする。肉は見事に炭になっていた。
「お使いたのもうと思ってたのに帰ってこないし! 店を空ければこの有様だし!」
リンスゥとマリアに降り注ぐお小言は、ゆうにいつもの二倍あった。
クス。
それをだまってながめていたクロサキが、小さく笑みをこぼす。
そして椅子を引いて席を立った。九十六号も後に続く。
「お代、ここに置くよ」
「あ、ありがとうございましたー」
二人は出て行った。
その後姿を見送って、マリアが言った。
「今のお客さん、なんか見た顔と思ったら、シロさんに似てたね」
「え、そう? 髪形ちがうし、バイザーしてたから、よくわかんないな」
「うん、でも、輪郭とか口元とかそっくりだったよ」
「ふーん」
それよりもリンスゥには、去り際にちらりとこちらを振り返った、連れていたクローンの方が気になった。
私たちと同じシリーズのクローン。
私たちと同じ。
その日の夜。
ごうごうと嵐がふきすさぶ。大きな雨粒が強い風に乗り、窓をたたいていた。
日が沈んだ頃から天気がくずれていった。低気圧が近づいているという予報だったので、お客さんたちもそれをわかっていて、客足のにぶい一日だった。常連のおじいさん三人組は、逆にそれを考えて、仕込みが終わっていないいつもよりも早い時間から来ていて、あの後早めに切り上げていたのだった。
低気圧と言っても、温暖化の影響で強力に発達したもの。台風の定義が熱帯域で発生した熱帯低気圧であることとなっているのでそう呼ばないだけで、威力は超大型台風同等までに発達していた。これから明日にかけ、天気は荒れたままだろう。
だから、そんな夜に出歩く者など、いるはずがなかった。
リンスゥとマリアは、寄りそって一つのベッドで寝ていた。
それは二人の習慣になっていた。もともとはマリアの言い出したことだが、今ではリンスゥも当然のように受け入れていた。温かいマリアの身体を感じながら、その歌声にまどろみの底へと導かれると、とてもよく眠れるのだ。
どちらの部屋で寝るかは気分次第。今日はリンスゥの部屋だった。
「ん……」
リンスゥにすがっていたマリアが吐息をもらす。何か楽しい夢を見ているのだろうか、その寝顔はほほえんでいる。
そえられた手が、リンスゥの頬にふれた。その手にさそわれるように、リンスゥももそもそと寝返りを打ち、マリアに向き直った。
マリアの手が頬をなでるように動く。
「ん……」
今度はリンスゥが吐息をもらし、気持ちよさそうにほほえんだ。
鏡合わせのような二人。
その時。
ばんっと大きな音がして、窓ガラスがふきとんだ。
窓が割れると同時に、センサーが発する侵入警報が意識につながり、リンスゥはたたき起こされた。緊急事態に、体内にうめこまれたバイオチップが一斉に起動。強制的に意識覚醒レベルを最大に引き上げる。
だがそれがなくても、リンスゥの意識は緊急警報を出していただろう。耳にしたのは破砕用炸薬の爆発音。自分も使っていたやつ。それが示すことは一つ。敵襲だ。
目を開いたその瞬間、視界に飛び込んできたのは、自分におおいかぶさろうとしている九十六号の姿。
リンスゥはすがりついていたマリアを突き飛ばして、ベッドから落とし、身をひねった。
どさっ。「いた!」
マリアの落ちた音と抗議めいた声がひびく。しかし床に落ちたぐらいは、まったくましだった。
九十六号は確実に命をうばうつもりだった。二人の寝ていた場所に、両手に持ったナイフを二本、深々と突き立てている。
リンスゥは際どいところでその一撃をかわしていた。反応が一瞬でも遅れていたら、やられていた。
即座に枕元にしのばせていた護身用のナイフを手に取る。寝る時も武器をそばに置くのは特に深く考えてのことではなく、なんとなく身についた習慣だった。厳密には自分の殺したクローン、リンサンの物だが、手に慣れた型のサバイバルナイフ。それを鞘からぬいて横なぐりに一閃する。九十六号は飛び退いた。
相手に距離を取らせ、そこで体勢を立て直そうと、リンスゥがベッドの上で片膝立ちに構える。
その一瞬で九十六号が消えた。
おどろき、辺りを見わたそうとしたリンスゥに、接続されたセンサーが視界の外に飛んだ九十六号の位置を教える。
上からだ。
九十六号は驚異的な跳躍でリンスゥの頭上を取っていた。身をひるがえし天井を蹴り、真下のリンスゥに飛びかからんとしているところ。
センサーにつながれたリンスゥは、この建物の中では三百六十度全周囲の視界を持っているのと同様だ。即座に身体が反応した。
前方へ飛んでベッドから床へ。前回り受身を取り、その勢いのまま素早く立ち上がる。振り向きざまに手に持ったナイフを突き出す。
リンスゥを追った九十六号は、目の前に突き出されたナイフを最小限の動きでかわすと、返しの突きをくり出す。
かわそうと身をひねったリンスゥだが、ナイフはパジャマに引っかかり、その生地をさいた。
そこへ九十六号の追撃。今度はそれをナイフではじく。キンッとするどい金属音とともに、辺りの闇を照らす火花が飛び散る。絶妙のタイミングでのはじき。相手の体勢をくずした手ごたえがあった。
しかし九十六号は一瞬の間もなく立て直し、追撃の手はゆるめず、一気呵成にたたみかけてくる。
リンスゥはセンサーにつながっていて、この建物内なら相手よりも有利なはずだ。暗がりはおたがい気にならない。強化された視覚は夜間戦闘にも対応している。だが補助視界を持つリンスゥはさらに多くの情報を受け取っており、どんな小さな動きの起こりも見逃さない。
これは格闘戦では生死を分けるほどの重要事で、相手の動きが読めていれば、それに合わせて後の先を取り勝負を決することもたやすい。
なのに、それができない。相手が異様に速い。動きは見えているのだが、身体の反応が追いつかない。
同じタイプのクローンのはずなのに、とリンスゥは驚愕した。見た目は明らかにSYRシリーズ。様々な派生型が開発されているので、タイプによってはリンスゥとマリアのように性能に大きく差が出るが、戦闘型同士ならそんなことはない。なのに防戦一方に追い込まれる。
何度か刃先が身体をかすめ、寝巻きは破れ、皮膚も浅く切れた。血がにじむ。
その時ぱっと灯りがついた。そして。
パアン!
部屋にひびく銃声。
「動かないで!」
マリアが声を張り上げる。いきなりの展開についていけてなかったが、ようやく事態を把握して、部屋に置いてあった銃を取り出し、リンスゥに加勢したのだ。こちらはマリアの護身用。この辺りは物騒だ。そして、その懸念が今現実のものとして目の前にある。
そういう心構えができていたので、侵入者を確認するとすぐ行動に移ったマリア。灯りをつけ、一瞬二人がはなれたところをねらったまではよかったが、残念ながら射撃の腕は不確かだ。銃弾は九十六号の髪を一房散らして、窓ガラスを割っただけに終わった。
だが援護の効果はあったようだ。リンスゥを追い込んでいた九十六号の手が止まる。振り向く九十六号。
しかし、それはマリアの銃撃が九十六号に恐怖を呼び起こしたからではなかった。銃を持ったマリアの方が危険と判断したのか、一歩ふみ出す。排除の優先順位が変わり、攻撃対象がマリアに移っただけ。
危機的状況。けれど射撃の腕は今一つでも、マリアは怖気づく性格ではなかった。もう一度引き金を引く。
当たらない。
「えっ!」
おどろいたのはリンスゥだ。
センサーによる全周視界を維持しているリンスゥには、はっきり見えた。マリアはまた自分が当てそこねたと思ったようだが、今の射撃は目標をとらえていた。相手はマリアが引き金を引く動作に入るやいなや、少しだけ動いて射線から身体を外している。
精密で最小限の動き。タイミングもマリアが目標修正できないぎりぎりの瞬間。ふつうの人間には、いや戦闘型のクローンでさえ容易にはできない動きだ。完全にマリアより上手。三発目も外れた。
これはだめだ。マリアの腕では相手を阻止できない。
そして、マリアの腕では、リンスゥも動けなかった。射線のぶれが大きすぎて、同士討ちの危険があり、援護する位置を取れない。けれど。
「危ない! 逃げて、マリア!」
これ以上傍観できないと、リンスゥがさけぶと同時に誤射されるリスクを取って助けに入ろうとした時。
マリアが背負っていた部屋の扉がさっと開いた。
そこにはシロウが立っていた。手に持ったショットガンを撃つ。制圧用のスタンガン。銃弾代わりに極細のワイヤーがついた針を撃ち出す。一本でもさされば、高電圧の電流が走る。急所に当たらなくても、行動力を制限できる代物だ。
かわそうとした九十六号だったが、拳銃とちがい射角が広い。よけきれずに右腕上腕部に一本ささる。
高圧電流が流れ、しびれる右腕。ナイフを取り落とした。
九十六号の判断は早かった。高い戦闘能力を持つ戦闘型クローンに、銃を持つ者が二人。それに対して自分は右腕が使えなくなり、左手のナイフ一本。
形勢不利を見てとると、一瞬のためらいもなく身をひるがえし、破れた窓から外へ。リンスゥが追い、窓の外を確認した時には、すでに姿は見えなくなっていた。
遅れてそのわきから外をのぞいたシロウがつぶやく。
「速いな。二発目を撃ちそびれた」
「シロさん……ありがとうー!」
マリアがしがみつく。
危ない所だった。もう一歩近寄られたら、相手の攻撃圏内だった。マリアには防ぎようがなかっただろう。
「よしよし」
シロウの表情にも、先ほどの言葉とは裏腹に安堵の色が見える。一度対峙したリンスゥの感触からすると、シロウ自身は素人ではないと思われる。だが、マリアはちがう。最初の援護には助けられたが、あのままだったらどうなっていたか。とにかくマリアが刃にかかる前に相手が撤退してくれてよかった。
シロウはマリアの背をぽんぽんとたたき、リンスゥに振り向いた。
「リンスゥも大丈夫かい? 血が出てるけど」
「ええ……そんなに深い傷は……」
九十六号との攻防で押し込まれ、何度か刃先が身体をかすめていた。パジャマはあちこちさけ、そこに赤く血がにじんでいる。
「あ、ホントだ! すぐ手当てしないと!」
マリアは薬箱を持ってきて、リンスゥのパジャマをまくり上げた。
血をぬぐい、消毒する。傷は確かにどれも深くない。止血パッドをあてがい、はりつける。
「ああ、もう、せっかくきれいな玉の肌なのに……痛くない? だいじょうぶ?」
「うん」
傷がたいしたことなく、リンスゥ自身も落ち着いているので、今度はマリアが安堵する番だった。手当てが終わり、ちょっとはなれたところから見落としがないかながめる。
その時、ふと何かを思いついたようだ。
シロウの方を振り返る。ちょっと見つめた後、マリアがおもむろに口を開く。
「そういえばシロさん、どうやってこの部屋に入ったの? 鍵かけてたのに」
「ん? 合鍵」
シロウはさらっと答えた。マリアがおどろいたように言う。
「えっ! いつの間にそんな物作ったの? え、じゃあ人の部屋に入り放題? シロさん、もしかして私たちに夜這いをするつもりだったんじゃ……!」
「へっへっへ、まあねえ。SYRシリーズ二体となんて、なかなかできないからねえ」
切りさかれたパジャマをまくり上げて、白い肌があらわになったリンスゥの身体を、ねめまわすように見る。
パッドをあちこちはってはいるが、それでもわかるしなやかな腰つき。なめらかなお腹。下着を着けていないので、胸元までまくった裾から少しだけ顔を出すやわらかな曲線……。
その視線にリンスゥはびっくり。あわてて裾を下ろす。けれどパジャマはすでにぼろぼろなので、あちこちから素肌が見える。自分の頬の血流が増したのがわかる。これはあれだ。チェンにお尻をなでられて覚えた感覚。
恥ずかしい。
ボロボロになったパジャマの前を両腕でぎゅっとかき合わせて、ますます赤くなった顔でシロウを見上げる。チェンの言ったとおり、表情は大きく変わっていないのだが、おさえた表情の中に恥じらいがじわじわともれ出し、その瞳がうるみ始め……。
「ぷぷっ」
シロウがふきだす。
「冗談だよー! そんなにあわてなくても」
マリアもけらけら笑っている。
「リンスゥって素直だから、からかいがいがあるよねー」
二人の間で以心伝心の小芝居だったらしい。マリアが振り向いて少し間があった時だと、リンスゥは気づいた。あそこで多分マリアが目配せかなんかしてたのだ。
「ひどい」
赤い顔のまま、リンスゥは口をへの字にした。どうも二人とも、リンスゥの事を隙あらばからかって楽しもうとする傾向がある。
「ごめん、ごめん。無事でほっとしたから、つい、ね」
マリアは抱きついてすりすりとほおずり。マリアはすぐこうやってごまかそうとする。いつもそうなんだからとリンスゥは思いながらも、やわらかいほっぺたが気持ちよくて、表情がゆるんでしまう。
リンスゥのご機嫌を取ったところで、これじゃ今日こっちにはもう寝れないねと言って、マリアは自分の寝室を用意しに行った。窓が割れて、そこから風雨がふきこんでいる。それにベッドにも、深々とナイフがささったあとがある。修繕しないと寝室としては使えない。
それにしても、マリアの肝のすわり方はたいしたものだ。こんな際どい襲撃があったのに、リンスゥをからかったり、すぐに切り替えて寝室の用意に行ったり。リンスゥは元々そういう世界の住人だったので慣れているが、マリアはそうではないのに。リンスゥは感心して、マリアが出ていった扉をながめる。
「ごめんな、リンスゥ。巻き込んで」
「はい?」
そこにいきなり、シロウの謝罪。
振り返ると、やれやれという顔で苦笑いしている。
「どこだかは心当たりがありすぎてわからないんだけどさ、多分俺をねらった襲撃なんだ。仕事柄、いろいろうらみを買ってるからねえ。以前も何度かあったんだよ。」
なるほど、そういうことか。リンスゥはその言葉で、いろいろと腑に落ちた。
マリアの肝がすわっているのも、シロウが用意周到に制圧用の武器を持ってきたのも、これが想定されていた事態だからだ。
さらに言えば、リンスゥがここの人たちにすんなり受け入れてもらえたのにも、きっと影響している。本当に用心棒が必要だったという事情があったのだ。
「それにしても、俺の部屋じゃなくてリンスゥたちの部屋をおそうなんて、とんだリサーチ不足……」
シロウは笑いながら、散らかった部屋の片付けを手伝おうと身をかがめた。九十六号の落としていったナイフに目を止める。
ぽつりと口からつぶやきがもれる。
「これは……」
「どうしたの、シロさん」
リンスゥの問いにシロウは無言。
ナイフを手に取り、表、裏といくどかながめ、ようやく顔を上げた。
「どうやらただの相手じゃないな。リンスゥが苦戦したのも当然だ。これ見てごらん」
ナイフを手わたす。刀身がゆるやかにくねった、大型のサバイバルナイフ。それをリンスゥはしげしげと見つめた。
「私のと似てる……けど、少しちがう?」
形はそっくりだ。だが、なじんだ手は、かすかなちがいを敏感に感じ取った。
「ああ、刃が特殊な材質でできている。高価な物で、その辺では手に入らない。リンスゥ」
「はい?」
「相手とやってみてどうだった? 自分と比べて?」
「ええと……私はこの部屋のセンサーと接続されているから有利なはずと思ったんだけど……相手の反応がものすごく速かった。攻める隙がほとんどなくて。あの時マリアが援護射撃してくれなかったら、多分あと何手かで深手を負ってたと……」
「そうか……」
答えを聞いたシロウは、少し考え込み、小さく舌打ちした。
「クロックアップか……」
「え? それは?」
シロウの口から聞きなれない単語が飛び出し、リンスゥは聞き返した。
「相手はリンスゥより性能が上だ。でもリンスゥはシリーズ最新型なんだ。まだモデルチェンジはされてない。それに俺がきちんとメンテナンスしているし、自慢みたいだから言っちゃうとあれだけど、でも市販されている個体相手に引けを取るはずはないんだよ。なのに後れを取った。特別な武器といい、可能性は一つ」
シロウは真剣な顔でリンスゥを真っ直ぐ見つめた。
「リンスゥの製造元、『暁里(シャオリ)生物科技』が追ってきたんだよ」
ここから先は

銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE
2016年から活動しているセルパブSF雑誌『銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE』のnote版です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
