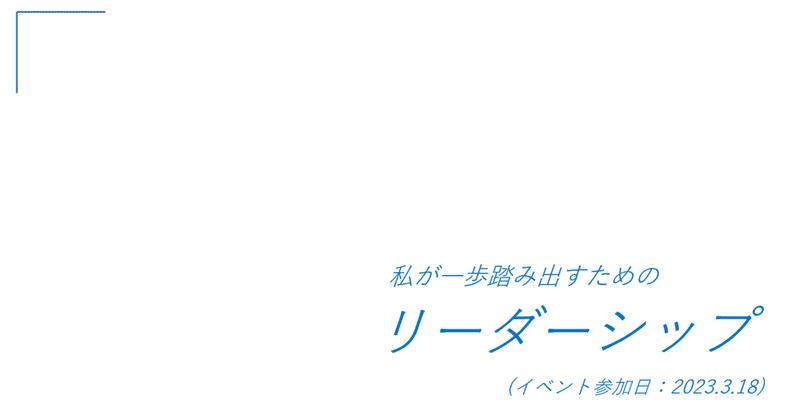
『私が一歩踏み出すためのリーダーシップ』を通じて (本編)
社内有志団体が企画する「リーダーシップ」に関するイベント、題して『私が一歩踏み出すためのリーダーシップ』に参加した。アウトプットを推奨している位置づけを踏まえ、"社内情報"的な観点でグレーになりそうな部分については重々配慮しつつ、得た学びや気付きを (お裾分け的な観点も一部踏まえながら) 自分のための備忘録として書き残す。
~ メモ:筆者の参加動機 ( ..)φ ~
2022年10月より "自身も含め7名のチーム" をマネジメントする立場になった。本note記載時点で、すでに半年は経過しているものの《自身のマネジメントあり方》についてはまだまだ葛藤が多い状況である。そんな中、このイベントが目に留まり『日々のチームマネジメントをより良くすることに繋がる新しい気付きを得られたら』と考えたことが動機である。
0.振り返りの構成について
振り返りを書いていたら、思いの他に文字数が嵩んでしまったので、"読み返した時の自分自身の頭の整理" のために2つのnoteに分けて記載する。
ーーー
🏳🌈本編:登壇者の聴講セッションを通じての学び ←本noteはこちら
🏁サブ:他参加者とのワークや雑談を通じての学び ←下記リンク
ーーー
1.聴講セッションを通じての学び
本イベントの聴講セッションは1日を通して2回行われ、各部門における社内トップの方(計3名)の言葉に触れる機会となった。ここでは、3名の社内トップの話から学んだ《より良いリーダーシップに向けて大切なこと》を3点に整理して記載する。
ーーー
Ⅰ.リーダーの考える "当たり前の姿" を示す
Ⅱ.メッセージングは "文書化・抽象化" する
Ⅲ.”ルールは変えても良い” ことを明言する
ーーー
以下整理は筆者主観に基づく。「何が印象に残ったか?」は人それぞれ📣
Ⅰ.リーダーの考える "当たり前の姿" を示す
『各職場におけるリーダーシップ』を切り口に話が進む場面の中で『職場に10名の社員がいたとしたら、10名全員が自主責任感を持って仕事に臨んでいることが本来 "当たり前の姿” だよね』という語りがあった。自分にはその言葉が『そうか、それが本来は"当たり前の姿"か』とガツンときた。
この観点、筆者自身としても課題感はあり、日頃から自身の上司と本点も絡むテーマで関する会話も度々あるのだが、これまで自身にとっては『職場メンバー全員が自主責任感を持つ』というのは、”あるべき姿” としては考えつつも "当たり前の姿" という踏み込みまでは正直出来ていなかった。
今回のイベントを通じ、『 "あるべき姿" なのではなく "当たり前の姿" だ』と認識したことで、本件に関する職場改善に向けて自分自身ギアの上がるのを感じる次第であった。時間にしてほんの数10秒の間に、ほんのちょっと認識が変わっただけであるのに、本当に不思議だと思う。
そして、そんな自分自身の変化を振り返りながら、『リーダーからは "目指す姿"や"あるべき姿" を示すだけでなく、それに加えて リーダーが考える "当たり前の姿" 示すということが、聞き手側のマインドを変える上で非常に大切である 』ことを体感の中で気付けたことが1つ目の学びである。
"目指す姿"や"あるべき姿"については、若干言い訳の様なものが介入できる余地があるが、"当たり前の姿"にはその余地が一切ない分、マインドを変える力が強いのではないかと感じる次第。受け手によっては重たいかもだが。

Ⅱ.メッセージングは "文書化・抽象化" する
『リーダーシップにおけるコミュニケーション』を切り口に話が進む場面の中で、「リーダシップを発揮する必要がある対象人数が50名や100名を超えると、とてもじゃないが1人1人のTodoを細かく指示することは出来ない。」、『だからこそ、自分が伝えたいことを文書化する必要があると共に、抽象化する必要がある。』という話があった。
この観点、筆者自身としては "文書化" の観点については強く共感しながら、"抽象化" という観点が印象に残った。話の中でも「10名くらいまでなら、細かいTodoを会話&把握することは可能だが、更に人数が増えるとやり方を変える必要が出て来る 」という旨のコメントがあったが、
実際、筆者としても取りまとめているチームメンバー数が自分を含めて7名であることもあり、メッセージングについては "文書化" のみの観点に留まっていたし、それでも何とかなっていた。また、筆者自身の性格も相まって、"文書化" の内容は "抽象化" からはまだ一歩遠い内容である様に思う。
だからこそ、"抽象化" の観点が非常に印象に残ると共に、今後チームメンバーに対するメッセージングを行う上では『同じ想いや指針を、より抽象的な・シンプルなメッセージングでメンバーに伝えるには?』という観点を持ちながら、言葉を紡ぐ意識をしてみようと考える次第であった。
「この伝え方だと、こう伝わってしまうのか」や「このメッセージングをこの頻度で実施するとこうなるのか」など、小さな検証・体感を重ねて『メンバーへのメッセージの伝え方』をブラッシュアップしていきたいと思う。

Ⅲ.”ルールは変えても良い” ことを明言する
『変革のためのリーダーシップ』を切り口に話が進む場面の中で、「1人1人が真面目な会社だと、これまでのルールを守ろうとする強く意識が働いてしまう」、『その意識に対し、"ルールは変えても良い" ということを伝えていくことが必要である』という話があった。
本noteの上段にも記載したが「職場全員が自主責任感を持てているか?」と問われると、率直に言って「いや、、」と答えざる負えない状況ではあるが、その一方で「職場全員が真面目に働いているか?」と問われたなら、その問いについては「真面目に働いている」と即答できる。
そんな自問を行いながら、トップが当たり前の姿とする 自主責任感に満ちた姿 から一歩遠い職場状況を生んでいるのは、『暗黙の中でインストールされ、強固にロックされた「既存のルール/手順を守らねばならぬ」という前提条件によるもの』なのではないかと思う次第であった。
いずれにしても、「職場全員、真面目に働いている」ということを思い返せたと共に『真面目さを向ける方向を変えれば良い』という視点を改めて持てたことで、自職場に対する期待感を大きく高めることが出来たと共に、職場に対して発揮するリーダーシップの方向がより明確になるのを感じた。
今まさに4月からのチーム方針や体制を策定中だったが、その中に含めるメッセージングとして『ルールは変えても良い』という旨は盛り込みたいと思うし、"一回り大きい職場全体への波及" を加味して内容を練っていきたい。

2.手元に置いておきたい3つの言葉
ここでは、自身が聴講セッションに触れた言葉で『手元に置いて定期的に振り返りたいと感じた言葉』を3つピックアップして記載する。
・Management By Walking Around (MBWA)
「マネージャーは現場を歩き回りましょう」の意である。席に座って報告を待っているのではなく、現場を歩きまわり、メンバーと対話をし、状況を確認する。メンバーとの関係を深め、スムーズな動きを実現する。
・ポジションパワー / パーソナルパワー
リーダーシップを成立させるパワーには大きく2つがあり、1つは地位や立場に基づくポジションパワーで. もう1つは人間力(感受性)に基づくパーソナルパワーである。双方のパワーを持つことでリーダーシップを発揮できる、
・Our Leadership Principles (OLP)
14項目で構成されるAmazonにおけるリーダーシップの原則。「チームを持つマネージャーだけでなく、社員全員がリーダーであるとする考え方」に基づく原則であり、Amazonの行動規範となっている。

3.聴講セッション全体を通して
今回のイベントで期待されたアウトプットの観点は『自分なりのリーダーシップを見つける』であった。その観点に沿ってこのイベントを振り返った時に、筆者自身としては職場に対して持っている課題感に対して臨む際に、
ーーー
・みんな真面目であるという事を前提に
・メッセージングの抽象化を意識しつつ
・まず "当たり前の姿" を発信・共有する
ーーー
という、自身がリーダーシップを発揮する上でこれまでは持っていなかった "新たな1つの軸/流れ"を見つけられたこと が『自分なりのリーダーシップを見つける』に相当する学びであった様に思う。今回のイベントを通じて得たリーダーシップの観点を踏まえ、実行(Execution)に励んでいきたい。
~ メモ:8文字の言葉 ~
聴講セッション中、「あなたは "リーダー" してますか?」という問いかけに対して発言する機会を得た。わずか1分ほどの間であったにも関わらず胃に穴が空きそうだったが、筆者自身が紡いだ言葉に対して返して頂いた『一理ありますね』という言葉は、今後の研鑽に向けた熱源となりそうである。
P.s.
ここまでお読み頂きありがとうございました!最後に個人的な内容になりますが、10名弱くらいのチームのマネジメント/リーダーシップに関して、一緒に試行錯誤できる方と繋がりたい 想いがあります。もし、置かれている状況や課題感などが似ている方がいれば、お声掛け頂けると嬉しいです ^^
(筆者自身のマネジメント歴はまだ半年で、めちゃ駆け出しです)
(参考)本noteに関連する情報
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
