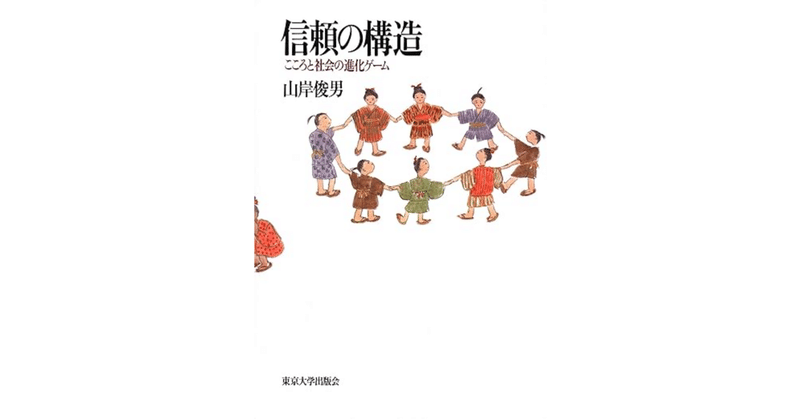
信頼の構造 - 感想・引用
著者プロフィール: 山岸俊男
一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻特任教授
今回の記事は、信頼と裏切りの起源とメカニズムを進化ゲーム論と実験データから解明した本です。
この記事では、本の要約をするのではなく、輪読会を行うにあたり、私が読んだ感想や本からの学び、一部引用を紹介するものです。輪読会用のメモなので、一般的な記事のようにきちんと整理されているわけではないのでご了承ください。
感想
コネ社会と転職の機会は緩くつながっている人からもたらされるという知識はこれまで頭にあったが、これを構造化、理論化してはいなかったので、面白く有益だった。
日本社会とアメリカ社会の信頼の面からの比較はあったが、なぜそうなっているのかという部分については説明がなかった。本が論文形式なので、推測は書かないだろうが、考察は聞いてみたい。
一般的信頼性が高い人はお人好しではなく、社会的知能が高い人というのは面白い発見だった。でも、考えてみればそうかと思う。
社会的な構造を実験と理論によって解き明かしていくのはとても面白い。何か社会課題や構造を考え続けられるのは大変だろうけど、意義があって幸せだろうなと思う。
読み終えてみて、開かれた社会と普遍的な原理に従った公正な社会を作るのがいかに大事なことなのかと思い知らされた。社会的不確実性が高くとも効率的に生きている社会というのは、それだけで非常に価値のある財産だと思う。
グローバル化していく中では、日本の集団主義的社会は抵抗になってしまうと思う。
また、グローバル化とかは関係なしに、日本の社会を変えていくというのは非常に骨が折れると思う。機会コストが増加することは見えていても、変えていく際の上の年代の抵抗がかなり大きそう。どういう風に変えていくのが良いだろうか。
ジェノバ商人とマグレブ商人の話を思い出した。
内容とは全く関係ないけど、6つの命題をわざわざ6回実験するのではなく、論理的に考えて、実はそれが2つの実験で証明されると帰結し、実際にそれで全て証明するのが素晴らしいと思った。今やっているプロジェクトとかも、情報の構造化だったり関連をちゃんと考えてみるのが大事だと考えさせられた。
19世紀末のアメリカで社会構造が変化したのはなぜか?
「商人と屏風は直ぐでは立たぬ」
機会に対応する一般的信頼の高い社会はオープンであり、豊かさにも繋がっていく話だと思った。
「信なくば立たず」
引用
19世紀末から20世紀初頭のアメリカ社会でやくざ型コミットメントが与える安心(もちろんザッカーはこれらの言葉を使ってはいないが)が失われつつあるときに,一般的信頼にもとづく開放的なビジネス関係を可能とするための様々な制度の整備が進み,現在のアメリカのビジネス関係の基礎が築かれたとするものである。
この記事で掲載した引用は、Glaspの機能を使ってエクスポートしています。Kindleのハイライトをエクスポートすることに興味がある方は、以下の記事をご覧ください。
また、この本のトップハイライトは以下のリンクよりご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
