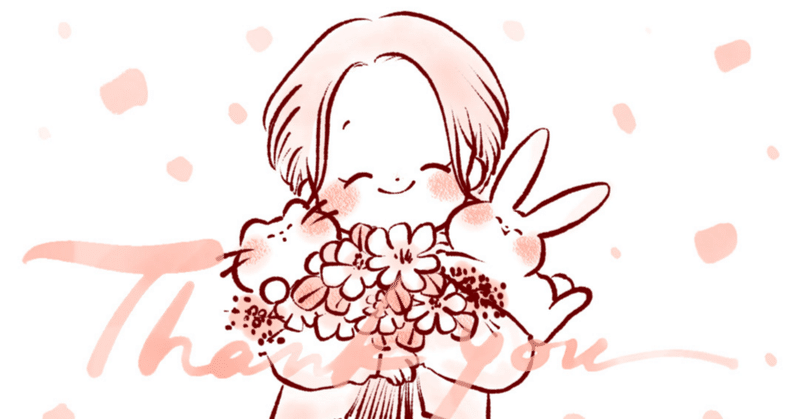
20231130_日露戦争後の日米関係について考えたこと_覇権で読み解けば世界史がわかる_紹介と感想54
はじめに
こんにちは、Keiです。
今まで私にとって"元気が出た"と思ったコンテンツや"役に立つかもな"と思ったコンテンツや考え方を紹介してきました。今回も良い人生にするために"役に立つかもな"と思った考え方を紹介していきます。
参考書
この度、参考にした本は
『「覇権」で読み解けば世界史がわかる』神野正史
です。
内容と感想
前回の記事では"満州争奪戦"までの部分を読んで感じた事を書きました。
今回の記事では"日露戦争後の日米関係"までの部分を読んで感じた事を書いていきます。
内容
当時の日露は圧倒的な国力差(人口と海軍力が3倍、陸軍力が15倍、歳入が8倍)がある状態で本来、日本には勝ち目のない戦いだったが、イギリスとアメリカの援護もあり、なんとか勝つことができた。
ロシアを満州から撤退させることに成功したが賠償金は取れず、歳入の7年分の戦費を費やした日本は収益を得る方法を模索する事になった。満州、朝鮮から利益を得るためには投資が必要となるが、元金の無かった日本は借金を返すために借金をするという状態になっていった。
アメリカの鉄道王エドワード・ハリマンは1億円の資金提供の代わりに南満州鉄道の共同経営を要求。日本は桂ハリマン覚書を交わしてしまう。小村寿太郎は、名ばかりの共同経営であることを指摘し、日露戦争での日本人の犠牲も考慮し拒否することを訴えた。結果として、日本が一方的に拒否する形となり、東アジアを支配したいアメリカにとって日本が障壁となっていった。
感想
改めて歴史を見ていくと、日露戦争突入時の状況は存亡の危機であったということを理解できると思います。教科書などでは事実が淡々と記載されていて、勝ったことが当たり前のように思えますが、決して当たり前の結果では無かったと学ぶことができると思います。当時の様々な人々が必死に考え、取り組んだ結果が表れているということは覚えておくべきだと思いました。
当たり前のように見えるものでも、様々な人々が必死に考え、作り上げてきた結果というものは多いと思います。歴史だけでなく、日々の生活でも当てはまるものは多いと思います。具体的に、必要な物が近くのお店で購入できる事、インフラが整っている事、選挙権がある事などは当たり前に感じやすいですが、元々は無かったことだと考えると恵まれているという事に気づくことができると思います。ここまで大きな単位でなくても、誰かが自分を支えてくれること、気にかけてくれることも当たり前の事ではないと思います。そのような相手がいることは人間関係に恵まれていることだと思います。当たり前のことなど無いと自覚し、些細なことに有難みを感じながら生きていけると良いと思いました。
余裕が無くなると多かれ少なかれ判断力が鈍ってしまうというのは、どんな人にも当てはまってしまうものだと思います。そして自分に余裕が無くなっている時ほど、多くの人から様々な甘い誘いを受けることになると思います。余裕がない時程、注意して日々を過ごす必要があると思いました。
日米の対立がこの頃から深まっているということを学ぶことができました。外交的な判断には様々な見方があり、どちらが良いかという判断は正直できないのですが、様々な人の結論や理由を調べることは自分の考えを深めるためにも有効なことだと思います。今後も、自分の思考力を伸ばすために活用していきたいと思いました。
最後に
普段、当たり前のように感じることも様々な人々の努力の賜物であることは多いと思います。自分に余裕が無くなると、このような事を考えることもできなくなってしまうと思います。余裕を保ち思考を巡らすことで些細なことにも有難みを感じながら生きていけると良いと思いました。
日々の些細なことに有難みを感じ、感謝の心を保ちながら人と接することが出来る人を共に目指していきましょう!
どなたかの参考になれば幸いです。
以下、私の記事一覧ページと自己紹介ページです。
ご興味ございましたら、ご覧いただけると嬉しいです。
Xの紹介です。
よろしければご覧ください。
"応援したい"と思って下さった方はサポート頂けると嬉しいです。
