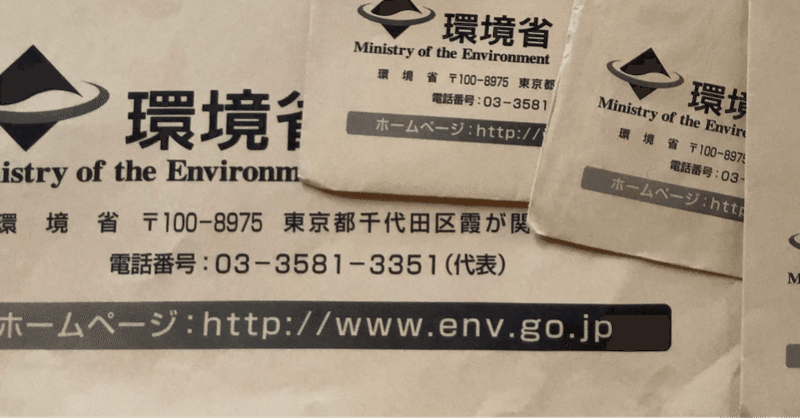
行政文書開示:除去土壌(除染土)再利用のための省令改正見送りの理由
放射性廃棄物の処理・処分のあり方に関する研究の一環として、除去土壌(除染土と一般に言われています。これは、除染してきれいになった土のほうではなく、取り除いた土のほう、つまり放射性物質で汚染されている土のほうです。)の再生利用についての省令改正を見送った理由について情報開示請求をしたところ、行政文書が開示されました。
以下に全文書をおいておきます。
開示文書はこちら (※ 開示文書は特に私に連絡することなく使用していただいて構いません。ただし、大島が行政文書開示請求で得たものであることを明記しておいてください。)
※まず、一般向けに、できるだけわかりやすく経緯と内容を書きます。
要するに・・
除染土(放射性物質で汚染されている土)を道路や堤防の基盤材として再利用することを可能にする省令案が2020年1月に提示され、3月に作られる予定でした。ところが、急に撤回となりました。一体、理由は何だったのでしょうか?
開示請求したところ、要するに、これまで議論したこともない農業での利用を持ち出して、農作物を植えることを検討することにしたので、省令改正しなかったんだ!、と環境省は説明しました。(要約終わり)
皆理解できないでしょう。

はっきり言って、事情を詳しく調べている私でも、ナンノコトヤラ理解に苦しみます・・。もともと除染土(除去土壌)の再利用に大義がないことを認めたようなものです。(環境省はそう言っていませんが)。
それでも、一度も、公開の場では検討したことのない農業での利用を言い出したのは重大です。
ちなみに、除染土(除染で剥がした”放射性物質で汚染された土壌”のことです)の再利用は、法律に書かれていません。法律で決められていないことを行政は勝手に行ってはいけません。(※ですが、廃棄物分野は法令改正が頻繁に後付けで行われています。こういう、たちの悪いやり方が、除染土でも起きないか、専門家の間では心配されているところです。国民が見ていないと、何をするかわからない、というのが正直なところです。いつも注意してみているぞ!ということを示すことが必要でしょう。
※環境省に対して、私は特に悪意はありません[どの省庁にもないですが。]。個人的に知り合いも沢山おり、環境省にはいい人が多いです。ですが、なぜかこうなっちゃうんですよね・・。
====
詳しい経緯
用語がさまざまあるので、ごくわかりやすく書きます。(※正確には『科学』(岩波書店)2020年3月号に寄稿した拙文をご覧ください。放射性物質対処特措法にも、どの省令にも、再利用・再生利用は定められていません。これは、廃棄物に関する法律(廃掃法)には再生利用が含まれているのは対照的です。つまり、国・環境省が進めようとしている再生利用・再利用は、法律に基づかない可能性が高く、極めて問題です。)
1)国・環境省は、除染土(「除染」で剥がした”放射性物質で汚染された土壌のこと)の再利用を進めようとしていました。これは法律に基づいているものとは言えず、なし崩し的に進められてきたと言ってよいものです。
2)除染土は、道路や堤防等、公共事業で一定の「管理」が行われる場所で、基盤材などに使うと説明していました。
(※各地で実証事業をすすめようとしましたが、反対に遭い、環境省はいったん持ち帰っています。今後どうなるか、放射性物質管理の観点から私は注目しています。私は、東海村での事業を除き、全ての現場を訪れ、話を聞いてています。)
3)省令改正案が提示されたのは2020年1月。パブリックコメントにかけられれました。
パブリックコメントのリンクはこちら。
4)パブリックコメントは、省令そのものではなく、「改正案の概要」に対するものでした。経緯をある程度知る私や、環境法を専門にしてこの問題に詳しい先生にとっても非常にわかりにくいものです。問題が多いと思われる内容でした。(※詳細は上記の拙文参照)
5)パブリックコメントの大半は反対意見であったとされています。(※入手していますので、詳しくは分析後どこかで報告します。一見して、反対意見がほとんどです。)
6)2020年3月、環境省が省令改正を見送りました。その理由は全く不明でした。省令改正案が撤回されるのは非常に稀なことです。
行政情報開示内容
1)パブリックコメントを募集しておきながら、撤回し、その理由について何ら説明がないのは、行政の説明責任の観点からしても大変問題です。とりわけ、放射性物質の管理にかかわるものは、市民の議論への参加が不可欠です。
※高レベル放射性廃棄物処分等でも、市民の参加がなければ最終的に必ず失敗します。
2)放射性物質の管理についてどのように考えたのか、政策決定のプロセスはいかなるものであったのか、を知るために、以下のように行政文書開示請求を5月に行いました。
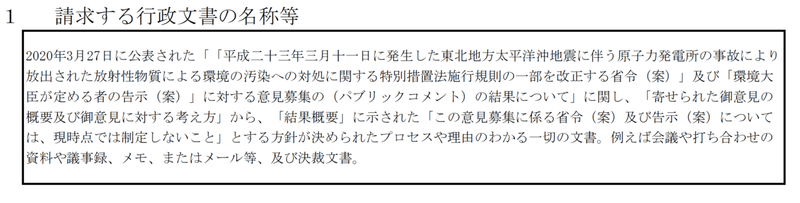
3)2020年8月に文書が開示されました。
文書1:2020年2月9日に飯舘村で行われた環境大臣意見交換会の議事録
文書2:2020年3月18日付けの環境大臣レク資料
文書3:阿部知子議員への小泉大臣の答弁メモ
4)いずれも、元々の省令改正の理由を検討した経緯がよくわからないものです。したがって、まずは、省令改正の大義がなかったということを認めたようなもの、と判断できます。(※開示してほしい文書とは言えないのですが、とりあえずまあいいでしょう。)
5)詳しくみると、まず、「再生利用の推進に当たって、国民の方々、地元の方々の御理解が重要」であり、「実証事業の結果等を含め、丁寧な説明に努めまいりたい」から、丁寧な説明をしなければならないと考えた、ということのようです。(ですが、誰に対する説明なのかは判然としない上に、国民に対する説明も全然していません。)
6)しかも、理由として挙げられているものは、「農業再生のための取組に全面的な支援をお願いしたい」「長泥の気候に合う野菜を作りたい。早くまたここに戻って農業をやりたい」ということです。再生土・除染土を利用して農業したいとは誰も言っていません。
7)「農業再生」と「再生土(除染土)の利用」は全く違う意味です。意図的かどうかわかりませんが、全く違うことを混同して行政を行うべきではないでしょう。
8)小泉大臣の国会説明資料では、「様々な作物に対しての実証事業等を引き続き行い、その結果も踏まえて制度化の検討を行うことが最も良い」としたといいます。ちなみに、これまで、公開の審議会の場では、道路や堤防の下に埋める(それ自体が問題ですが)のが再利用であると環境省は説明してきました。そのために大変な時間を費やしています。それでも問題百出です。作物を植えることについては、全く検討されていませんでした。見えるところで検討せずに、いきなりここで(わけのわからない)理由が書かれています。
以下は私の考えです
1)説明してこなかったことを持ち出して、省令改正案を撤回した理由にするというのは、行政としての説明責任を果たしているとは言えません。
2)放射性物質の管理には、国民の理解が不可欠です。だからこそ、検討の段階から透明性を確保し、議論を尽くす必要があります。
3)省令改正のためにパブリックコメントにかけながら、論点ずらしを行っていることは、放射性物質の適正管理を行うという観点からも問題と言わざるをえません。
4)そもそも、除去土壌の再利用は、法律にはどこにも明記されていません。法律に基づいた行政を行うべきです。今は無法そのものと評価されても仕方ないでしょう。
(2020/08/12)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
