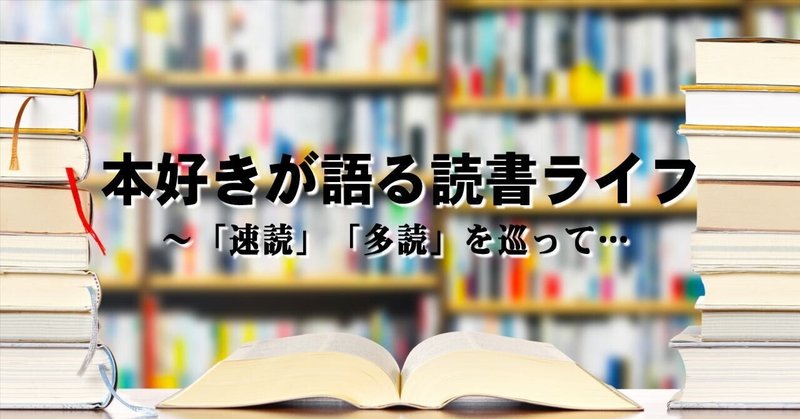
本好きが語る読書ライフ ~「速読」「多読」を巡って…
■本が好き!
僕は本を愛している。読書が大好きだ。本を読むことで新しい知識を得られることが楽しいし、何よりも本の中で紡がれる物語を味わう時間が好きだ。本を読んでいる時間、活字に没入している時間はとても幸せだ。だから僕は、「多幸感を味わう」ためにたくさんの本を読む。あらゆるジャンルの本を読む。純文学(小説、散文、詩歌等)、文学評論、自伝、ミステリー・ハードボイルド、ノンフィクション・ドキュメント、旅行記・探検記、思想家・科学者のエッセイ集、歴史・哲学・経済学・文化人類学、民俗学、社会学等の専門書、コンピュータ・情報処理の専門書、科学(主に自然科学)・化学の入門書・専門書、物理・天文学の入門書、音楽・美術書、写真集など、人文系、理化学系を問わずほぼすべてのジャンルの本を読む。一方でほぼ読まないジャンルの本も少しはある。ビジネス書は全く興味がない。「人生論」は嫌いだ。「生き方」を説かれるのも大嫌いだ。自己啓発書は有害図書だ。スピリチュアル系も有害図書だ。実用書もあまり読まない。芸能人や有名スポーツ選手が書いた本は絶対に読まない。信仰を説く本や宗教家の書いた本も読まない。占術も全く関心がない。ちなみにマンガはほぼ読まない。
世の中の人の平均的な読書量はどれくらいなのかよく知らないが、僕はけっこう読書量が多い。「多読家」「乱読家」である(多読法についてはこちら)。仕事の上で必要があって読む本を除き、あくまで趣味の範囲の読書に限定して、平均すると現在は月間30~50冊、年間で500冊以上の本を読む。他に雑誌・専門誌も相当数読む。これを20代の半ば頃から数十年間続けてきた。もっと遡って10代の頃もけっこう多読だったが、当時は読書以外にやりたいことが多く、また多読しようにも主に経済的理由で多数の本の入手が簡単ではなかったこともあって、そこまでの読書量ではなかった。やたらと「多読」をするようになったのは社会人になってからだ。本を好きなだけ自由に購入できる経済状況になったこと(多読生活は間違いなくお金がかかる)、社会人になって自分で時間の管理ができるようになったこと大きい。
僕は、バイクツーリングや登山、そして海外旅行が好きなので、けっしてインドア派ではない。さらに、自営業で休日は少なく、出張も多い多忙な日々を送ってきた。にもかかわらず、可能な限り時間を作って本を読んできた。読書ペースが落ちたのは、本の入手とストックが難しかった海外に在住していた時期だけだ。
僕は、場所を選ばずどこでも読書に没入できる。乗り物の中でも、騒々しいカフェでも、公園のベンチでも、キャンプ場のテントの中でも、そして歩きながらでも本が読める。電車に乗りながら読んでいて、あと少しで読了するという時など、電車を降りたホームで立ったまま読んで読了することがある。本に夢中になって電車を乗り越すことがけっこうあるし、終電を乗り越して終着駅からタクシーで帰宅したこともある。いったん本を読みだしたら、周囲の環境は気にならなくなる。
僕が本を多読するのは、実利的な理由からではない。よく「読書によって様々な知識・教養が身につく」「読書が人生を豊かにしてくれる」などという理由で読書を勧める人がいるが、それ自体間違いではないにしても、僕が本を読む理由とは違う。僕は基本的に「読書が楽しい」から本を読んでいる。確かに本から新しい知識を得られることは楽しいが、ただ「楽しい」というだけの話である。「教養を身に付けるために本を読む」なんてことは絶対に考えない。そして「本から様々な新しい知識を得ること」が「人生に必要なこと」だとは、特に思っていない。「読書によって自己を高める」なんてバカバカしいことは全く考えていない。「本から様々な新しい知識を得ること」は、人生に必要かどうかとは関係なく、それ自体が僕にとって単純に楽しいことなのだ。
例えば、「教養を身につけるために映画を見る」人は少ないだろう。多くの人は「楽しいから映画を見る」のだと思う。僕にとって「本を読む」ことは「映画を見る」ことと同じだ。映画を見てる時間が楽しいのと同じで、本を読んでいる時間が楽しいのだ。僕は絶対に「読書」を「学習」にしたくはない。
「楽しみ」として読書するのだから、読書の対象となる本は、ジャンルを問わず「面白い本」でなくてはならない。僕は「面白い本」を見つけ出す嗅覚に、かなり自信がある。そのために、まめに大型書店に足を運ぶ労を厭わない。他者の推薦や新聞や雑誌の書評欄などは、あまり気にしない。
当然ながら、たくさんの本を読んで多くの知識を有していることを誇ったり自慢したりする気持ちは全くない。また、他人に読書の効能を説く気もない。むろん、自分が面白いと思った本を他人に勧めることもしない。「面白い本」というのは、人によって違うからだ。他人に「読書」を勧めるなど、大きなお世話だ。自分さえ読書を楽しめればそれでいい。
基本的に僕は、「本を読むのが嫌いな人は読まなければいい」と思っている。これは皮肉でも何でもない。本を読んだからといって、誰もが賢くなるわけではない。いくら本を読んでも、バカはバカだ。読書量が多い人間が偉いわけではない。別に本を読まなくても、人は普通に生きていける。本を読めない世界中の貧しい人々、本など読まない砂漠の民やジャングルに暮らす民の中にも、日常生活の中で思索を深めている人はたくさんいる。北宋の畢昇(ひつしょう)が11世紀に活版印刷を発明し、グーテンベルクが15世紀のヨーロッパで活版印刷を使い始める前は、「本」は写本と木版印刷が中心で、多種の本が安価に流通していたわけではなく、本を読める人間はごく限られていた。本を読まなければ有用な知識・教養を得られないというならば、活版印刷が普及する前に生きていた人間は皆、まともな知識も教養を持っていなかったことになる。本がほとんどなかった時代に生きた紫式部は、たくさんの本を読むことなどできなかったのに「源氏物語」を書いた。中世の哲学者スピノザは、ひたすらレンズを磨きながらあの「エチカ」を著した(本当かどうか怪しいが)…
僕は、たぶん本を読むスピードが人よりも少し速い(具体的に他人と比較したことはないが…)。特に「速読法」などを学んだことはないが、長年の多読生活の中で早く読む習慣・技術が自然に身についた。極端な速読ではないが、一般的な小説やミステリー、エッセイ集などの内容で平均的な文庫本や新書1冊程度の文章量なら、だいたい30分~1時間前後で読了する(むろん本の種類・内容にもよるが…)。現在の片道15分の通勤時間の往復30分で、たいていは1冊の本を読める。それに就寝前の30分の読書時間を併せれば毎日2冊は読める。総文字数が少なめの新刊小説やエッセイ集ならば、わざわざ購入しなくても昼休みにランチを摂った後に立ち寄る書店の店頭で15~20分ほど立ち読みすることで読了する。内容の要約だけならもっと短い時間でできる。書店でパラパラと4~5分間本をめくれば、かなり深いところまでその本の内容を把握することができる。新刊書などは、この方法で片っ端から読んでみて、気に入った内容の本だけを購入している。また、同時並行で複数の本を読むことも普通だ。例えば専門書や学術書など読むのに時間がかかる本を数日または1週間以上掛けて読み続けながら、それと並行して短時間で読める本を毎日読了していく…といったスタイルだ。
さらに僕の読書スタイルは、「完読」を目的としていない。面白くない本は途中で読むのをやめて、次の本へと移行する。途中まで読んでつまらない本は捨てる。…といっても本当に捨てるのではなく、そこら辺に放っておいて、また気が向い時に続きを読む。逆に「途中から読む」「一部だけ読む」本も多い。こうした完読していない本は、もし再読する気にならなければ、当面は「書棚のこやし」になる。そして5年後か10年後かわからないが、再読する気になるまで放っておかれるのだ。
内容が難しくて読めない、または読むのが面倒で途中で投げ出す本もある。例えば、数学が好きな僕は「オイラーの贈物―人類の至宝eiπ=-1を学ぶ」(吉田武:ちくま学芸文庫)を買って読んだ。これが非常に面白かったので同じちくま学芸文庫から出ている「オイラー博士の素敵な数式」(ポール・J・ナーイン)を買ったのだが、こちらは難しくて理解できないところが多く、複素数のところで躓き、結局途中で投げてしまった。ともかく、面白くない本を無理に読了しようとはしない。要するに、本は「読み捨て」が基本だ。そして僕は、前述したように同時に複数の本を読む。2~3冊、またはそれ以上の本を並行して読むのは、ごく普通のことだ。
僕は何十年間も、こんなスタイル、こんなペースで本を読んできた。
「ジャンルを問わず、気の趣くまままに、ひたすら大量の本を読み続ける」…という、ある意味で節操のない僕の読書スタイルに違和感を持つ「本好き」も多いだろう。「本から何かを学ぶ」ためではなく、ただ「本を読んで多幸感を得る」ことだけが読書の目的なのだから、系統的、戦略的に読書対象の本を選ぶなんてことはしない。ジャンルを問わず、全く脈絡なく「面白そうな本」を読み漁る。僕が読む本を選ぶ基準は「面白そう」以外にはない。「読書」にもっと崇高な意義を見出し、読書の効用を広く啓蒙しようとしている人から見たら、許せないことかもしれない。でも、僕にとっての「読書」は「呼吸」とおなじぐらい、自然で生理的なものだ。本を読んでいることが自然な状態…と言い換えてもいい。もしかすると僕は「活字中毒者」なのかもしれない。
■視覚認識作業としての読書
先に書いたことを繰り返すが、他人がどのように本を読んでいるのか、また一般的な「速読法」がどんなものかは知らない。だけど、僕自身がどうやって本を読んでいるかは、なんとなく説明できる。僕は、速く本を読み短時間で内容を理解する行為は、「相当な読書時間をかけて習熟した、それなりに高度で複雑な視覚認識作業」だと思っている。
普通、本や雑誌などの和書を読むとき(縦組みの場合)、右から左へ1行ずつ、そして上から下へと1文字ずつ活字を眼で追って行く。しかし、版面を目で見たある瞬間に視野に入る文字はけっして1文字だけではない。人間は一瞬で、文字の集合である「単語」、そして単語の羅列である「文節」「文章」を読める。読んでいる場所の前後にある複数の単語や文章を見て(画像情報として)認識することができる。だから読書中には、読み進んでいる位置にある単語の先にある単語、文節、読んでいる行の次の行や、さらにその次の行など視野に入る部分を広範囲に視覚情報として認識する。これは、うまく説明できないが「目で写真を撮る」「画像として認識する」に近い感覚だ。そうやって脳に記録し認識された視覚情報が、ある部分を読みながら同時に文章の先読みをして、読んでいる部分の文意・解釈に関する最適な判断を下していく…という脳の作業につながっていく…というような感じだ。また、例えば見開きの左ページを読み進んでいるときに、ちょっと前の文章の内容を確認したければ、一瞬視線を右ページに戻して既に読んだ場所を再読したりもする。つまり読書という作業は、けっして「1文字ずつ活字を目で追って認識していく」作業ではなく、視線をあちこちに飛ばしながら総合的に情報を読み取っていく作業なのだ。そして、長年に渡って多読生活を続けていると、短時間に認識可能な視覚情報の範囲が拡大し、結果として「速読」できるようになるということだろう。見開きの2ページ分をほぼ同時に読む(見て内容を理解する)ことだって、ある程度は出来るのだ。これが「立ち読みの数分で本の内容を把握する」やり方でもある。
逆に、数式や図式が多い専門書などは、どうしても読書のスピードが落ちる。数式や図式は文字のように「瞬時に読み取れる視覚情報」ではないからだ。また、初めて見る単語(例えば自分が知らない分野の専門用語など)が多い書物は、大幅に読書スピードが落ちる。そして「下手な文章」、つまり「論理性のない文章」や「意味を簡潔に表現していない文章」は、読みづらく、理解するのに時間を要する。そしてもう1つ、横書き(横組み)の本は、縦組みの本よりも読むのに時間がかかる。こうした点については解決法がない。
こうしてみると、人間の目の働きとそこから得られる視覚情報をフルに活用して理解を深めていくのが、「読書」という作業だ。従って、狭義の文字認識だけではなく、広い意味での画像認識も伴う作業だとも考えられる。一般的な文章の中で使用頻度が高く視覚的に馴染みのある単語は、「読む」のではなく「見る」ことで、記号のように理解することができる。
こうした「多面的に視覚情報を活用する読書技術」を身に付けるためには、「眼で広範囲の活字を追いながら、素早く文章の内容を理解する」という訓練(慣れ)が必要になる。「単時間で文章の内容を正確に理解する」ためには、一定の訓練(読書経験)が必要となる。ここでいう「訓練」とは、視覚作業としての「読書をする」行為自体を指しており、要するに「たくさん本を読む」ことが訓練だ。だから僕に限らず、多読をしている人の多くは本を読むスピードが速いはずだ。
■速読のためには「手技」も必要
本を読んでいる時には、ちょっと前のページに戻りたくなることがよくある。よくある…というよりも、読書というのはページを「行きつ戻りつ」しながらするものだ。前のページに書いてあった内容を再確認することは専門書を読んでいると頻繁にあるし、ミステリーや小説を読んでいても前に出てきた「人名」や「シチュエーション」を確認したいことはよくある。そうした時、製本された本(電子書籍ではなく)なら、素早く目的のページを探し出せる。本の「小口」(紙端)の、それまで読んでいたページ分をまとめて「親指の原」に当て、パラパラ動画を見る時のようにページを素早くめくって目的のページを探すのだ。ハードカバーであれば表紙を除いて、カバーが柔らかい文庫や新書ならカバーごと、小口の読了ページ分に親指を当て、パラパラとページをめくって目的のページを探し出すのだ。この時、いかに高速でページをめくりながら目的のページを見つけ出すかが、速読の鍵となる。そしてここで必要なのは、本文を読むときと同じ「視覚認識」の作業だ。
本は、各ページに同じように活字が並んでいるわけではない。ページごとに、微妙に空白の位置が違う。章名や小見出しがあるページと無いページがある。章名や小見出しの前後には空白行がある。その章名や小見出しの位置(ページ全体のどのあたりにあるか等)も長さもページによって異なる。ページには固有の「濃淡」がある。こうしたことを手掛かりに、目的のページを素早く見つけ出すのだ。むろん、探したい情報がどんな雰囲気(活字の並び)のページにあったかを「画像」として記憶していることが前提だ。そしてもう1つ。目的とする内容がどのくらい前のページにあったかを、ページ数に比例した「小口の厚み」で把握していることも大事である。本ごとに異なる本の厚み、用紙の厚みによって変わるページ数を「親指の腹の感触」で把握することで、目的のページに近い部分を素早く開くことができる。
つまり、本を「速く・効率よく」読み、内容を理解するためには、「目」と「手」と、そしてそれらを総合的に認知する「脳」の合わせ技…が必要になる。
■電子書籍は速読に向かない
僕はここ数年、かなり電子書籍を購入して読むようになった。スマホやタブレット、そしてkindle paperwhiteを使っている。最近の僕が頻繁に電子書籍を購入するようになった理由は2つある。ひとつは老眼が進んだこと。もともと近視だったので、とりあえず近視用メガネの度を弱くすることで一応は普通の書籍や文庫本も読めてはいる。しかし、カフェなど周囲がちょっと暗めの場所だと読みにくくなってしまう。電子書籍はバックライトを使うことで周囲の明るさに影響されずに読め、さらに表示フォントの種類やサイズを自由に変えられるので便利だ。もうひとつは複数の本を持ち歩く体力が無くなってきたこと。速読の僕はいつ読みかけの本を読み終えるかわからないので、常時2~3冊の本をバッグに入れている。年齢とともに体力がなくなり、この書籍数冊分がプラスされるバッグの重さが、つらくなってきたのだ。スマホなら1台に何百冊の本でも入れておける。実際に僕のスマホの中には、既読・未読を併せて1千冊以上の本が収録されている。
しかし、この「電子書籍」を読み出したことが、速読を妨げる大きな要因となっている。電子書籍は簡単にページを飛ばして行ったり来たりできないからだ。基本的にページ移動は1ページずつしかできないし、複数ページを一気に移動するスライドバーを使っても、ピンポイントで数十ページを移動するのは非常に難しい。瞬時に目的とするページに移動することは不可能だ。表示ぺージを指定する機能を持つリーダーがあっても、曖昧な記憶をもとに「ページを行きつ戻り」する読書のためには役に立たない。
もうひとつつまらない話だが、電子書籍には「風情」「趣き」がない。僕は読書が好きだが、実は「形あるモノ」としての「本」も好きだ。装丁・デザインが優れた本が好きだし、組版や書体、紙質にもこだわりがある。そして僕は「本棚に本が並んでいる」ところを眺めるのも好きだ。背表紙を見て瞬時に読みたい本を探し出せるようになっていることも重要だ。電子書籍は装丁を愛でることができないし、大量の本のストックの中から「書名や著者についての記憶が曖昧な」目的の本を見つけ出すのも面倒だ。第一、何百冊、何千冊持っていようとしょせんは「メモリ」の中だ。この紙の本と電子書籍の関係は、レコードと音楽データの関係に似ている。レコードもジャケットのデザインやライナーノーツの体裁などが重要であり、音楽はただ「聴ければよい」というものではない。
…なんてことを思いながらも、近年は購入する本に占める電子書籍の割合がさらに増え続けている。既に書籍として持っている本を再読するために、同じ本をわざわざ電子書籍で追加購入することも多い。一方で未だ電子化されていない書籍が多いこと、特に1950~80年代に出版された本の電子化が遅れていることは不満だが、ワープロやDTP普及前の書籍の電子化は難しく(原稿も組版も電子データとして残っていない)、これを嘆いてもしょうがない。
■速読できる本とできない本
本を読む速度と内容の理解の速度には関連がある。だから速読できない本というのは、俗な表現だが「内容が難しい本」「内容が濃い本」だ。「難しい」とか「濃い」という抽象的な言葉ではわかりにくいので、ここで具体的な書名を挙げて比較してみよう。
例えば「新書」は比較的早く読める本が多い。…というより、意図的に中身の薄いタイトルが量産されている感もある。一例として最近書店店頭で目に付いた「不道徳ロック講座」(神舘和典:新潮新書)という本、ロック好きの僕はつい手に取って、そのまま立ち読みし始めた。結局この本は購入するまでもなく、そのまま15分ほどの立ち読みで完全に読了してしまった。同じく最近刊行された新書で「ダーウィンの呪い」(千葉聡:講談社現代新書)という本がある。進化論と優生思想の関連を説く内容は興味深く、これは購入した。で、読み始めたが約30~40分で読了した。割と面白かった。このあたりまでが「速読可能な内容」の具体例だ。
一方で同じ新書でも読むのに結構時間がかかった本の例として、「『その日暮らし』の人類学 ~もう一つの資本主義経済~ 」(小川さやか:光文社新書)を挙げる。気鋭の文化人類学者によるアフリカでのフィールドワークをベースに書かれたこの本は、既存の経済学を軽く斜めにとび越えた斬新な内容で、実に面白かった。で、この本はカフェで1時間近く読んで半分も読了できず、家に持ち帰って続きを読み、最終的に読み終えるまでに2時間以上は掛かった。このあたりの本が自分にとって「内容が濃い本」の尺度になる。余談だが、この新書で「小川さやか」の面白さを知り、同じ著者の「チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学」を購入して読んだ。恥ずかしながら、この本が2020年に第51回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞していたとは知らず、あまりの面白さに悶絶しながら読了したという後日談がある。
ところで「本をゆっくりと味わって読む」という行為を勧める人がいる。「意図的にゆっくり読むと内容に対する理解度が深まる」という話で、これは「例え早く簡単に読める本でも、わざとゆっくり読むことで内容をじっくりと味わうことができる」…ということらしい。個人的には、まったく意味不明の論理だ。完全に内容を理解することが前提なら、早く読むかゆっくり読むかで「本の味わい」や「内容の理解度」が変わるわけはない。内容から得られる面白さや感動の質も変わらない。読書の余韻を味わいたければ、同じ本を何度も読めばいい。僕も、何十年間も渡って繰り返し読む本がたくさんある。
■ワード・パフォーマンス
「ワード・パフォーマンス」というのは、僕が適当に作った造語だ。より正確には「ワードカウント・パフォーマンス」とでもいうべきだろうか…、要するに「1文字当たりの本の価格」のことである。多読家の僕は、文字数の少ない本は、それだけで読む気がしない。文字数が多い本、すなわち活字が小さく、ページ数が多く、そして分厚い本が好きだ。
バカな話だが、僕は「ワード・パフォーマンスが低い本」つまり「1文字当たりの価格が高い本」は、それだけで損をしたような気になり、買う気がなくなってしまう。これは本の内容以前の問題で、長時間読書を楽しむことに愉悦を感じる多読家の「性(さが)」のようなものかもしれない。
ところが、最近は文字数が少ない本が増えつつある。特に小説分野でその傾向が激しいし、新書などでも入門書系統を中心に極端に文字数が少ない本が増えた。やたら行間を空ける本も多く、余白が多いスカスカのページを見ると僕は悲しくなる。出版関係者の誰かが「読書習慣がない若者向けの本は、文字数が多いとそれだけで読まれない。だから、わざわざ手に取ってもらいやすくするために文字数を減らしている」…と発言している記事を読んだ。本当にその通りなら、とても悲しい話だ。
分厚い本、特に文庫本で分厚く文字数の多い本というと、パッとイメージするのが「古本屋探偵の事件簿」(紀田順一郎:創元推理文庫)あたりだ。同じミステリーなら「匣の中の失楽」(竹本健治:講談社文庫)もすぐに思い浮かぶ。ミステリーではないが「神田神保町書肆街考」(鹿島茂:ちくま文庫)も、今この文章を書いていて思い浮かんだ。神保町の古書店街の歴史を綴った、とても好きな本だ。ちなみに、速読によって短時間で読める本ではない。僕は、こんな「中身の濃い」「読み応えがある」本が好きだ。 ちなみにページ数が多くて分厚い本、特にミステリー小説で分厚い文庫本や新書版のことを「レンガ本」と言うらしい。
ところで、最近「分厚い」というだけで買ってしまった本がある。「編集者ディドロ:仲間と歩く『百科全書』の森」(鷲見洋一:平凡社)だ。第74回読売文学賞 研究・翻訳賞受賞作とのこと。あの「百科全書」を編纂したフランスの啓蒙思想家ディドロの人物像、本の編集・制作・発行過程、さらには「百科全書」の内容をどう理解すべきか…などについて書かれた研究書だ。この本は約900ページあり、厚さは10センチに達するまさしく「レンガ本」である。本棚に並んでいても、テーブルの上に置いてあってもともかく存在感があって満足度が高い。表紙デザインも好きだし装丁も美しく、まさしく「所有する喜び」を感じさせる本で、書店で見かけて速攻で購入した。リュックに入れて持って帰ったが、実に重かった。で、この本、買って半年以上経つのだが、実はまだ読んでいない。パラパラと全ページをめくって大まかな内容だけは理解したつもりだが、ちゃんと読んではいない。ちなみに僕はディドロの「百科全書」自体を読んだことがない(確か岩波文庫から出ていたと思うが…)。で、いずれこの「編集者ディドロ」をきちんと読了したら、「百科全書」も読んでみるかもしれないが、おそらくその日はなかなか来ないだろう。多読家である僕の「教養」なんて、しょせんこの程度のものなのだ。
断っておくが、分厚い本なら何でも食指がそそられるわけではない。京極夏彦の作品のように「売るためにわざと文字数が多い分厚い本にする」…というのは、あざとい版元の思惑が透けて見える。逆に読む気がしなくなる。
■音読をしてはいけない
ここから先は完全な余談になるが、「音読」を勧める評論家や識者・学者がけっこういる。中には「音読することで理解が深まる」なんてバカなことを言う人間がいる(ここはハッキリ「バカなこと」と言っておこう)。僕は「音読で理解が深まる」などとは全く思わない。逆に「音読」は、書かれている内容を素早く正確に理解する上での妨げとなる…と考えている。
視覚認識作業としての読書は、声に出しながら逐語読みしていく作業とは、根本的に脳の使い方が異なる。また、「オーディオブックを聴く」…という読書も同じだ。第一、オーディオブックを聴くというのは「読書」ではない。他人が朗読した作品を耳で聞いて理解する…というプロセスでは、短い時間の間に「前へ進んだり後ろへ戻ったり」することができない(テープを戻さない限り…)。また、視野に入ってくる様々な場所の活字を同時に記憶に焼き付ける…といったこともできない。常に「聞こえている場所」の部分に含まれる情報しか入ってこない。結果的に、文章に対する理解度は確実に浅くなる。
さらに、音読をしたり朗読を聞くことによって得られる「時間当たりの情報量」(これは自分で朗読しながら得られる時間当たりの情報量と同じ)は、決定的に少な過ぎる。例えば文庫本で200ページ程度のちょっとした小説や論文程度なら、眼で読めば最短で30分~1時間で読了して隅々まで理解できるが、朗読を聴くか自分で朗読をすれば、その何倍もの時間、最低でも数時間を要する。さらに、後で触れるが、音読では「文字面の美しさ」や「余韻」を楽しむことができない。
教育現場(小学校低学年あたり)で日本語を朗読することの有効性や、小さな子供に本読み聞かせることの有効性については、ある程度納得できる部分もある。しかし、自分で朗読したり、朗読されたものを聴くことと「読書力の養成」とは別のものだと考えるべきだ。朗読をすること、また朗読されたものを聴くことは、必ずしも読書力や理解力のアップに繋がらないだけでなく、逆に高度な理解を阻害する要因にもなりかねない…と考える。声に出して読むことに注意を払うと「眼で広範囲な活字を追う」という高度な視覚作業に対する集中力が、逆に損なわれると思う。
そして、「朗読で日本語の美しさを知る…」という理屈にも大きな疑問がある。「日本語の美しさ」というものがあるとすれば(私は必ずしも日本語が他の言語より美しいとは思っていないが…)、そこには「音の美しさ」と「文字面の美しさ」の両者があるはずだ。「音の美しさ」は、本来「話し言葉」や「日本語の歌を歌う」などの日常生活の中で味わい、培われるべきで、「文学作品を朗読して味わう」ものではない。あえて音読する意味がある作品となると、それは短歌や韻を重要視する一部の詩歌ぐらいだろう。小説などの文学作品は、内容とともに「文字面の美しさ」を追求したものでもあり、声に出すことを想定して書かれていない作品が大半のはずだ(意図的に読むことを目的にかかれた作品もないわけではないが…)。「文字面の美しさ」は、音読ではわからないばかりか、逆に音読することで味わえなくなる…ものだ。
※ 本稿は、視覚障害を持つ方、ディスレクシア(難読症)の方等への配慮をあえてせず、健常者のみを対象に書いている点をお断りしておく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
