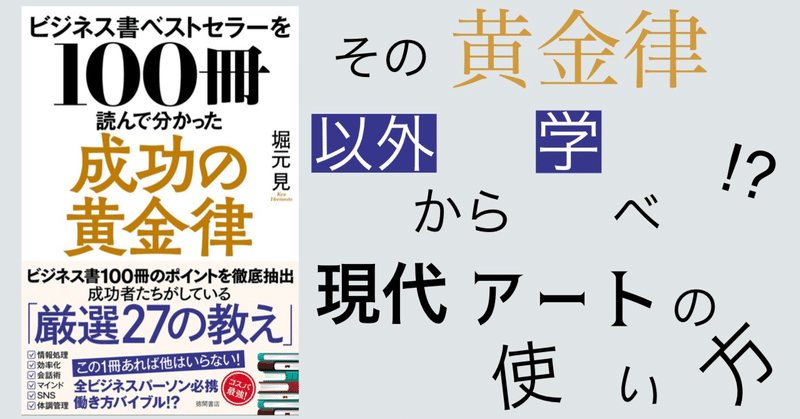
その黄金律以外から学べ!?現代アートの使い方
ある日Amazonのビジネス書ランキングに驚愕のタイトルが鎮座していた。
なんとも有益そうなタイトルで、
「この1冊あれば他はいらない」という言葉からも著者の自信が窺える。
しかし内容を見ると、例えば
教え23 ひとつのことをやり続ける のあとに、
教え24 ひとつのことをやり続けない と矛盾した教えが並んでいたりする。
このような内容や著者のSNS等を見るとわかるが、本書は筆者の主観のみに基づく科学的な根拠のない主張や、一部の人を扇動させて成功を収めている筆者の美談をそれらしく並べて自らを魔法使いに見せるだけのような、現代のビジネス書の累々に対して一石を投じる現代アートであった。
【見どころ⑤ 参加型現代アート】
— 堀元 見@ビジネス書100冊本、予約受付中 (@kenhori2) March 26, 2022
本書はビジネス書ではなく、参加型現代アートです。
騙されて買った人が、Amazonレビューで「結局何をしたらいいか分からなかった。星ひとつ」と書くことで完成します。
ですから、皆さんもぜひレビューを書いて作品に参加してください!https://t.co/ZsO3tkawtu pic.twitter.com/1UD94EIDT8
何を隠そう私もこのアートの参加者であり
ビジネス書100冊を読むYouTube liveをほぼ全て視聴している。
しかし本書を読むと、タイトルの黄金律こそ無いものの、
多くの学びになる要素が隠れている。
そこで現代アートをアートで終わらせるのはもったいない。
アートからビジネスを学ぶのも面白いだろう、ということで
本書から明日に活かせる成功への教えを見出そうではないか。
シントピカル読書の教科書
ビジネス云々よりも先に、本書はシントピカル読書の教科書として
これ以上ないくらいに優れている。
シントピカル読書とは同じテーマについて書かれた複数の本を読むことで、
前書きにも本書がシントピカル読書によるものだと書かれている。
私が本書が教科書として優秀と考える理由は、まず純粋に複数の主張を
受け入れていることにある。複数の主張を聞くとどうしても
最初に聞いたものを卵から孵ったひよこのように信用して、
それ以降の主張は最初の主張を盾に跳ね返し続けたくなるが、
本書ではどのような主張でもまずは受け入れようとする意思が窺える。
また書籍の前提も比較している。わかりやすいのはコラム中のこの文
2冊の本のどちらが正しいのだろうか。
僕には判断できないが、『多動力』(幻冬舎)はホリエモンの意見だけを基に書かれているのに対して、『Think CIVILITY』はそれなりに実験データや統計データが出てくるので、説得力においては後者に軍配が上がる。
単に内容だけを比較するのではなく、どこから来た内容なのか
誰に向けて書かれた本なのかなど、内容以外にも着目する事で
より客観的に主張を比較できるのではないだろうか。
注意したい点として、本書では万人に向けた書籍という特性上か
相反する部分もそのまま形になっているが、多くの場合は
自分の意見を持てるまで、読み込むのが好ましいだろう。
他のシントピカル読書の例として、堀元氏の処女作「教養悪口本」と
「文豪たちの悪口本」をシントピカル読書したnoteがあるので、
そちらも参考にされたい。
ビジネス用語の単語帳
本書中には「プロセスエコノミー」「フレームワーク」など
現在よく使われているビジネス用語がいくつも紹介されている。
もしこの中に、あなたが知らない単語があった場合は注意したい
その言葉はもう社会にありふれている。周りに取り残される手前だ。
まずは本書を読んでその言葉の概要を掴み、それでも理解できなければ
引用元の書籍を読んで自分のものにしよう。
同じ単語が複数の書籍から引用されていたら、
シントピカル読書をするのも、一冊を選択してそれを読み込むのも良い。
こうすることで1冊の本から100冊の学びのチャンスを得ることができる。
例えば「MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)」に
興味を持ったとしよう。本書では教え17で主に登場した単語だが、
そこを参考にして概要を学んだ後は引用元の
・『超・箇条書き』杉野幹人/ダイヤモンド社
・『ゼロ秒思考』赤羽雄二/ダイヤモンド社
・『一番伝わる説明の順番』田中耕比古/フォレスト出版
などを読むことで、さらに理解を深めることができる。
この本の言葉を一つ残らず説明できるようになれば、
ビジネスマンとして大きく成長した証になるだろう。
読書案内として
本書の位置付けとして、著者が発信しているように現代アートがあるものの
100冊のビジネス書を抽出して生まれた本ということは変わりない。
つまりビジネス書のブックリストとして膨大な情報量を保持しているため
ビジネス書を選ぶのに適しているだろう。
例えば本書中でのビジネス書の扱いは、茶化している/いないに大別できる。
茶化されていない本は読む価値が比較的あるといえよう。
「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考
読みたいことを、書けばいい。
などがこれに当たる。
また自分が納得できない意見の本を選ぶのも良いだろう。
先のシントピカル読書と似た話になるが、様々な視点でものを視ることで、
新たな意見が生まれたり、自分の意見を補強できたりする。
シンプルに多視点を持つ練習としても良いだろう。
『Think CIVILITY「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である』と『多動力』はコラム2から意見が対立しているので、練習にはもってこいだ。
終わりに
本書の作成過程であるライブ配信を視聴していたため、本書を読んでも
目新しいものは特にないかと思っていたが、配信のほどの悪ふざけはなく、
極めて論理的にビジネス書に向かっていたのは新鮮に思えた。
配信だけ見て本書を読んでない方は是非手に取っていただきたい。
本書を読んでビジネス書の滑稽さに笑い転げたり、信じていたものを
無下にされ怒ったりなど人によって多様な感情が湧いただろう。
そしてそれは本書の現代アートの側面から見たら期待通りだ。
しかしそれ以上の魅力が本書にある。それを知っていただけたら幸いだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
