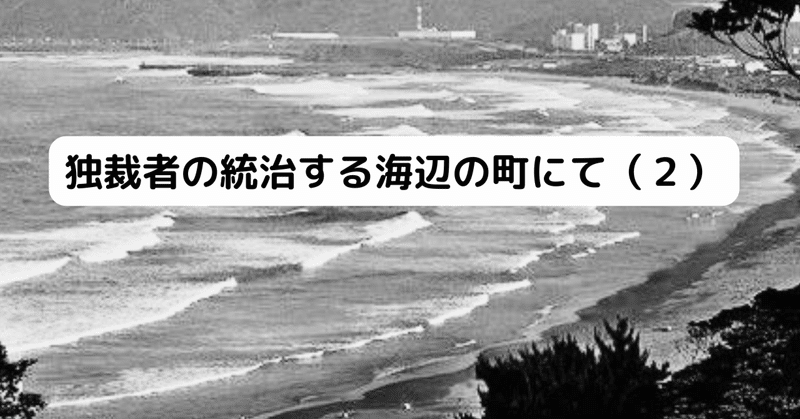
独裁者の統治する海辺の町にて(2)


次の朝は、ひどい暑さだった。柱の温度計をみると、10時だというのにもう体温よりも高くなっていた。おまけに、凛子とわかれたあとに寄った「レッドヒール」でウォッカをジン割で飲んだせいで、こめかみがうずいた。それに、そこにたむろしていた護岸工事の労務者とやりあったせいで、目の下に青あざができている。
全く、昨日の始末の後味の悪さったらない。なにが、正義の粛正だ。これでおれは唯一の友人を失った。もう、心を許して話す相手はいなくなった。一生孤立無援。組織の歯車、いや、「蟻」として、いや、蟻のふりをしてやっていくしかない。
あれが、よくなかったんだ。もう3年前に書いた論文だ。たかが大学の卒論だが、その内容が組織にとって不都合だったのだ。登坂は神父の息子で、坂道のてっぺんにある教会の跡継ぎとして父親と同じようにF市にあるカトリック系の神学科に進んだ。
文明が存在する以前の社会形態は、生産力の低さが「共存共栄」を必然にし、私有財産も階級も存在しなかった、というのがあいつらのいう「原始共産制」で、それが目指すべき理想社会なのだ。
もちろん、そんなばかげたことはない。それは猿山共同体においても必ずボス猿が統治しているのをみれば明らかだ。
登坂がおれの当時通っていた同じ県の国立大の寮に尋ねてきたときにもおれはそんなことを言った。あいつは、そうともいえる、とかるくうなずくとメガネを拭きながら次のように言った。
たしかに、幻想だよね。人間の本質は欲望だ。生産力の低さはむしろ強者による強制と収奪の源泉となる。食料が少なければ奪い合う。分配はその後だ。その分配もたんに備蓄システムがなかっただけだけどね。
つまり、強者の欲望によって・・・とおれは言ったのをあいつはそのまま引き継いだ。
強者の欲望が社会を進化させるのさ。それは支配と被支配の構造の精密化で、いきつくさきは官僚組織と軍隊組織を組み込んだ階級制だ。あいつらが目指してるのも
「もうやめろ」
おれは登坂がやや興奮気味になり、声が高くなりかけたのであわてて止めた。
「そうだな、父さんにも注意される」
「教会は大丈夫なのか」
「今のところは」
そのときはまだ凛子は彼の「妹」だった。凛子が組織の正式に訓練生になったのはその2年後だ。そしてその翌年の5月、2人の父登坂神父は殺された。自殺に見せかけて。
登坂の卒論の内容は概ねさっき彼が言った通りだが、結論が一番いただけなかった。もちろん党にとってだが。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
