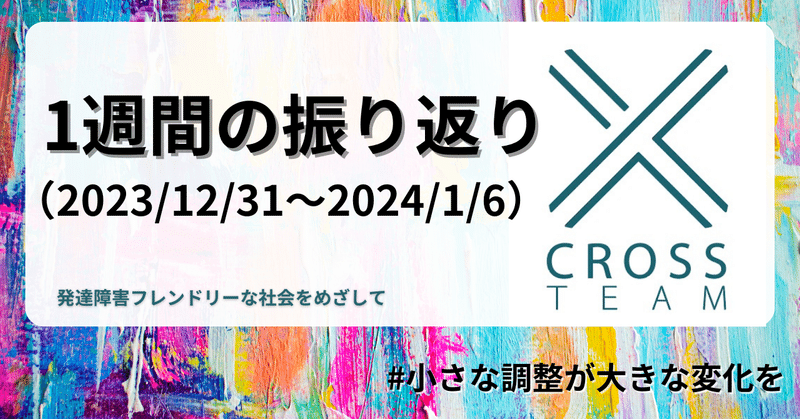
1週間の振り返り(2023/12/31〜2024/1/6)
この記事は3,917文字あります。個人差はありますが、6分〜9分でお読みいただけます。
今日はnoteの連続更新92日目です。noteのほかに、Voicy(音声配信)もしておりますので、併せてご活用いただけると理解しやすいと思います。また、noteの通知をオンにしていただけると記事が更新するたびに通知がいきますので、フォロー、スキ、シェアと合わせて通知オンもしていただけると嬉しいです。
毎週日曜日は1週間の情報発信の振り返りです。ほぼ、非常時の対応や心構え等について投稿していますので、ご負担になる人もおられるかもしれません。そうした方は閲覧を避けてもらえればと思いますが、どうぞお付き合いください。
東北の自閉症支援の未来に向けて
この記事が2023年最後の記事でした。2022年にTEACCHプログラム研究会東北支部という団体を設立し、代表を務めています。
今は100人以上の方々が入会してくださっていて、本当に有難いなぁと思っています。だからこそ、最低限「東北支部に入ったことを後悔させない」と思って頂くこと、そして「東北支部に入ってよかった」と思って頂けるように活動するのが、ぼくの責任です。
そう思って、研修会以外の中身もたくさん用意していて、2024年も新たなチャレンジをしていくつもりです。
東北支部ってどんな活動してるの?と思った方は、ぜひ下記の記事を読んでください。いや、興味がないとしても、読むだけでも、読んでいただけると嬉しいです。東北支部の皆さん、2024年も一緒に頑張りましょうね。
2024年も未来に目を向けて
2024年最初の記事では、2023年の振り返りをしました。
その上で、過去をどうするかよりも「これからどうしようか?」という未来に目を向けていくことが大切という内容です。
講演会や支援現場でも「過去よりも未来の話を」とお伝えすることがあります。これは過去を考えなくていいと言っているのでもないし、なんでも「将来のため」と考えたらいいと言っているのでもありません。過去の情報はとても大切です。例えば、何か困ったことが生じている時に、一体何があったのか、その原因は何だろうかを考えたり、困っていない時間はなかったかを考えたりは、とても大事です。でも、何のためにこうしたことを考えるかというと「これからのこと(=未来)を考えるため」なんです。
もちろん、綺麗事だけじゃなくて、実際の支援現場や生活場面では頭を悩ませることも少なくありません。時に疲弊したり、何とかご自分を奮い立たせておられる方々もいます。そうした時に、ぼくの立場として考えることは一緒に疲弊することではありません。一緒に悩みますが、その上で「これから具体的にどうしていきましょうか?」と前向きに考えていくことです。
改めて、非常時の支援を
1月1日は能登半島地震があり、甚大な被害をもたらしています。今もなお、多くの方々が困難な状況にあります。自分にできることはなんだろうかと考え、それは情報発信を続けることだと思い、この1週間は非常時の対応について中心的に発信をしました。Xもいつもよりも更新頻度を上げています。
この時には、2023年3月11日に、TEACCHプログラム研究会東北支部の会員の皆さんに向けて書いた記事を一般公開したものです。非常時の支援についての概説しました。
特別なことが必要というよりも、平時であれ、有事であれ、必要なことは基本的な支援です。
非常時の対応で「避けてほしい」こと
有事には、自分はいつも通りのこと、楽しみをしていいんだろうか?と悩まれる方々もおられます。
だけれども、そこは引っ張られすぎずに、いつも通りの活動をすることも大切です。自粛しすぎてしまうことで、自身のメンタルの問題が出てしまうこともありますし、いつも通りの活動をすることが、「心配していない」ということにもなりません。むしろ、何らかのサポートをしたいと思うのであれば、自分達が心身ともに健康でいることが、まずは大事になります。
それぞれの考え方があるとは思いますけれども、日常生活を送ることも意識してもらえるといいかなと思っています。
そして、現場で対応する際には、子どもであっても、大人であっても、
・そうした体験を無理に思い出させようとしない
・無理に絵を描かせたり、作文を書かせたりしない
・無理に聞き出すことは傷口を広げる可能性がある
ということも意識していただけると良いと思います。
サイコロジカル・ファーストエイドとは?
サイコロジカル・ファーストエイド(Psychological First Aid;PFA)は、災害等の直後に伴う苦痛や困難を和らげ、被災された方々が回復することを助けることを目的としています。その対象は、被災された方々だけでなく、復旧・復興のための救助者の方々まで含みます。
この回では、サイコロジカル・ファーストエイドの考え方をもとに、子ども、高齢者、障害者それぞれに対して「避けるべき対応」についてまとめました。
そして、難しいこともあるかもしれませんが、自分自身が動揺せずに、穏やかに、落ち着いた態度でいることで、必要なことがあればサポートできるような準備をしておくことも重要ではないでしょうか。
現状把握のない支援は支援にならない
よく支援現場では、「まずは現状を知ることがスタート」という話をします。現状を知らずに、自分の経験則からだけでものごとを判断しようとするのは、支援が支援にならずに、むしろ「自己満足の支援」にもなり得ます。
これは非常時も同じです。
前日に紹介したサイコロジカル・ファーストエイドでは、大事にしている8つの活動というのがあるのですが、その中の2つは「現状把握をした上で、現実的な問題の解決をサポートする」というものです。
すぐになんとかしてほしい気持ちも、なんとかしたい気持ちも重々理解できますが、まずはすぐに介入を試みるのではなくて、現状を把握すること、その上で何ができるかを考えることが大事です。
不安のサインー#障害者を消さない
普段と異なる生活環境になることの負担は誰にとっても大きいのですが、自閉症スペクトラム(ASD)の方々にはより一層負担は大きなものになります。多分、これはぼくらが思う以上に大きなものだと思います。
災害時や非常時には、障害があってもなくても大変なのは皆同じです。それは理解ができます。だけども、ASD特性があるとより一層の困難を感じ、普段とは違う行動が目立つようになります。
例えば、
1)感覚過敏やこだわりが強まる
2)感覚遊びへの没頭
3)いつも以上に同じ質問や行動を繰り返す(終われない)
4)いつもなら流せるような変化や変更で混乱・動揺する
というようなことが、強い不安、負担、困難の現れとして出ることがあります。
もし、こうしたことがあれば、それらを周囲の方々は「そうか、不安なんだよね」と思えないとしても、「仕方ないよね」と思えないとしても、大きな声で注意をしたりせずに(いや、ヒソヒソを言われるのも嫌ですし、してほしくありません)、どうか見守っていただけないか、そんな風にぼくは思ったりもします。そのことだけで、救われる当事者やご家族がいます。
まとめ
この1週間にnoteとVoicyで発信した内容をまとめました。少しでもお役に立てば幸いです。そして、一人でも多くの方々に知ってほしい内容ですから、できればこうした情報の拡散にご協力頂ければと思っています。どうか力を貸してください。
そして、この1週間、情報発信以外にできることはないだろうか考えていました。何がお役に立って、何が迷惑になるのか、まだまだ把握できていません。
代表を務めている東北支部内でも協議しました。会員の方々からも、「何かできることはないか」と申し出をいただきました。今できることは限られており、直接的にお役に立てることはほとんどないかもしれません。
それでも、今ぼくらにできることを考え、過去に配信したオンラインセミナーを再度配信させていただき、その売上(配信や販売に関わる手数料を差し引いた全額)を能登半島地震の支援・復興に向けた寄付することに決めました。
寄付先につきましては、支援を必要としている福祉関連の団体への寄付を検討していますが、決定後には当支部のホームページやSNS等で後日お知らせします。
配信するオンラインセミナーは、ぼくが2022年、2023年に東北支部で話をした下記2テーマです(それぞれ100分ほどで、1本の動画にまとめています)。
・自閉症スペクトラムの方々の支援で大切なこと
・わかりやすい支援のために必要なこと
寄付型セミナーみたいな形です。下記よりお申込が可能です。
個人だけでなく、法人単位でもお申込み可能にしました。法人の場合には、法人内研修としてもご活用いただけます。自分でいうのもなんですが、そんなに悪い内容じゃないと思います。
そして、役員の皆さんには、連日勝手に方針を打ち出しては連絡しているのですが、どれも快くご賛同してくださっています。会員の皆さんからも、色々なお申出を頂いています。本当に良い仲間に巡り会えていると思います。東北支部の皆さん、ぼくは皆さんを誇りに思いますし、大好きな仲間です。
現地の皆さまの無事と安全を、そして1日でも早い復興と穏やかな日常が戻ってくることを東北支部一同、心より祈念しております。
補足はVoicyの配信をお聴き頂ければと思いますので、宜しければVoicyの方も応援していただければと思います!
佐々木康栄
災害時に役立つさまざまな情報
被災地で、発達障害児・者に対応されるみなさんへ(国立障害者リハビリテーションセンター)
防災・支援ハンドブック(日本自閉症協会)
災害時、発達障害の子どもの支援についての医療関係者へのお願い(内山登紀夫先生)
災害時の発達障害児・者支援エッセンス
#障害者を消さない (ヘラルボニー)
その他お知らせ
オンラインサロン「みんなで考える発達障害支援」
クラウドファンディング
▼9月に大阪にて講演会をさせて頂いた「一般社団法人泉大津・発達支援勉強会Lien」さんが、「大阪府泉大津市、及び、泉州地域である近隣市町村一帯が、発達障がいや多様な子どもたちにとってより過ごしやすい地域に」を目指して、クラウドファンディングをされています。特に、4月2日の世界自閉症啓発デーでは、世界中がブルーライトアップされます。これは色々な人に目を向けてもらうための活動でもある一方で、それだけ予算がかかります。
そのため、どの地域でもできるわけではありません。今回、泉大津市内のブルーライトアップをしたい!という想いを叶えるためのクラウドファンディングです。目標金額は220万円です。ちなみに、これは行政と一緒に取り組んでいるものなので、「ふるさと納税」として寄付ができます。
ぼくも応援メッセージを出させて頂いています。どうか皆さんも応援していただけないでしょうか。
皆さんの応援が力になり、その力が地域を進める行動になり、その行動が当事者やご家族の未来になります。
一緒に地域の未来を変えるお手伝いをしてくれませんか?
セミナー情報
▼TEACCHプログラム研究会 第16回実践研究大会 in 東北・東京・熊本・鹿児島 「共に学び 成長する 熱い冬」
ぼくは仙台会場にいって、一丁前にコメンテーターというのをさせて頂きます!翌日にはTEACCHプログラム研究会東北支部主催でイベント「自閉症支援の未来会議 in 仙台」も開催しますので、2月10日(土)、11日(日)はご予定の確保をお願いします!
▼会員限定動画▼
これまで、会員の皆さんには限定のコラムや動画を配信してきました。現在下記のような動画を配信中です。閲覧にはパスコードが必要です。何度かメールでご案内しておりますが、もし会員の方で「パスコードがわからない!」という方はteacch.tohoku@gmail.comまでご連絡ください。
▼会員限定コンテンツ▼
現在、会員限定の質問フォームを設けています。匿名にしようかとも思ったのですが、会員の方からのご質問であることを確認するためにお名前のご記入をお願いしたいと思います。ご質問については、全てにお返事できるわけではなく、会員の皆さん全体にとって有益だろうと思うものを中心に取り上げて、限定コラムなどで書いていきたいと思います。
▼その他▼
ここに記載した以外にも、東北支部ではさまざまな取り組みを今後もしていきます。会員の皆さんには、「今こんなことを考えています」というのもお届けしますのでお楽しみに。公式LINEもあり、会員以外の方もぜひご登録ください!定期的に情報発信していく予定ですので、「TEACCHって何だろう?」「興味はあるんだけれども、どんな活動をしているんだろう?」という方はぜひご登録ください!
SNS
▼Voicy
▼stand.fm
▼X
https://twitter.com/KoeiSasaki
https://www.instagram.com/koei.sasaki/
https://www.facebook.com/koei.sasaki.5
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
