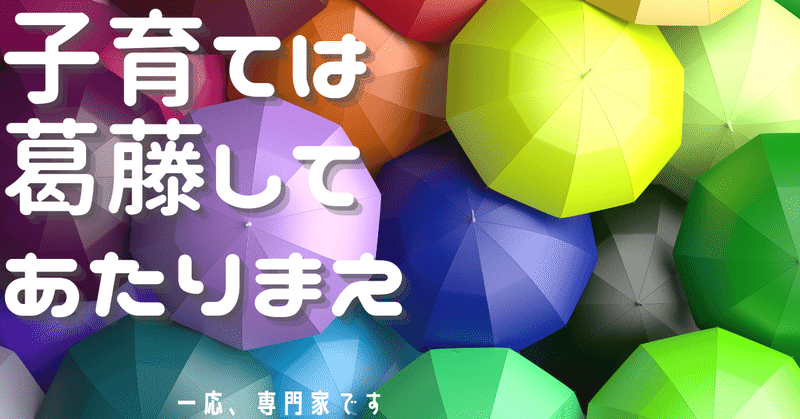
専門家だって子育てには葛藤がいっぱい
この記事は2200文字あります。個人差はありますが、4分〜6分でお読みいただけます。
自分が子育てをするようになって

僕の専門領域は発達心理学で、その中でも発達障害という領域になります。ですので、基本的にはその領域に関する発信がほとんどです。
でも、同時に2児の父親でもあるので、子育て中の立場でもあります。子育てをするようになってからは、これまでの生活スタイルとは全く違う生活スタイルになりました。以前は夜も仕事ができていたのですが、今はだいたい寝落ちをしてしまって、「またやってしまった…」と目覚めることがほとんどです。
それ以外にも、子どもが体調を崩せば、患者さんたちには非常に申し訳ないのですが予約を調整いただいたり、日々の送迎、お風呂、食事、宿題のチェック、翌日の準備、寝かしつけ、玩具の片付け、その他家事などです(とはいえ、僕よりも妻が担ってくれる分量の方が圧倒的に大きいので、頭があがりませんが)。
子育てで悩むのはあたりまえ

日々のご相談の中では、さまざまな親御さんたちにお会いします。自分が子育て真っ只中であるからこそ思うことがあります。
子育ては、想定外のこと、自分の思い通りにいかないことの連続です。親御さんたちは、「自分の子どもなんだからわかって当然でしょう」という視線を向けられることがありますが、どんなに我が子のことを愛していても、どんなに考えても、全てを理解できることなんてないと思うのです。僕もそうした親の一人です。
「子育て中といっても、それ以外のこともできてあたりまえ」と思われたりすることもあるかもしれません。でも、毎日の生活をまわしておられるだけで、どれだけ大変なことか。
子どもは十人十色であり、子育てのあり方も十人十色です。正解はないし、苦しい時間帯もあります。僕だって、うまくいかないことばかりです。
一般の育児書には、
・たくさん声をかけましょう
・たくさん触れ合いましょう
・トイレットトレーニングのコツ
など、あげればキリがないほど、さまざまなことが書かれています。でも、育児書に書かれている全てのことが、我が子に当てはまるとは限りません。
教えていけるタイミングがある

育児書に書かれているのは、子どもの発達の目安であって、その年齢で達成していなければならないことではありません。
発達のペースはさまざまです。平均的に発達していく方もいれば、得手不得手の差が大きい方もいます。心理学の中には、「発達の最近接領域」という言葉があります。これは、以前よこはま発達相談室のnoteでも紹介しました。
ざっくり言うと、
・人の発達は「できる」「できない」ではなく、「サポートがあればできる」領域がある
・この「サポートがあればできる」領域が「発達の最近接領域」と言われる
・この領域にあることがらをサポートしていくことが、最も発達を促進する
みたいな感じです。詳しくは下記をご覧ください。
一旦引くことは、育児をサボっていることにはならない

ですので、教えてみてできそうであれば教える、今は難しいと思ったら手はひくということが大切です。
僕自身はそうしています。例えば、トイレットトレーニングひとつとっても、「これは本人もモチベーションがないし、教えてみてもできる感じがしない」と思えば、教えませんでした。それでも、「今はできそうかな?」というタイミングで教えてあげたらすんなりできたり。トイレットトレーニング以外でもそうです。
子育ての中では、どんなに周囲と比べるものではないと理屈としては分かっていても、周囲の子どもたちを目にすると、
「もうこんなことができているのか…」
「我が家は教えてないからできないのかな…」
「いつできるようになるんだろう…」
色々な不安がよぎると思います。あたりまえです。でも、そのことを非難する権利は誰にもないし、無理をして親子ともにストレスがかかるのであれば取り組む必要もないと、僕は思います。
「愛情不足」と言われることもあるかもしれません。でも、たくさん無理をさせることは愛情でしょうか?
大切なことは、子どもが安心して生活できること、安心して親を頼ってくれること、親子ともに苦労はありながらも、「我が家の生活も悪くないよね!」と思えることではないでしょうか。そして、「あーもう!大変!」と思う中に、「こんなことして、可愛いね」と思える瞬間を大切にしていきたいと思っています。
まとめ
今回は自分の子育て観的なことを書いてみました。簡単にまとめると、
専門的に勉強していてもわからないことはいっぱい。
子育てで悩むのは当たり前で、親だから何でも知っているということはない。
子どももさまざま、子育てのあり方もさまざま(正解はない)。
焦ることもあるけれども、それは悪いことではない。でも、「子どもの発達」という視点も役に立つ=教えていけるタイミングがある。
そのタイミングは一律ではない。
たくさん関わり、時に無理をさせることが愛情ではなくて、子どもにとって安心が手に入るような関わり方が愛情では?
大変な時間もあるけれども、それも含めて「悪くないよね」と思える時間を大切にしていこう。
時々は、こうした自分の子育て観のようなことも書いていきたいと思います。それ以外にも、いくつかカテゴリーに分けて記事を書いていますので、そちらもお読みいただけると嬉しいです。
佐々木康栄
こんな記事も書いています
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
