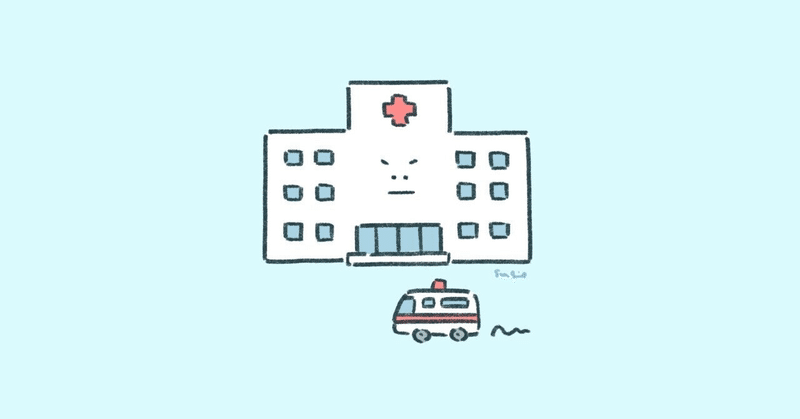
結婚記念日に急性虫垂炎(盲腸)で緊急入院した話
1000人に1〜1.5人の割合で罹ると言われている虫垂炎(盲腸)。この記事は、3年目の結婚記念日当日に急性虫垂炎を患い、緊急入院することになった筆者による入院レポート(エッセイ)です。虫垂炎を患っているかた、患っている気配のあるかた、あるいはそうしたかたがたのご家族など、もしものときの参考になるかもしれません(し、ならないかもしれません)。なお、この記事はあくまでも筆者固有のケースに過ぎない旨、くれぐれもご承知おきください。
11/1(水)緊急入院
この日は外勤の仕事があったので、昼前に家をでた。11時に、東京駅で合流した同僚と早めのランチをとり、その後、用務のために舞浜界隈へ向かう。昼食後から、腹痛とまではいかないけれども、胃もたれのような違和感があり、用務のあいだ、しだいにその感じが亢進していった。15時をまわったあたりでいったん用務は終わり、同僚とは別れて、先に帰ることに。京葉線に乗って東京駅へ向かうも、車中、「さすがにこりゃあ、ただの胃もたれとは違うかもしれん……」と苦しみが募りだす。
実はこの日は、3年目の結婚記念日だった。早めに仕事が退ける予定だったので、アテスウェイでケーキを買い、ビーフシチューの材料(ちょっといいお肉と煮込む用のワイン)を買い、カルディでノンアルコールのスパークリングジュースを買って帰るつもりだった。……のだけれども、東京駅に着くころには、胃もたれは鈍い腹痛に変わっていて、とうてい、あちこちに寄って帰れるような状態ではない。しかたなく妻に、「腹痛でどこにも立ち寄れないぐらいに死んでいる」とLINEで報告する。
やっとこさ、中央線に乗り込む。目的の吉祥寺までは、30分とかからない。もう少しの辛抱だ……とじぶんを励ましてはみるものの、にわかに、冷や汗がとまらなくなる。このとき、はっきりと、「あ、これ、もう、ただの腹痛じゃねえわ」と自覚し、辛抱たまらなくなって、御茶ノ水駅にて途中下車。駅員に告げて、駅の医務室にて横にならせてもらう。だが、横になっても、いっこうに痛みがひかない。しんどい。どうあがいたって、しんどい。実は、御茶ノ水界隈には、社会人になってから6年ほど住んでいたので、土地勘があり、この辺に大病院がたくさんあることは知っていた。なので、「救急車をお呼びしますか?」という駅員の提案は丁重にお断りして、自力で、J病院まで歩いて向かった。
……のだけれども、この、J病院! 受付がとんでもなく塩対応だった。一般の診察はすでに終わっていることをなんども強調され、救急のほうなら対応できるかもとは口でぼそぼそ言いながら(ふかした芋でも食ってんのか?)、しかしあきらかにめんどくさそうな表情をして、よその病院を紹介するコールセンターの電話番号をつきつけてきた。こうして目の前で苦しんでいる急病人がいるのに、どこまでも頑なに事務的な対応しかしようとしない健気なまでの職業的使命感(?)に二の句が継げず、空いた口がふさがらない。なんだかそうなるとこっちはこっちで、こんな病院には死んでも世話にはなりたかないわ、こっちから願い下げじゃ、あほんだら! と、メロスも激怒。しかたなくセリヌンティウスたるわたしは、そのコールセンターとやらに問い合わせをして、この界隈で緊急で腹痛を診てくれる病院があるかきいてみる。
すると、Yクリニックを紹介された。すかさず、今度はこちらに電話をかけてみる。……ところが、である。なんと、当該の医師本人が急病のために不在、とのこと! ああ、無情(レ・ミゼラブル)。もうおれはここで野垂れ死ぬしかないんだろうか。儚い33年の人生であったなあ……と、J病院のベンチで絶望にうちひしがれながら意識も遠のいてゆくなか、念のため、そのYクリニックの電話口のひとにも(ちなみにこのかたはとても丁寧な対応をしてくれました)、このあたりで緊急で腹痛を診てくれる病院がないかをきいてみる。すると、杏雲堂病院の名前があがる。杏雲堂といえば、明治大学はリバティータワーの対面にある、あの大病院だ。かつてこの界隈に住んでいたころ、御茶ノ水から神保町方面に向かうとき、いつも目の前を(いつかお世話になる日がくるなんて想像だにしないまま)素通りしていた、あの大病院だ。そして、夏目漱石をして、「変人」と言わしめた佐々木東洋が、明治時代にこの神田駿河台の地に開業した、あの大病院だ。たぶん。
一縷ののぞみをかけて、杏雲堂に電話を入れると、すぐに事情を理解してくれ、受け入れてくれることに。もはやタクシーを呼んで向かうほうが、夕方の混雑した時間帯でもあり、かえって遅くなる予感もされたので、急がば回れ。腹をおさえおさえ、最後の力をふりしぼり、J病院のベンチから、杏雲堂まで歩いて向かうことにする。
命からがらたどり着いた杏雲堂で受付を済ませ、そのころにはもう、座っていることさえできない状態。受付のソファーに横だおれになると、すぐに、医師と看護師がストレッチャーをひいてきてくれて、一時的な往診室のようなところまで運ばれる。が、この時点で、目をひらくことすらできないほど、悶絶。聴覚だけはかろうじて生きているので、音で状況を把握しながら、口頭で問診を受ける。「最近、生ものとか食べましたか?」という質問に、ぐるぐると記憶をたどってみる。……と、さかのぼること2日前。会社の会食で、神楽坂でラム肉を食べたことをはたと思いだす。そのコースのなかに、「もう、これ、全ナマですやん。だいじょぶなん?」という感じのラムチョップが出てきたのだった。そのことを看護師に告げると、「ナマのラム肉だって? なんとまあ、ばかねえあんた」てな感じの反応で(はなかったけれども)、なんだかじぶんも、まちがいねえ、そのときのラムチョップがあたったにちげえねえ、と思いつつ、となると、そのとき会食した同僚たちは大丈夫なんだろうか? 今ごろわが編集部は全滅していないだろうか? と不安になるも、そちらの安否を確認するいっさいの余裕は皆無。
引きつづき悶絶をしているうちに、採血、そしてCTスキャン(CTスキャンの際には、「息止めでお願いしますねー」的なことを看護師から言われたので、さっそく息を止めていたところ、いよいよ窒息しそうになったころになって機械から「息を止めてください」の指示が。おおお。そういうことね。腹痛うんぬんいぜんに、ポックリいきそうなできごとがあったりもした)。
結果、感染症の数値が異様に高く、虫垂が腫れているとの診断。いわゆる、盲腸(急性虫垂炎)だった。「も、もうちょう……?」と、じぶんは青天のヘキレキだったけれども、そういえば、この日の数日前にお昼にそばを食べたときにも胃もたれ以上の違和感があったことなど思いだし、シグナルはあったんだなあと思ったりもする。
医師からは緊急入院を勧められ(というかもはや薬で散らせるレベルではない)、もちろん、こちらとしても一刻でもはやくこの苦しみとおさらばしたく、即刻、緊急入院となる。ただし入院のためには、コロナの検査が陽性である必要があるとのことで、鼻の奥に例のアレを(なぜだか左右両方に)ぶっこまれ、ぐりぐりされ、このときばかりは、腹の痛みよりも鼻の奥の痛みに悶絶したしだいで、ぴえん超えてぱおん。そして流れる涙。
点滴を打たれながら(人生はじめての点滴)、ゆいいつ空いていた個室へ。このとき、直後に三連休を控えていたこともあって、大部屋も、低ランクの個室も埋まっていたらしく、でももうこちらとしては、そんな金のことなどどーでもいい、人生どうでも飯田橋(ここはチャラチャラ流れる御茶ノ水)、の状態であるにはあった。
さて、このときすでに18時ごろにはなっていただろうか。抗生剤を打ち、痛み止めを打ち、いろんなものをキメ込みながら、もうろうとしたまま一日を終えたのだった。
11/2(木)手術当日
入院時の話では、この日も、続く三連休も、担当の医師の手術の予定が詰まってしまっているとのことだった。だから、手術は、連休明けの週のどこかに行う可能性が高いと聞かされていた。「もしや、それまでずっと点滴だけで、米粒ひとつ食えない日々がつづくのだろうか?」という不安を抱えていたのだが、結果、いつ虫垂が破裂して穴が空いてもおかしくはない状態であり、緊急性が高いことからも、この日の夕方17時以降に手術をすることが決まる。
午前中に、母親が、妻のもとに寄ってから入院に必要な一式を持参してくれた(妻は0歳7か月のファニーボーイの世話につきっきり)。
昼すぎ、医師からの手術の説明を母親ときく。医師いわく……虫垂、というのは、大腸の一部である盲腸から垂れ下がった部位。その入り口のところに、糞石が詰まってしまっており、炎症を起こしている。まだ穴は空いていないが、もし破裂してしまうと、内容物がお腹のなかにぶちまけられてしまい、腹膜炎などにつながってしまう危険もある。手術は、むかしは開腹手術が多かったが、いまは、腹腔鏡手術が主流である。腹腔鏡というのは、お腹に12mm(1か所)、5mm(2か所)の穴をあけ、内視鏡で確認しながら手術をすること。術後の回復が、開腹よりも早いメリットがある(ただし、虫垂の真上のお腹に切り込みを入れる開腹のほうが、直に患部にアプローチができるのは確かである)。なお、CTなどの様子から、患部の炎症がひどく、ドレーン(管)を入れる可能性が高い。その他、合併症のリスクについてはこれこれである……。話をきいて想像しているだけで腹痛がしてくるようで、ついお腹をおさえながらきいていたところ、「痛みますか?」と心配されてしまった。お恥ずかしいかぎりでございます。
ちなみに、わたしの母親も、その母親も、盲腸罹患者。1000人に1〜1.5人の割合というのが事実なら、確率的に三代つづくことは考えづらいので、たぶん、盲腸は、体質(器官)的に遺伝します(これ、重要)。
その後、病室に戻り、母親が帰ったころに、看護師から手術が14時半からに変更になったことを急に告げられる。風雲急を告げるとはこのことで、とはいえ心の準備をする暇もないまま、手術用の服に着替え、紙パンツを履き(人生はじめての紙パンツ)、静脈の血栓(いわゆるエコノミークラス症候群)を防ぐための着圧ソックスを履く。
そうしているうちに、姉が見舞いにくる。正岡子規の『仰臥漫録』を買って持ってきてくれた。だが、姉の面会時間がはじまってすぐに、手術室への移動を告げられる。点滴を引きずりつつ、じぶんがこれから全身麻酔の手術を受ける人間だという当事者意識も自覚もほとんど欠いたまま、手術コスチューム姿(?)を記念して、姉と写真をパシャリ。そうして姉に見送られながら、あれよあれよという間に手術室へチェックイン。
踏み込んだ手術室は、テレビとかでよく見る、まさにあの通りの空間だった。空間全体が、青っぽいというか水色っぽいというか、窓のない静かな無機質な空間で、10名に近いくらいの数の医師が、青い手術服を身にまとっていた。はじめに、名前や生年月日などを確認される。全身麻酔の説明も(緊急手術だったので)この場で受ける。そうして、いよいよ、手術をするための個室に通された。
部屋の中央に手術台がぽつねんと置かれていて、まるでこれから解体されるマグロを載せるまな板か何かのようだった。死の気配、というのを直感せざるをえない風景だったが、言われるがままにそこに横たわり、酸素マスクをかぶせられる。するうちに、麻酔医から、「じきに全身麻酔の薬を入れますよ」と告げられる。「10秒、ないし5秒ぐらいですぐに意識がなくなりますからねー」とおっしゃるのだけれども、これが、なかなかどうして信じられない。というのも、強烈な自意識家をもって自認しているこのわたし。こんな非日常的な緊張した死の気配ただよう空間で、麻酔を打たれるままにおめおめと入眠してしまう、などというのがとても考えられなかったのだ。「もし麻酔がぜんぜん効かなかったらどうしよう」という不安が、黒い風船のようにどんどん大きくなってゆく。「そろそろ麻酔入れていきますよ」という医師のことばは聞こえてはいるものの、半分覚醒している状態のままハラキリに突入してしまったらどうしよう、と恐怖におそわれる。あるいは、もし、術中に目が覚めることがあったりしたら……。
なんてのは、とんでもない杞憂だった。たぶん、麻酔を投入されて、秒でオチた。秒? コンマ一秒だったかもしれない。結局のところ、明敏な自意識(自称)なんてものは、科学技術の前にはなんの自制心も価値もないものらしい。
……目を覚ました。とてもふしぎな感じだった。というのは、「目を覚ます」とわたしたちが言うとき、すくなくとも、寝ているそのあいだも(寝ながらも)時間の持続している感覚が確かにある。だから、「あ、ちょっと寝すぎちゃったかも」とか、「すこししか寝れなかった」とか、起きぬけにすぐ直感的に、寝ているあいだの時間の流れをなんとなく意識することができる。けれど、全身麻酔はまったくそうではなかった。目を覚ましたときにまず感じたのは、眠りについた瞬間から、まばたきていどの時間しか経っていないのでないか、という感覚だった。いわば、まるで、時間そのものを(虫垂とともに)ごっそりメスで切り取られてしまった。そんな感じだった。
「あれ? もう手術したんですか? ほんとに?」という虚けた感覚のまま、とにかく手術が終わったと医師が言うのだから、終わったのだろう。もうろうとした意識のまま、ストレッチャーに乗せられて、病棟の個室へと運ばれてゆく。……と、だんだんと、下腹部にモーレツな感覚が兆してきて、それがあまりにもモーレツだったものだから、つい、運んでくれている看護師にモーレツに訴えてしまった。「すみません、いま、モーレツにおしっこがしたいんですが……」。
手術自体は1時間半の予定で、たぶん予定通りに終わったのだろう。その後、手術室で1時間くらいは目が覚めるまで寝ていたはずなので、このとき、おそらく17時ごろだったと思われる。すでに日の落ちかけた個室に戻ってからは、時間だけは把握しておきたかったので、テレビをNHKにしてつけっぱなしにしておいてください、と看護師にお願いした。以降、麻酔が尾をひいてもうろうとしつづけており、1時間起きにやってくる看護師が、「手術から◯時間経ちましたよー」と報告をしてくれるのをぼんやり意識の底に聞いていたのだった。
しだいに、麻酔も切れてゆき、全身の感覚を取り戻してゆく。……のだけれども、ほんとうのジゴクは、ここからがはじまりだった。実際のところ、ハラキリの痛み、下腹部全体にひろがる鈍痛、それはそれでぼんやりとつらいのだけれども、あるいはそれ以上につらいのが、まずは肩から背中にかけての痛み。手術以来(というか入院以来)、寝っぱなしの姿勢が基本だったので、体を動かせないことによる筋肉への負荷がけっこうあった。しかも、寝返りを打とうにも、腹は痛いしあちこちが管につながっているしで、とてもろくに動けない。しかも、両足のふくらはぎには、やはり血栓をふせぐためらしい空気ポンプのようなものが取りつけられ、機械的にふくらんではしぼんでを、えんえんとぶきみに不快に繰り返しているのだ……。ひたすら筋肉の痛みに耐えつつ、しかしさらにそれ以上に、ずっと、ずっと気になっていたことがある。そう、術後すぐに「モーレツにおしっこがしたい」といった、そのあたりのデリケートなゾーンのことである。
あいかわらずわたしは、「モーレツにおしっこがしたい」と思いつづけていた。もう少し正確にいうと、「モーレツにおしっこがしたい感覚があるのに、全然おしっこが出ない」という感じ。膀胱の奥からタコさんウィンナーの先端にいたるまで、強烈な違和感、痛み、がある。つい、またしても、看護師に「おしっこがしたいんですけれど……」と訴えると、「それ、覚えてないかもしれませんが、術後すぐにも言ってましたよ」と半笑いで返される。ぐぬぬ。覚えてますよ、こちとら強烈な自意識家(自称)なんですからね。ともあれ、そうしてこのときになってようやく気づいたのだけれど、この違和感、痛みの正体は、自己導尿のために、尿道にカテーテルを突っ込まれていることからきているのだった。
男子諸君。ぜひ想像してもらいたい。タコさんウィンナーに管を通されている状況というのが、どのようなものであるか。綿棒をまるごと突っ込まれている感覚というか、それによってタコさんが息も絶え絶えに悶え苦しんでいるというか、いま思い返すだけで、これだけは、二度と体験したくない。まじで。絶対。まだ、腹を切る痛みのほうがはるかに耐えられるというか……。とにもかくにも、「おしっこがしたいのに出ない!」という不能感と違和感と鈍痛が終わりなくつづくのだ。実際には、下腹部に力を入れると、カテーテルを通しておしっこはちゃんと出ているらしい。でも、その感覚はまったくなく、奇妙な残尿感と異物感がずっとそこにあるのである(なお、女性の方が尿道が短いぶんこの点はまだマシらしいです)。
ハラキリの痛み。背中全体の痛み。カテーテルの痛み。これら三重苦を背負わされながら、翌朝をむかえるまで、何十回と、まどろんではすぐ起きて、を繰り返す手術当日の夜なのだった。
11/3(金・祝)術後1日目
昨日の手術以降は、スマホなんて触れる状況ではまったくなく(そもそも枕元にも置いてなかった)、ようやくこの日の朝になって、なんとかスマホをかろうじていじれるぐらいにはなった。術後、医師から妻に連絡が入るはずだったのだが、携帯番号がうまく伝わっていなかったのか、妻には電話がこなかったらしい。そのため、家族にはいっさい安否を知らせる連絡が入らず、心配をかけてしまったようではあった(そのため、妻には「生きてる」の一報のみLINEで取りいそぎ報告)。
患部の状態にかんがみて、この日も、点滴のみとの話があり、あいかわらずの背中全体の痛み(はやく起きあがらせてくれ)と、カテーテルの違和感(はやく抜いてくれ)に引きつづき耐えながら、苦悶する。しているうちに、どでかい機械が個室に闖入してきた。なんと、この寝たきりの姿勢のまま、レントゲンを取るらしい! こんなあちこち管につながれた状態で正気ですか……? とはうたがいつつも、抵抗する余地もないままに、看護師は慣れた手付きでわたしを軽くごろんと横にむけ、すかさずレントゲンの板を背中とベッドの隙間に滑り込ませる。そうして、どでかい機械が、わたしの体に覆いかぶさるように降りてくるのだけれど、この瞬間の、恐怖たるや、さながら近未来型のティラノザウルスに襲われでもするかのごとし。「もし、このままこのティラノザウルスが、なにかのまちがいで襲いかかってきたら、即死だわ、わて」と、いらない不安におそわれる。
ジュラシックパークの恐怖も去ったころ、看護師に、じきに起きあがれるだろうこと、カテーテルも抜けるだろうこと、告げられる。よろこんだのもつかのま、ふと気づいたのだけれども、カテーテルを抜くってことは、この管を物理的に引っこ抜くということであり、ということは、当然それは想像するだにおそろしい痛みをともないそうで、それはそれで、またいやな予感におそわれはじめる。でも、一刻もはやく抜いてほしいのは抜いてほしい。そうして内心びくびくとせめぎあっているうちに、じゃあ、抜きますね、ということでいきおいよくカテーテルを抜いてくれたのだけれども、はい。案の定、めっちゃ、痛かったです。しかも、しばらくは、トイレでおしっこをするたびに痛むかもしれない、ということで、実際、その後2日間くらいは、おしっこのたびに鋭い痛みが尿道を尿とともに奔馬のごとく駆け抜けつづけたこと、一生わたしは忘れないだろう。
ベッドから起きあがるときは、ひとによってはめまいなども起こるそうだけれども、じぶんはさほどの苦労はなかった。とにかく、背中の痛みから解放されること、そのよろこびが大きかった。
でも、結局、何をしたって、腹は痛むんですよね。あたりまえですけど。起きあがったところで、背中じゅうの痛みも、消えないんですよね。頻繁に検温もするのだけれども、38度近い熱もあって、全身、だるい。とにかく、だるい。でも、そんな状態でも、腸が癒着してしまうことをふせぐために、術後1日目だろうが、歩くことが推奨されているのだ(ちなみに、帝王切開で赤ちゃんを産んだりしても、すぐに歩かされるみたいですね。正直、盲腸はつらいよ男はつらいよとかわあわあわめきながら、自然分娩だろうが帝王切開だろうが、世界中のお母さんという存在にはまったくもってかなわないなあ、ともいっそう強く思ったりもしたしだいでした)。
歩け、とは言われたものの、どこをどれぐらい歩けばいいのかわからなかったので、せいいっぱいじぶんを甘やかし、部屋の中をすこしばかりうろうろするのみで、ひとまず満足。いちにち、何をする気もおこらず、倦怠感と痛みに耐えながら、この日はとっぷりと暮れていったのだった。
11/4(土)術後2日目
朝、6時過ぎに起床。夜中になんどか目を覚ましはしたが、昨日よりは深い眠りにつくことができた。多少、全身の痛みやらだるさやらは楽にはなっているものの、熱は、あいかわらず37度台後半から下がる気配がない。スマホやテレビはずっと見ているとだんだんと目も体調もしんどくなってくるので、妻に頼んで持ってきてもらった、『風立ちぬ』を読みはじめる。たぶん、人生で5回目ぐらいの再読。ただ、このときほど、「いざ生きめやも」というヴァレリーの(堀辰雄の訳の)ことばが肺腑にしみたことはなかっただろう。
昼になり、ついにはじめての食事が許される。食事、とはいうものの、いわゆる重湯というやつで(無知なわたしははじめそれを「じゅうゆ」と読んでいた)、固形物はいっさい含まれていない。お粥の汁だけ(?)のような液体と、コンソメスープ。それから、小さめのコーンスープのパックと、やはり小さめのジュースのパック。少量の塩も添えられており、用途がよくわからなかったけれども、たぶん粥めいた液体にかけるのだろうと判断しつつ、小さじスプーンでちびちびと食べはじめる。
最後に食事をしたのが、11/1のお昼だったから、ちょうど3日ぶりに口から栄養を摂取できたわけだ。けれども、少量の液体ばかりのメニューであるにもかかわらず、休み休みでないと食べ進めることがなかなかつらい。実質閉店休業状態だった胃袋に、にわかに大量の発注が届いててんやわんやな感じというか。離乳食をぱくぱく食べてミルクをぐびぐび飲み干しているわが家のファニーボーイよりも、はるかに胃が弱っていることを痛感する。息子よ、どうかおまえにはこの盲腸が遺伝しないとよいのだけれど……。
食後すぐに、最初の便通の気配がにわかに起こる。いや、便通とはいっても、(尾籠な話にて恐縮ですが)ほとんど水のごとき下痢便。ただ、もともと医師からの説明で、しばらくは下痢がつづくと言われていたので、なるほど、こういうことかとむしろ安心した気持ちにはなった。手術をしたのが(大腸の一部である)盲腸であるゆえ、むべなるかな、ということだ。
午後になって、その日の看護師から、ロキソニンと胃薬の支給があった。この日までの看護師は、とくにそういう薬の存在を教えてくれなかったのだけれども、こうなってくると、藁にもすがる思いで、薬に頼る。そうして飲むと、だんだんと楽になってゆく。楽になったついでに、看護師に、「医師から歩けと言われているのですが、どれぐらいの距離でしょうか?」と調子に乗ってきいてみたところ、散歩のめやすは、術後日数×(病室のフロア)10周、だと告げられる。……って、わりと明確な数値目標があったんかい! と思わず心のなかでエセ関西弁で突っ込んでしまったものの、すくなくとも昨日は、病室をうろちょろしただけではあり、にわかに腸の癒着の恐怖にかられる。今日からしっかりと歩かねば……今日はトータル20周だ。ということで、点滴をがらがらひきながら、ひとまず7周ほど歩く。
起きあがって本を読んでは、またすぐに横になり、ぼーっとする。そのくりかえし。気づけばもう夕方だ。夕飯は、ふたたび、重湯、汁物、コーンスープ。それから、スティックの佃煮がついてきた。子規の『仰臥漫録』は、日々、何を食べたかとか、いつ便通があったかとか、まさしく病人然とした単調な(しかし滋味のある)日記だが、ひとつ気づいたことには、子規の食べているご飯にもしょっちゅう佃煮がでてくるということ。この奇跡的な偶然の一致にシンパシーを感じながら、じぶんのなかで正岡子規の読み味わい方も、そのプレゼンスもまったく以前とは変わったことを感じていた。いや、子規の大病と、じぶんの一時的な入院とを類比するのはおこがましいことはなはだしいのだけれども、「禍福錯綜人智の予知すべきにあらず」、こういう子規のことばがしみじみとセンチメンタルに染み入ってしまうくらいには、つらい入院生活であるにはあった。てなわけで、一滴のこさず、佃煮をしぼりとる。
そうしてふたたび夜がくる。消灯は21時だが、それまでに、もう少しだけ歩いておこうと、ふたたび散歩に出向く。すると、歩行を勧められているらしいフロアの病人たちが、ひとり、ふたり、と、わたしと同様に懸命に歩いているではないか。ぐるぐるぐるぐる、ナースセンターのまわりを金魚鉢の金魚のようにゆったりと歩き周り、いや、待てよ、なんだかこの感じ、どこかで実際に体験したことがあるぞ……? と思い返してみれば、まさに皇居ランそのものだった。とはいえ、ここはたしかに皇居にほど近いとはいうものの、病棟だ。しかも、ランではなくウォークだ。ということで、この日、わたしを編集長として新しい雑誌『Byoto Walker』を創刊した(こののち、3号(3日)で廃刊)。
この日は、待ちに待った『進撃の巨人』のアニメの最終回放送日にあたっていたが、放送時間まで起きていられる体力もなかったので、はやばやと就寝することとした。
11/5(日)術後3日目
朝、7時起床。待ちわびた一日がやってきた。というのも、実は、この日の『朝日新聞』の朝日歌壇の紙面のコラム「うたをよむ」に、わたしが書いた文章(「歌を探し求めて」)が掲載されることがきまっていたからだ。わたしはデジタル版の購読者で、紙面は取ってはいなかったのだけれども、当初の想定では、朝一でコンビニに駆け込み、新聞を買いもとめ、全国にじぶんの文章が届けられてゆくことにしんみりとほくそ笑む……というつもりだったのに、なんの因果か、このうえなくベストなタイミングで入院となり、病院で朝をむかえることになってしまったのだった。
が、なんと、看護師にきいてみると、病院の売店で新聞は買えるとのこと。8時の開店を待って、最上階の売店まで足を運んでみると、なんと! さすがは天下の『朝日新聞』。レジの目の前の棚に陳列されているではないか。朝刊一部180円をPASUMOで支払い、売店そばのテーブルにて広げる。ああ、載っている。じぶんの文章が載っている。たくさんの投稿短歌に囲まれながら、誇らしげに、しかしどことなく恥ずかしそうに……。ともあれ、そんな感じでほくほくとした朝ではあった。
その後、8時半ごろ、ロキソニンを飲み、ふたたび、読書をしたり休んだり。そうして昼前ごろだったろうか、ニコライ堂の鐘の音がふいにきこえた。かつてこのあたりに住んでいたころ、なんどとなく耳にした、ニコライ堂の鐘。それがいつになく宗教的な敬虔なひびきをともなってきこえてくるようだ。……などとほざいていたら、スマホを指からすべらせて、お腹の傷の真上にもろに落とすという大惨事が発生。しばしの、苦悶。ぴえん超えてぱおん、ふたたび。
この日のお昼から、三分菜食になる。つまり、固形のものが少し混じるようになる。お粥、汁物、豆腐、大根おろし、液状のヨーグルト。ちなみに、病院食は薄味でまずい、というのをよく耳にするけれども、すくなくともじぶんは、あまり薄味ともまずいとも感じなかった。何日か口から食べ物を入れなかったせい(おかげ)で味に敏感になったのか、それともここの病院のご飯の味付けがちゃんとしているのかはわからなかったけれども。
午後、面会時間に、妻と息子がお見舞いにくる。ただし、病院のきまりで、12歳未満は病室に入れないことから、母親にもきてもらい、妻の面会の間に息子の面倒をみてもらうことに。母親に息子(ベビーカー)を託しつつ、妻はパジャマ用のシャツなどを届けてくれ、不要な荷物を持ち帰ってくれた。病院の1階に、ガラス扉で外が見えるところがある、と看護師が親切に教えてくれたので、妻と向かう。そこで、息子とも、4日ぶりの対面をはたす。が、こちらからは外が見えているものの、外からは光の反射で内部が見えづらかったらしく、息子と目線がぜんぜんあわない。妻から引き離されたためにギャン泣きしたのか、涙をいっぱいに溜めていて、なんとも愛おしいというか、このガラス扉を突き破って抱っこしてあげたいような気持ちに駆られる。その後、妻と母親がバトンタッチし、妻と息子は帰宅。母親もしばし病室で面会ののち、帰宅した。
この日の夕方、ついに点滴が外れた。外れたちょうどそのころに、隣室からは笑点の曲がきこえ、ああ、まちがいなくいまおれは快方に向かっているようだ、という感がここでにわかにわいてきた。そうだ。点滴も外れたし、めいっぱい散歩をしよう。ということで、イヤホンをして、病棟ウォーク。あいみょん、藤井風、aikoなどを聞きながら、ぐるぐると歩き回る。病棟ウォークは、J-POPにかぎる。
夕飯は、お粥、汁物、鶏団子、ゼリー。そうして消灯。点滴もなく腕が自由な状態で眠れることの自由を謳歌しつつ、やすらかに、入眠。ちなみに、11/5は本居宣長の命日らしい。
11/6(月)術後4日目
朝一の検温は、36.6度。このとき、入院以来、はじめて37度を切った。体調も、わるくない。朝の採血ののち、朝食が運ばれてくる。この日も朝は三分菜食で、メニューは、お粥、汁物、ヨーグルト、魚のすり身、かぼちゃ。ぺろりとぜんぶ平らげる。
その後、別フロアにてレントゲンをとる。このときすでに、通常の7割くらいの速さで歩けるまでには回復した。ただ、まだなんとなく傷口がぴきぴきするようではあるので、ゆっくりと歩く。採血およびレントゲンの結果、翌日以降に退院は可能とのことなので、となれば、善はいそげ。さっそく妻と母親に、明日に退院する旨、連絡する。
この日、入院以来、はじめてのシャワーを浴びることもできた。これまでは体は濡れタオルで拭くのみで、頭だけは個室にそなえつけられた洗面台で洗うことができたものの、洗面台の高さまで腰をかがめたり、ひざまずいて洗ったり、とにかく大変だった。約6日ぶりのシャワーで身を清めつつ、ようやくひとりの人間としての主体を取り戻しつつあると感じる。
……だが、実はこのとき、腹の痛み以外のところでちょっとしたトラブルにおそわれだしていた。というのは、お腹には3か所の切開跡があり、そのそれぞれが、綿(?)のようなもので保護され、さらにその綿(?)を固定するために、養生テープ(?)のようなものがお腹全面に貼られていたのだ。シャワーに入るタイミングでそれらの綿とテープは外れたものの、テープを何日間も直に肌に貼っていたためか、お腹の皮膚がそうとうにかぶれていたのである。
これが、痒いのなんのって……。もともと皮膚の弱さには自信があったのだけれども、なかなかのかぶれように、さすがに看護師も医師も心配したのか、軟膏を届けてくれた。実は、お腹だけではなく、ふくらはぎまでかぶれていて(2日間ほど履きつづけていた着圧ソックスのせい)、この前日の夜中から、その痒みとの戦いがはじまっていたのである。一難去ってまた一難。軟膏を塗りたくりつつ、だましだまし、なんとかやりすごす。
この日の昼から、五分菜食がはじまる。お粥(三分菜にくらべるともうすこしとろみがある)、中華スープ、南蛮漬け、野菜ジュース、煮物(里芋、にんじん)。夕飯は、お粥。コンソメスープ。鶏団子(トマト煮)。ツナサラダ。ぶどうゼリー。
この日も例によって、タイミングをみて日に何度か病棟ウォークをする。やはりイヤホンをしながら、JUNG KOOK、New Jeansなどを聴く。前言(前日の言葉)撤回。病棟ウォークはK-POPにかぎる。ちなみにこの日は、父親の誕生日だった。就寝。
11/7(火)退院
お腹の痒みで、夜中に目が覚める。とにかく、掻きつづけていないと、つらい。いや、掻いてはいけないと頭ではわかってはいるものの、お腹全面がかぶれまくって、とても耐え抜くことができない。指先が勝手にぼりぼり掻きむしってしまう。もそもそと起きあがり、軟膏を塗り、ひたすら痒みに耐えながら、ふたたび眠りにつく。
7時、起床。この日は、朝から雨。検温をすると、37度台に逆戻りしていた。だが、それほどのだるさは感じられない。その後、医師の回診を受け、問題なく退院できることを確認する。最後の病院食(朝食)は、全粥、汁物、豆腐の味噌煮、ほうれん草のおひたし、ジョア。
この日の10時に母親が車で迎えにきてくれる手はずになっていたので、荷詰めを済ませたのち、退院までの時間をしみじみと病室ですごす。思い返せば、腹痛におそわれながら病院をたらい回しにされ、命からがらこの病院に駆け込んだのが6日前。それからまるまる一週間、この個室に寝泊まりしていたわけだ。入院の最後の時間は、これも家族に頼んで持ってきてもらった、笹井宏之の『えーえんとくちから』を読んで過ごす。
最後に、会計を済ませる。このとき明らかになった入院費用は、総額28万円。ふつうに、ヨーロッパ旅行一回分くらいの金額が吹き飛んだ。なお、そのうち、差額ベッド代(個室代)が約19万なので、手術・入院にかかる自己負担分としては、約9万円ほどだった。これを高いと考えるか、人生経験代と考えるか、いのちの重み(?)と考えるか……。差額ベッド代については、医療費控除の対象にもならないし、はたして費用対効果があったかどうかは悩ましいけれども、1点、メリットをあげるとすれば、トイレのついている個室だったことはよかったと思っている。というのは、点滴のせいか、入院中は頻繁に尿意をもよおし、1〜2時間に1回ぐらいはトイレに駆け込む、みたいな感じではあったので、それが毎回、大部屋やトイレのない個室だと、フロアのトイレまで点滴を引きずりながら毎回向かう必要があり、それはそれで大変だったと思うからだ。入院という非常事態のときくらい、お金で解決できるものは解決してしまったほうがよい気もするし、とはいえ、それにしてもかかる費用が高すぎるような気もするので、この辺は、個人の価値判断によるだろう(というか、じぶんの場合は、緊急入院だったのでそもそもの病室の選択肢がなかったわけだけれども)。
というしだいで、ついに、退院となる。病院をあとにするころには雨もあがって、御茶ノ水らしい慌ただしい活気に満ちていた。6泊7日の入院生活。怒涛の、怒涛の、日々だった。
エピローグ(反省と教訓)
以上、入院時のメモをもとに、入院した一週間のレポート(エッセイ)をまとめたわけだけれども、最後に、今回の経験を踏まえての反省(?)と教訓を書き残しておこうと思う。
まず、「そもそも予兆はあったのか?」ということから。盲腸の「予兆」については、正直、それをじぶんで把握することは難しいように感じた。というのは、確かに、ときどき、食後にすこし胃もたれがするなー、とか、軽い腹痛があるなーとか、そういう感覚におそわれることがないでもなかったけれども、それが「盲腸の可能性」であると想到することはかつていちどもなかったからである。もし、軽い腹痛でも病院に行ってみる、といったひとであれば、おそらく採血をしたりCTをとったりすれば、軽度の段階で盲腸だと気づくこともできたのだろう。でも、わたしは、これまでは比較的健康的な体ではあり(健康診断でも基本オールA)、よほどのことがないと病院には行かない、というタイプで、それがかえって災いしたのか、緊急入院というかたちになってしまった。健康である(という自負)が慢心の原因となり、こうして病状の発見が遅れてしまう。そのことの怖さを、身をもって体験したしだいではある。
つぎに、「日頃の生活習慣はどうだったのか?」という話。わたしは、タバコも吸わないし(26歳くらいでやめた)、酒もふだんはほとんど飲まない。ふつうに自炊もしているし(ただし夕飯を食べるのはいつも夜の21時過ぎごろ)、暴飲暴食をしているということもないと思う。運動だって、欠かさずしている(ここ10年以上、毎週1回、プールで2kmほど泳いでいる)。それでも盲腸を発症してしまったのは、まずは、すでに書いたけれども、遺伝の可能性があるということ。あとは、少し、疲労や睡眠不足も重なったタイミングだったということ。もっか、育児まっさかりではあり、日ごろの生活サイクルとしては、6時過ぎに起床し、出社し、19時ごろ帰宅し、子どもをお風呂に入れて、ミルクを飲ませ、寝かしつけをして、それから夕飯をつくり、妻と分担して皿洗いをしたりごみをまとめたり、そうして離乳食をつくらなければいけない日には妻の手伝いをする、という感じだ。入院となったその日は、日付をまたぐまで離乳食をつくっており、しかも、3時ごろに子どもの夜泣きで起こされた日だった。そういうタイミングで過労がピークにあったのかもしれない。
そのつぎに、「医療保険には入るべきか?」という話。これは正直、今回の手術や入院を経たいまになっても悩ましいことだとは思っている。わたしは、住宅ローン関係の保険(いわるゆ団体信用生命保険とか、7大疾病に罹って職場復帰できなくなるとローンがなくなく保険とか)には入っているのだが、医療保険は契約していない。もし今回、医療保険に入っていれば、差額ベッド代だろうが、入院一日あたりいくら、といったかたちでの支払いがあったはずだ。医療保険に入ってこなかったのは、やはりわたしに、永遠に健康であろうという根拠なき慢心があったからではあり、だからこそ、今回のことを奇貨にして保険を見直す、という選択肢も考えられなくはない。ただ、どうしても保険の勧誘、というものには信用がおけず、勧誘されて契約するつもりはないので(勧誘されるほどますます入りたくなくなる)、じぶんでじっくり考えようとは思う。
最後に。今回の入院を経て、やはりいちばんに感じたのは、医療従事者の尊さである。とつぜんの発症だったにもかかわらず、あたりまえのように日夜看病をしてくださった看護師のかたがた、そして執刀にあたってくださった医師のかたがた。これまで大病をわずらったことがなくはじめて長い病院生活を送ることになったからこそ、医療にたずさわるかたがたのありがたみというのをひしひしと肌身に感じる日々だった。
それから、なによりも家族に、感謝。あまりに急な入院ではあったけれど、翌日には必要な一式を用意して届けてくれ、見舞いにもちょくちょく来てくれた(これ、もし地方を離れて東京で一人暮らしをしているようなひとが同じ状況になったとしたら、いったいどう切り抜けていたんだろう……? と思ってしまう)。特に、1週間ものあいだ、子どものワンオペ育児を完遂してくれた妻には心から感謝したい(たぶん、じぶんだったら1週間のワンオペ育児には耐えられそうにないだろうな……)。
まさかの結婚記念日の緊急入院。ささやかなお祝いのケーキを食べることすらかなわなかったけれども、いずれ、有休をとって、ケーキを買って、ビーフシチューをつくって、快気祝いもかねてのあらためてのお祝いができればと思う。
みなさんも、うたがわしい腹痛には、くれぐれもご用心ください。気づけばここまでで1万6千字をゆうに超えていたので、これにて擱筆。
最後までお読みいただき、まことにありがとうございます。いただいたサポートは、チルの餌代に使わせていただきます。
