
展評|一望された建築と空間体験の宙吊り――CINE間 中山英之展
Gallery間がCINE間になった。ギャラリーではなく映画館だ。どうやらよく見る建築展とは違うようである。どんな建築映画をみせてくれるのだろうと、期待してフライヤーを眺めながら会場に入ると、すでに上映が始まっていた。
ここで上映されているのは、5つの建築をめぐるドローイングとそれらの映像からなる空間のイメージである。本展示は、建築と映画のそれぞれの空間のイメージから、建築を上映してみたり、映画を設計してみたり、と双方のメディアを行き来するような表現を見出している。プロジェクターによって映し出された建築の陰影など、今までの建築展には見られない表現がみられる。

建築を上映とは言ってみたものの、ふつう空間は体験されるということはあっても、空間が上映されるということについては言わないし、あまり考えることもないように思われる。しかし、もし観客がCINE間を鑑賞する上で、建築的にではなく映画的に鑑賞するのであれば、CINE間を”空間の体験”というよりも、”空間の上映”と言った方が豊かな鑑賞ができるのかもしれない。
3階から会場に入ると、模型とドローイングのここでの特別な関係からそれがわかる。その前に少し立ち止まって一呼吸おいて、建築の空間体験について考えてみたい。
一般に、実際の建築の空間体験においては、一度に空間の全容を見渡すことができない限り、何度も多くの部分の空間を見回すことになる。それは部分的な空間の把握から始まり、内部を動き回ることでやがて全体像へと統合される。建築が大規模で複雑になるにつれて、その過程は多く繰り返されていく。
一方で、建築の展示会の場合には、先に模型によってある程度全体像を把握した上で、模型を見回して擬似的に実際の空間体験を行う。この際、部分の空間へと想像が注力されて、元の模型と照らし合わせながら新たな全体像へと統合される。
実際の建築も、展示の模型も、部分から全体への過程において、様々な形態や細部が織り交ぜられて、鑑賞者に複合的な空間体験をもたらす。と同時に、一連の過程において統合されるまでに時間差が発生し、また体験者の順序によっても統合の様子が異なる。当然、同じ建築空間であっても、鑑賞者によって空間体験が異なる。例えば、桂離宮の複雑な平面は、同時に見ることはできず、鑑賞者の訪れる順序によって受ける印象は全く異なってくる。(註1)

それでは、CINE間の会場に戻ると、先述のような建築の展示会の空間体験の過程をちょうどひっくり返したようなドローイングと模型に出会う。それは模型の前に多くのドローイングが並べられている。このドローイングでは、統合された建築空間の全体像が、一つ一つの特徴的なシーンへと断片化されている。そして、シーン間で何かしらのストーリーを描くようにして、シークエンスとして建築空間が並び直されている。
このシークエンスによる建築空間の並びが、展示における建築の部分から全体への過程と逆に、全体像をよりも先に部分を提示してから、そこからストーリーを読み取らせるように全体像を想像させる。シークエンスから次々とやってくる想像された全体像は、”空間の上映”として、鑑賞者に受容される。
ところで、上映されるドローイングのシーンは、建築空間をありのままに伝える視点よりも、誰かが思い出した記憶が混ざったかのような漠たる建築の一部のようであり、あくまでも想像上の空間である。そこでは、統合された空間の確固とした全体像よりも、あいまいな余白を残した空間の部分が集まっている。その余白は鑑賞者へ、一見何ともない日常生活の情景の中に、描かれた人々の心に横たわる欲望の瞬間を浮かび上がらせている。同時にそれは、内側が外の世界へと反転された箱庭のようでもあり、逆にそこが俯瞰されるところに作者の情動が隠れている。
一方で、ドローイングから模型へと全体像を観ると、模型の造形は複雑であり、通常のカタチというよりも、トポロジカルなつながりによって構成されている。となると、全体像を一望するには難しく、必然的につながりを辿っていくいことで全体像が把握される。この過程で、先の連続するシーンが重なってくる。模型とドローイングの組合わせが重合されて擬似的な空間体験を生み出している。
ドローイングが箱庭のように思われたのも、どこかに擬似的な空間体験が感じられたからだろうか。箱庭といえば、そういえば先述の桂離宮の造園において、各々の巡路の造られた時代が異なり、それらが断片的が重なるように受容されることで、その時間の重層性によって、より複雑な不意の美を生むとされている。(註2)
そして、三階で観たものを何となく覚えておいて四階で上映されている映像作品を鑑賞する。どうやら、四階の映像でも三階の模型とドローイングで試みられていた空間体験は続いているようだ。しかも、より、明確に、である。
例えば、ある映像作品では建築の複雑な幾何学的形式をスクリーンの形式へと変換してカメラの動く方向の設計によって、また別の作品では建築の三面図のように多方向の観測点の重ね合わせによって、それぞれの建築空間を一望可能にしてみせている。
すなわち、ここでも、本来一望不可能だった立体を、不思議なハサミによって、一望可能な平面に展開しているのである。
三階では一般的な建築模型の空間体験の全体→部分の過程を、模型とドローイングを用いて部分→全体へと転倒させた上で新たな情景と重ねることで、擬似的な一望可能性=全体像を生み出していたが、四階では、映像における視点の複数性と同時性を上手く駆使することによって、スクリーン上に空間を再配置して、文字通り一望可能性を生み出しているのである。
この映像の一望可能性の空間体験から、かつて19世紀に映画が生まれる前に映画の原理にもなった、ステレオスコープによる空間知覚を思い出す。ステレオスコープとは、わずかに角度や位置の異なる視点による画像を重ね合わせ立体像を作る装置である。ステレオスコープが絵画や写真と異なるのは、そこに多層的な平面が前後されていることであり、バラバラで不統一な画像の寄せ集めからなっているという点である。(註3)

ただし、同じ寄せ集めでも単にモンタージュというよりも、ステレオスコープによる空間知覚は、角度や位置のズレといった、人間の両眼の視差のような、より身体的な空間認識に近い。それのみならず、それは確固たる一つの統一的な空間よりも、流動する複数化された空間(註4)であり、本展示の複雑な立体形状にも近い。
いずれにせよ、三階にしても四階にしても、CINE間においては、部分と全体の反転や、空間の重層化による一望不可能性の反転、といった新たな空間体験を、鑑賞者の身を以って示してくれている。そして、その新しさによって、観るものと観られるものの関係さえ、空間的にひっくり返してしまっているかもしれない。CINE間の鑑賞者は建築を観に来たのではなく、実は建築によって観られていた私たち自身。筆者は表現の端々からそういった視線を感じて、実は少し気味悪さも感じていた。もちろん展示はよくできていて、圧巻だったから、こそ。
CINE間のトリックは、展示会という既存のフォーマットさえをも逆さにしてしまう、スリリングな空間体験の宙吊りを私たちに上演している。さしずめ建築のサンスペンスといったところだろうか。
(註1)中谷礼仁 『セヴェラルネス 事物連鎖と人間』 鹿島出版会 2005年 p.36
(註2)同書 p.45
(註3)J・クレーリー『観察者の系譜: 視覚空間の変容とモダニティ』 以文社 2005年 p.184,186
(註4)同書 p.190

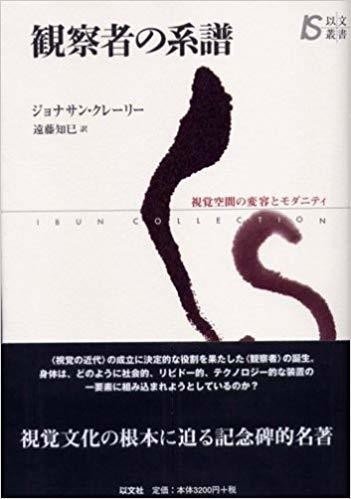
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
