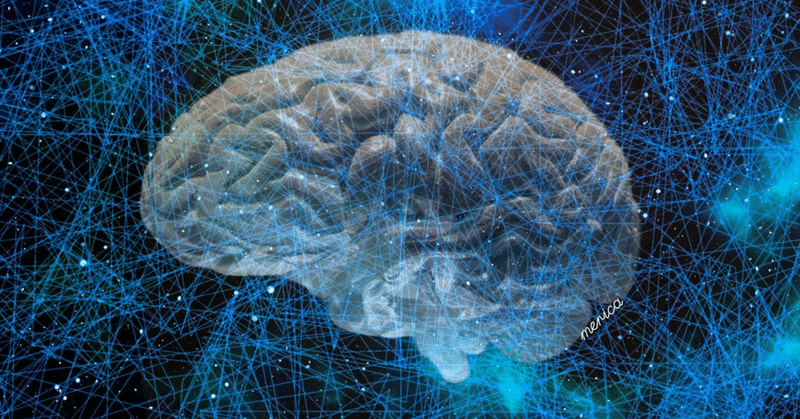
TureDure 33 : 即興ができることは頭の回転がはやいということなのか ― 能力神話へのアンチテーゼ
私は即興を学んだり、教えたり、パフォーマンスしたりする。私がするのは「インプロ」と呼ばれる即興演劇のメソッドを基盤にしたパフォーマンスである。即興演劇はその名の通り、台本もなければ、あらすじもなく、配役も事前に決まっておらず、どのように始まり、終わるのか、だれがどんなセリフをいつ言うのか、いつ照明がついて消えるのか、いつ音楽が流れ、途切れるのか、歌うのか、踊るのか、戦うのか、抱き合うのか、愛し合うのか、殺し合うのか分からない演劇のことを指す。
「頭の回転が速いですね!」
「パパっと情報を瞬時に処理してるんでしょうね!」
こうした言葉をいただくことがある。経験上、インプロのパフォーマンスをする能力と脳はよく結び付けられる。そして、その時に暗に示されているのは、「即興ができるのはある特定の資質によるものだ」、すなわち、“脳の出来”によるものだという考えであると感じる。あるいはそこまでいかなくとも「即興をするには頭をフル回転させないといけない」とか、「即興ができる人は頭がいい」とかそうしたハイパフォーマンスな脳が即興を可能にするという図式があるのではないかと思う(そして、たいていの場合、こうした図式を用いて「私/あの人には即興ができない」ということを説明することが目的だったりする)。そのため、本稿では即興することにおける脳科学(的)の蓄積を概観し、果たして即興をすることは脳とどのような関係があるのか、インプロと脳科学の双方から照らし出し、その上で私の所見を述べてみたい。
もちろん私はインプロの専門家ではあるが、脳科学の訓練を受けたわけでもないド素人である。そのため、本稿で展開する私の勝手気ままな推察はとんでもない勘違いや事実誤認を含む可能性が大いに高いことを考慮していただけると幸いだ。こうした点に関しては私の友人の中に脳科学を専門とする人がいないということがなんとも歯がゆいものである。もし、本記事を読まれている脳科学に明るい人がいれば私の誤りを指摘してほしいと思う。
まずはインプロから脳について見ていってみよう。私の行うインプロにおいて、脳への言及は多く、かつ興味深いことに実は先ほどの考え(即興するにはある能力(特に脳において)が長けている必要がある)とは異なる立場にある。すなわち、即興で演劇するという行為においては、能力を上げるのではなく、むしろ“ある種の能力に黙っておいてもらう”必要があるということだ。
インプロには様々なスタンスと方法論が混在しており、それらは日々更新されている。しかしおおよそのハウツーには理論的前提があり、おおむねその思想を元に展開されている。その理論的基盤を形作った一人がキース・ジョンストン(Keith Johnstone)である。ジョンストンはインプロの教育について理論的・技法的に多くの知見を発見しており、彼の理論はパフォーマンスにおいても、教育などの応用的な分野においても世界中に影響を与え続けており(Dudeck, 2018)、私もその恩恵に預かっている一人である。ジョンストンのインプロは時おり脳の機能、特に前頭葉の機能と共に説明がされる。では、ジョンストンは即興と脳の関係についてどのように述べているのか。
私たちが自分たちの中にある力を信じていない時に、私たちは頑張ろうとする。それぞれの脳は電気の束から宇宙をつくり上げている―脳がなければ宇宙もない―私たちは頭蓋骨の中にこの魔法のコンピューターを持っているにもかかわらず、もし絵を描けないとか、作曲できないとか、物語を書けないとか、即興できないと感じるならば、私たちは何かしらの禁止令に従っているに違いないのだ。(Johnstone, 1999 , p.67, 訳は引用者による)
ジョンストンはこのように、即興することだけでなくアート活動一般と脳の関りについて言及している。ここで重要なのは、その言及の仕方である。ジョンストンは、脳はそれ自体であらゆるアート活動が可能であると考えている。それにも関わらず、もし自分はアート活動ができないと感じるならば(実際に多くの人がそのように感じていると思われる)それは何らかの外的な作用によって”できないようにさせられている”(=禁止令に従っている)と考えている。すなわち、ジョンストンにとって、即興することこそ自然なもので、「即興ができない」という自己感覚こそが後天的に学習された一種の”能力”だと考えている。
ジョンストンはこのような前提に立っているため、即興を不可能にしているあらゆる外的なものを取り除いていく教育手法を用いる。その「外的なもの」のうち本稿で注目すべきは言語や社会性などを扱う前頭葉へのアプローチである。即興を難しくさせる「外的なもの」をあつかう前頭葉が生み出すものとしてジョンストンは「社会的こころ」(Social Mind)という言葉を用いる。私たちが社会生活を営む中で獲得されていった社会性や社会的自己が、即興することを難しくしていると指摘するのである。
例としてジョンストンがどのようなワークをして社会的こころを抑制していくのか2つご紹介する。
1つ目。ジョンストンにとって社会的こころは主に言語的な思考と関連していると考えられているため、言語的に混乱させることで意図しない表現を引き出すアプローチをとる。代表的なものは「マントラ」と呼ばれるエクササイズで、シーンを行う過程で常に「あなたが好き」と唱え続けながら行うというものだ。そうすることによって「このセリフを言ったらこう動こう」といった策略が封じられ、意図しない自動的な身体的表現が生まれやすくなる。
2つ目。ジョンストンは「仮面」と「トランス状態」に着目する。それは社会的自意識の混乱と、それに伴う即興的な自己が現れ出でることを企図してのことだ。「トランスマスク」と呼ばれる仮面のエクササイズによって俳優を一時的にトランス状態(ゾーンあるいはフロー状態とも呼ばれる超意識的状態の一種)へと引き込むことも、社会的自意識を一時的に抑制し、より自動的で即興的になるためのものだ(注1)。
ここまでの論を踏まえると、キース・ジョンストンのインプロは即興と脳の関係について次のように考えていることが分かる。すなわち、「インプロは脳という宇宙を自然に機能させることで可能になる。しかし、その機能は社会的こころが生み出す自意識や言語的思考によって妨害されている。そのため即興を可能にするためには社会的こころをあつかう前頭葉的な機能を混乱あるいは抑制する必要がある」である。
とはいえ、こうした前頭葉的機能と即興の関係はジョンストンの空想に過ぎないともいえるかもしれない。それはひとえにジョンストンは脳科学者ではなくインプロの教師であるためだ(実はジョンストンも好んで科学系学術雑誌を読むので、あながちただの空想ではなく一定程度科学的な知識に基づいているのであるが)。そのため、次は脳科学あるいは認知科学から即興という現象を眺めてみよう。
先のジョンストンの論理(即興のためにはある脳の機能を抑制する必要がある)を間接的に裏付ける研究がある。Limb & Braun (2008)はジャズピアニストの即興演奏中の脳内の血流を、fMRIを用いて測定している。得られた結果は非常に興味深い。即興中の脳内の活動は、前頭前野内での複雑な活動パターンに特徴づけられる。すなわち、前頭前野の広範囲が不活性化しながら、ある一部分は活性化させるという解離した活動をしているのである。前頭前野は担う役割は主に、複雑な認知的行動に加え、人格の形成、結果の予測、そして、社会的なコントロールが行われる。これはジョンストンの「社会的こころ」が行うことと非常に関連している。

青くなっている部分は不活性化が見られている部分で、オレンジになっている部分が活性化している部分である。感覚運動中枢の活性化と共に、前頭前野の中で一部分だけ活性化している部分がある。ここは内側前頭前野(MPFC)の前頭極、つまり最も前方の部分に当たる。この部分は大脳新皮質の解剖学的な区分であるブロードマン領野における「10野」と呼ばれる領野である。Limbらは議論として「自分で生み出した表現を自分で認識する」という内側前頭前野の働きを、外的な評価や監視を気にする外側前頭前野(LOFCやDLPFC)の働きを抑制し、自己生成的な行動(自発的な活動、すなわち即興と呼べる)が内側前頭前野の働きによって可能になることを示唆している。
この研究に関してはTED TalkにてLimb氏がプレゼンテーションを行っている動画もあるので興味のある方は見てみてほしい。実際にピアニストがfMRIに入って特別なピアノを用いて即興演奏をするのを実際の映像で見ることができる。
私がこの研究結果から非常に興味深く思うのは内側前頭前野の自己内省的な働きもそうだが、その前頭極、ブロードマン領野の「10野」についてである。この部分は別名、吻側外側前頭前野と言い、英語だとrostrolateral prefrontal cortex:RLPFCと呼ばれる。このRLPFCはDancing Einsteinの青砥瑞人氏が「不確かさドリブンの探索機能」として不確かなことに希望を持つための脳の機能だと紹介する領野に該当する(注2)。
RLPFCの機能に関してはDesrochersら(2015)の研究がこのことを裏付けている。この研究では不確実性を克服するためにRLPFCのみが役立っているとは言い切れないが、少なくとも不確実性の対処のために必要な領野の1つであることは言え、かつ、あるタスクをこなす流れの軌道に乗っておくために(keep us on track)必要だと結論付けている。不確実性に対処するのみならず、なんらかのタスクを処理する時の流れ(フロー?)に身を任せるときに必要な領野なのだということが明らかにされている。
即興中に前頭前野の広範囲が不活性化する一方でこのRLPFCが活性化していることを私なりに意味づけるとしたら次のように推察する。通常、私たちは社会生活を営みながらあらゆる考えやアイデアを自然に生み出し、セルフモニタリングしている(内側前頭前野の働き)。しかし、私たちはこうした考えを社会的な評価に値するかどうか、その表現が社会的にどのような結果を生み出すのかのリスクヘッジも同時に絶えず行っている(外側前頭前野の働き)。そうしたリスクヘッジが自分の生み出したアイデアの表現を検閲し、その流れをせき止めている。
その結果、即興を困難にさせているため、外側前頭前野の働きを抑制することで自分の中から出てきたアイデアの自己検閲が行われないようにすることで即興的活動を可能にする。そして同時に、先行きの見えない、どうなるかもわからない状況に対処しながら、自分の中に浮かび上がるアイデアの波に乗り続けるために吻側外側前頭前野(RLPFC)を活性化させる必要があるのである。
さて、ここからもう一度インプロから脳科学を眺めてみたときにどのような景色が広がるだろうか。ここで注意深く洞察をすると、ここまで個人の話にのみ終始しており、即興があたかも自分の内側から沸き起こってくる衝動性を呼び覚ます非常に能動的な、”本当の自分”の表出であるような、ある種のロマンティックな論理へ導かれるように思う。
しかし、ことはもう少し検討が必要である。なぜなら、即興とはパッシブな側面、つまりソーシャル/社会的に方向づけられた受動的な活動でもあるからである。即興が単に脳内のみで起こることではなく、特定の文化的・社会的コンテクストを参照しながら、そして他者のふるまいに依存しながら起きているのは間違いない。こうした私たちの即興的なパフォーマンスが社会的な呼びかけによって一定程度強制もされていることを指摘しているのは拙記事「パフォーマンスとジェンダー」においても言及した哲学者ジュディス・バトラーである。私たちは日々社会的な規範の枠組みの中で即興して生活をしており、たとえパフォーマンスとして即興をするにしてもそうした社会的な規範を断ち切ることはできないし、むしろ社会的なものに助けられながら即興をして社会規範を積極的に繰り返し、強化している側面も否定できない(Butler 2004)。
即興はこのように個人的であると同時に非常に社会的な性格も持ち合わせた活動である。即興のこうした特徴は何も目新しいものではない。先に紹介したキース・ジョンストンをはじめ、同じくインプロの理論的基盤として重要な存在であるヴァイオラ・スポーリン(Viola Spolin)、デル・クローズ(Del Close)などの思想において、個人が創造的になるために他者や集団、外的な環境へと注意を向けること、そして即興は何ものにも縛られない完全な自由ではなくむしろ構造によって自由は可能になることの重要性は指摘され、実践されている(Sawyer, 2008 ; Drinko, 2013)。
以上の検討を経て、私が最初に提起した問題に立ち戻りたい。即興が可能になるのは脳の働きによる能力なのかどうか、という点に関して、一定程度の妥当性があると言えるだろう。即興中、脳は前頭前野において特徴的な働きを見せるからである。しかし、それが何かのパロメーターが増大する「できなかったことができるようになった」能力ではなく、大部分はむしろ自分のアイデアについて社会的な評価に値するかどうか、その表現が社会的にどのような結果を生み出すのかという自己検閲ををしないようにするという「普段行っていることをやらないようにする」能力であると言えるだろう。しかし、だからと言って個人的な能力開発のモデルで即興を捉えるのは留保が必要だ。なぜなら即興は文化的実践であり、文化の中で生まれながら文化を遊ぶ非常に歴史的・社会的・文化的な現象であることを忘れてはならない。
この記事では便宜上、脳の存在をかなり重みづけして取り上げてきた。しかし後半部分でも指摘したように即興は非常にソーシャルな現象としても考えられるべきであると私は考えている。そして、脳に関する情報が非常に説得力を持ちやすい文化に生きているからこそ、即興を個人的な能力とみなしやすいバイアスの存在があるのではないかと考えられる。それはすなわち、私たちがいかに自分自身と脳を同一視しているかというアイデンティティの文化にどっぷり浸かっているかを示しているだろう。
私がインプロに感じる魅力の1つはそうした文化的なゲームにおいて能力を上げ、できることを増やし、強くなるのではなく、そのゲームから降りながらも生き延びることのできる抜け道をもインプロは示してくれるからでもある。
【注】
注1:ジョンストンの場合、この仮面のエクササイズにヨーロッパ的文化との摩擦を指摘する。すなわち、「自分はどこにいるか」というのは文化的に構築されるものであり、国によって「自分」の居場所は異なる。ヨーロッパの場合は自分の居場所は「頭の中」すなわち「脳」に置く文化だが、これが仏教圏になれば「丹田」になり、ミクロネシアなどの場合「どこか/どこにでも」という場合もある。ジョンストンが試みる仮面のエクササイズにおいてはこうしたヨーロッパ式の「自分=脳」という方程式を解体するものと言える。そのため、こうした前提を踏まえるとジョンストンのインプロを脳機能から考えるというのはそもそもジョンストンの狙いと論理矛盾があるとの批判が考えられる。
注2:https://careerhack.en-japan.com/report/detail/1284
【参考文献】
苧阪直行 (2007) 「意識と前頭葉―ワーキングメモリからのアプローチ」, 『心理学研究』, 77(6) , pp.553-566
園部友里恵 (2021) 『インプロがひらく〈老い〉の創造性―「くるる即興劇団」の実践』, 新曜社
高尾隆 (2006) 『インプロ教育―即興演劇は創造性を育てるか?』, フィルムアート社
三村將 (2007)「前頭葉と記憶―精神科の立場から」, 『高次脳機能研究』, 27(4) , pp.278-289
虫明元 (2006)「認知的行動制御の神経機構」, 『東北医学雑誌』, 118(2) , pp.125-128
虫明元 (2018) 『学ぶ脳―ぼんやりにこそ意味がある』岩波書店
山下洋輔・茂木健一郎 (2011) 『脳と即興性―不確実性をいかに楽しむか』PHP新書
Butler, J. (2004) "Undoing Gender." Routledge.
Charles J. Limb and Allen R. Braun (2008) "Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: An fMRI Study of Jazz Improvisation." PloS One, 3(2)
Drinko, C. (2013) "Theatrical Improvisation, Consciousness, and Cognition." Palgrave Macmillan.
Johnstone, K. (1999) "Impro for Storytellers : Theatresports and the Art of Making Things Happen." Faber and Faber.
Siddall, G and Waterman, E (eds.) (2016) "Negotiated Moments ; Improvisation, Sound, and Subjectivity." Duke University Press.
Desrochers, T and Chatham, C and Badre, D (2015) "The necessity of rostrolateral prefrontal cortex for higher-level sequential behavior." Neuron, 87(6)
Sawyer, K. (2008) "Group Genius : The Creative Power of Collaboration." Basic Books. ( キース・ソーヤー(2009) (金子宣子 (訳) )『凡才の集団は孤高の天才に勝る―「グループ・ジーニアス」が生み出すものすごいアイデア』ダイヤモンド社 )
Theresa, D and McClure C (eds.) (2018) "Applied Improvisation : Leading, Collaborating, and Creating Beyond the Theatre." Methuen Drama. (テレサ・ロビンズ・デュデク & ケイトリン・マクルア―(絹川友梨(監訳))(2020)『応用インプロの挑戦―医療・教育・ビジネスを変える即興の力』, 新曜社)
【参考HP】
https://careerhack.en-japan.com/report/detail/1284 (最終閲覧日 : 2021年5月13日)
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kaigai/1265708.html (最終閲覧日 : 2021年5月13日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
