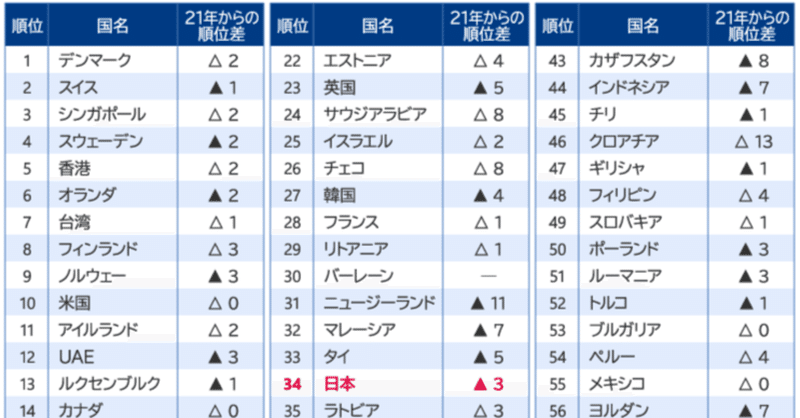
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の調整に関する法律案」略称「民事整備法」について調査しました。(政治家女子48党の参議院浜田聡議員のお手伝い)
1・行政サービスのデジタル化
この法案の詳細を見る前に、昨年から行政サービスのデジタル化への法案が一気に出ています。
この流れを押さえつつ、今回調査した「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の調整に関する法律案」略称「民事整備法」を見て頂きたいです。
・2022年2月デジタル庁法案提出:情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案
・2022年3月法務省法案提出:民事訴訟法等の一部を改正する法律案
・2023年3月デジタル庁法案提出:デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案
・2023年3月法務省法案提出:民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の調整に関する法律案
・2023年3月法務省法案提出:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案
・2023年3月:公正証書作成のデジタル化も検討
行政に詳しくない方は参考にどうぞ(#^^#)
今回の調査テーマの「民事整備法」は、令和5年3月14日第211国会に閣法にて法務省から提出され、参議院の「本院先議」で審議されます。
民事関係手続とは、個人間の法的な紛争で、お金の貸し借りや不動産売買、交通事故などによる損害賠償などの裁判所で行われる訴訟の事です。

令和5年3月14日(火)に法案の内容について、法務大臣が閣議後記者会見で説明しています。
『まず、「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、令和4年の民事訴訟法の改正を踏まえ、民事訴訟以外の民事関係手続のデジタル化に関する規定を整備することなどを内容とするものです。
例えば、判決等に基づいて債務者の財産を差し押さえ、債権を回収する民事執行の手続などにおきまして、これまで紙の申立書を提出することによってしていた裁判の申立てを、インターネットを利用してすることができるようにしています。これによって、国民の皆様が民事執行の手続などの民事関係手続をより利用しやすくなることにつながるものと考えております。』
令和4年の民事訴訟法の改正とは、下の図の「民事訴訟法等の改正に関する法律」で法務省から出されたものです。
施行日が令和5年2月20日の「DVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができる」などは、現場から強く緊急に求められたものです。

今回の「民事整備法」は、民事訴訟以外の民事関係の手続でインターネットで書類提出したり裁判所や行政機関とのやりとりをインターネットで行う事ができる様に改正します。
それに伴い公正証書作成のデジタル化も検討され、令和5年3月17日法務省においては作成に係る一連の手続についてデジタル化を実現するため準備を進め、令和5年の通常国会で法案提出、7年度上期の施行を目指すと書かれています。

タイトルに書かれている略称「民事整備法」については、法務大臣政務官の自民党議員宮崎政久議員のツイッターに書いてありました。
連日の #自民党法務部会 、昨日は略称民事整備法を了承。この法律は現在進めている #民事裁判のIT化 に続き、訴訟以外の手続きもIT化を進めオンライン申立て等を制度化するもの。多くの法律が関係するので、新旧対照資料は手で抱えるほどの厚み。関係省庁職員の仕事に感謝の思いで披露しました。 pic.twitter.com/beLGfn9F7h
— 宮崎政久(みやざきまさひさ)@沖縄2区 (@Miyazaki_kirin) March 4, 2023
この法案前に、デジタル庁では2022年令和4年2月8日に「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案」を可決し、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により税金などの納付が可能になるよう法律を作っています。
基本的な手続きの方法が書かれた要綱案がありました。
「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続の見直しに関する要綱案」(令和5年1月20日)
要綱というのは具体的に公的機関で行うかの手続きのやり方が書いてあります。
例えば、「インターネットを用いてする申立て等の義務付け 民事執行の手続において、民訴法第132条の11の規定と同様に、委任を受けた代理人(民執法第13条第1項又は民訴法第54条第1項ただし書の許可を得て代理人となったものを除く。)等は、裁判所に対して行う申立て等をインターネットを用いてしなければならないものとする。」とあり、民事訴訟の申し立てがインターネットを使うよう義務になっています。
義務ともなると、インターネットが使えない人や使えない状況の時はどうするのでだろうという疑問が湧いてきます。
民事整備法と同じ211回国会に、デジタル庁から「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案」が提出されています。
内容は「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を基に、フロッピーディスク等の記録でもオンラインで申請できる様になったり、インターネットで所在不明者への通知等を一定期間掲示されたり、公的機関の案内なども表示されるようになります。

この民事整備法に至るまでにいくつかの法律を改正し、新たに法律を作っています。その内容をざっと図でみてみます。



手続きがアナログからオンラインになる事で改正される法律は幾つあるのでしょう?
民事整備法案の条文を見てみると他の法案の条文と違って随分馴染みのない条文です。
目次が第一章~第三十四章まであり、改正する箇所が書かれ、次に第一条から具体的に削ったり加えたりと忙しい条文で、なんと第三百八十九条まであります。
附則でこの法律は、「公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とあり、各条文の手続き変更の日程がA4サイズに234頁にも渡って書かれています。


この法案によって改正される法律は、民事執行法、民法、鉄道抵当法、公証人法、民事調停法、企業担保法、執行官法、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律、民事訴訟費用等に関する法律、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律、民事保全法、借地借家法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、会社更生法、人事訴訟法、仲裁法、労働審判法、破産法、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、信託法、非訟事件手続法、家事事件手続法、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律、民事訴訟法等の一部を改正する法律、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の、34個の法律です。これまで関わった事があるのか無いのかもわからない物ばかりです。

令和4年6月3日
アナログ規制のデジタル化は、主に経団連等の大企業が中心となって要望したものに対応しているようです。よって、今後電子機器の使用や購入費用に対応できない人達は行政書士や弁護士などの専門家に依頼するケースが多くなると予想されます。
時間経過とともに対応できない小さな企業の統廃合が起こり、会社の定款取得や個人の相続手続きなどが数多く起こることが予想され、公正証書のデジタル化も急がれるのだろうと想像しています。
2・日本の行政サービス
これまで日本のIT化やDXの遅れは民間企業でも問題になっていましたが、その大きな原因が日本のアナログ行政にあると言われていました。
山口県阿武町で2022年4月、住民税非課税世帯への臨時特別給付金を誤入金した名簿にフロッピーディスクが使われていた話しは日本国民の多くが驚きました。
北欧のエストニアは10年以上前にIT先進国として多くの国が視察に行き、日本政府も認知しており視察に行く議員も増えていたにも拘らず、その取り組みをした自治体は極わずかであったと記憶しています。
結局日本の省庁での行政手続きが旧態依然のアナログであって、デジタル化しない事には地方自治体も企業も時間と費用がかかり世界との競争力はますます広がるばかりでした。
日本生命サイトにある令和2年度の報告でOECDの調べによると「日本の行政手続のオンライン利用率は7.3%、30カ国の中最下位」で、①日本全体でデジタル化を担う人材が不足していること、②人材の勤務先がIT関連産業に偏っており、行政などの公的部門で働く人材が少ないこと、などを指摘しています。

確かに3年位前にはIT企業の人材不足で募集も多かったように思いますし、2020年の新型コロナウィルス感染症の影響で失業した若者向けに職業訓練としてデジタル人材育成のカリュキュラムが多く見られ、2020年度からは小学校にもプログラミング教育が導入されタブレットを1人1台持つようになりました。
今回のデジタル庁の資料に、オンライン化等による行政手続コスト (営業の許認可、社会保険、労務管理、補助金等)の20%削減による経済効果は、1.3兆円と推計 、中小企業AI導入による経済効果は、2025年までに11兆円と推計とありました。特にこの「行政手続きコストの20%削減」の根拠は何処にあるのでしょう?

アベノミクスの第二弾として、「日本再興戦略2016」の中で第4次産業革命に向けてイノベーションを起こす為に、規制の見直しという点から経済3団体の参加にて2017 年 平成29年3月29日規制改革・行政手続の簡素化・IT化の一体的推進について話し合われ、取り組みが行われたようです。
2000年代における欧米諸国の取組に書かれていますが、2000 年代、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、カナダでは、政府全体で「行政手続コスト」に対する一定の削減率(25%等)を目標に定め、その実現に向けて「標準的費用モデル(SCM:Standard Cost Model)」を用いて行政手続コスト(規制等を遵守するために事業者において発生する事業者の事務作業負担)を数値化し、一定の期間をかけて、目標25%削減に取り組んだとあります。

2010 年代に入ると欧米諸国での取組は多様化し、 英国やデンマークでは政府全体の行政手続コストを削減し、2010年代では目標を「削減率」から「絶対額」に変更し削減に取り組んだとあります。
ドイツ、カナダ、英国、米国3では、2000年代に既存の行政手続コスト(ストック)の削減に注力する取組を行った後、一旦削減した既存の行政手続コストをこれ以上増やさないための基準(「One-in/One-out」)等を設定する取組も見られた。
フランスでは、削減目標は設定せずに、事業者への電話ヒアリングに基づく行政手続に対する事業者の改善ニーズを踏まえて重点分野を選定し、その内容に応じ、会社設立・事業拡大など事業者のライフイベント毎に組織された官民の 10 の分野別ワーキンググループ(WG)を設置して、具体的な個別措置を検討している。

国内においては、国の出先機関ごとの独自の運用ルール(いわゆるローカル・ルール)の撤廃があげられ、2007年平成19年度から鳥取県が行政コストの削減に早くから取り組んでました。その手続き削減20%削減を全国に展開する事で計算上約2億時間(約5千億円)の効果が見込まれるという試算が日本政府の言う根拠の様です。

2007年平井伸治氏が知事に就任し行政コスト削減の為の取り組み、基金を維持しながら県債残高を大幅に削減。
○県債残高(臨財債除く):1,038億円削減(H18末:4,711億円→R4末:3,673億円)・・でも・・・なんでこんなに借金作ってるんだろう?(大雨洪水もあったからなぁ~)

また、近年では福島県で、民事訴訟手続き、ウェブ会議で 福島県内、進むオンライン化などの記事が見られた。
やはり、東北大震災による被害者を多く出し、福島原子力発電所からの避難で多くの方が長期間自宅に戻れず、行政も県民もいち早く行政のデジタル化の必要性を強く感じたのかも知れないですね。
3・質問してみたい事
①かなり以前から日本全体のデジタル化はもとより行政のデジタル化の遅れは言われ、早くからデジタル先進国エストニア等に視察に行ったり隣国韓国に行ってるにも拘らず、この様に実現が遅れたのはなぜか?
②政府は海外の規制の廃止で行政コストの削減を認識しているにもかかわらず、参議院浜田議員の議会で「政府として、今後更に規制緩和を進めていくことで、例えばアメリカのような二対一ルール、カナダのようなワン・フォー・ワン・ルールなど、規制緩和のルール導入を検討する方針はありますでしょうか?」という質問に、政府参考人「我が国でも、本年三月までの三年間で行政手続コストの二〇%削減を目標とした取組を進めており、その目標を達成したところでございます。民間の行政手続コストを削減することは重要であり、引き続き、どのような取組が必要か、しっかりと検討してまいりたいと考えております。」と応えてます。
・今回の行政コストの削減目標は各法案ごとに何%になるのか?
・海外では次の段階の取り組み事例があるが、日本での引き続きの取り組みは何か?
・また、国民への負担は何がどれくらいと試算しているのか?
・この法案で、地方自治体の行政コストの削減は目標の20%削減になるのか?


③将来的にデジタル化で統廃合省庁は?
民間企業の統廃合する企業はどれくらいと予想しているか?
④自治体ごとにシステムが違っているが、標準化・統一化されるのか?地方の対応できない自治体への対策はなされているのか?
⑤行政のデジタル化で、サイバー攻撃やセキュリティクリアランスに関し、懸念されることは何か?
➅マイナンバーを持っていない日本在住者への対応は想定しているか?
⑦なりすましや背乗りへの対策は如何の様にするのか?
⑧行政のデジタル化で今後予定している事は何か?
⑨日本が成長出来ないのはデジタル化の遅れによって海外との競争力が無いからという理由があったかと思うが、行政のデジタル化がほぼ完成するのは何時頃で、その時に日本は何%の経済成長が成されると予想されますか?
以上になります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
