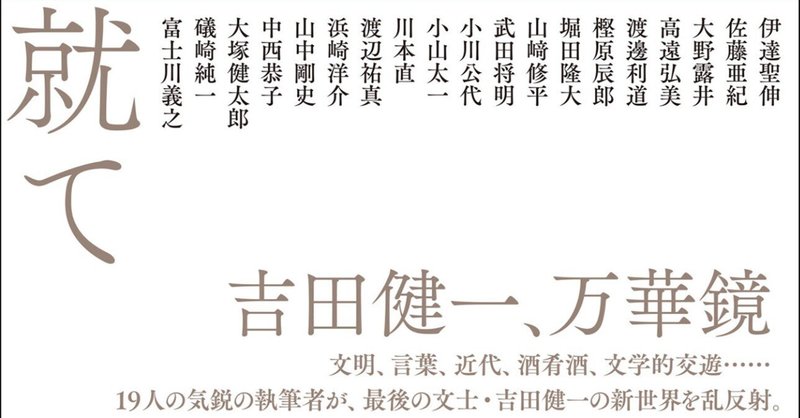
『吉田健一に就て』刊行記念・「序文」「あとがき」公開
2023年10月、『吉田健一に就て』(川本直/樫原辰郎/武田将明 編)が刊行されました。
19人におよぶ執筆者が、《最後の文士》と言われる吉田健一をさまざまな観点から論じた、550頁を超える破格の本です。
本書の成り立ちおよび各論の特色について書かれた、川本直さんによる「序文」と、本書の読みどころに触れた、武田将明さんの「あとがき」を、ここに全文公開いたします。
序文
川本直
吉田健一(1912~1977)は様々な顔を持つ。英文学、フランス文学、日本文学を自在に往還し、今で言う世界文学の領域で独自の美学を追究した文芸評論家にして翻訳家。食と酒を語った随筆や喜劇的な短編小説で健筆を揮ったユーモア溢れるエッセイストにして小説家。晩年には批評『ヨオロツパの世紀末』や『時間』、長編小説『瓦礫の中』、『金沢』、『東京の昔』などでさらに深みを増した文明批評を展開した。そして、吉田健一自身が距離を取っていたパブリック・イメージではあるものの、戦後日本を代表する宰相・吉田茂の御曹司でもある。
だが、こういった表層的なレッテルは、徹底した分析がなされない限り、吉田健一を論じるにあたって何ら意味をなさない。
2019年、私は本書の執筆者でもある樫原辰郎、武田将明、富士川義之、渡邊利道らと共に吉田健一論集『吉田健一ふたたび』を冨山房インターナショナルから出版した。『吉田健一ふたたび』は若い新進の書き手たちが中心となって論じることで、吉田健一の言葉を現代と再接続し、吉田健一を知らない読者の手に届けるための所謂、入門書だった。入門書であることを優先するために、アプローチとしては、それまでに出た最も浩瀚な吉田健一の評伝である長谷川郁夫の『吉田健一』(新潮社、2014年)が提示した吉田像をもっぱら踏襲する形を採っている。しかし、本書『吉田健一に就て』はその企画段階から全く異なるアプローチを採ることになった。
その起点は、2020年9月、本書の担当編集者であり、最終的には共著者の一人ともなった礒崎純一が、川本との最初の打ち合わせで述べた長谷川の著書に対しての大きな違和感にある。澁澤龍彦の伝記作家でもある礒崎は、「吉田さん」という呼称で吉田を記述する長谷川の本が、はなから吉田の都合の良くない側面を封印する姿勢になっており、奇人的な要素も色濃いはずの吉田健一があたかも聖人君子のように描かれているのは少なからぬ問題を感じる、との意見だった。確かに長谷川の『吉田健一』は初めて吉田健一の生涯を包括的に綴った記念碑的な評伝だが、礒崎が指摘した欠点はもちろん、記述からは海外文学の見識が欠け、特に伝記の後半では吉田の生涯に起きた出来事に関して長谷川が忖度して動機を代弁している箇所が目立つ。良くも悪くも聖人伝だという認識を私も礒崎と共にしていた。
また、私自身はそれとは違う理由でも、当時の吉田健一の受容には不満を抱いていた。コロナ禍以前には「戦争に反対する唯一の手段は、各自の生活を美しくして、それに執着することである」(「長崎」)という吉田の言葉が、インターネット・ミームの「丁寧な暮らし」と結びつけられる事態が発生し、SNSでは吉田のテクストを自己啓発染みた浅薄な人生哲学として援用をする者が跡を絶たなかった。吉田健一自身が「青年時代のことは別として、人生とは何ぞやといふ態度にどれ程の意味があるのか、兎に角、つまらない」(「わが人生処方」)と述べているにもかかわらずだ。一方、吉田のその言葉を批判する側は自らの拠って立つイデオロギーから断罪するだけだった。そして吉田の大して重要でもない短い新聞記事の「長崎」の一節を賛美する者も批判する者も、吉田健一の著作をろくに読もうともしない。私も「長崎」という随筆には異論があるが(それは本論で述べた)、対象を知り尽くしていなければ批判は鈍(なまく)らになってしまうだけだ。
私自身の吉田健一観も本書の準備中に大きく変わった。2022年4月から神奈川近代文学館で開催された「生誕110年 吉田健一展 文學の樂み」で初めて目にした吉田健一の書簡や写真は、長谷川の描く聖人君子めいた人物像とは全く異なっていた。F・L・ルカスに宛てた手紙での吉田は熱に浮かされたような文学青年と表現しても過言ではなく、ビール飲みコンテストでビールジョッキを前にする吉田は明らかに変人で、三島由紀夫への謝罪の手紙を中村光夫に添削されている吉田は全く以て大人気がなかった。そこには人間としての一貫性が感じられなかった。考えてみるまでもなく、人間という生き物には、ある程度の個体差は見出されるかもしれないが、作家自らがその作品群で主張するような終始一貫した美学を持たないし、伝記作家が描くような人格的な一貫性なども持たない。危うく吉田が著作で行っている自己演出に呑まれるところだったと勘付いたし、長谷川の『吉田健一』は「私(長谷川)の吉田さん」に過ぎないことに気づいた。
私が吉田健一を最初に読んだのはイーヴリン・ウォーの『ブライヅヘッドふたたび』の翻訳からだったが、初めて手に取った吉田自身の著作『私の食物誌』を読んで延々同語反復で綴られる文章を「異様」だと思ったからこそ他の本も読もうと思ったのだし、『三文紳士』や『酒に呑まれた頭』に大笑いしたのはそのエキセントリックなユーモアがあってこそだし、『英国の近代文学』や『英国の文学の横道』や『ヨオロツパの世紀末』に夢中になったのも既存の文芸批評ではお目にかかれないオルタナティヴな文学観に心躍らされたからではないか。「吉田健一展」と前後して吉田の著作の再読も開始したが、「禿山頑太」名義で書かれた匿名コラム「大波小波」以外では存命の日本の書き手を名指しでは批判しないものの、存命の海外の書き手や日本の物故作家には言いたい放題と言っていいほど批判は苛烈で、『文学の楽み』はタイトルに反して好戦的だ。『東西文学論』に至っては攻撃に暗い情熱を燃やすあまり筆が浮足立っている箇所が多々見受けられる。父譲りの政治家肌ではないかと思われるほどの腹黒さがあるし、その一方で繰り返される私小説批判・ロマン主義嫌いからは鬱屈したストイックさすら感じた。私は、いったん初心に帰って吉田健一に対する考えを白紙に戻し、本書のコンセプトをいま一度練り直す必要を感じた。
吉田健一の文学はアイロニーと逆説に彩られており、評論と翻訳とともに得意とした随筆にはフィクションの要素が濃厚で、一筋縄で行くものではない。英文学の解釈も日本文学の解釈も奇妙と言って差し支えないものだ。たとえば『英国の近代文学』のよく知られた書き出しである「英国では、近代はワイルドから始る」は完全なる逆説だ。学術的な英文学史でワイルドが近代文学の始祖とされることは全くないし、吉田の言う「近代」が「モダニズム」を指したとしても、ワイルドがモダニズム文学の始祖とされることもない。ワイルドはそのポピュラリティに反し、近年までは十九世紀末文学の異端児として扱われ、現在ではポストモダニズムの遠い祖先と考えられている。「英国では、近代はワイルドから始る」と宣言したことによって吉田が無視したのは、吉田が「野暮」と見做した十九世紀のイギリスのリアリズム文学やロマン主義文学だ。そして通常モダニズム文学の代表的な存在とされる作家たちにも 吉田はそこまで高い評価は与えていない。T・S・エリオットには肯定的とまでは言い難く、ジェイムズ・ジョイスに否定的で、ヴァージニア・ウルフは黙殺してしまい、その一方、当時まだ存命で日本では翻訳もされていなかったイーヴリン・ウォーを最終章に持ってきて高く評価している。「英国では、近代はワイルドから始る」とは、そのような吉田健一の文学観を打ち出すための操作であって、そこに提示されているのはワイルドよろしく「芸術家としての批評家」たる吉田健一独自の批評に他ならない。
日本文学の批評でも同様だ。『東西文学論』の私小説批判も、そもそも小説という形式に吉田が懐疑的だということを知らなければ一知半解に留まるだろうし、夏目漱石や永井荷風への否定的な見解も吉田がその二人と重なる洋行体験を持ったが故の自己批判の側面を持つと見抜けなければ、その苛烈さの理由は理解できないだろう。
事は批評だけに留まらず、酒食に関するものを除いて随筆はほとんどフィクションとしか思えない作品か、モンテーニュの『随想録』(エセー)にその起源を求めた方が良いような小論考の形を採っており、日本文学によく見られる身辺雑記とは全く異なる。長編小説は多数派の読者が想定する所謂「小説」の型をほとんど守っていない。
つまり吉田健一を読むためには吉田健一を読むだけでは十分ではない。全てのジャンルにおいて臍曲りと形容してもいいほど批評的なスタイルを貫いているわけだから、吉田健一の言うことを単に字義通り受け取るだけでは仕方がないことになる。吉田健一のテクストを読む場合、「吉田健一が何を言っているか」より「吉田健一が何を言っていないか」の方が重要だと言っても過言ではないだろう。吉田を理解するには、吉田が抗っている既存の文学に対する知識も必要だからだ。
吉田健一の著作は現在でも書店に数多く並んで根強い読者がいるが、それにもかかわらず広範に読まれていると言い難い。それは、このあまりにもメタなスタイルが原因の一つだろう。吉田が批評において異形と言っていい文学観を故意に打ち出して来るのをアイロニーや逆説だと思わず、真に受ければ単に奇矯な文学観の支持者になってしまうし、その随筆の韜晦を額面通りに受け取れば読んだところで何が可笑しいのかもわからない。
吉田健一の作品を読むと、あたかも韜晦という堀に皮肉という塀と逆説という櫓をはりめぐらし、作者は「野暮はお断り」と書いた貼り紙を貼って門を閉ざしてしまったかのように見えなくもない。作品を著して作者はその影に隠れる。確かにそれは作者として理想的かもしれないが、これまでの吉田健一の論者は吉田の該博な教養と広範な他言語使用と独自な文体に気圧されてか、その作品を崇めるかそのパフォーマンスを肯定するばかりで、立ち入った評価を差し控えて来た傾向さえある。吉田健一を評価しつつも忌憚のない批評を行ってきたのは、金井美恵子などごくわずかだ。これは作品の受容として健全な状況とはとても言えない。
結果として本書のコンセプトは、野暮を承知で、偶像崇拝的な従来の吉田健一像を打ち壊し、吉田健一の新たな可能性とその限界をも提示することによって、現時点での吉田健一をめぐる書物としての決定版を目指した。もちろん、ここまで色々述べて来た私のこの吉田像を共有することを各執筆者たちに求めたわけでは全くないが、各著者たちが自らの視点や専門性を全面に押し出して吉田健一を論じることによって、吉田健一の世界を乱反射させる、万華鏡のような多面的なアプローチを採用した。また、ジャンル別や編年体による目次割りを廃し、「文明」、「言葉」、「近代」、「酒肴酒」、「文学」、「文学的交遊録」、「吉田健一頌」とキーワード毎に分類している。
吉田文学の長い愛好家たちからこれまで吉田健一を評したことはなかった新進気鋭の書き手まで、執筆陣は英文学者、フランス文学者、日本文学者、宗教学者、映画監督、小説家、劇作家、文芸批評家、 詩人、書評家、ライター、編集者と多岐に及び、著者は総勢19名。作家論、作品論、翻訳論、比較論、エッセイだけではなく、吉田健一の作品(翻訳)を要素とした戯曲台本も収録している。これまで吉田健一を論じた者のほとんどが避けて通ったその政治性にも踏み込むことを辞さなかったし、吉田に対して批判的な論考もある。伝記的な事実に関しても証言を取材するだけでなく、神奈川近代文学館に寄贈された原稿・草稿・手帳・書簡・遺品、「鉢の木会」連歌帳などが収められた吉田健一文庫の調査も行い、その結果は可能な限り本書に盛り込んだが、2020年7月に吉田健一文庫は運用が開始されたものの、内容は5710点に及ぶ。吉田健一の伝記研究はその緒に就いたばかりで、吉田の伝記的な全貌が明らかになるには最低でもあと十年は掛かるのではないだろうか。
本編の紹介に移ろう。
「Ⅰ.文明」は吉田健一の文明批評についての論考を収録した。フランス文化・宗教学者の伊達聖伸の「宗教と世俗の歴史から見た人新世の吉田健一」で幕を開ける。伊達は吉田の批評を縦横無尽に援用し、宗教と世俗の歴史に位置づけるだけではなく、「現代の壊れゆく世界」=「人新世」を生き抜くために吉田のテクストを読み継ぐ意義を論じている。小説家・佐藤亜紀の「ヨオロッパの世紀末」は、自身ヨーロッパを知悉した文人である佐藤が、同名の吉田の批評『ヨオロツパの世紀末』を建築・経済・美術・宗教・政治・文学とありとあらゆる角度から照射した鮮烈なエッセイだ。佐藤はヨーロッパを知ろうともしない日本人に批判の矢を放ち、『ヨオロツパの世紀末』刊行当時の時代状況も踏まえて吉田と自らの反逆に反逆する真性保守の姿勢を論じ、吉田の讃えたヨーロッパの世紀末をエキセントリックではなく、セントリック=正統と位置づけている。
「Ⅱ.言葉」には吉田健一の他言語体験と翻訳詩を論じた論考を収めた。日本文学者・翻訳家の大野露井による「Queerly Native——奇妙にぺらぺら」で、吉田と酷似した経歴を持つ大野は、『東西文学論』の夏目漱石批判・永井荷風批判を再検討したうえで、多言語使いとして奉られているきらいがあった従来の吉田健一観をあっけらかんと偶像破壊する。「静寂と響き」は「吉田の著作に出会ふまでは、いはゆる現代詩がよく理解できずにゐた者の一人として、『詩に就て』はいはば最良の教科書となつた」と語るフランス文学者の高遠弘美が、吉田の翻訳詩を原文と比較しつつ仔細に検討し、吉田訳の問題を指摘しその「真骨頂」を論じる、優れた翻訳家にしか書けない論考だ。
「Ⅲ.近代」では近代とモダニズムに関する論考を扱っている。作家・文芸評論家の渡邊利道は「吉田健一と近代」で、従来とは異なる吉田独自の概念である「近代」を解き明かす難題に真っ向から挑んだ。渡邊は事実上の吉田のデビュー作である「ラフォルグ論」から始め、ボードレールの「モデルニテ」の概念や吉田のヴァレリー体験を検討して吉田の言う「近代」とは何かに答えを出すのみならず、そこに素朴実在論とポストモダニズムの「歴史の終わり」と類似した思想を見出している。映画監督・文筆家の樫原辰郎の「モダニズムの忘れもの」は、吉田健一のテクストが今も通用するのか、夥しい蘊蓄を交えながら論じている。ウィリアム・ジェイムズが提唱した「意識の流れ」の記述法を、「新心理主義文学」、今で言うモダニズム文学に属するジョイスやフォークナーだけではなく、谷崎潤一郎も歴史小説で使用していたことを説きながら、そういったモダニズム文学の後継としてヌーヴォー・ロマンを位置づける。そして樫原は読者が思いも寄らない仰天の方法で吉田健一の長編小説や『時間』をヌーヴォー・ロマンと接続する。それがいかなる方法なのかは読んでのお楽しみと言うしかない。
「Ⅳ.酒肴酒」には酒と食にまつわる論考と随筆を収めた。編集者・ライターの堀田隆大による「吉田健一と「飲む場所」」は吉田健一のお気に入りだった酒場を「修練の場所」「孤独の場所」「夢幻の場所」の三つに分けて、実地に訪問して論じている。取材は吉田行きつけの銀座と神保町の店、そして金沢の料亭にまで及ぶ。堀田は吉田の随筆や伝記的な資料に徹底してあたりながら写真を交えて、緻密な論考を展開している。詩人・文芸評論家の山﨑修平の「淡いを愛する」は、吉田健一の食についての楽しいエッセイだ。自身グルマンで若き日の吉田と同じく資生堂パーラーを愛する山﨑は、銀座の吉田行きつけの店を食べ歩いた一日を滋味溢れる軽妙な筆致で描いている。
「Ⅴ.文学」は吉田の文芸批評と小説に関する論考四編。英文学者・文芸評論家の武田将明による「〈芸術家としての批評家〉の誕生」は、吉田のデビュー作である『英国の文学』の初版から『英国の近代文学』を経て、『英国の文学』改訂版までに焦点を合わせ、ポストヒストリカルな〈芸術家としての批評家〉吉田健一が如何に誕生したか、そして『英国の文学』改訂版で吉田が文体と内容の変更を行って、最初からその「批評家・吉田健一」が完成された形で存在していたかのように如何に自己演出したかを抉り出す迫真の論考だ。英文学者・小川公代の「吉田健一と「社交」」は、吉田健一の『交遊録』を引きながら、吉田の「社交」をイギリス十八世紀のヒュームや十九世紀末のワイルドに倣ったものとし、吉田がワイルドの批評に「存在論」を見出したことを指摘。そして、吉田の師であったディキンソン、その友人であったウルフ、そして同じくディキンソンの友人で吉田が実際に会っているフォースターの『ハワーズ・エンド』を踏まえて、吉田の“多孔的な自己“を論じている。英文学者・翻訳家の小山太一による「大海蛇のうねり」は、「海坊主」の緻密な読解から始まり、『時間』を引用して語句レベルの超絶技巧の分析を加え、吉田健一の文章すべてが最初から『時間』で語ったものを繰り返していることを明らかにする。小山自身の『時間』冒頭の英訳も付されている。川本の「小説家としての吉田健一」は、吉田の「批評」ではなく「小説」を、最初の未完の小説「過去」、商業媒体に初めて小説と銘打って発表された短編「春の野原」、吉田の小説がそのスタイルを大きく変えた「辰三の場合」、そして最初の長編小説『瓦礫の中』と最後の長編『埋れ木』を、「批評家」としてではなく「小説家」のスタンスから批判的に論じた140枚を超える論考だ。川本はここで吉田健一が下敷きにした小説のルーツを探り、三島由紀夫と比較したうえで、その自らへの影響を語るとともに、吉田健一の文学への一旦の決別を告げている。
「Ⅵ.文学的交遊録」では吉田と交友のあった石川淳、師であった河上徹太郎を通じて微妙な関係にあった小林秀雄、若い時から深い親交があった福田恆存、絶交したとされていた三島由紀夫、同時代に活躍してあい重なる愛読者を持ちその類似性を指摘されつつも生前は没交渉だった澁澤龍彦、これらの文学者との比較論考を収録した。渡邊利道の「石川淳と吉田健一」は、政治的立場も派閥も超えて交友のあった石川淳を「文学言語としての日本語の散文」における吉田健一の「先行者」と見做して、二人の共通項と差異について論じている。書評家の渡辺祐真「小林秀雄と吉田健一」では、これまで論じられることが少なかった小林秀雄と吉田健一の「近代」をめぐる論考だ。吉田を破門するように河上徹太郎に告げた小林、小林ではなく河上を選んだ吉田。この二人は、「小林秀雄文庫」での全解説を吉田が行い、吉田没後の河上との対談で小林が吉田を評価したことで互いを認め合うに至る。文芸批評家であり福田恆存を専門とする浜崎洋介「福田恆存と吉田健一」は、政治についてほとんど語らなかった吉田健一が書いた、当時大きな批判に晒されていた保守の福田恆存を擁護した評論「知識人批判」を中心に、 福田と吉田が「政治と文学」の区別において一致していたことを指摘し、吉田の文学の「思想」を正面切って論じた堂々たる批評だ。日本文学者で三島由紀夫を専門とする山中剛史「三島由紀夫と吉田健一」は、絶交したとされ、これまでは数々のゴシップが囁かれていた三島と吉田の関係の真相に、実証的なアプローチで迫っている。三島の鉢の木会脱退以降にも二人の関係は続いていた事実を突き止めて従来の定説を覆した、知的スリル溢れる論考だ。宗教学者・詩人の中西恭子の「澁澤龍彦と吉田健一」では、西洋の中軸の文学に関心を寄せた吉田と、西洋思想の地下水脈に博物学的アプローチを採った澁澤を比較して、戦後日本で、文学の自律性を重んじ、文学の楽しみを説いた両者の共通点を論じている。
「Ⅶ.吉田健一頌」は、吉田の翻訳と随筆を〈批評〉する戯曲「ソネット」とその自作解題、吉田の伝記的な新発見を元にしたエッセイ「英国人の見た吉田健一」、そして最後に特別寄稿として、吉田健一のリアルタイムの読者であり、その謦咳にも接した執筆者による「回想の中の吉田健一」を収録した。劇作家・演出家の大塚健太郎の戯曲「ソネット」は吉田の「海坊主」を入れ子構図の外枠に用い、「シェイクスピア十四行詩抄」を主軸に展開する静謐且つ才気縦横の作品で、初演を観て感嘆した川本からのたっての希望で今回本書へ収録するに至った。自作解題も単なる「解題」の域を超え、吉田健一への「批評」と言っていい。編集者・作家の礒崎純一「英国人の見た吉田健一」は、小山太一から齎された文章を紹介した上で、英国人たちのポートレートの中の吉田健一が、長谷川郁夫ら日本人が描いた吉田像とは大きく異なり、むしろ吉田本人が初期の随筆で自ら綴った狷介でエキセントリック極まりない姿だったことを明らかにしている。吉田健一の伝記的な研究はまだまだ始まったばかりだと思わざるを得ない。そして本編は、英文学者・評論家の富士川義之による「回想の中の吉田健一」で幕を閉じる。富士川は、『英国の近代文学』が当時は評価が極めて低かったオスカー・ワイルドから論じ始められていることや、また『英国の文学』の生成過程が如何に大胆不敵なものだったかを語り、「決して一筋縄では行かない、およそ規格外の不思議な人物」である吉田健一とその吉田文学を読む幸福を回想する。
序文は川本が、あとがきは武田が、それぞれ担当した。
本書には多くの方々のご助力を賜った。調査と取材に快く協力してくださった吉田健一のご遺族、辻原登氏・池上聡氏をはじめとした神奈川近代文学館の皆様、石川眞樹氏、石川素樹氏、澁澤龍子氏、澁澤龍太氏、新潮社の矢野優氏、文藝春秋の飯窪成幸氏と西泰志氏と山下覚氏、貴重な資料を提供してくださった高澤秀次氏、新潮社の田中範央氏、河出書房新社の尾形龍太郎氏、温かい助言と励ましをくださった高橋睦郎氏、北丸雄二氏、島田雅彦氏、嶽本野ばら氏に心から感謝を申し述べる。
本書の完成には3年を要した。2020年9月に企画がスタートし、2021年は丸1年かけてコンセプトを練り上げつつ、執筆者への依頼と取材に費やされた。その年の8月には山中と取り壊された吉田健一邸跡と防衛省に実地調査に赴き、10月には堀田と山﨑と銀座の吉田の行きつけの店を取材している。2022年は4月から開催された神奈川近代文学館の吉田健一展に合わせて横浜に泊まり込みで取材と吉田健一文庫の調査を行い、吉田健一・石川淳・澁澤龍彦の各ご遺族にもお話を伺った。文字通り東奔西走だったが、私などはまだマシな方で、著者の中には取材のために金沢まで訪れた者までいる。そして執筆と編集作業がスタートしたが、全員凄まじい熱の入りようで、ほとんどの原稿が依頼枚数の30枚を超えてしまった。その熱に煽られる形で、編者の3人もそれをさらに大幅に超える量の原稿を執筆してしまう異常事態となった。原稿は増え続け、400字原稿用紙換算で1000枚以上、550ページを超える大作となった。
企画段階から校了まで、川本・樫原・武田の編者3人と担当編集者であり共著者でもある礒崎は、主にネットと電話を介したひっきりなしのブレインストーミングを行い、他の著者から相談があった場合は双方が納得するまで話し合った。本書の編纂は暴走型の川本一人では不可能だった。出版に漕ぎ着けたのは豊かな学識と経験と人格とを併せ持つ樫原と武田のおかげであり、そして百戦錬磨の編集者であり、吉田健一を知悉した礒崎の悪魔的なまでに巧みな手腕による。
可能な限りありとあらゆる角度から吉田健一を照らした本書『吉田健一に就て』によって、吉田健一の読解がさらなる発展を遂げることを願ってやまない。しかし、編者の一人としては、吉田健一をめぐる饗宴というよりは狂宴と呼ぶにふさわしいこの本を読者の方々にまずは単に楽しんで戴ければ、これに勝る幸いはない。
* * *
あとがき
武田将明
本書の編集に関して私から言うべきことはない。執筆者に声をかけたのは川本さんであり、集まった様々な執筆者と連絡を取り、本の形にまとめたのは礒崎さんである。樫原さんは川本さん、礒崎さんと連絡を取りながら編集を助けられた。私はその様子を眺めながら、都合のよいときに勝手なことを呟いた程度である。だから、このあとがきを書いているのは決して編集に寄与したからではなく、ろくに編者らしい仕事のできなかった罪滅ぼしのようなものだ。
そういう半ば外側の視点で本書を読むと、所属・年齢などの異なる多数の執筆者が、それぞれの切り口で吉田健一を論じたものでありながら、いくつか共通した主題があるのに気づく。そのうち私が注目するのは、〈近代〉、〈人間〉、〈社交〉の三つである。〈近代〉については、「近代」と題されたセクションに「吉田健一と近代」という論考が掲載されている。この渡邊利道による文章は、吉田健一の執筆活動全体を視野に入れ、吉田の〈近代〉が特定の時代を指すものから「普遍的」で「超歴史的」な概念へと変性する過程を緻密に跡づけている。有意義な知見を多く含むこの論考を読んでから、本書の他の章を再読すると、密かに渡邊の分析と共鳴する箇所を多数見出せる。例えば、吉田の「超歴史的な「近代」概念」は「敗戦後」に確立されたという渡邊の主張は、第二次大戦後の世界で歴史上の〈近代〉が終焉し、一種の人間主義が回復したと指摘する伊達聖伸の論考(「宗教と世俗の歴史から見た人新世の吉田健一」)と併読することで議論の射程がさらに広がる。さらには、浜崎洋介の「福田恆存と吉田健一」における、吉田健一の〈近代〉と戦後日本の(進歩主義とほぼ同義の)「近代主義」との異質さへの言及は、「近代」という言葉の厄介さに読者の注意を差し向ける。また、渡辺祐真は「小林秀雄と吉田健一」において(この章の副題が「正面から来る近代と己に内在する近代」であるのにも注意)、前者が戦時中に発表した有名な随筆「当麻」(1942年)が後者の批評観と共振すると述べるが、渡邊利道もまた、吉田健一の〈近代〉概念の変化の鍵をなす作品として、この「当麻」に注目している。
本書における〈近代〉への言及を少したどるだけでも、これらの章を超えた連携が見られる。にもかかわらず、本書の編集過程において、執筆者同士で内容の整合性を話し合う機会はほとんどなかった。コロナ禍の外出制限もあったが、そもそも執筆者の数が多く、全員が都合をつけて会うのは難しかった。しかし、多彩な書き手が各章で個性を発揮しながらも、一冊の論集としてのまとまりも生じたのは、吉田健一の作品がまさに多様性と一貫性を併せ持っているからであろうし、これに加えて、各論者が単に吉田健一への個人的な愛着を語るのではなく、いま吉田健一を読み返す意味まで考えたおかげでもあるだろう。
次に〈人間〉という概念は、吉田において〈近代〉と対立的とも補完的とも言える際どい関係を結んでいる。この点について、富士川義之の「回想の中の吉田健一」を参照すると、『英国の近代文学』において、「人間の解体に向った時代」としての近代を批判したのをきっかけに、吉田は「人間」と「時間」という大きなテーマ」に直面し、それが後年の「人間」を再び取り戻すためには何をなすべきか」という問いに繋がったと論じられている。同じ問題は、私の拙い文章(「〈芸術家としての批評家〉の誕生」)も取り上げているが、そこでは分析的理性が発展した近代の終焉後に人間回復の時代としての現代が来るという吉田の主張が、素朴なヒューマニズムへの回帰とは異質であることを示したつもりである。これは「吉田の言う「人間」がヒューマニズムとはまったく関係がない」(渡邊)「吉田健一が言う「人間」という言葉に、近代主義者が語るヒューマニズム──その延長線上で観念さ、れる近代個人主義──の響きがほとんどなかった」(浜崎)という他章の論述と軌を一にする。伊達論文はさらに踏み込んで、吉田健一の独自の人間観が、人間中心主義の臨界点たる現代(人新世)において、同時代の思想として参照されるべきだと宣言する。ここには、さきほど指摘した吉田健一の同時代的な意味への問いかけが鮮明に現れている。
しかし直ちに補足すべきは、この吉田の人間観は、単に人間を地球環境の中に位置づけ直すという健全で正しい思想にお墨つきを与えるものというより、むしろ〈人間〉の輪郭そのものを問い直していることだ。ここで参照すべきは小山太一の文章(「大海蛇のうねり」)である。1950年代の短篇「海坊主」や「酒宴」を引き合いに、「絶えることのない世界の流動のなかに不意に顔を出す怪しいものたち、得体の知れないものたち──人間のようでもありお化けのようでもあるが、(中略)どっちであっても構わないものたち」に触れることから始まり、吉田作品における自己と他者との関係の異様さが浮き彫りにされる。すなわち、「海坊主」に出てくる人とも大亀ともつかない怪物のようなポストヒューマン的な存在が、いかに自己のあり方を変容するかがここでは問われている。
そしてこの〈人間〉をめぐる問いは、ただちに〈社交〉の問題とつながる。なぜなら小山も示唆するように、〈人間〉の輪郭を捉え直すことは〈自己〉と〈他者〉の境界線を引き直すこと、あるいは境界そのものを疑うことにつながるからだ。小山は、「海坊主」の語り手と大亀が交わす「一杯如何ですか」という台詞に注目し、こうした控え目な働きかけが親密な社交(吉田の語彙では「交遊」)を可能にすると述べる。吉田作品における〈自己〉と〈他者〉の関係は、唯一無二の個と個の対峙ではなく、「こっち」と「相手」の「互換性」を基礎としている。これは、吉田の人間観には「近代的個人主義(中略)の響きがほとんどな」いという先述の浜崎の論述と符合している。
〈社交〉といえば、本書には小川公代の「吉田健一と「社交」」が収められており、そこではいわゆる近代的な個人に当たる「緩衝材で覆われた自己」ではなく、「多孔的な自己」への関心が吉田健一と様々な二十世紀英国の文人たち──ディキンソン、フォースター、ウルフ──を結びつける鍵となることが示される。また、吉田健一自身は、『ヨオロッパの世紀末』(1970年)ほかに見られるように、
「社交文化を基盤とした18世紀文学を理想化」する一方で、ロマン主義文学の内面性や自我への執着に批判的だったと考えられるものの、小川は近年のロマン主義研究を参照しつつ、パーシー・ビッシュ・シェリーなどロマン主義者における社交性と吉田との繋がりも考察している。これは奇しくも、川本直が「小説家としての吉田健一」において、吉田健一の初期小説がオルダス・ハクスリーの『クローム・イエロー』(1921年)を参照し、そのハクスリーはトマス・ラヴ・ピーコックに影響を受けたと述べているのと共鳴する。川本も記すとおり、ピーコックは──彼自身は典型的なロマン派とは言い難いものの──シェリーの親友として知られているからだ。
また、小川は相互依存的な社交の性質を「ケアの倫理」と結びつけてもいるが、これは先述した小山による「控え目な働きかけ」が可能にする親密さに通じる。この親密さは、小山が注意するとおり、「目の前にいる相手とひとつに溶け合うような一体感」とは似て非なるもので、「人がみずからの存在を拡げ、静かな海に一人で入ってゆくような」、孤独と包摂とが渾然一体となった雰囲気のうちに実現するものだ。吉田の社交ないし交遊の根底にあるこの雰囲気は、本書のうち、直接〈社交〉を論じていない各章にも浸透している。富士川が吉田における「居場所」や「土地への愛着」を論じて英国の田園風景に思いを馳せる際──高遠弘美の詩論「静寂と響き」が、「一篇の詩を取り巻くものは静寂であつてそれが先づ伝はらなければそれは詩でないか或は我々とその詩がその時は縁がないのである」という吉田『詩に就て』の一節から、古代ギリシアの詩人シモーニデースの一篇(呉茂一訳)を連想し、その言葉と行間に漂う静寂に耳を澄ますとき──さらには山﨑修平(「淡いを愛する」)が吉田の通いつめたビアホール「ランチョン」を訪ね、吉田の考案になる「ビーフパイ」を食したところ、その「上品な淡さ」に虚を衝かれた瞬間──孤独で親密な雰囲気が匂い立ち、かの大亀がどこかから控え目な眼差しを送っているのを読者は感じるだろう。「ランチョン」については、堀田隆大(「吉田健一と「飲む場所」)も取材している。堀田によれば、吉田はビアホールを「皆で集まれて楽しく飲める場所」というより、「自分一人で楽しめるような空間」として語ったそうだが、実は「ランチョン」のようなビアホールこそ、親密な孤独の淡い味わいを楽しむには格好の場所だったのかもしれない。また、大塚健太郎による戯曲「ソネット」は、全篇で吉田的な居場所を描いているが(「一杯如何ですか」という台詞もある)、最後には隅田川のほとりで酒を飲む二人が舞台にいて、その片方が「ゆっくりと移動し、やがて川の中に消え」、残った方が一人で酒を飲み続ける。まさに「静かな海に一人で入ってゆくような」、存在と無、生と死のあわいを思わせる幽玄さを纏いながら、吉田的な世界観が感覚的に捉えられている。
もっとも、本書ではすべての要素が予定調和的な和声を響かせているわけではない。それどころか、よく読めば〈近代〉、〈人間〉、〈社交〉について、論者たちの力点の置き方に紛れもない差異があることも分かる。細かい意見の相違も随所に見られ、一例を挙げるならば、『英国の文学』改版(1963年)の「後記」における「この本が出来上つて、これから先、是非ともして置きたいと思ふ仕事はもう何も残つてゐない」という同じ一節について、私はある程度本音が吐露されたものと見るが、川本は完全なる「ブラフ」だと解釈する。果たしてどちらかが正しいのか? いや、こうした意見の差異を捉えて、マウンティングだ論破だと、SNS的あるいは討論番組的に対立を煽り立てるのは、吉田と福田が軽蔑した「戦後文化人」的な党派精神の残滓を嘗めることに他ならない。それよりは、バロック音楽の対位法的な音の駆け引きや、(読者のお好み次第で)ロマン派音楽のアラベスク的な音のせめぎ合いを聴き取る方が吉田健一的であるのは確かだ。
さきほどから私は「吉田的」とか「吉田健一的」という言葉を知ったような口で使っているが、正直なところ、本書を読めば読むほど、吉田健一の捉えどころのなさに半ば感心し、半ば途方に暮れてしまう。人間とも人外とも得体の知れない不気味なもの、それでいて妙に愛嬌があって心惹かれるもの、吉田健一の描く怪物たちの性格は、どこか彼自身に似ている。大野露井によるエッセイのタイトル「Queerly Native──奇妙にぺらぺら」は、吉田の著作を読むものが抱く心持ちを明瞭簡潔に表現した言葉ともいえる。大野自身の体験と吉田のそれを重ね合わせながら、感覚的に、かつ同時代的に吉田健一を読み直したこの文章は、最終的に吉田的な「言葉との奇妙(クイア)な関係」こそが言葉の、そして言葉が媒介する世界の普通のあり方なのだと指摘するが、これは『時間』(1976年)において「我々は変人、奇人であってはならない」と、およそ常軌を逸した──まさに「大海蛇のうね」るような──文体で大真面目に主張した吉田の姿勢を反復している。
同様の認識は佐藤亜紀「ヨオロッパの世紀末」にも示される。佐藤によれば、吉田健一は一見するとエキセントリック(異端)なものが実はセントリック(正統)だと示した書き手である。例えば『ヨオロッパの世紀末』は、「19世紀末から20世紀初頭に掛けてヨーロッパに現れた表現や文化はエキセントリックではなくセントリック」だと論じたものだといえる。さらに佐藤は、吉田健一もまた、戦後日本の言説空間では「エキセントリック」に見えるが、実は「完全に正気で普通」の「セントリック」な物書きだったのではないか、と問いかける。これは、吉田と福田恆存による戦後知識人批判に通じる点で浜崎論文とも関連するが、佐藤の批判の射程は戦後を超えて同時代にも及ぶ。『ヨオロッパの世紀末』の刊行された1970年を回顧しつつ、佐藤自身、「反逆に何の夢も希望も抱け」ず、「反逆に反逆する」しかなかったと述懐する。そんな佐藤は「反逆に対する反逆者」吉田の保守性に深い共感を示している。
他方、礒崎純一(「英国人の見た吉田健一」)は、聖人視されがちな吉田健一の「エキセントリックな部分」に注意を喚起するが、これは佐藤の主張と対立するものではない。ここで礒崎は吉田を健全な知識人として祀り上げ、無毒化する傾向に異を唱えている。それは正統か異端かと関係なく、吉田健一を彼自身が批判した戦後知識人と同一視することにつながりかねない。
吉田の捉えがたさを冷静に分析するために、他者との関係を見るのは有効であろう。その点、本書には「文学的交遊録」というセクションがあり、石川淳、小林秀雄、福田恆存、三島由紀夫、澁澤龍彦との比較がなされている。「石川淳と吉田健一」(渡邊利道)における、未来を志向する石川と過去を回想する吉田との鮮やかな対比や、「三島由紀夫と吉田健一」(山中剛史)における、この二人の「絶交」という誇張された噂の精査など、参考になる論述がある。また、「澁澤龍彦と吉田健一」(中西恭子)は、文学史における正統と異端との関係を転倒させた点に澁澤と吉田の共通点を見出しており、先述の佐藤や礒崎の議論と併読すると興味深い。さらには、すでに明らかなように、比較を全面に出していない章においても、様々な作家・作品との比較がなされており、樫原辰郎「モダニズムの忘れもの」は、ジョイスなど英語圏のモダニズムおよびフランスのヌーヴォーロマンと吉田を比べ、川本の論考でも、「政治を美学化」する三島由紀夫と「生活を美学化する」吉田との対照や、夏目漱石『坊っちゃん』(1906年)と吉田『埋れ木』(1974年)との意外な類似点が指摘される。
もうひとつ特筆すべきは、富士川によるカズオ・イシグロと吉田健一の比較である。文体も作風も異なる二人だが、確かにイシグロにおける「日本」と吉田における「英国」は、いずれも半ば架空の場所でありながら、それぞれの原点となっている。その結果、イシグロは英語、吉田は日本語において「Queerly Native」な文学を紡ぐこととなった。この二人の比較は、近年イシグロが世界文学の作家として注目されている点(レベッカ・L・ウォルコウィッツ『生まれつき翻訳』(松籟社、2022年)などを参照)を想起するならば、吉田文学を世界文学として読むという、新たな試みへのヒントともなるだろう。本書で吉田の友人としてたびたび言及されるドナルド・キーンなど、海外の近代日本文学研究者はことごとく吉田の作品を無視、あるいは(大野によれば)「敬遠」してきた。吉田自身の書いた英文を除けば、外国語にされた吉田のテクストは非常に少ないはずである(その点、本書に収められた小山による『時間』冒頭の英訳は貴重だ)。しかし、自国語に閉塞しないテクストにこそ文学の未来があると考える世界文学論が文学研究を席捲している現在、吉田の「日本文学」を越境する文章が実際に国境を越える日が来ているのではないか。ちなみに、久生十蘭の「母子像」が第二回世界短編小説コンクールで第一席に選ばれたのは有名だが、このとき「母子像」を英訳したのが吉田健一だったことは、恥ずかしながら本書の川本論文を読むまで知らなかった。翻訳を原典から独立した作品とみなすのも世界文学研究の特徴であり、この点からも日英・英日の翻訳に従事した吉田は関心の対象となるだろう。
将来の評論・研究へのヒントという点では、本書には吉田の比較的マイナーなテクストの再評価も随所に見られる。伊達が注目する「現代文学における神の問題」、渡邊利道が引用する「近代の東洋的性格に就て」、渡辺祐真が小林秀雄との比較で紹介した吉田のランボー論など、読者は思わず読みたくなるはずだし(私はそうだった)、拙論における『英国の文学』初版と改版の比較が示すような、テクストの版ごとの差異についても、今後さらに研究されるべきだろう。また、前に触れた川本による『埋れ木』論は、吉田の小説中ひときわ厄介なこの作品への格好の案内となっている。他にも、礒崎が(小山と協力して)紹介する『日本体験記』における英国人による吉田評、さらに礒崎と川本の両名が言及する庄司孝男による吉田の回想録など、知られざる資料への案内があるし、富士川と山中の章を読めば、吉田健一の未公開書簡のなかにも、これからの吉田研究にとって重要な記述があるようだ。もちろん、山中が惜しげもなく提供する「鉢の木会」(吉田を中心メンバーのひとりとする文人たちの親睦会)の記録も貴重である。
一点、残念だったことも記しておくと、執筆者のジェンダーの偏りが、本書の多様性に影を落としている。これは編者のひとりである私にも責任があるのは言うまでもない。ただ、本書の各論考には、金井美恵子や高橋智子、島内裕子など、女性の読み手・研究者への言及も少なからずあり、これで幾分かは不足が補われていることを願う。
最後にもうひとつ白状すると、私はもともと吉田健一の愛読者ではなかった。川本さんに誘われて前の論集『吉田健一ふたたび』に参加したときも、吉田への興味というより、偶像破壊への欲望に駆られていた。愚かな話だが、英国通で日本語文学の辺境性を超越した特殊な作家という、世間一般の(と当時の私が思い込んでいた)「吉田健一」像に異を唱えようとしたのだった。この出来心は「吉田健一の「英国」」という論文を生み、自分としてはこれで吉田を卒業したつもりでいた。だから、『吉田健一に就て』への寄稿依頼が来たとき、最初はお断りすることも考えた。だが、なぜか二度目の出来心を起こし、前の論考で拾い忘れたものを寄せ集めればもう一本書けるだろうと『英国の文学』と『英国の近代文学』を再読したところ、偶像ならぬ吉田健一自身の肉声が急に聞こえ始めた。ただしそれは、「肉声」という言葉が示唆するナイーヴな現前性への信仰を相対化した上で、あえて発せられる奇声だった。一英文学者による偶像破壊などとうに織り込みずみの怪物として、吉田健一は私の前に再び、あるいは初めて現れた。今回、拙論を準備する中で考えた様々なことは、とても一本の論文には収まりきらない。加えて他の執筆者による刺激的な論考を拝読したいま、私の吉田への興味は広がるばかりだ。
逆にこれまで吉田健一をこよなく愛読してきた川本さんが、本書をもっていったん吉田健一を卒業する、と書いているのは面白い。もっとも、「この本が出来上つて、これから先、是非ともして置きたいと思ふ仕事はもう何も残つてゐない」という吉田の言葉をブラフと喝破した人のことだから、あっさりと舞い戻ってくるかもしれない。ともあれ私は、本書を手がかりにして、E・M・フォースターやジョイスなど、今回踏み込めなかった作家たちと吉田との比較や、扱えなかった著作の読解──特に『時間』など後期の文章と長篇小説を、十八世紀研究者の視点で分析すること──をいつかできればと思っている。本書を手に取る方々も、これをきっかけとして、それぞれの吉田健一を見出していかれんことを。
* * *
吉田健一に就て
川本直/樫原辰郎/武田将明 編
四六判・554頁
定価 4,950円(本体価格4,500円)
ISBN978-4-336-07537-6
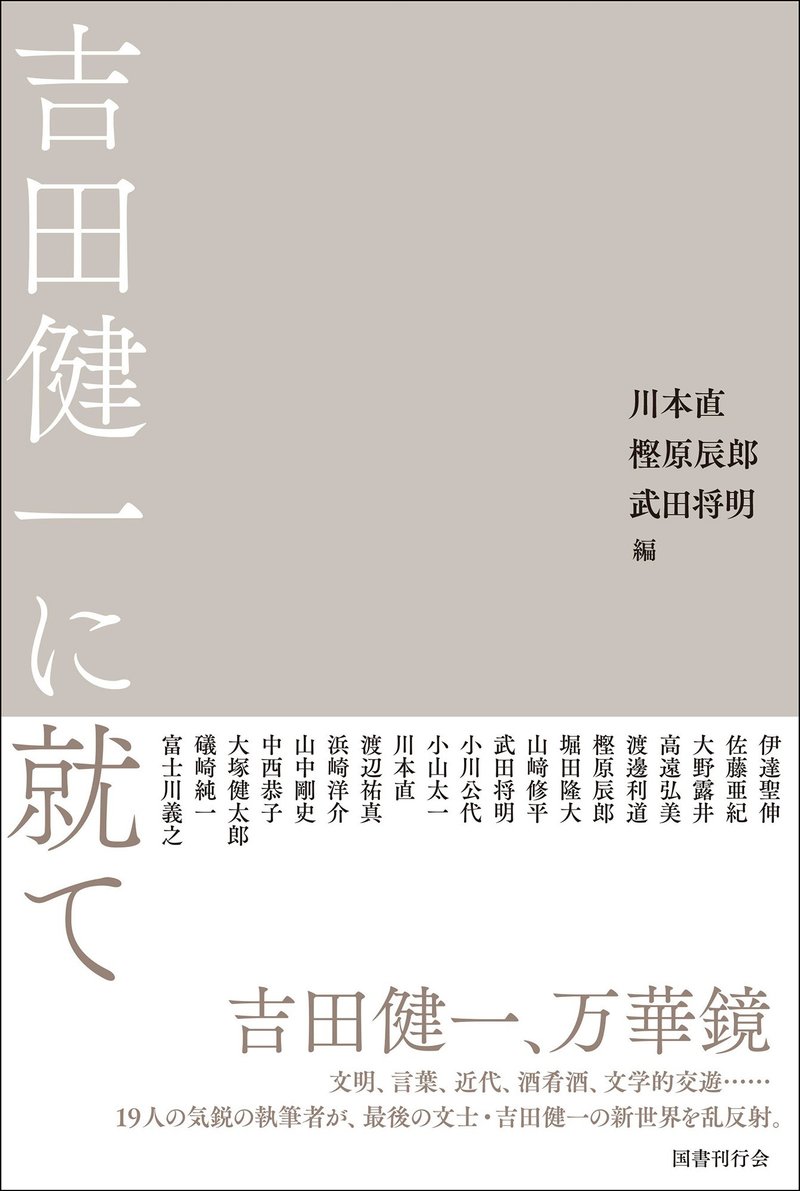
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
