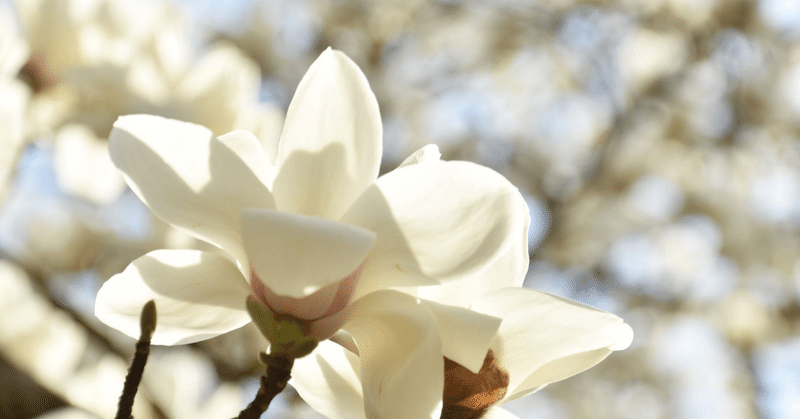
読書メモ / 「人を動かす」D・カーネギー
名著がaudiobookの聴き放題に追加されていたので初めて読んで(聞いて)みた。
再生時間は11時間超え。私には文字で読むのは難しかったと思う。
結果、もっと早く読めばよかったと後悔。2周した。
タイトルの印象から、マネジメントの内容で自分には関係性が薄いと思っていたが、そうではなかった。
職場や日常生活、相手との関係性問わず、汎用的に使える人との接し方について説いている。
正直、それは目新しい内容ではなく、驚きや新鮮さは感じない。ただ、豊富な例をもって深く踏み込んで説明されることで、強い説得力がある。
何より、この本が1936年初版でありながら、現代においてもまったく違和感のない、むしろ多様性や個々の嗜好性が主張される今の時代にこそ適っていることから、時代に依らない人の本質を著しているものと思われた。
相手の心を開くには、相手の自己承認欲求を満たすこと(相手を認める、褒める、聴く)
相手の関心事に興味を示すこと
議論に勝つには、議論しないこと
ネット上の「レスバ」が散見される。なかには、明らかにコメント主に非があり、他者から批判されても、それが冷静でロジカルな指摘であるときでさえ、そのコメント主にまったく響かず自論の主張を続けているときがある。
その人の問題ももちろんあるかもしれないが、そもそも人は自分に対する指摘を真っ向から受け入れられないのだ。理屈の問題ではなく、「敵」「反対勢力」とみなされた時点で結果はほぼ決まっている。
その前提にたてば、「議論をする」というのは確かに無駄な労力を浪費することに他ならない。「噛み付いてきた犬を殺すよりも道を譲った方がいい。もし殺したとしても、噛まれた傷は癒えないのだから」
難しいと感じるのが、これらの原則を小手先のテクニックとして使っても意味がないということ。
相手を「褒める」ことの効力が大きいとはいえ、それは褒め言葉を言うことではない。本心から褒めなければならない。
この本が述べる原則を実行するには、人に関心を持つこと、人を頭から否定せず良い点を見つけようとする姿勢が必要なのだと思う。
その訓練の仕方は本書に書かれていない。
日々のコミュニケーションのなかで訓練する必要があるのだろうと思う。
人に関心を持つことは、私にとっては大きな課題だ。
本当に関心がないわけではないが、あえて関心を持たないように振る舞い、1歩引くことで、他人との関係性において自身を傷つけないように自衛する癖があるから。
それが褒められたことではないと理解していても、必要性に駆られず正せないでいた。
それを改めるべきと、この本に今一度教えられたような気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
