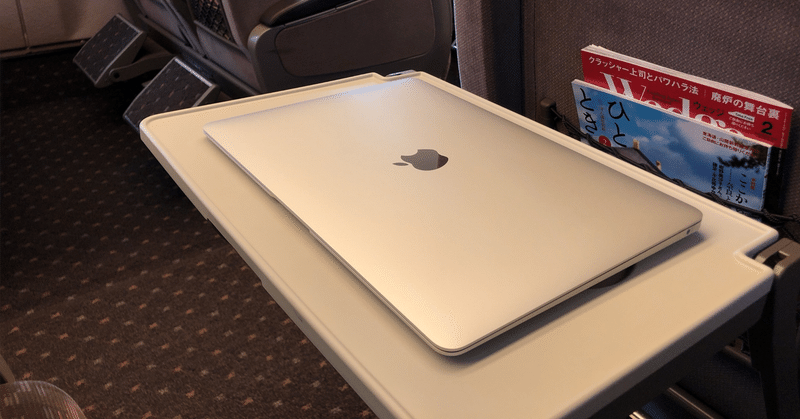
地方自治体の債権回収において,滞納処分による差押えの対象についてのお話をします。
地方自治体の債権管理について,『明日からできる債権回収』をテーマに,過去の研修原稿をもとにして記事を書いています。
※ヘッダー画像は記事内容とは関係ありません。みんなのフォトギャラリーからお気に入りのものを使わせていただいてます。
どうもこんにちは,まっつんです。
今回は,地方自治体の債権について滞納処分による『差押えをすることができる財産にはどのようなものがあるか』,についてお話ししたいと思います

税金などの強制徴収債権について,滞納が発生した場合は差押をしないといけないというお話をしましたが,差押えができる財産はどのようなものがあるでしょうか。
まずは,『預貯金』ですね。
預金っていうのは,銀行を中心とした金融機関のことを言います。
貯金っていうのは,ゆうちょ銀行のものが代表的です。
もともと郵便貯金なので,これはわかりやすいと思います。
他にもJAなんかも貯金って言います。
細かい話なのですが,例えばゆうちょ銀行の差押をする場合の書類に[預金]って書いてしまうと,やり直し(差し替え)をさせられることがあります。
実際に私もやらかしたことがありますので,気をつけてくださいね。
預貯金の差押えについては,その金融機関で契約している(ほぼ)全ての口座が対象となります。
『普通口座』はもちろんですが,『定期』や『積立』なども対象となります。
事業の取引口座として開設している『当座』も対象になります。
滞納者の開設しているこれらの口座にある残額を差押するわけです。
続いて,『保険』の差押えも可能です。
『生命保険』や『損害保険』などが主なものですが,最近ではいろんな種類の保険が出てきていますので,それらも対象になると覚えておいてください。
保険については,複数年契約で掛金が積立型のものを差押えするという方法が中心となります。
掛金の積立型の場合は,満期の給付や解約時の一定金額の返戻金などがありますので,それらを差押えすることとなります。
また,入院給付や無事故報酬のような,基本契約に付随する特約なども対象となります。
そのため,積立型だけでなく,掛け捨て保険でも差押えをしておくことも検討していくことが重要です。
そして,給与や年金も差押え対象になります。
これらは,給与の支払者(雇用先)や年金だと日本年金機構などに対して差押え手続きを行うこととなります。
なお,年金については,非強制徴収債権で適用される民事執行法においては,差押えが禁止されています。
強制徴収債権で適用される『国税徴収法』にのみ認められている権限になります。
他にも,契約先から支払われる『売掛金』やいろんな組合などに出資している『出資金』なども対象になります。
ここまでにあげてきた差押え財産については,その支払元に直接調査を行い,滞納者がその財産を所有していることが判明したら,差押えをすることとなります。
これら(出資金は除く)をまとめて『債権』の差押えと言います。
※出資金は,『無体財産権』といいますが,今回は省略します。
差押え対象となる財産は,まだまだあります。
『不動産』『自動車』『動産』なども差押え対象になります。
※自動車は,普通自動車のことをいいます。軽自動車は,動産に含まれます。
『不動産』『自動車』については,その登記,登録を管轄する法務局(登記所)や運輸支局(陸運局)に調査をし,その所有と内容を確認します。
『動産』については,滞納者の自宅等に直接訪問し,家財道具や貴金属などを差押えします。
動産の差押えについては,別の記事でもう少し掘り下げたいと思います。
これらの財産については,差押えた後に『公売』という方法で売却し,その代金を滞納税等に充てることとなります。
知っている方も多いかも知れませんが,官公庁オークションというのが有名ですね。
これとは別に,私たちが独自で企画・運営している『公売』もありますので,機会があればご紹介したいと思います。
今回は,差押えの対象財産について代表的なものをご紹介しましたが,これらを差押えする際には,それぞれ差押禁止財産(禁止額)というものもあります。
滞納者が所有する財産の大半が差押可能なのですが,なんでもかんでも差押していいワケではありませんので,注意してください。
『国税徴収法第75条〜78条』に規定されております。
滞納しているとはいえ,生きていくための最低限の生活費保証や事業を継続する上での必要なものについては,禁止されているということを覚えておいてください。
差押え後によくある話ですが,
「生活ができなくなる」とか「厳し過ぎる」とかいう声が上がることがあります。
しかし,生活に直結する財産については,法律により『差押禁止』を規定することで,その濫用を規制し,『生存権』を担保していますので,こういうことを言う人たちはそもそもの生活(家計)の見直しが必要であるといえます。
最近では,福祉担当部署や社会福祉協議会などが家計支援などのサービスを提供したりしているので,そちらに繋いであげることも検討してはいかがでしょうか?
それでは,今日はここまでにしたいと思います。
次回の記事も楽しみにしていてください。
スキ,フォローいただけると,これからの励みになります。
(できる限りフォローバック(気持ちは100%)いたします)
[引用研修]
令和元年11月29日 須崎県税事務所管内地方税研究会 徴収事務研修会
『徴収事務について』~徴収率UPのための滞納整理の実務~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
